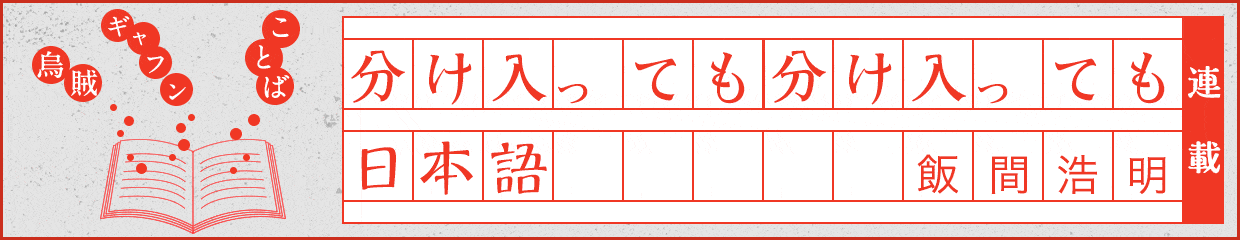結婚する運命にある男女は、小指と小指が赤い糸で結ばれていると言われます。ロマンチックな話です。とはいえ、「赤い」と色彩を示しているからには、目で見えなければならないはず。「見えない赤い糸」というのは形容矛盾ではないでしょうか。「赤い透明人間」みたいなもので、何だか変な感じです。
そのせいかどうか、インターネット上では、「赤い糸」は実は「明い糸」である、という主張もあります。これもおかしいですね。明い、つまり明るい色の糸であるにしても、それが見えないというのは、やはり理屈に合いません。
いわゆる「赤い糸伝説」は、特に最近、話題に上ることが多くなったような気がします。いつ頃から現れた伝説でしょうか。
太宰治は「思い出」(1940年)で、学校の教師から聞いた話を記しています。
〈私たちの右足の小指に眼に見えぬ赤い糸がむすばれていて、それがするすると長く伸びて一方の端がきっと或る女の子のおなじ足指にむすびつけられているのである〉
この話は「津軽」(44年)にも引用されているので、太宰の作品でこの話を知った、という人も多いかもしれません。ただ、今日、一般には、糸が結ぶのは手の小指どうしだと理解されています。太宰の話は足の小指どうしなので、必ずしも彼の作品が発信源というわけではなさそうです。
結婚の仲人をする人のことを「月下老人」(普通は「月下氷人」)と言います。この由来を調べていると、赤い糸伝説に似た話に行き当たります。中国唐代の『続幽怪録』という書物に出ている「定婚店」という話がそうです。
主人公は韋固という青年。彼はもともと孤児で、早く結婚したいという願望を強く持っていました。でも、なかなかいい話がまとまらないまま、すでに十年の歳月が過ぎていました。
そんなある日、青年は縁談の紹介をしてくれた人に会うため、朝の暗いうちから出かけました。途中の石段で老人に出会いました。大きな袋に寄りかかって座り、月明かりで本を読んでいます。のぞき込んでみると、見知らぬ文字が書いてあります。
聞けば、老人が読んでいるのは冥界の本であり、老人も冥界から来たのだと言います。人々の結婚に関する運命を管理しているようです。
「その袋の中には何が入っているのですか」
「これは赤い縄だ。夫婦になる者どうしの足をつなぐものだ。たとえ敵味方であっても、いったんこの縄でつながれたら、運命を逃れることはできない。君の場合は、今度の縁談はうまくいかない。本当の相手はまだ幼く、十数年後に結婚できるだろう」
青年はそれでは困る、と運命を変えようとするのですが、結局は老人の言うとおりになり、十数年後に幸せな結婚をすることができました。青年の結婚相手が育った村は、後に「定婚店」と名付けられました。
――ざっとこんな話です。この話に出てくる老人が「月下老人」です。
この話によれば、使われるのは糸ではなく縄であり、結ぶ部分も手の小指ではなく、足の小指ですらなく、足どうしを括りつけるというのです。「赤い糸伝説」ならぬ「赤い縄伝説」です。
ずいぶんイメージが違いますが、「月下老人」などの慣用句を生んだ有名な話であり、「赤い糸」の源流と見なすことには無理がありません。問題は、「足に縄を括りつける」が、どうして「小指に糸を結びつける」に変わったのか、ということです。
これは、日本での「小指」の意味づけが関係していると考えられます。
昔は、誓約の気持ちを表すため、手の小指を切り落とすということがありました。江戸時代の初めには、女が男に、遊女が客に、真心の証として指を切って渡した例があります。これを「指切り」と言います。今日「指切りげんまん」と言って小指を絡めて約束するのも、これと関係があるのでしょう。
やくざが落とし前(もめ事の決着)をつけるために指を詰めるのも、発想が似ています。この場合も、まずは小指を詰めることが多いはずです。
中国の伝説の「足と足を縄でつなぐ」という設定は、囚人を連想させます。これでは結婚のイメージに合わない、と思う人がいたんでしょうね。いつの間にか、誓約の象徴である小指に話がすり替わり、また、指には縄はつけられないので、サイズ的にふさわしい細い糸に変わった、ということではないかと推測します。
おおもとの伝説は古いのに、昭和戦前の時点でも、太宰治が珍しそうに紹介し、しかも細部が今日と違っています。このことから、戦前にはまだ「赤い糸伝説」は一般的ではなかったと考えられます。
伝説が一般化したのは、早くとも戦後でしょう。私の場合、子どもの頃(70年代)には「赤い糸で結ばれる」という表現を耳にした記憶はなく(子どもだからかもしれませんが)、よく聞くようになったのはもっと後です。
冒頭に示した疑問、「見えないのにどうして赤い糸か」については、中国の伝説を考えれば分かります。人間には色が見えないけれども、結婚の運命をつかさどる冥界の人には赤い色に見えるわけですね。冥界の人の目はサーモグラフィーのようになっているのかもしれません。
-

-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら