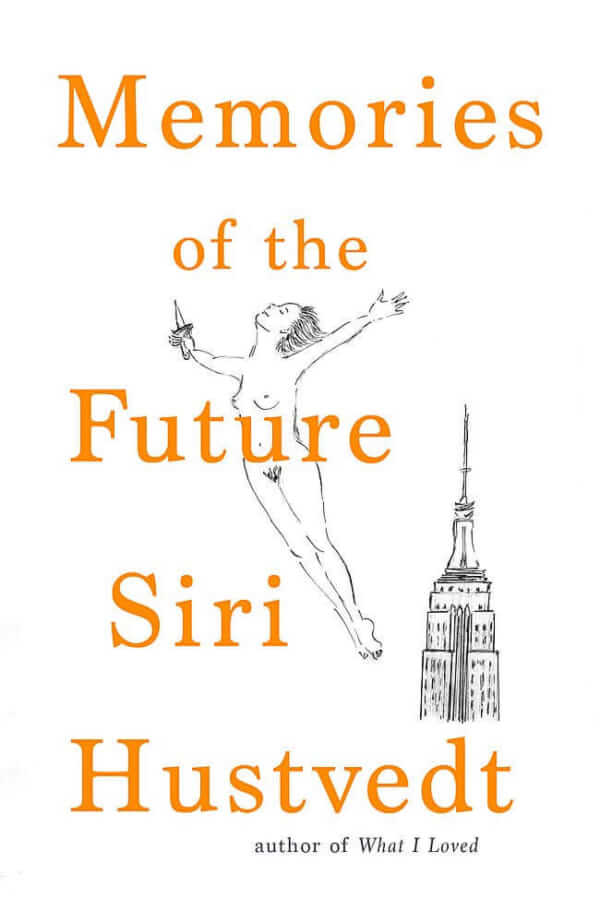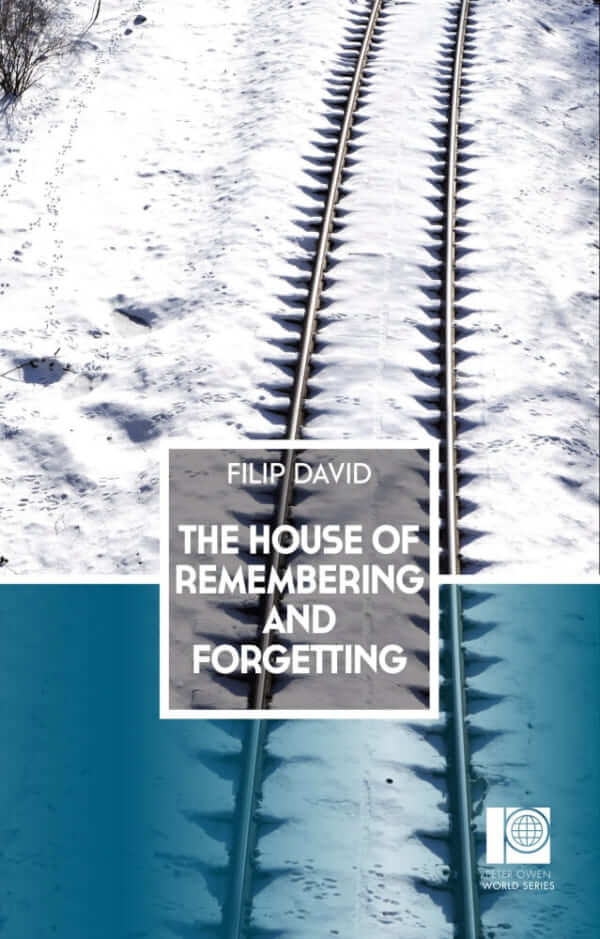(13)怒りと記憶――シリ・ハストヴェットの新作
Siri Hustvedt, Memories of the Future (Simon & Schuster, 2019)
Filip David, The House of Remembering and Forgetting, translated by Christina Pribichevich Zorić (2014; Peter Owen World Series, 2017)
著者: 柴田元幸
……)のに対し、ピカソ自身を「パブロ」と呼ぶことは――彼の少年時代を語るとき以外は――めったにないと指摘している。男性の友人たちはつねに姓で呼ばれるのに対し、女性は文豪ガートルード・スタインでさえ「ガートルード」。“I am fascinated that no one I have read seems to have noticed that the literature on Picasso continually turns grown-up women into girls”(これまで私が読んできた誰一人、ピカソをめぐる文献が大人の女性を終始女の子にしてしまうのを気にしていないように思える。そのことに私は感じ入ってしまう)。
この「女性を低く見る」ことの不公平という問題は、ハストヴェット2014年の前作The Blazing World(光り輝く世界、未訳)のテーマでもあった。自身も芸術家なのに、ニューヨークの超大物アートディーラーである夫の陰に霞んでしまった女性が、夫の死後、自作を男の名で発表し(というか、男性芸術家を雇って彼らの作品として発表させ)大きな反響を得るが、作者は女性だという事実を明かそうとすると……。長らく嘲笑・無視されてきたイギリスの哲学者・科学者・文人のマーガレット・キャヴェンディッシュ(1623?—73)のユートピア小説The Description of a New World, Called The Blazing-World(邦題『新世界誌 光り輝く世界』)の通称をそのまま借りたThe Blazing Worldというタイトルは、主人公の中で燃えさかり、光り輝く創造的衝動の炎であると同時に、女性を同等に見ない男たちへの怒りの炎も示唆しているだろう。
今年春に刊行されたハストヴェットの最新作Memories of the Future(『未来の記憶』)でも、女性が低く見られることへの憤りは作品全体を貫いている。その問題の根深さは、登場人物・作者の怒りが、いかにもマッチョで男性中心主義的な男(たとえばヒロインを強姦しようとする男)だけでなく、たとえば、医者としてはほぼ理想的に患者思いだったと思える父親にも向けられていることに表われている。子供だった彼女が、人体の骨の名を次々列挙してみせると(彼女はまだfemur〔大腿骨〕の正しい発音も知らないくらい幼い)、父親は微笑んで言う。“Oh, you’ll make a fine nurse”(うん、お前は立派な看護婦になる)――彼女が医者になりたいのだという可能性は少しも考えずに。
あるいは、ミネソタの田舎からニューヨークにやって来た彼女を、親しみを込めて「ミネソタ」と呼ぶ仲間たち。アメリカの女性作家たちの文学にあっては、とかく金と権力のある男は女を理解せず助ける気もなく、女に理解ある男は金も権力もなく結局やっぱり助けられない、というのが通り相場だが、そんななかでは相当マシと思えるその男たちでさえ、時にミネソタを“girl”の枠に押し込んで彼女を苛立たせる。28歳、ユーモアのセンスもたっぷり持ちあわせた物理学者の卵ジェイコブは、あるとき彼女に問う。“I know you’re not insane, Minnesota, but are you or are you not a romancière?”(なあミネソタ、君が狂っていないことはわかってるが、君は女流作家なのか、そうではないのか?)
Romancière, the feminine of romancier, is inevitably touched by the condescension the French have shown toward writers with the wrong genitalia for centuries, and that is why this sentence that began with the fact that I was not crazy and ended with the feminized noun for “novelist” has never left me.
I loved to play with Jacob, enjoyed the speedy back-and-forth of our talk, although I couldn't match his manner. We are still friends. This apparently innocuous comment hurt me because in it I recognized a familiar, patronizing music. Jacob did not and does not make a habit of looking down on me from on high, but at that instant his voice blurred with other voices I had heard over the years of my then still short life. If that particular tonality had played in my presence only once or if it had belonged to a single person, I am certain it would have vanished from my memory, but those demeaning notes have over the course of the years become a nauseating refrain.(Siri Hustvedt, Memories of the Future, Ch. 8)
「作家」を意味するフランス語romancierの女性形romancièreにはつねに、間違った性器を持った書き手に対しフランス人が何世紀も示してきた優越的態度が伴っている。だからこそ私は、私が狂ってはいないという事実で始まり「小説家」の女性形で終わるこのセンテンスを一度も忘れたことがないのだ。
ジェイコブと戯れるのは楽しかった。彼のやり方には匹敵すべくもなかったが、言葉のスピーディなやりとりは愉快だった。私たちはいまでも仲よしだ。この一見無害なひと言に私が傷ついたのは、そのなかに、聞き慣れた、相手を見下す音楽を聞きとったからだ。ジェイコブは私を上から見下ろすような態度をしじゅう取っていたわけではないし、それはいまも同じだが、その瞬間、彼の声は、まだ長くないそれまでの人生で私が聞いてきた多くの声と混じりあった。もしその音色が、私の前で一度奏でられただけだったら、あるいはその音色が一人だけの人間に属するものだったなら、きっとあっさり記憶から消えたことだろう。だがその、相手を貶めるメロディは、現在までの長い年月のあいだに、吐き気を催すリフレインと化しているのだ。
現在を生きる語り手は年配の作家であり、文学、哲学、心理学の豊富な知識を作者ハストヴェットと共有している。その語り口はきわめて知的だが、怒りはストレートである。知的なのに怒りは素朴、なのではない。「知的な女性」の存在を許さない空気に、語り手も作者も怒っているのだ。1980年から90年代にかけて、哲学者でもある作家レベッカ・ゴールドスタインが取り上げていた問題(たとえば1991年刊のThe Dark Sisterは、大哲学者ウィリアムと文豪ヘンリーの陰に埋もれた妹アリス・ジェームズをめぐる物語だった)はいまも小さくなっていないように思える。ケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(西山敦子訳、C. I. P. Books)、ジャッキー・フレミング『問題だらけの女性たち』(松田青子訳、河出書房新社)などの邦訳書で語られていることにもそのまま通じる話だし、女性をアフリカ系アメリカ人と置き換えれば、前々回取り上げたジョン・キーンのCounternarrativesなどにもつながる。
(ちなみに僕はいまさっき、レベッカ・ゴールドスタインの現在の夫はスティーヴン・ピンカーだとウィキペディアで知って、とっさにそのことを書こうと思った。たぶんそういう反射神経に、語り手もハストヴェットも苛立つのだろう。ポール・オースターの妻として、ハストヴェットが相当腹立たしい思いを味わってきたことは想像に難くない。)
こうした「怒り」で話が終わるとすれば、『未来の記憶』は『光り輝く世界』の二番煎じということになってしまうだろうが、そうではない。まず、ミネソタの住むニューヨークの安アパートの隣の部屋には奇妙な女性が住んでいて、一度も見たことのないその女性の声をミネソタは薄い壁越しに聞く。“Amsah”と祈りの文句のようなものをくり返し唱えたり、奇怪な独白をえんえん続けたり……この不思議な女性ルーシーをめぐる部分がこの小説では一番面白い(ハストヴェットは以前から、社会の隅っこにいる奇妙なキャラクターを描くのが上手いのだ)。やがて、“Amsah”は“I’m sad”と言っているのだということが判明する。なぜそんなによく聞こえるかというと、ミネソタはルーシーの独白を、父親からもらった聴診器を壁に当てて聞きとるのだ。医者になりたいという子供のころの願望との、何とも皮肉な対比。
そして、記憶の曖昧さというテーマが今回は前景化されていることも重要である。このモチーフに独自性を与えている仕掛けが、ミネソタが母親の家で発見する、大学時代に書いていた日誌や小説である。『アンネの日記』に敬意を表するかのように、日誌は「ページ」に宛てて(“Dear Page …”)書かれている。
March 17, 1979
Page, I am learning to dance the city dance; it’s a tap dance, in case you didn’t know, shuffle ball changes and hops and riff walks. I can beat it out with the best of them. I have been practicing my superior and disdainful face in the mirror. You need to lower your eyes and turn your face a bit to one side and make sure you don’t smile or, if you smile, it has to come from the corners of your mouth, slyly. Of course, I save this look for jerks. I do not use it on my real friends, never on the gang of five. Whitney does it naturally, of course.
I have no memory of this “practice.” And I wonder if the writer is making it up, preening, not in the mirror but in the notebook. I cannot say. The gang of five had been recently formed and consisted of Whitney Tilt, Gus Scavelli, Fanny Cumberland (aforementioned flamboyant roommate), Jacob Ackermann (physicist), and me. (More about the gang and its consolidation in Chapter Eight.)
(Ch. 7)
ページ、私は都市のダンスを学んでいます。念のため言っておくとそれはタップダンスです――シャッフルボールチェンジ、ホップ、リフウォーク。最高に上手い連中にも負けません。見下した、尊大な顔も鏡で練習しています。目を伏せて、顔をちょっと横に向け、微笑まないことが肝腎です。微笑むとすれば、口許だけで陰険にやらないといけません。もちろんその表情は、阿呆な奴らのために取っておきます。本当の友だちには使わないし、五人組には絶対使いません。もちろんホイットニーはこれをごく自然にやってのけます。
この「練習」の記憶はまったくない。この書き手がでっち上げているんじゃないか、鏡の前じゃなくてノートの中でポーズを取っているんじゃないか、と思ってしまう。わからない。五人組というのは当時出来たてだった仲間で、ホイットニー・ティルト、ガス・スキャヴェリ、ファニー・カンバーランド(前述の派手なルームメート)、ジェイコブ・アッカーマン(物理学者)、そして私(五人組とその結成過程についてはさらに第8章で)。(編集部注:原著では青字部分は違う字体を使っている)
普通なら、現在の自分が過去の自分を一方的に回想(または捏造)するしかないわけだが、ここにはノートという形で、過去からの直接の声がある。もちろん直接の声だって、語り手が言っているとおり、ノートの中で自分を捏造しているかもしれないわけだが、そうやって捏造することもひっくるめて、何がなんだかわからないまま都会で必死に生きている一人の人間の切実さがそこにはある。だからこの本では、現在の自分(実体)⇔過去の自分(影)という不均等な対比ではなく、等しく生々しく等しく曖昧さを含む人間二人がゆるやかに対峙しているような印象がある。小説冒頭の“My unformed hero and I were headed for a place that was little more than a gleaming fiction: the future”(わが未だ形成されざるヒーローと私は、ほのかに光る虚構でしかない場に向かっていた――すなわち、未来に)という一文でも示唆されているように、一方がもう一方に一方的にまなざしを向けるのではなく、あたかも両者がたがいに視線を向けあっているような感覚。この本のタイトルが『未来の記憶』となっているゆえんもそこにある。読んでいるうちに、深く沈み込んでいけば記憶とはまさにそういうものだ、という納得が深まっていく。
一方でたとえば、セルビアの作家フィリップ・ダヴィドの初英訳The House of Remembering and Forgetting (2014, Christina Pribichevich Zorić英訳2017) を読むと、記憶についてまた違った感慨を得る。この小説の主要人物は、主人公のアルベルト・ヴァイスをはじめほぼ全員、第二次世界大戦中に旧ユーゴスラビアで幼年期を送り、親が何らかの策を弄してくれたおかげで生きのびたユダヤ系の人びとである。収容所へ向かう列車の床に穴を開けて子供を落としたり(アルベルトはこれで助かる)、理解ある非ユダヤ系の隣人に預けてその家の子として育ててもらったり……。
ここでは、記憶の曖昧さは問題ではない。辛い記憶を保つか、捨てるか、どちらかである。すでに老人となったアルベルトは、ニューヨークを訪れ夜中の街にさまよい出て、「記憶と忘却の家」という看板がかかった不思議な建物に行きあたる。「記憶の部屋」(“The Remembering Room”)を選べば記憶に伴う痛みがふたたび生々しくよみがえるし、「忘却の部屋」(“The Forgetting Room”)を選べば記憶は失われ痛みもすべて消える。
For a moment Albert thought how much easier it would be if he could expunge this deep-rooted, persistent pain that he would not even have were it not for the memory of all the dark, disturbing, monstrous things that had comprised the better part of his life. But what would he do without that deep, penetrating pain? It held the memory of his father, his mother, Elijah. That pain was everything he was, and without it he, Albert Weisz, did not exist. Nor did the people he cared about most.
(Filip David, The House of Remembering and Forgetting, Ch. 11)
一瞬アルベルトは、この根深い、執拗な痛みを抹消できたらどんなに楽だろう、と考える。自分の人生の大半を構成してきたすべての暗い、心乱される、おぞましいものたちの記憶がなかったら、こんな痛みはそもそもありえない。だが、その深い、刺す痛みがなかったら自分はどうするのか? 痛みは父、母、弟エリジャの記憶も含んでいる。その痛みは彼という人間すべてだ。それがなかったら、彼アルベルト・ヴァイスは存在しない。彼にとって誰より大切な人たちも存在しない。
英訳に付された歴史学者デジャン・ジョキッチによる序文によれば、作者のダヴィド自身、戦時中九死に一生を得た体験があるという。彼を救ったのは、サクランボが大好物であることだった――“… exhausted by a long march and unable to walk any further, he was about to be shot by an Ustaša soldier but found additional strength to continue when his mother told him a cherry tree awaited at the destination as a reward for those who arrived first”(長い行進に疲れはて、もうそれ以上歩けなくなった彼は、ウスタシャ〔大戦中にドイツと同盟を結んだクロアチアのファシスト党〕の兵士にいまにも撃ち殺されそうになったが、そのとき母親に、行き先にはサクラの木が一本待っていて、一番早く着いた人たちがご褒美にもらえるんだよと言われて先へ進む力が出たのだった)。
こういう凄絶な記憶のありようを前にすると、記憶の曖昧さといったことを問題にできる、いわば「恵まれた」立場は「負けて」しまいそうだが、そうはならない強さがハストヴェットの『未来の記憶』にはある。その強さの源は、いくつものテクストを巧みに組みあわせた構成、老いはじめた作家である現在の語り手の自然な謙虚さ、などに求められるだろうが、もうひとつ、過去の自分と現在の自分とで対話が閉じておらず、語り手が「あなた」と呼ぶ存在、要するに「読者」も引き入れられているのが大きい気がする。こう言うと、何だか19世紀小説みたいじゃないか、と思われる方もいるかもしれないがそれは正解である。この本は、19世紀によくあった、主人公が都会に出てきて次第に成長していく小説の現代版であり女性版でありパロディなのだ(特に結末の、「誰それはその後どうなった」式のいかにも19世紀的なまとめが秀逸)。そのなかで、「あなた」への語りかけはストレートに温かい。自分に向きあうときと同じように、語り手は己と対等の存在として「あなた」に語りかけるのだ。
We all suffer and we all die, but you, the person who is reading this book right now, you are not dead yet. I may be dead, but you are not. You are breathing in and out as you read and if you pause and place your hand on your chest, you will feel your heart beating, and there must be light in the room where you are, a light from a window or a lamp or a screen that illuminates the page and part of your body as you read.
(Memories of the Future, Ch. 17)
私たちはみな苦しみ、みな死ぬ。でもあなたは、この本をたったいま読んでいる人は、まだ死んでいない。私は死んでいるかもしれないが、あなたはそうじゃない。あなたは読みながら息を吸って、吐いていて、もししばし目を休め片手を胸に当てれば、心臓が脈打っているのがわかるだろう。そしてあなたがいる部屋には光がなくてはならない。ページと、読んでいるあなたの体の一部とを照らす窓からの光、ランプの光、もしくは画面の光が。
最新情報
8月2日(金)1時~2時、有楽町よみうりホールで〈夏の文学教室〉講演「翻訳と日本語」。8月28日(水)8時~10時、下北沢B&Bで江國香織『彼女たちの場合は』刊行記念イベントに参加。「波」8月号にバリー・ユアグロー連載「オヤジギャグの華」第4回「奇妙な一日の話」掲載。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら