(4)翻訳家・鴻巣友季子の10冊
ワインをゆるゆる飲みながら読みたい10冊
著者: 鴻巣友季子
ロアルド・ダール/田口俊樹訳「味」(『あなたに似た人』所収)
E・A・ポー/鴻巣友季子訳「アモンティリャードの酒樽」(鴻巣友季子・桜庭一樹編『E・A・ポー ポケットマスターピース 09』所収)
テア・オブレヒト/藤井光訳『タイガーズ・ワイフ』
イーヴリン・ウォー/小野寺健訳『回想のブライズヘッド』
ポール・トーディ/小竹由美子訳『ウィルバーフォース氏のヴィンテージ・ワイン』
アントワーヌ・ローラン/吉田洋之訳『ミッテランの帽子』
パトリック・デウィット/茂木健訳『みんなバーに帰る』
マルカム・ラウリー/斎藤兆史監修、渡辺暁・山崎暁子訳『火山の下』
河合香織『ウスケボーイズ』
開高健「ロマネ・コンティ・一九三五年」(『ロマネ・コンティ・一九三五年 六つの短篇小説』所収)
「ワインをゆるゆる飲みながら読みたい本」というお題をいただきました。本とワインはとても相性がいいですよね。どちらも上質なものは、長く豊かな余韻があとに残るものです。また、どちらも読んで(飲んで)からあなたの記憶の一部となり、静かに熟成していくものだとも言えます。
ワインが題材になっている小説、ワインがアクセントになっている小説、ワイン以外のお酒が出てくる小説などを取り混ぜて選びました。ちょっと(だいぶ)怖い二編と、戦争を背景にした二冊を中心にご紹介します。
ロアルド・ダール/田口俊樹訳「味」
ロアルド・ダールの「味」と言えば、ひと昔前はダールの名作としてよく知られていました。この短編を含む『あなたに似た人』とか『キス・キス』とかも広く読まれたものです。でも、最近はダールと言うと、むしろ児童文学なのですね。『チョコレート工場の秘密』や『マチルダは小さな大天才』の作者ですので、児童文学以外もぜひごひいきに!
「味」の原題はTaste。ワインでtasteといえば、「味覚」とか「賞味」などと訳す方がいいかもしれません。「味」では、ある家の主人がワイン通の客人とブラインド・テイスティングで賭けをします。これは、ワインの銘柄名やラベルを一切伏せて、グラスに注がれた液体だけを虚心に味わい、その風味を率直に評価する方法で、先入観や偏見に左右されない公平な評価ができます。小説でいえば、たとえば、村上春樹さんの文章を事前情報なしにノーラベルで提示し、その味わいを述べ、どんな作家の作品なのか当てる、というような鑑賞の仕方です。おもしろそうでしょ?
さて、「味」でのブラインド・テイスティング対決では、家の主人が出したワインの銘柄やヴィンテージを客人が当てることになります。主人は客人に煽られて自分の娘を賭けてしまい、客人は自分の所有する二つの屋敷を賭けます。ワインの鑑識では人後に落ちないと自認する中年の客人は、もったいつけてワインを同定していきます。
客人はまず、これはフランスの「バーガンディ」(ブルゴーニュ)ではなく、「クラレット」(ボルドー)だと絞りこみます。バーガンディ、クラレットは、イギリス特有の言い方ですね。次に、グラーヴ地区でもなければ、サンテミリオン地区でもないと除外。では、メドック地区だと絞りますが、マルゴーのすさまじい芳香がないと断言。そうなると、残りは三つの村です。客人は、ポイヤックにしては土臭さがないなどと言い、結局、サンジュリアンだと特定します。さらに消去法で推理をつづけますが、「どう見ても、一級シャトーではないな。二級ですらない」と言ったところで、馬脚を現します。
サンジュリアンに一級シャトーが存在しないのは、ワイン通には知られていることなので、ここは二級から攻めなければいけません。ですから、ここは「ふっ…」と微苦笑しつつ読みましょう。
さあ、ワイン対決の行方は? 老メイドの活躍があります。執事、女中(家政婦)といえば、家の秘密をよくよく見ている曲者たちですね。ウッドハウスの「ジーヴス探偵」もの、カズオ・イシグロ『日の名残り』、エミリー・ブロンテの『嵐が丘』など、小説でも大いに活躍する人たちです。
読書のお供に、手ごろなクラレット、メドック産のワインはいかがでしょう。

-
ロアルド・ダール/ 田口俊樹訳
2013/5/10発売
E・A・ポー/鴻巣友季子訳「アモンティリャードの酒樽」
ポーのなかでも最も知られた作品の一つですね。舞台はイタリアの町。零落した旧家の語り手は、フォルチュナートという友人に積年の恨みを抱いています。冒頭からこうです。「フォルチュナートにはこれまで一千回も傷つけられ、そのたびになるたけの我慢をしてきたわたしだが、いよいよ故意の侮辱を受けるにおよんで、奴への復讐を誓った」。
なにを言われたのか、されたのか、はっきり書かない。まどろっこしいのがポーの味です。ともあれ、語り手は奸計をめぐらし、カーニヴァルの酒でいいかげん出来上がったフォルチュナートに、シェリーの上物であるアモンティリャードだというふれこみの大樽を手に入れたので、本物かどうか鑑識してほしいと持ちかけます。
ちなみに、シェリーは伝統的な製法では、ピラミッドみたいに樽を組んで造ります。瓶詰めする際は、ソレラと呼ばれる最下段の樽からシェリーを抜く。「大樽(pipe)」というのは、それのこと。ワイン通を自認するフォルチュナートはこの話に食いついてきます。「アモンティリャードを、しかも大樽でか。ありえんだろ! しかもこのカーニヴァルの時季に!」と。
ここのセリフの真意はいくつか考えられます。謝肉祭の後には四旬節が来て、荒野のキリストを思って祈るため、懺悔や断食をおこなう。肉類や酒類など、もってのほかです。だからこそ、謝肉祭にはみんな思う存分、飲み食いをする。だから、どこのシェリー樽も空になっているだろうに、という意味でしょうか? あるいは、このタイミングでそんな美味しい酒がざぶざぶ大量に手に入るなんて!(やばすぎ!)という歓喜のセリフでしょうか。
ともあれ、道化師もどきの仮装をしてうきうきするフォルチュナートの末路やいかに! ポーらしい主題とモチーフに彩られた一編です。
シェリーって、樽で熟成させているうちに酵母の働きのせいで、表面に「フロール」という白い花のような膜が張るんです。この膜によって酸化が止まり、花は枯れたらしずしずとシェリーの中に沈んでいきます。ポーにはこの膜が白い経帷子のように見えたのかも、なんてわたしは思っています。どこかしら退廃的なシェリーをポーが愛したわけがわかる気がします。
少し枯れた味のシェリーをお供にどうぞ。

-
エドガー・アラン・ポー/鴻巣友季子・桜庭 一樹編
2016/6/23発売
テア・オブレヒト/藤井光訳『タイガーズ・ワイフ』
次はコンテンポラリー作品を。作者は旧ユーゴスラビア、ベオグラードに生まれ、ユーゴ崩壊の始まる七歳のころ国を出て、キプロスやカイロで暮らした後、アメリカに定住しました。
『タイガーズ・ワイフ』は名前のない国の物語。語り手の「ナタリア」は女医で、紛争地区を飛びまわっています。史実をとりいれたリアリズムと、バルカン独特の幻想性を帯びたおとぎ話という、異質なふたつの物語がシームレスに混ざりあう見事な構成です。
ワインを注ぐというだけの短いくだりに、複雑な歴史の相関関係を浮かびあがらせる、いわば物言わぬワインが雄弁に語るシーンがあります。
ユーゴから独立を図るボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエヴォ(と、おぼしき街)。あるとき、翌日爆破計画が実行されることを知らされたナタリアの祖父(「ユーゴスラビア人」を自認するセルビア人医師)は、逃走するどころか、ホテルのレストランに最後の晩餐に出かけるのです。爆撃に揺れ、閃光に照らされるテラス席で、祖父は街を眺めつつ、限られた食材での食事を楽しむ。額に黒いあざのある老給仕は「今夜はハウスワインしかご用意できておりません」と言って、ワインを持ってきます。少し引用しましょう。
「今でも覚えている。八八年のシャリマッチ産ワイン、じきに私たちの側につくことになる有名なブドウ畑のワインだった。そんなことはまったく気にかけていないように彼は私のグラスにワインを注いだ。そのワインを出すことで自分の強さを誇示したがっているのだ、と私には思えた。まさにそのとき、当のブドウ畑の所有者が航空機工場にいる彼の息子を銃剣で刺していようが、彼にはどうでもいいのだ、とね」
一九九〇年代初めのサラエヴォは、セルビア人、クロアチア人、ムスリム人(ボスニャク人)の三つ巴状態になっていました。給仕の「額に黒いあざ」があるというのは、彼が敬虔なムスリムであることを示すものでしょう。礼拝の際に額を敷物にこすりつけた跡です。そういう老給仕の元に敵方のセルビア人がやってきてワインを頼む。給仕学校で高度な教育を受けた給仕は矜持をもって、どこまでも礼儀正しく完璧なサービスをします。勧めた料理は、水揚げされたばかりのニシマトウダイの姿焼きです。
この街が明日には吹き飛ぶことをセルビア人医師は知っているし、彼にとってこれがこの街最後の晩餐になることをムスリム人給仕も知っている。出された白ワインの産地は架空のようですが、「じきに私たちの側につく」という記述から、モンテネグロのワイナリーかもしれません。老給仕は敵方となる土地のワインをべつな敵方の客に注ぐ。洗練されたもてなしのなかにも、そこはかとない緊張があるでしょう。また、緊張のなかにも、ひとつの文化の最期を見届ける、いわく言いがたい連帯のようなものも感じられるのです。ワインの名場面だと思います。

-
テア・オブレヒト/藤井光訳
2012/8/1発売
イーヴリン・ウォー/小野寺健訳『回想のブライズヘッド』
この小説も戦争を背景にしており、ブラインド・テイスティングをする場面も出てきます。ワイン好きにも好評な一作です。
この小説でブラインド・テイスティングをするのは、うるわしい男性ふたり。物語は、第二次大戦中、イギリスのブライズヘッドに駐屯した一連隊の話に始まり、語り手「ライダー」の若き日の回想へ。オックスフォード大学時代の親友「セバスチアン」は侯爵家の息子なのですが、いつもテディベアを抱えている変わり者で、一族のプレッシャーに耐えかねてだんだん身を持ち崩していきます。そんなセバスチアンにライダーは魅せられ、ふたりで美酒美食の甘美さに酔います。じつにいい感じですね!
「今夜はふたりでたっぷり楽しめるぜ」などというBL的名セリフの後、ふたりはブラインド・テイスティングに興じます。まあ、そのコメントたるや、むず痒いような、ぞくぞくするような。
「これは羚羊(かもしか)のようにおびえた目をしたワインというところだ」「アイルランドの女房たちの手伝いをする、あの親切な妖精さ」「これは白きうなじにかかる真珠の首飾りだ」「最後に生き残った一角獣さ」などなど。
どれだけワイン修行を積めば、「アイルランドの女房たちの手伝いをする妖精」の風味を感じられるのでしょう! しかしライダーはこの後長らくつづく「不毛の歳月」を、セバスチアンと交わした言葉を支えに生き抜いていくのです。
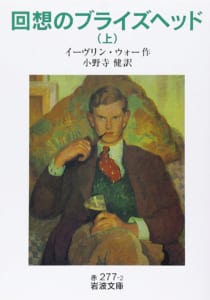
-
イーヴリン・ウォー/小野寺健 訳
2009/1/16発売
ポール・トーディ/小竹由美子訳『ウィルバーフォース氏のヴィンテージ・ワイン』
ワイン蒐集家から膨大なコレクションを譲られ、ワインに魅入られた男性の数奇な人生を逆回転で見せる四つのヴィンテージの物語。主人公いわく、テイスティングとただの飲酒をごっちゃにするな。

-
ポール・トーディ/小竹由美子訳
2010/8/17発売
アントワーヌ・ローラン/吉田洋之訳『ミッテランの帽子』
ミッテランはたいへんなワイン好きで、垂涎のコレクションを持っていました。そんな彼がレストランに帽子を忘れていく。帽子がつなぐ不思議な連作短編集です。
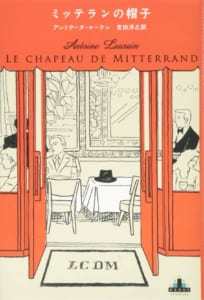
-
アントワーヌ・ローラン/吉田洋之訳
2018/12/26発売
パトリック・デウィット/茂木健訳『みんなバーに帰る』
泥酔文学の最前線です。酔いどれ文学の多くは一人称語りですが、本作はなんと二人称語り。「あなたが、あなたが」と言われているうちにこちらが酔っぱらいます。
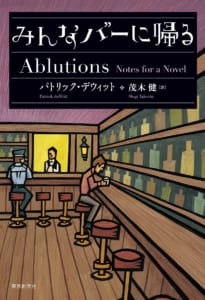
-
パトリック・デウィット/茂木健訳
2015/1/29発売
マルカム・ラウリー/斎藤兆史監訳、渡辺暁・山崎暁子訳『火山の下』
大江健三郎も心酔した泥酔文学の金字塔です。国を遠く離れたメキシコで、妻も社会的地位も失いひたすらメスカルに溺れる元英国領事の一日。破滅の美学。
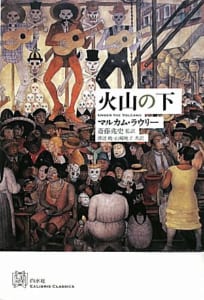
-
マルカム・ラウリー/斎藤兆史監訳、渡辺暁・山崎暁子訳
2010/3/26発売
河合香織『ウスケボーイズ』
日本のワインメイカーの草分け麻井宇介の教え子であり若き革命者たち「ウスケボーイズ」の試行錯誤を取材した秀逸なノンフィクション。神の雫は地道な虫取り作業から生まれる。

-
河合香織
2018/10/5発売
開高健「ロマネ・コンティ・一九三五年」
美味しいワインを讃える文学は数あれど、本作ほど、不味いワインを言葉の限りを尽くして描いた作品もないでしょう。なにせ、「耳に毛が生え」たワインが登場するのですよ。

-
開高健
2009/12/4発売
-

-
鴻巣友季子
1963年、東京生まれ。翻訳家、文芸評論家。英語圏の現代文学の紹介とともに古典新訳にも力を注ぐ。『風と共に去りぬ』(全5巻、新潮文庫)の他、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』(同)、ヴァージニア・ウルフ「灯台へ」(『世界文学全集2-01』河出書房新社)の新訳も手がける。他訳書に、J・M・クッツェー『恥辱』『イエスの幼子時代』(ともに早川書房)、アマンダ・ゴーマン『わたしたちの登る丘』(文春文庫)など多数。『熟成する物語たち』『謎とき『風と共に去りぬ』 矛盾と葛藤にみちた世界文学』(ともに新潮社)、『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』(ともに筑摩書房)など翻訳に関する著書も多い。
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 鴻巣友季子
-
1963年、東京生まれ。翻訳家、文芸評論家。英語圏の現代文学の紹介とともに古典新訳にも力を注ぐ。『風と共に去りぬ』(全5巻、新潮文庫)の他、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』(同)、ヴァージニア・ウルフ「灯台へ」(『世界文学全集2-01』河出書房新社)の新訳も手がける。他訳書に、J・M・クッツェー『恥辱』『イエスの幼子時代』(ともに早川書房)、アマンダ・ゴーマン『わたしたちの登る丘』(文春文庫)など多数。『熟成する物語たち』『謎とき『風と共に去りぬ』 矛盾と葛藤にみちた世界文学』(ともに新潮社)、『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』(ともに筑摩書房)など翻訳に関する著書も多い。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら







