(5)歴史学者・與那覇潤の10冊
重い病気のあとで新しい人生をはじめるのに役立った10冊
著者: 與那覇潤
網野善彦『無縁・公界・楽 日本中世の自由と平和』
東畑開人『居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書』
冬目景『ACONY』
清家雪子『月に吠えらんねえ』
逢坂八代『瑠璃宮夢幻古物店』
青木昌彦『私の履歴書 人生越境ゲーム』
西尾幹二『人生について』
ケイ・ジャミソン/田中啓子 訳『躁うつ病を生きる わたしはこの残酷で魅惑的な病気を愛せるか?』
椎名麟三『永遠なる序章』
ジョン・ヴァーリイ/冬川亘 訳「残像」
アジールの原理を探して
「ここは無縁所だな――。」
2015年の3月、ある大学病院の精神科に入院して意識の回復をみたとき、最初に思いついたのはそれでした。「意識の回復」といっても、オーバードーズで記憶が飛んでいるといったことではありません。思考に靄がかかり、目や耳から入ってきたことばの意味が脳裏に浮かばず、自分の頭が自分のものとは思えない。そうした重度のうつ状態が、ようやく薄れてきたという意味です。
無縁所とは、日本中世史の大家だった網野善彦が『無縁・公界・楽 日本中世の自由と平和』(平凡社ライブラリー、原著1978年)で用いた概念で、一般にはアジール(避難所)の同義語だと解釈されます。外部の世界では差別や迫害にあう人びとが逃げ込んで、マイノリティどうしの結束による自治を営むイメージでしょうか。そうした同書の描写は『吉原御免状』(隆慶一郎著、原著1986年)の遊郭や、『もののけ姫』(宮崎駿監督、1997年)のたたら場の造形に影響を与えると同時に、被差別民の実態を美化しすぎているとして、他の歴史学者から猛烈な批判にさらされもしました。
しかし学者時代に同書を論じたことのある私が思い出したのは、ロマン主義的なコミューンの幻想とは少し違うことです(冬に刊行の『荒れ野の六十年(仮)』勉誠出版、に再録予定)。病院では自分から名乗らないかぎり、入院前の職業や専門とは縁が切れている――つまり、無縁である。私であれば大学の准教授をしていたとか、何冊かの歴史書を書いたことがあるとか、そういった「業績」めいたこととは切り離された状態で、いま他の人と話をしたり聞いたりしている。それは、かなり貴重な体験ではないだろうか。
無縁所の外側で、私たちは普段「俺はこのような実績のある人間であり、だから俺の話は聞くに値する」という発想で、つまり自分の過去と有縁――関連づけることで人に物事を伝えようとしている。しかしいくらそうしても、話が通じないときは通じない。逆にそうした縁をすべて断ち切ったところから、新しいかたちの人との関係が生まれることがある。それが網野さんの真意ではなかったかという気持ちが、ふっと湧いたのでした。
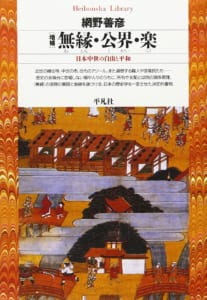
-
1996/6/12発売
2か月ほどして退院した後は、メンタルクリニックが開設するリワークデイケアに通いました。デイケアについて知るには、臨床心理士としての勤務体験をつづった東畑開人さんの『居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書』(医学書院、2019年)がよいでしょう。厳密にいうと同書の舞台は、就労が困難な重度の病者を受けいれる「居場所型デイケア」で、復職・再就職の支援を主務とするリワークとは異なりますが、双方に、というかむしろ生活のために特定の場所に「居る」人すべて――つまり万人に共通する教訓が汲みとられています。
著者の東畑さんとの対談でも話題になりましたが、それは時間のとらえ方に関わっています。「時間はほんらい、時計で測れる客観的なものではなく、主観的に流れる」といった哲学的な考察は、健康なときに勉強してもさほど得心しないのですが、うつ状態では文字通りの実感に変わる。無意識のうちにこなしていた日常の些事(食事・洗濯等)が、異様なほどの長時間を要する労役に感じられると同時に、布団の中で恐怖におびえて震えているだけで、「一瞬」のうちに日が暮れてしまったりするからです。
「これだけ実績のある俺に、相応しい待遇はこうだ」として自己を過去と有縁づける論理の裏には、人は業績を積み上げて日々ステップアップしていくという直線的な時間像――わかりやすく言えば自己啓発本がうたう「成長」のイメージがあります。もちろん、それが無意味なわけではない。しかしそれは、人間が体験する時間や自己のすべてでもないのです。そこに無縁という、オルタナティヴな(=もうひとつの)人間関係の原理がかかわってくる。東畑さんがやはり、デイケアが果たすべき機能を「アジール」と呼ぶ理由でもあるのでしょう。

-
東畑開人
2019/2/18発売
回復はイメージとともに
デイケアに通い始めてもしばらくは、うつの作用で活字が読めない(識字能力は残っているが、読んだ文章の意味がわからない)状態が続いたので、思い切ってしばらくはマンガを読んでいました。ストーリー性が強い作品は、活字の小説と同様に脳がついていきにくいので、とにかく絵柄(イメージ)が気に入ったものを選んで作中の世界に没頭する。短編集や連作4コマの形式を狙うのも、いま病気に悩んでいる方にはおすすめできると思います。
独特のタッチが昔から好きだった冬目景さんの作品は、完結しているものはほぼすべて読みましたが、ひとつあげるなら『ACONY』(講談社、全3巻。2009~10年)です。今日まで残存した同潤会アパート(大正モダンの時期に建設された、マンションの走り)という、いわば「時間が止まった」かのような空間を舞台に、思春期の少年少女と各種のもののけ――生者とは異なる時間を生きる人びとの交流を描いています。
ネタバレにならないよう詳述は避けますが、「流れる時間が遅い」ことは、ほんとうに成長にとってマイナスなのか。むしろ複数の時間を生きている人どうしの交わりこそが、人生において豊かな成熟をもたらすのではないか。そうした温かいメッセージを感じる作品です。「アジール」の具体像がなかなか浮かばないという方にも、まずは本書をおすすめします。

-
冬目景
2009/3/23発売
戦争協力やナショナリズム、あるいはエゴイズムの主題をあつかうため、近日はグロテスクな描写が多くなり病中の方にはすすめられないのですが、清家雪子さんが連載中の『月に吠えらんねえ』(講談社、現在10巻。2014年~)の序盤も心に残りました。□街(しかく=詩・歌・句の町、の意)という、日本近代の詩人・歌人をモチーフとしたキャラクターが暮らす架空の世界を舞台に、彼らの自意識やトラウマがユーモラスに描かれています。
たとえば「抒情歌の達人」とされる詩人は、たんに好色だったのかもしれないし、「薄命の天才」と呼ばれる作家が、メンタルを病んでいた可能性もかなり高い。それを、昨今流行のキャラ化(イケメン化や美少女化)の手法でカリカチュアしてしまうのではなく、本人の詩作やテキストを豊富に読解・引用しながら、深い敬意と愛情をもってオリジナルの作中人物に反映させてゆく手つきに共感を覚えました。たんなる既成の史実のデータベースではなく、改めてもういちど「生きなおす」対象として歴史をあつかう感性が、サブカルチャーの世界に残っているのは嬉しいことです。

-
清家雪子
2014/4/23発売
もともと活字を読み書きする仕事だった研究者が、病気の症状のためにマンガしか読めないでいる。こうした状態では当然、「能力」ということについても考えざるを得ません。格好のヒントになるエピソードは、逢坂八代さんの『瑠璃宮夢幻古物店』(双葉社、全7巻。2014~18年)に入っていました。第6巻収録の第38話です。
本作は呪いめいた謎の力をもつアンティークが、持ち主のエゴと結びついて悲喜劇を巻き起こす様子を、古物ひとつにつき原則一話の形式で描いた連作で、星新一のショートショートのような味わいがあります。今回登場するのは持っているだけで「勝ちを呼び込む」という、ドーピング級の効果をもつメダル。しかし逆にいうと持ち続けるかぎり、「ほんとうは自分は無能で、メダルの力で勝っているだけかも」という猜疑心にさいなまれる。さて、あなたならこの品物、どうしますか?
平成の30年(と4か月)のあいだには「能力のある個人を伸ばし、その力で社会全体を引っ張る」という発想が、雇用改革や文教政策までの広い分野を席巻し、「それは弱肉強食の新自由主義だ」といった反発も招きました。しかし、能力とはそもそも「誰か」が保有できるものなのか。たんに結果が判明した後に、これはあの人が有能(無能)だったせいだ「ということにしよう」として責任の帰属先を決める、約束事があるにすぎないのではないか。そんなことを考えさせられます。この回を国語ないし道徳の教科書に丸ごと収録するだけで、令和は生きやすい時代となるでしょう。

-
逢坂八代
2017/8/10発売
人生で出会う問いたち
私はいま、「能力のコミュニズム」ということを言っています。冷戦下――昭和の時代に世界の半分を支配した、あらゆる会社を国営企業にし、土地を収公して国有にする「財産のコミュニズム」は、暴力装置としての国家を肥大化させるだけの失敗に終わりました。しかし共有ではなく強い個人だ、けっきょく人は私利私欲でしか動かないとするシニシズムも、たいしたものを生まないことは平成のあいだに証明されています。
ようやく活字が読めるようになった後、いちばん励まされた本は、経済学者の青木昌彦さんの自伝『私の履歴書 人生越境ゲーム』(日本経済新聞出版社、2008年)でした。留置場に入れられた際の描写から始まるとおり、青木さんはもともと、60年安保の際に学生運動を主導したブント(共産主義者同盟)の若き指導部。運動体が崩壊したのち、マルクス経済学から近代経済学に「転向」して渡米し、歴史や制度といった市場合理性では説明しにくい問題を、ゲーム理論に基づいて数式化する世界的な業績を上げた――というのが、一般的な理解でしょう。
もちろんそれが間違っているわけではなく、多くの伝説的な学者たちとの親交も含めて、本書にもそうした学問的な軌跡は記されています。しかしより強く印象に残るのは、青木さんが最後まで、なによりも「自由」を大事にする人だったということ。ひとりひとりが創造的に振る舞える環境であれば、どこにでも足を運んだし、逆に個人を集団に同化させようとする画一化の圧力が忍び寄ってきた際には、反政府の運動であれ国のシンクタンクであれ、きっぱり手を切った。思わず快哉を叫びたくなる生きざまです。
青木さんには一度だけお目にかかり、また私の書いたものについてご批判をいただいたのもあって、以降拙著をお送りしたこともありました。2015年の7月に亡くなられたため、もう、そうした献本をさせていただけないのが心残りです。

-
青木昌彦
2008/4/1発売
人生つながりでは、西尾幹二さんの『人生について』(新潮文庫。原著2005年)も忘れがたい読書になりました。保守の論客として知られ、平成なかばには「新しい歴史教科書をつくる会」の会長を務めたために、歴史学者にこれほど忌み嫌われた研究者もいないでしょう。本書も終盤でフェミニズムをあてこするあたりは、個人的にあまり共感をしないのですが、それだけで読まないのはもったいない好著です。
本書では怒り・虚栄・孤独……など一章にひとつずつ、人生で直面する感情や境遇がとりあげられ、「深く掘り下げると、それはそもそもいかなる事態であるのか」が検討されます。たとえば、怒りとはなにか。ふつうはなんとなく「褒められると喜び、けなされると怒る」と考えますが、たとえば勤務先の会社名ばかりを立派だと褒められたら、多くの人はむしろ怒る。だから西尾さんは、怒りとはだれもが内心持っている「他人からこう見られたいと期待している理想の自画像」と、実際に他人から下された評価とのギャップのことだ、と分析します。
面白かったのは、こうした西尾さんの――彼はほんらいニーチェの研究者ですが、本書ではむしろ現象学的な――筆の運びが、ちょうどデイケアで体験した認知療法と重なっていたことです。認知療法では「気分が落ち込んだとき」「怒りがわいたとき」などの記録をワークシートにとり、感情がおさまり冷静になった後で「なにがいったいそんなに不愉快だったのか」を解析する。そうすると「自分がなにを嫌っているのか」を明晰に把握できるし、思いこみで落ち込んでいた場合は立ちなおれるようになるんですね。
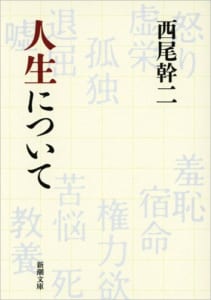
-
西尾幹二
2015/4/30発売
平成には「バズワード」(流行語)という用語が、それ自体バズワードになりました。その単語を使っておけば「それっぽく」見えて、世界の最先端の動向すべてを諳んじた人間を装える。名詞に2.0や3.0をつけたり、訳せばどうということのない概念をわざとカタカナで書くのが典型です。しかし知的な営為とは、言葉の包装紙を替えて右から左に流していくことではなく、むしろある用語を使うことで「わかったつもりになっていること」の中身に目を凝らし、誤魔化しなしでも通じるよう平易に語りなおす試みだと思うのです。
これは病気の体験を、未経験の人にも伝わるように書く上でも役立つことでした。いちばんの理想とした体験記は、米国の精神科医(ジョンズ・ホプキンズ大学の医学部精神科教授)にして、自身が激しい双極性障害の当事者でもある女性が書いた、ケイ・ジャミソンの『躁うつ病を生きる わたしはこの残酷で魅惑的な病気を愛せるか?』(新曜社、田中啓子訳。原著1995年)です。
躁状態で発揮したパワーによる研究面での活躍と、その副作用、うつに転じたときの絶望と苦しみ。治療者であると同時に患者でもあることの複雑さ、その状態での友情と恋愛、あるいは偏見との戦い。それらが品位ある文章で、情感をもって綴られていきます。
自分の病気について書くことは、恥ずかしくない。なぜならそれは、これ見よがしに同情を惹くことでもないし、暗い怨恨を叩きつけることでもないから。それらの感情を昇華し、体験を通じて得たものを公に「共有」していく書き方の存在に触れて、執筆への勇気をもらうことができたのです。

-
躁うつ病を生きる わたしはこの残酷で魅惑的な病気を愛せるか?
ケイ・レッドフィールド・ジャミソン
1998/12/25発売
歴史の代わりに古典を
病気をする前は日本史の学者として、明治維新から高度成長期まではいちおう自分で研究し、また先行研究の成果をお借りして、マクロヒストリー(一千年単位の歴史)の本も何冊か作りました。そのなかでもやはり惹かれるのは、敗戦直後の「戦後初期」ですね。この時代に(ついて)書かれたものは、いまも趣味として手に取ることが多いんです。
最近読んで印象深かったのは、椎名麟三の代表作のひとつ『永遠なる序章』(原著1948年6月刊)。単行本や文庫はもう絶版ながら、各種の文学全集に入っているので、図書館で借りれば読むことは容易です。椎名は実存主義の流行を代表する作家ですが、デビュー作「深夜の酒宴」(1947年)は海外の動向とは無縁に執筆され、むしろ投稿先の雑誌を「サルトルの模倣だと思われたくないので、翻訳が出る前に載せてほしい」と急かした逸話が残っています。
貧困のさなかに育った椎名は20歳だった1931年、非合法だった日本共産党の活動家として逮捕。拷問や同志の獄死のなかでニーチェの『この人を見よ』に出会い転向、出獄後はドストエフスキーに沈潜しました。『永遠なる序章』の軸になるのは結核で余命三か月の主人公・砂川安太と、その悪友でありライバルのような竹内銀次郎の対比です。竹内は「死ぬための大義」としてのみキリスト教の神を見いだす一方、にわかに戦後の合法共産党に入党してみるニヒリストで、いわば著者自身の観念的な部分を具現化した存在。
たいして実生活者としての著者の投影である砂川は、自身の寿命が見えたことでかえって、貧しさが溢れる周囲の日常に愛おしみを感じはじめます。
今日一日の生活をはじめるのだ。そして人類は、長い歴史を通じてそうして来たのではなかったか。瞬間、瞬間にはじめ、一日、一日にはじめ、永遠にはじめているのではなかったか。たとえはじめることのなかに滅ぶのが人類の運命であっても。
重度のうつから徐々に回復してくる過程で、病前にはさして省みなかった日常の些細なサイクルを、また送れるようになったこと、繰り返せること自体が嬉しい。大文字の思想が優位だった執筆当時を背景として、いささか登場人物が類型的となっている感はありますが、このもう一度「はじめる」ことの歓びを、肉感をもって伝える文体が胸を打ちます。病気を体験していない方が読んでも、回復過程の患者の気持ちを想像する一助になるかもしれません。
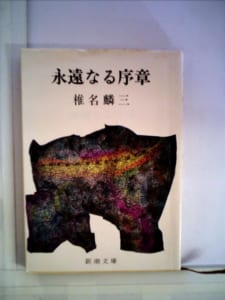
-
椎名麟三
1957発売
執筆時に成立していた社会党首班の政権(48年3月に退陣)を背景として、同書の後半は「唯物史観」に基づき人類全体の解放を掲げる左翼運動と、主人公の個別的な生との対照が見せ場になります。私も病気を経た結果、日本社会の全体を貫く「通史」によって、なにか統一された針路を指し示すといった発想は、もうやめました。はっきり言えばわれわれの社会において、「歴史」はもう必要ない。むしろ生きていく個々のひとりひとりが、その人にとっての「古典」を持つことがはるかに大事だと、そういう風に考えています。
古典とは、時間をおいて人生のなかで何度も触れなおし、そのたびに新たな省察や発見を与えてくれる作品のこと。聖書やコーランを全員に共通の古典とする宗教社会は今もありますが、世俗化した自由社会においては、選択は多様であってよい。文学全集や哲学書から選ぶ必要はないし、活字でなくてもいいんです。マンガやアニメを「ぼくのバイブルです」と言ったら軽蔑されたのは昔の話で、いまは富野ガンダムでも『SLAM DUNK』でも、批判する方がむしろ勇気のいる「古典」がいっぱいあるのですから。
私にとっての古典をあげるなら、病棟で網野善彦の次に思い出した作品である、米国のSF作家ジョン・ヴァーリィの中編「残像」(原著1978年)。現在は『逆行の夏 ジョン・ヴァーリィ傑作選』(ハヤカワ文庫、浅倉久志ほか訳、2015年)に収録されたバージョンが入手しやすいですが、個人的には慣れもあって『残像』(同、冬川亘・大野万紀訳、1980年)に入っている旧訳のほうが好みです。新訳に際して「盲聾者」が「視聴覚障害者」に替わるのがやむをえないとしても、オージーを「乱交パーティ」と訳すのはいかがなものでしょうか。

-
ジョン・ヴァーリイ
1980/2発売
最初に読んだのは、高校2年生くらいだと思います。そのときの衝撃を、これから読む方から損ないたくないので、核心に触れることができないのですが、本作もまたアジールの話――パラレルワールドのような架空の米国史のなかで描かれる、西海岸のヒッピー・コミューンにおける「ありえたかもしれない可能性」を探究した寓話です。目が見えず、耳も聞こえない状態で生まれた男女が結成した独立共同体ケラー(もちろん、ヘレン・ケラーから来ています)の内実が、訪れた「健常者」の男性の視点で語られる。その洞察は深く、仮想人類学とすら呼べるでしょう。
世に映像化不可能をうたう作品は多々ありますが、ほんとうにできないのは本作くらいではないでしょうか。視聴覚が「ない」ことを前提とした世界では、人びとは(われわれの考える意味での)言語を用いずもっぱら身体、すなわち触覚によってコミュニケーションをとることになる。はたしてそれは「不自由」な、成員の「能力が低い」がゆえのしかたない選択なのでしょうか。そうした評価はたんに、私たちの社会の前提が彼らと異なるからにすぎず、真の意味で「障害者」であるのが、むしろ狭義の(=視聴覚を通じて伝達する)言語に拘束されている側だとしたらどうでしょうか。
入院病棟やリワークデイケアで、病気を通じて知りあった友人と交際するときに、つねに私の念頭にあったのは本作のケラーであり、これからもそうあり続けるでしょう。人がみずからの規範とする共同体は、その人自身が思索と内省を通じて見いだせばよく、けっして既存の所属集団などに限られる必要はない。そう思い至ったとき、「大学」なる名ばかりの自治を掲げた組織も、現実の制約下に展開した出来事ばかりの連鎖を語る「歴史」も、私にとってはもはや、依拠する理由はないことを知ったのです。
重い病気の際に役立った本というタイトルから、健康ハウツー的なブックリストを連想された方には、ちょっと意外な10冊だったでしょうか。しかし病気をする「前の状態に戻る」ことだけが、必ずしも療養や快復のあり方とはかぎりません。むろん、もし戻れたらその幸運を大切にされてほしいと願いますが、病気を通じて決定的になにかが変わってしまったとしても、以前より心ゆたかに生きていける形の新しい自己を見つける。そうした試みにおいてこそ、読書は真価を発揮するのではないかと思います。
-

-
與那覇潤
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 與那覇潤
-
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





