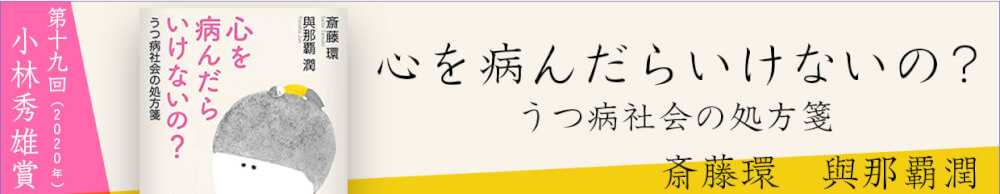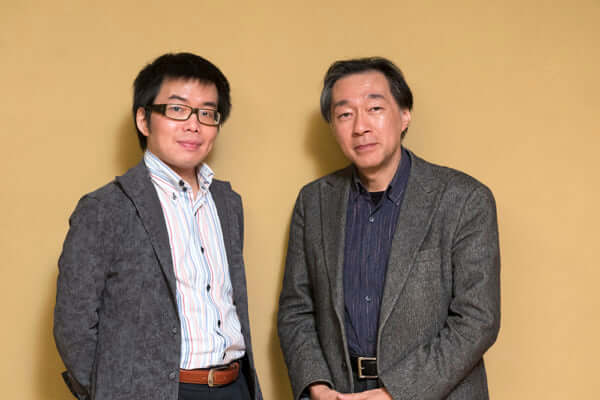
第1信(與那覇潤さんから斎藤環さんへ)
斎藤環さま
ご無沙汰しています。私たちの共著『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』が小林秀雄賞をいただくことになり、新たな書簡を交せることを嬉しく思います。対談形式の作品がこうした賞に恵まれることは珍しく、同書で「対話」の重要性を訴えてきた私たちにとっては、その点でも励まされる出来事でした。
3月にお目にかかった後、世界的なパンデミック/インフォデミックの波が日本にも及び、大きな混乱がもたらされました。新型コロナウイルスへの感染を避けるための自粛や在宅の要請(国によっては強制)は、多くの失業者を生み出したばかりか、強いられた不自由とストレスとがDVなどの対人トラブルも増加させ、「うつ」やさらには自殺の増加をもたらすことが強く懸念されています。共著の副題にある「うつ病社会」が、同時多発的に世界で作り出されたとすらいえる、想定外の状況が出現しました。
この間、わが国で驚かされたのは、あまりにも安易に「自粛こそがすべてに優越する正義だ」との価値判断を下し、異なる立場との対話を閉ざす人の多さでした。上記のとおり、自粛のコストはタダではなく、ノーリスクでもありません。人びとがいっせいに外出や消費を控えれば、収入のみならず将来の展望を奪われて、命を絶つ人さえ出る。なにより「一か月で感染を収束させる」といった強迫的な目標を掲げれば、多くの国民は「だったら絶対に、感染したくない。他の人はともかく、自分はうつされたくない」と思い込み、感染リスクの高い職業に従事する人を忌避しだすでしょう。
「危機のいまだから、自分の権利でも多少はがまんしよう」とする行為自体は、純粋な善意から出たものかもしれません。しかし後に不正確だとわかる情報も含めて、コロナ関連のネガティヴ・ニュースを日々拡散し、ほとんど潔癖症的にリスクの削減を煽る行為は、結果としてそうした差別の「共犯」になったと批判されてもやむを得ない。その教訓を、私たちは忘れてはならないと思います。
残念ながらパニックの渦中では言論の専門家さえもが、自らの発言の副作用を反省し、被害を与えるかもしれない他者に配慮する理性を失ってゆきました。たとえば「感染しないようにするのは当然の義務」「いま病院にかかるのは社会の迷惑」といったツイートを連発しながら、コロナに感染した著名人が謝罪に追い込まれると、他人事のように「そこまでやらせる同調圧力はおかしい」と論評する(自分の言動こそが圧力の一部なのに!)。あるいは夜の街こそが最大のクラスターであるように印象づける記事を書きながら、別の記事では収入が途絶え、偏見にも晒される風俗従業者への「同情」を語る。そうした遂行矛盾が、そこかしこで見られました。
当初、私はそうした風潮に、燃えるような怒りを抱きました。しかしいまふり返るとき、有名・無名のこうした「無意識の加害者」たちにもまた、社会に傷つけられてきた被害者としての相貌があったことに気づきます。
なぜ人びとはいま、自分の執筆する記事や論説が「読者の側にどういったパニックや、偏見を誘発するか」を考えることができないのか。それは日々、学問や言論などと言っても「どうせこの社会では何の影響力もない」「だれも本気で読みやしないし、まともに応答してくれもしない」と、そうした砂を噛む思いをしながら過ごしているからではないか。
ことばに関わる仕事をする人ほど、自らの活動に対して承認を得られず、自己の尊厳を見失ってゆく。そうした現状に対する処方箋こそが、まさに「対話」でなくてはなりません。「聴いているよ。しっかり受けとめて、考えているよ」。そうしたメッセージを届けてゆく、それも本書で私たち二人が実践したような、対面での身体的な臨在感を伴う形で実現してゆくことが、いまなにより必要です。その手間を省き、オンライン上の「いいね」の個数で代替しようとするとき、いかに多くの人が思考停止――周囲が熱狂するものをより煽り、自己を「失う」ことで承認を得ようとする倒錯へと堕ちてゆくかを、われわれは目撃したのですから。
斎藤さんが後記にお書きになったとおり、本書は3~4時間近い対談を6回も繰り返す形で作られ、最後の収録が終わったのはコロナ禍の直前にあたる今年の1月でしたね。疫病のために長らく社会から奪われてきた「対話」による成果が、ようやく混乱のトンネルを抜けて過去を顧みる兆しの見え始めたいま、賞を得ることで新たな読者に届く。それがこの国にもういちど、「対話」の環を広げる再出発の一歩となるなら、まさに著者冥利の一語に尽きると感じています。
與那覇潤
第2信(斎藤環さんから與那覇潤さんへ)
與那覇潤さま
小林秀雄賞の受賞、うれしいですよね。本当に光栄なことなんですが、でもちょっと、驚きませんでしたか? それほど気負わずに対話を重ねてきて、もちろん非常に充実した体験ではあったんですが、それでも今回の受賞はまったくの想定外でした。事前に候補になっていることも知らされていませんでしたから、なんというか「棚ぼた」に近い気分がいまだに抜けません。まあ真面目な話、本書の成立は與那覇さんの周到なトピックの準備と、編集担当Sさんの編集技術の賜物であって、私はちゃっかりそれに便乗しただけという感覚もあるので、お二人には感謝しかありません。ついでに言えば、私は鹿島茂さんの「小林秀雄=ヤンキー説」に元ネタを提供したという経緯もあり、にもかかわらずの受賞と思えば、この賞の寛容性に感激もひとしおという気分です。
それにしても、この対談をコロナ禍直前に終えていたことは、ある意味で幸運だったと思います。もし話題がコロナにまで及んでいたら、話が広がりすぎて収拾がつかなくなっていたに違いありませんから。
與那覇さんからの往復書簡の話題提供は、私にとっても好機でした。コロナ禍に関して言えば、私は與那覇さんに近い考えを持っていたからです。もちろん私も自分なりにいろいろ考え、noteやTwitterでも積極的に発言してきました。コロナ関連本にも無節操にも三冊ほど関わっており、自身のコロナ本も準備中です。
まず與那覇さんのご意見で、わが国のメディアの論調としての「自粛こそが正義」という傾向には、私も強い危惧を感じていました。自粛とか三密回避とかは、どう考えても医療上の望ましい行動変容という以上の意味はないのに、いつの間にか道徳的規範に祭り上げられ、これを錦の御旗にみたてた人々が自粛警察などの暴走に至ってしまった。この状況を皮肉って、noteに「コロナ・ピューリタニズムの懸念」という文章を書いたところ、当初の予想を遥かに超えた反響をいただきました。自粛の推奨はパンデミック状況下での一時的なものに過ぎないはずなのに、それを守らなければ、まるで「公共の敵」扱い。さらに感染してしまった場合は、実質的に公衆の面前で謝罪を強要されてしまう。こんなことをしていたら、それこそ感染隠しは横行するし、感染ルートも隠蔽されてしまうでしょう。なぜそんな単純なことが理解されないのか。
ただ、今回の状況で難しいのは、ことが潔癖症vs反自粛という二項対立におさまりきらない点にもあると思います。私のFacebook上の友人には医師が多いので、コロナに関する意見をさまざまに学んでいますが、少なくとも医師で自粛絶対、感染者けしからん、という人は少数派です。精神科医が多いせいか、感染で死ななくても経済的に困窮して死んだら自粛は意味ないよね、という意見が多数派なので、そこはご安心いただきたい。意見がわかれる、というか対立が目立つのは、「全例PCR検査」とか「集団免疫の是非」とか「日本のコロナ対策は成功なのか失敗なのか」といったあたりでしょうか。
つまりその限りにおいては、医療関係者はけっこう現実的にことの経緯を見守っていたように思います。「八割おじさん」こと西浦先生も、あえて数理的に最悪の見通しを語る役割を引き受けている印象もあり、いたずらに危険を煽っていたとはみていません(やや説明不足、勇み足のきらいはあったかもしれませんが)。それでも、医師の中にも「全例PCR検査するのが当然」派から「マスクは無意味だからやめよう」派まで、つまり潔癖派から無頼派までの幅があったという印象です。エビデンスらしきものが二転三転したのも混乱に拍車をかけたとは思いますが。
そこに対話が欠けていた、というのもご指摘の通りだと思いますし、多くの人文系の論者までもが自粛要請に異議申し立てをしないことには私も違和感がありました。哲学者ジョルジョ・アガンベンは、緊急事態宣言に異を唱え、バイオセキュリティのために人権を含むあらゆるものが犠牲にされようとしている現状を批判しましたが、コロナウイルスを甘く見すぎと集中砲火を浴びてしまいました。しかし私は、絶対的な安全よりも人間的な価値を優先しようとする彼の姿に「同意なき共感」を禁じえません。時には科学的エビデンスに抗する自由なくして、なんのための人文科学でしょうか。
しかしそれ以上に、私の危惧は政府の迷走ぶりにありました。「アベ政治」がファシズムなんて過大評価もいいところ、人々の声、それもSNSの声に押されて右往左往するさまには、一回転してちょっと好感をいだいてしまったほどです。
問題は圧倒的な説明不足、これにつきます。
どうして政治家が学習しないのかまったく不可解なんですが、海外で国民の支持を集めているのは、台湾やニュージーランドのように、感染拡大をうまく抑え込んだ国ばかりではありません。失敗したというほかはないニューヨークのクオモ知事やイタリアのコンテ首相、自分もコロナに感染してしまったイギリスのジョンソン首相、成功とまではいかなかったドイツのメルケル首相、軒並み支持率を大きく上げています。一方、日本の内閣支持率は、安倍総理辞任直前の8月には最低水準の34%にまで落ち込みました(NHK世論調査)。先進諸国中では、感染者数も死者数もきわめて少なく、比較的うまくいっていると言えるレベルの日本が、です。これはどういうことなのか。
最大の違いは、繰り返しますがコロナ対策についての説明不足だと思います。内閣の首長が国民の前に「臨場」して、あらゆる質問に丁寧に回答し、国としての方針——間違った方針を含むにしても——を繰り返し、対話的に訴える。そうやって国民の不安と向き合う姿勢があれば、むしろ支持率は最高記録を更新したかもしれません。にもかかわらず日本政府は十分な説明も回避しがちで、記録すらろくに残さず、あるいは廃棄してしまう。まさに「対話」の欠如です。その意味では、菅内閣にもあまり大きな期待はできないでしょう。
しかし私は、まだ希望を持っています。それは、とりもなおさず、対話の大切さを語ることに終始した本書のような対談集が、大きな賞をいただいたという現実にです。この賞が、私たちが考える対話の価値に対しても与えられたとするならば、医療以外の現場にも対話が拡がっていく可能性に期待するのは、あながち荒唐無稽とばかりも言えないでしょう。最後にあらためて與那覇さんと編集担当Sさんに深い感謝を捧げつつ、擱筆したいと思います。
斎藤環
選評
歴史と精神分析の相互貫入
片山杜秀
ユング心理学者の河合隼雄さんを設立準備委員長として日本臨床心理士資格認定協会が誕生し、カウンセラーやセラピストの資格がオーソライズされたのは1988年のこと。アンソニー・ホプキンス演じるフロイト派なのだろう精神分析医、ハンニバル・レクター博士の戦慄的キャラクターが評判となったアメリカ映画『羊たちの沈黙』は1991年の封切り。クリントン大統領が、自分はアダルトチルドレンだと告白したのは1995年。酒鬼薔薇聖斗を名乗る人物が連続児童殺傷事件を引き起こし、不可解な犯人像を解明するため、心理学者や精神分析医が引っ張り凧になったのは1997年。災害や犯罪被害に遭遇して精神に不調を生じ、また平時の生活でのストレスに苦しむ老若男女のためには〝心のケア〟が大切という新しい常識が広く社会に共有され始めたのも、1990年代でしょう。
こうした展開は、ソ連のペレストロイカからベルリンの壁の崩壊、さらにソ連の解体に伴う冷戦構造の終わりと新しい時代の始まりの時期と、大方ダブっております。そして改めて申すまでもなく、冷戦の終わりは歴史の終わりと意識されました。イデオロギーの相剋の織りなす〝大きな物語〟が終わった。ブルジョワの時代だ、プロレタリアートの時代だと、経済や社会を歴史段階的に切り出して見せる物語が切実さを失ってしまった。そういう歴史なき時代に、哲学や政治学や経済学に代わって浮上したのは、心理学であり精神分析なのでしょう。そこで重視されるのは〝小さな物語〟。個の経験、個の生きてきた環境。とてもミクロ。でも、その〝小さな物語〟を分析するときには、人間の心を見きるための概念として超歴史的に有効とされる、意識と無意識とか、エロスとタナトスとか、成熟と未成熟とか、正常と異常とかが、当然援用されるのです。つまり、〝小さな物語〟と超歴史が手を組んで、〝大きな物語〟と歴史を消し去ってきたのが、歴史の終わりを謳った時代の〝歴史〟なのではありますまいか。
このテーマにアプローチしようと思ったら、ひとりでは無理なのです。精神分析の分かっている人と歴史の分かっている人が互いに治療し治療され、発見し合い、2つの歯車をかみ合わせないと何も開けてきません。その意味で斎藤環さんと與那覇潤さんのコンビは見事に相互貫入しました。
書名をはるかに超え、とても射程を広くして、現代が人の心に何を見ようとしてきたのかを解きほぐし、未来への視点まで与えてくれるダイアローグの名編です。
過去の重力から自由であること
國分功一郎
ある作物を前にすると、どうしても人はその作者の過去のすべてがその作物に収斂していくように感じてしまう。特にその作物がすばらしいものであった場合には、この作物のためにはあのような過去が必要であったと考えてしまう。そうなると、その作者の過去を「それでよかった」と正当化してしまうまでほんのもう一歩である。
これは作者自身、己の作物を、己の過去の集積がもたらした成果として捉えざるを得ないことの結果であるのかもしれない。作物を残すことにはどこか過去の正当化という側面がある。だからこそ、それを受け取る側もまた作物を過去から見てしまう。
斎藤環氏と與那覇潤氏の共著、『心を病んだらいけないの?』を読み終えた後で気がつくのは、二人の言葉にはこのような過去の重力が少しも感じられないということである。
重度の鬱のため、勤めていた大学を退職した與那覇氏は、入院中の人間関係がもたらした認識について斎藤氏に雄弁に語る。それは確かに氏が病を得たがゆえに獲得した認識であろう。
だが、読者はそれを読んでいても過去の重力に引かれることがない。つまり、氏の過去についての何か判断のようなものを下す気にはならない。「これはこれでよかった」とも「こうならなければよかったのに」とも思わない。
読者はいわば一つの現在に立ち会うのである。これが本書の言葉の特徴である。ここには生きられている現在そのものが記録されている。
どうしてそのようなことが可能になったのだろうか。與那覇氏の前著『知性は死なない』に言われる通り、能力は個人に帰属するものではなくて一定の環境と諸関係の中で実現されるものであるとすれば、まさに両氏が本書を担当した編集者たちと共に、他ならぬこの時期に、対談本の出版を目指して企画を実現したからとしか言いようがない。これは一つの出来事であったのだろう。
他ならぬこの時期という偶然にも注目せねばならない。一九八九年と二〇一九年に改元の政令が公布されたことは、二人の個人史とも冷戦後の世界史とも何の関係もない。にもかかわらず、本書において二人の知的能力は「平成」というポスト冷戦期の30年間を見事に描き出すに至った。特に「成熟」をめぐる二人の議論は広く共有されるべきものだ。
まさにいま読まれるべき本が登場したと言わねばならない。以上が、本書を小林秀雄賞に値する著作と考えた理由である。
やはりこれは「歴史」だ
関川夏央
若い與那覇潤氏には、十八歳年長の斎藤環氏に話したいこと、聞いてもらいたいことがたくさんある。ありすぎるほどある。
一年間に六回、それぞれが長時間にわたる興味深い対談では、回を重ねるごとに與那覇氏の真面目さ一途さの水位は上がっていくようで、そんなとき読者は、この本を対談というより「相談」、ときに「泣訴」のように感じたりもする。それほどに双極性障害に苦しんだ経験のある與那覇氏の、対話へのモチベーションは高いということだ。
一方斎藤氏はあくまでも落着いた態度を崩さない。むやみに「同意」はしないが、相手の発言・告白・観察に対して「共感」を惜しまないという方法をつらぬく。まさに彼が主唱する「開かれた対話」の実践であろうか。
咳こむような発語、前のめり感ある話題の展開は、與那覇氏内部の必然から生じたことだと思うが、この本に欠けているものがあるとすれば「ユーモア」だろう。それをおぎなうため、要所要所に二人の「(苦笑)」がはさみこまれるのは、一歩読者に近づこうとする與那覇氏の気配りであろう。
「新型うつ病」が「流行」したとき、それは「新型怠け病」の言い換えだという非難がかまびすしかった。その後は「発達障害」である。自他を客観すればみな「発達障害」だといい得るようで、それは「バブル化」した。この三十年、人間関係に「遊び」がなくなり、高度経済成長時代に「気楽な稼業」であったはずのサラリーマンの居心地は悪い。そうして、いわゆる「インテリ」には居場所と目的がない。
與那覇氏は、現代人に歴史の受容体が失われたと苦く認識した末に、歴史学者廃業を宣言された。しかし、この本『心を病んだらいけないの?――うつ病社会の処方箋』で與那覇氏が斎藤氏に話し、斎藤氏がこたえている議論は、まさにこの三十年の歴史の分析、およびそれに対する強烈な批評精神から発している。
医者と元患者という立場を超えてなされた対談によってお二人は「平成三十年史」を書かれたのだと思う。その意味で、斎藤環氏は医者を兼ねる文芸研究家であり、與那覇潤氏はやはり歴史家にほかならなかったのである。
同意のある共感にむけて
堀江敏幸
対話とはなにかをつきつめていく実践の場なのに、両者がどこか対等になりきれていない。そんなふうに感じる読者もいるだろう。與那覇氏は心の病を克服した経験を具体的な言葉にして、鋭く、かつ明快な回答を期待しながらまっすぐに問いを投げる。斎藤氏はそれに対して正面から答えず、良い意味での軽い挑発を巧みにいなして、語義、治療法、病名の歴史的背景などの説明をあいだに置き、臨床医としての豊富な知見を披瀝して緊張感をゆるめ、相手の内側には入らずあえて距離をとってから、つぎの言葉に備える。
ところが、話が進むにつれて、対話というより診療に近いこの空気の層にひそむ「不徹底な平等」の活用こそ、両者のやりとりを前に推し進めていくための、無言の合意にもとづく戦略であったことがわかってくる。
主な話題は、この三十年ほどの社会の歪みにかかわるもので、そこに與那覇氏の心身のフィルターを通した問題提起と分析が加わる。平成と呼ばれた時代に、最後まで平らかに成らなかったものは何なのか。飽和状態にある身体の容量を精神の仮想メモリーで補うというあの昭和の倒錯から逃れようとする者をさらに惑わせるために、外面だけの平等をふりまいたことが、逆に自由を奪う結果となり、閉塞を生んだ。その閉塞を破るために必要なのは、関係性の見かけの均衡やものごとの効率化ではなく、むしろ心身のバグや話の「冗長性」なのだ。
すべてをきれいに均すことはできないという認識のもとで、「他人が、その他者性を残しつつも、しかし他人でなくなっている瞬間」を待つこと。一対一の対話はもちろん、複数の参加者がいるオープンダイアローグのなかでその瞬間に立ち会い、結論も急がないこと。そうしないかぎり、関係性の改善も個の救済も望めないだろう。
ふたりの距離は、保たれたままだ。しかし、「共感」はするが「同意」はしないという空気のなかでさらに迂路をたどって、双方が「必要ななにか」を掴み取っていく道の先に、「同意」をともなう「共感」が開けてくるかもしれない。先の見えない令和の時代の心構えを、本書に教えられた。
組織の問題
養老孟司
内容に重みのある本である。一章が普通なら一冊の対談本になるような作りになっている。だから読むのが大変で、個人的には年齢を思い知らされた。体力がないと読めないという感じだった。近年の日本社会における様々な問題を、二人で多角的に議論していく。最後の主題はオープンダイアローグ(OD)になっているが、これは著者が実践している分野でもあり、明るい未来を予想させる。この本自体が良い対話の例になっているというべきかもしれない。私自身は五十代で勤めを辞するまでは心理に関心があったが、やめると同時に自分でも驚くほど心理的な問題への関心が薄れた。問題は自分個人の心理ではなく、組織の問題、社会的問題だったからであろう。それを自分の側に引き付けていただけのことだったか、と本書を読んで感じた。私は組織を離脱することで問題を解決(?)した。それが不可能な人が多いはずだから、こうした本が出る。現代日本社会を具体的に探究した優れた作品というべきであろう。
-

-
斎藤環
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
-

-
與那覇潤
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 斎藤環
-
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
-

- 與那覇潤
-
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら