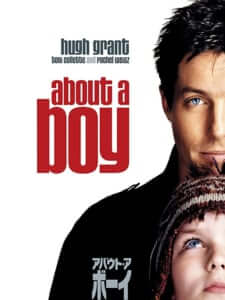2020年7月13日
斎藤環×與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』刊行記念特別企画
「よりよいコミュニケーション」を考える映画(前編)
『ザ・フォール/落下の王国』&『アバウト・ア・ボーイ』
精神科医・斎藤環さんと歴史学者・與那覇潤さんの対談本『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋 』(新潮選書)の刊行を記念して、著者のお二人に、治療者の視点から、体験者の視点から、それぞれのお薦め映画について話していただきました。今回のテーマは、「よりよいコミュニケーション」の条件を考える映画の前編です。ぜひご一読ください。
「共有される文脈」で伝え方が変わる
與那覇 コミュニケーションの問題を考えるさいに、私たちの対談本では「ハイコンテクストとローコンテクスト」の二分法を使いました。コンテクストとは「文脈」のことですが、これは映画の魅力を語る上でも大事な観点だと思うんです。
昔の日本映画だと「あの人は戦争で苦労して……」という台詞だけで、太平洋戦争のことだとわかる。むしろ「苦労して」だけでも、あるいは身体に大きな外傷があるといった映像のみでも伝わるかもしれない。これがハイコンテクスト、つまりコミュニケーションの発し手(映画の製作者)と受け手(視聴者)とが、共有している文脈の度合いが高い状態です。
斎藤 逆にローコンテクストとは共有の度合いが低くても伝わる、「逐語的に“誰が聞いてもわかる”言い方で明示的に表現する」手法のことですね。戦争の例で言えば、「1941年12月8日、日本はアメリカとの戦争に突入した……」とナレーションで補って、一から丁寧に解説してあげる見せ方が該当します。
対談本でも議論しましたが、日本では企業内でも「あとは適当にあれやっといて」のような、ハイコンテクストな言い方で指示が出されがちだと思うんです。これだと、発達障害のように文脈を読むことが苦手な人はもちろん、若い新入社員がなかなか適応できない。
與那覇 難しいのは、では「全部ローコンテクストで表現すればいい」かというと、そうもいかない部分があることです。ハイコンテクストな表現だからこそ伝わるものの例としては、アクション映画の中でのコミュニケーションを想像するとわかりやすい。
黙ったまま、お互いの目配せだけで「信じてる。頼むぞ」「わかった」と伝えあって敵役を倒すから、カッコいいわけですよね。同じシーンで「俺が足元の拳銃をお前の方に蹴るから、拾って撃ってくれ。その隙に俺は別の奴を殴るから」とローコンテクストな台詞を読まれたら、ちょっと見ていられない(苦笑)。
斎藤 それはそうですね(笑)。恋愛映画も同じで、「君は最高だ。愛してる」みたいな台詞ばかり続いたら、見ている方は白けてきます。言葉にはしていないけど、相手に寄せるすごく深い愛情があるんだなと、そう感じさせるシーンに観客はぐっとくるわけです。
対談本では近日のAIブームについても総括しましたが、AIが人間に追いつけない理由は、こうしたハイコンテクストな形の「意味」を扱うことができないからです。「別に曖昧な文学性なんて要らない。AIでも処理できる論理性だけが大事だ」と言い張って、すべてをローコンテクストに処理しようとすると、人間が持つ可能性を切り詰めて、むしろ「人間をAIに近づけて」しまう。そう議論してきました。
「襞」的な関係が物語を紡ぐ
與那覇 つまり、よりよいコミュニケーションを考えるとき、ハイ/ローコンテクストの「どちらか片方を推す」やり方ではダメなわけです。発達障害の人が「空気が読めないのか!」と怒鳴られるような職場も嫌ですが、「あなたの主張はAIが読み取れませんでした。よって却下します」みたいなSF社会にも住みたくないわけで……。
ではどのように、よきコミュニケーションの条件を考えるか。ぼくが紹介する一本目は、『ザ・フォール/落下の王国』(2006年)です。厳密なクレジットとしては「インド・英国・米国合作」となるらしい、ちょっと珍しい映画ですね。
斎藤 監督のターセム・シンがインド出身なんですよね。とてもきれいな映像を撮る監督さんです。2000年のデビュー作だった『ザ・セル』も、ダミアン・ハーストなど現代アートからの引用が「オマージュか、パクリか」で論争になったりはしましたが(笑)、とにかくそれくらい凝った画面作りをする人です。
與那覇 一種のミステリー映画なので、ネタバレしないようにお話ししますが、本作の舞台は1915年、カリフォルニアの病院です。足を骨折し寝たきり状態で入院している青年が、オレンジ摘みの最中に木から落下して腕を折っちゃった移民労働者の少女と親しくなる。青年は「お話」を作るのが得意で、冒険者たちのチームが悪と戦うために世界をまたにかけて活躍する、ファンタジーのような物語を少女に聞かせてあげるんですね。
その「作中作」の形で提示される冒険譚を、実在する世界遺産をロケしながら映像化している。その映像美がすごいという評判を聞いて、うつからのリハビリ中に鑑賞しました。
斎藤 なるほど。クレジットを見ると、衣装も絢爛豪華なデザインで知られる石岡瑛子さん。監督のビジュアルに対するこだわりが伝わってきます。
與那覇 ええ。なので見るきっかけはあくまでも映像だったのですが、ストーリーにもすごく影響を受けました。
この青年の「お話」は、(作中世界では)少女との「二人の間だけ」で語られているという意味でハイコンテクストですが、それが映像化されて観客も見て楽しんでいるという点ではローコンテクストですよね。では、そのお話がよいコミュニケーションになるか否かは、何で決まるのか。それこそが、この映画の主題だと感じたんです。
斎藤 ほほう。「文脈の共有度の高低」とは異なる価値基準が、コミュニケーションの充実度を決めているのではないかと。
與那覇 作品の序盤では、女の子は青年になついて、「もっと続きが聞きたい!」となってゆく。ところがこの青年、実はそうすることで少女を手なずけて、「じゃあ、動けないぼくのためにあれを取ってきてよ」というように使っていたんです。いわば、相手を自分の思い通りに動かすためにコミュニケーションをしていた。
ところがある事件をきっかけに、青年は自分の間違いに気づきます。「他人を操るため」に物語を使うという発想自体が、卑しいことではなかったか。そう反省して、以降はむしろ少女のリクエストに耳を傾けながら、語る内容も改めていく。すると、当初は「うつ」的な青年の状態ゆえに暗かった作中世界のストーリーが、希望を持たせるものに変わっていき、入院病棟の現実にも変化が訪れます。
斎藤 それは気になる内容ですね。與那覇さん自身がうつ状態からのリハビリ中に、この作品を見たというのと相まって、大変に印象深い。
前回の対談では「操作主義ではなく人薬(ひとぐすり)を」という話をしました。治す側(精神科医)が一方的に、治される側を「効くというエビデンスがある手法」で操ろうとするのではなく、両者の垣根をいちど取り払い、そこから生まれる偶然を大切にすることでこそ、事前に予想できない効果が上がる。それが人薬だと論じてきました。
そのとき取り上げたのはグループデイケアでの集団療法でしたが、この映画の中では「語り手と聞き手」という二人の間でも、操作主義から人薬への移行が発生していると。
與那覇 ええ。対談本の終章「結局、他人は他人なの?」では、ドゥルーズの「襞」という概念に言及しました。その時想定していたのが、実はこの映画なんです。
襞とは、何重にも折りたたまれて「どちらが内側で、どちらが外側かわからない」という状態の比喩ですが、作中の青年の視点で考えると、最初は「わかっていた」わけですよ。俺があれをしたい、という欲求が自分の“内側”に存在し、それを実現するために“外側”にいる女の子を操る。そのための道具が、彼女が飛びつきそうな「お話」である。
しかしそうした前提が、少女との関係が進展して崩れていったわけです。本気でこの子に喜んでほしいな、と思うようになったときには、むしろ彼女の“内側”と自分の“内側”がつながっていた。そうした体験を経て、主人公の青年はもういちど生きる意欲を取り戻していくんですね。
斎藤 自己と他者が襞のように折り重なっていく中で、主体(語り手)と客体(聞き手)の境界が曖昧になり、双方に治癒がもたらされる。それは人薬が生成するプロセスであると同時に、よりよいコミュニケーションの条件でもあるということですね。
コミュニケーションのあり方を論じるとき、ローコンテクストの方が「伝わりやすいからいいんだ」とか、いやハイコンテクストの方が「通人だけがわかる、文学性の高い表現ができる」のように言い張りあうと、袋小路に陥りがちです。そうではなく、どれだけ「他者の他者性」を尊重しつつ、相手と自分のあいだの関係性を豊かなものにできているか。対談本の鍵概念で言えば、「ポリフォニー」(多声性)の達成度に注目することが大切だということになります。
相手の「一番大事なもの」に気づく
斎藤 では私の最初のお薦めは、ちょっと古い映画ですが『アバウト・ア・ボーイ』(2002年・英)です。
與那覇 レンタルショップで何度も大きく陳列されていたので、結構人気のある作品だと思います。たしか、主演はヒュー・グラントだったような……。
斎藤 ええ。グラントの役は女好きの独身男性で、まじめに働かずナンパ師みたいなことをしています。しかし彼が近所のいじめられっ子になつかれてしまった結果、そのお母さんであるシングルマザーとも交流を持ち、まじめに人生を考えはじめる……という、ストーリーとしては割とありがちな話です。
ではなぜ取り上げるかというと、実はこの映画、オープンダイアローグのテキストブックで引用されているんですよ(斎藤監訳『開かれた対話と未来』医学書院、179頁以降)。
與那覇 とくにメンタルの病気を扱った映画ではないはずなのに、ちょっと意外ですね。どういう文脈なのでしょう。
斎藤 具体的には、その主人公の男性とシングルマザーとが喧嘩するシーンが紹介されています。男の子がいじめで靴を盗まれちゃったので、グラントがスニーカーを買ってあげるのだけど、男の子はそれまで、彼との交際をきちんと母親に知らせていなかったんですね。結果としてお母さんは激怒してしまい、グラントが食事中のレストランにやってきて怒鳴りつけるんです。
與那覇 「勝手な真似をするな。うちは物乞いじゃない!」ということですか。
斎藤 ええ。しかしグラントにとっては親切をしたつもりなのに、青天の霹靂ですから「あんたが子どもを放ったらかしだから、この子は一人でいじめを我慢してたんじゃないか。普段は親らしいこともしないで、他人を非難するな!」とキレ返してしまいます。
與那覇 修羅場ですね。しかし、それは全然よいコミュニケーションに見えないというか、一方的に自分の主張を押しつけあっているだけではないですか? オープンダイアローグの理念とはほど遠い事例に見えるのに、なぜテキストに載っているのでしょう。
斎藤 ポイントは、私たちが何度も議論してきた「同意なき共感」です。じつは映画ではこの怒鳴りあいの結果、二人とも「子どものことを一番大切に思っている」点では同じだということに気づいて、むしろ互いに理解しあう糸口をつかむ。つまり「靴を買った」という行為の当否については同意できないけれど、「子どもを大切にしている」という点では共感できたわけです。
もちろん通常の治療行為と同様、オープンダイアローグでも基本的には冷静に、理性的な姿勢で対話することが求められます。しかし、ではそこに「怒り」を持ち込むのはタブーかというと、必ずしもそうではない。時と場合によっては、感情表出を伴うコミュニケーションも大切だということを示すために、このシーンが引用されているんですね。
むろん、度を超えて相手を罵倒したりするのはNGですから、その場合は医療スタッフが止めに入るのが前提です。しかし怒りに限らず、論理だけではなく感情を交えないと伝えられず、それ抜きでは分かりあえないことも存在するのが人間なんですね。
與那覇 なるほど。私たちの対談本では家族問題を扱った2章で、「毒親ブーム」の副作用について考察しました。親に対する怒りを意図的に“煽って”いるとしか思えない書籍も、いま書店には氾濫していますが、それらには大きな見落としがある。
子どもが「おまえは毒親なんだ!」と告発すること自体が大事なのではなく、そうして「つらさ」を表明できるようになった後に、親子で話しあって関係を修復してゆく営為をサポートする。それこそが、あるべき家族問題との向きあい方だと論じてきました。
斎藤 怒りは結論ではなく、プロセスなんです。オープンダイアローグでも、たまに患者さんがすごく怒ってしまい、一見すると後味の悪い形でセッションが終わってしまうことがあります。ところが次のセッションのときには、かえって憑き物が落ちたように病状が改善していたりするんです。
治療の場に限らず職場の会議等でも、“キレちゃう人”が出てきた時点でつい「ああ、今回は失敗だわ」と思い込みがちですよね。しかし、そうじゃない。もちろん挑発や侮辱などの、意図的に怒りを誘発するような行為は厳禁ですが、「感情表出もコミュニケーション・プロセスの一つである」という視点は大切だと思います。
與那覇 マニュアルで機械的に「怒りはNG」と禁止してしまうのではなく、むしろ、その怒りの背後にある本人なりの「文脈」を想像し、配慮していくことが重要なのですね。そのお話は、対談本の第7章で扱ったハラスメント問題を思い出させます。
マニュアルだけを見て「Aという行為は載っているからアウト、Bは載っていないからぎりぎりセーフ」のように判定するのは、ローコンテクスト一辺倒なやり方で、たしかに「客観性・透明性」が高いように見えます。しかしそれにあぐらをかいて、コミュニケーションの内実を捉える作業を怠ると、かえってマニュアルの裏をかく巧妙なハラスメントを蔓延させてしまう。
斎藤 ええ。もちろん「誰がされても嫌なこと」をマニュアルで規制しておくのはいいのですが、「なにに傷つくか」は人によって違うわけです。そうした個々の尊厳に配慮するためにこそ、「それはハラスメントだ」という訴えを(結論ではなく)“出発点”にしなくてはいけません。
たとえば『アバウト・ア・ボーイ』では、お母さんの「勝手に靴を恵まれて嫌だった」という気持ちの表出から、彼女にとっては「男の子の“良い親”である」のが一番大切なことだったと、互いに気づく契機が得られました。「何を一番大事にしているか」を見つけるのは、理解しがたく見える相手とのコミュニケーションの肝なんですね。
実際にオープンダイアローグでも、しばしば聞くのは「いまあなたにとって、何が一番大事ですか?」という質問。もちろん、即座にはっきりした答えを求めているのではなくて、対話の糸口をつくるための“きっかけ”として有効なんです。
多くの点で対立していたとしても、まずは相手が一番大切にしているものを把握し、そこに共感を寄せてみるところから、豊かなコミュニケ―ションの第一歩が始まる――そのことをこの映画のワンシーンは、教えてくれていると思います。
(後編へつづく)
斎藤環、與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』
【目次】
第1章 友達っていないといけないの? ――ヤンキー論争その後
第2章 家族ってそんなに大事なの? ――毒親ブームの副作用
第3章 お金で買えないものってあるの? ――SNSと承認ビジネス
第4章 夢をあきらめたら負け組なの? ――自己啓発本にだまされない
第5章 話でスベるのはイタいことなの? ――発達障害バブルの功罪
第6章 人間はAIに追い抜かれるの? ――ダメな未来像と教育の失敗
第7章 不快にさせたらセクハラなの? ――息苦しくない公正さを
第8章 辞めたら人生終わりなの? ――働きすぎの治し方
終章 結局、他人は他人なの? ――オープンダイアローグとコミュニズム
斎藤環「『対話』によって人間関係と自分自身を変えるための10冊」
與那覇潤「重い病気のあとで新しい人生をはじめるのに役立った10冊」
-

-
斎藤環
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
-

-
與那覇潤
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
この記事をシェアする
「斎藤環×與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』刊行記念特別企画」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 斎藤環
-
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
-

- 與那覇潤
-
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら