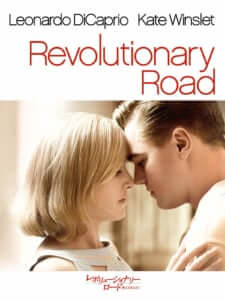2020年6月23日
斎藤環×與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』刊行記念特別企画
「病気を理解したい人」にお薦めの映画(前編)
『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』&『精神』
精神科医・斎藤環さんと歴史学者・與那覇潤さんの対談本『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋 』(新潮選書)の刊行を記念して、著者のお二人に、治療者の視点から、体験者の視点から、それぞれのお薦め映画について話していただきました。今回は患者さんの家族・友人や医療スタッフなど、「病気を理解したい人」にお薦めしたい映画です。ぜひご一読ください。
「うつ」を切り口に映画を見ると
與那覇 うつになって「よかった」と思うことは普通ないでしょうけれども、ぼくにとっての貴重な例外は「映画に出てくるうつ」がわかるようになった点です。セリフなどの形で明示的には説明されていなくても、演じている俳優さんの表情やしぐさで、「あ、この登場人物はいま、うつだという設定じゃないか」とピンとくるようになりました。
斎藤 ほほう。映画に関する著書もある與那覇さんだけに、それは興味深いですね。
與那覇 典型例を示すと、1980年にアカデミー賞を独占した『クレイマー、クレイマー』(公開は前年)。ダスティン・ホフマンと子どもの親権を争う奥さんをメリル・ストリープが演じて、彼女の出世作(助演女優賞を受賞)になった映画ですね。自分が子どもを置いて家を出ていったくせに、突然また戻ってきて「親権はあたしがもらう」と主張したりして、ストーリー上の行動だけだと一見ワガママな人にも見えてしまいます。
ところが「演じ方」に注目すると、相当きついことを夫に言っているにもかかわらず、顔の表情がずっと能面のように凍りついたままで、泣き出す一歩手前にも見える。たぶん精神的に追い込まれて、気持ちが苦しい状態ゆえの振る舞いなんだなと、すっと伝わってくるんですね。若い頃からこんなにもすごい名優だったんだと、再認識しました。もっともいまはあらゆる役が上手すぎて、逆に「なにを演じてもメリル・ストリープにしか見えない」女優さんになってしまいましたが……(苦笑)。
斎藤 たしかに(笑)。前回の「自己啓発の限界」の議論ではありませんが、個人としての才能がありすぎるのも問題かもしれません。
與那覇 今回は患者さんの家族や、医療関係者など「病気を理解したい人」に薦める映画ということで、こうしたうつ体験者の目で見たとき、心の病気のことがリアルに描けているなと感じた作品を紹介したいと思います。
反面教師としての『逆・タイタニック』
與那覇 私の一本目は、『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』(2008年・英米)。ただしあらかじめ注意しておきますが、この映画は絶対に「病気で苦しんでいる本人」に見せてはいけません。
なぜなら、同作のストーリーは「心を病んでいる人に、『こういう対応だけはしてはいけない』ことを(無自覚に)繰り返した結果、悲劇が起きる」というものなんです。あくまでも反面教師として、「ああ、自分も気をつけよう」と周囲の人が自覚を持つ上でのみ優れた素材であって、いま、現に心が苦しい人の目に入れてはいけません。
斎藤 それは臨床にあたる精神科医としても、気になる内容です。しかしデータを見ると、主人公のカップルがレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットで、恋愛映画の超大作だった1997年の『タイタニック』と同じ配役(監督は異なる)。しかも1950年代の黄金期のアメリカが舞台で、むしろ楽しめそうな作品に思えてしまいますが……。
與那覇 映画としては、まさにそこが味噌なんです。『タイタニック』は、身分制的な差別が残るヨーロッパで抑圧されていた女性が、大西洋上で自由な恋に目覚め、米国に渡って成功を収める結末ですから、ある種のアメリカ賛歌ですよね。
ところが『レボリューショナリー・ロード』ではむしろ、黄金期とされる時代のアメリカだって「そんなにいい社会じゃなかったよ」という観点から、知的な美男美女の「タイタニック・カップル」の家庭が崩壊していく様子を撮っていく。脇役にも『タイタニック』と同じ俳優をキャスティングして物語のカギを握らせたりして、非常に意地悪に作られた、いわば『逆・タイタニック』なんです。
タイトルに「レボリューショナリー」(革命的な)と入っているのも皮肉が効いていて、これ自体は主人公夫婦が住む通りの名前なんですけど、暮らしているうちに平凡すぎる日常の耐えがたさが、どんどん二人を押しつぶしてゆく。「もう革命なんか来ないぜ」という虚無感が、アメリカ的な消費生活の裏側にあるんじゃないかと、強く示唆していますね。
斎藤 たしかに意味深なタイトルですね。私たちの対談本では精神病理学の知見を借りて、うつとは「ポスト・フェストゥム(祭りの後)」の精神状態、つまり「画期的な理想社会をめざす革命などというものは、すでに終わってしまって、もう二度と来ない」とする感覚だと論じてきました。
今日の日本でいうと、「平成のあいだに目指した政権交代なんて、もう無理。うだうだ言いつつも、まぁ安倍政権でしょうがない」といった意識がポスト・フェストゥムですが、そうした生活実感の原点を、50年代の米国に見る映画であると。
與那覇 ええ。しかしウィンスレットが演じる奥さんは、いまでいう「意識高い系」で、自分で市民劇団を立ち上げたりして「もっと刺激と夢のある、輝かしい日常」を取り戻そうともがくんです。ディカプリオの旦那さんは彼女を持て余しつつ、しかし自分も会社の歯車であることに嫌気がさして、こっそり不倫したりしてうさを晴らしている。
こうした煮詰まった状態で、メンタルが不安定になってきた奥さんが「もうこの国を捨ててヨーロッパ、なかでもパリに引っ越そう。そこでなら、出会った当初のクリエイティヴな私たちに戻れる!」と言い出しちゃう。
斎藤 なるほど。まさしく『タイタニック』の航海とは、逆向きの設定ですね。
與那覇 ところが、この後の夫の対応が非常にまずい。本人も日常に疲弊していたせいもあり、最初は奥さんの話に「悪くないね」と乗っておきながら、会社で昇進が決まるや「あのプランは現実的じゃない。夢見がちすぎる」と反対に転じて説教を始め、「君はこのところ、不安定なんじゃないか。精神分析医が必要なら、お金は出すよ」と病気認定したりする。
たしかにウィンスレットの演技からも、奥さんが心を病んでいることは伝わってきますから、事実認識として間違ってはいないんですよ。しかし問題は、こうした「手のひら返し」がいかに相手を傷つけているかという自覚が、まったくないことです。
斎藤 うーん、それはダメですね。対談本でも議論したとおり、カウンセリングの基本は「同意なき共感」です。つまり、病気ゆえに現実感のないことを言ってしまう相談者に対しては、発言内容に同意はしない。しかし「私はそれには賛成できないけど、でも、あなたが本当に苦しんでいることはわかるつもりだよ」と、最後まで相手の立場に寄り添うわけです。
與那覇 この映画の夫の場合は、中途半端に「同意」しておきながら、途中で突き放して事実上、「そんな提案は病気ゆえの妄想だ」と言ってしまう。いわば「同意していたくせに共感を捨てる」態度で、あるべき寄り添い方の正反対なわけですよね。
さらに最悪なのは、奥さんに「君は病気だと思う」と告げて、ウィンスレット自身がその自覚を持った後になっても、ディカプリオは彼女にダブルスタンダードで接するんです。彼女が「病気ゆえに生じる、普通でない言動やコミュニケーション上のミス」をしたときに、「なに言ってんだ! 頭がおかしいのか!」みたいに怒鳴ってしまう。
つまり「あなたは病気だ」とスティグマ(烙印)を押しつけながら、怒るときだけはあたかも相手が正常な状態で、病気の症状ゆえに「しかたない部分」がまったくないかのように扱うわけです。これは患者(ウィンスレット)の視点で見れば、病気扱いという形で侮辱されるだけされて、しかしディカプリオにとって都合のよいときだけは「健常者扱い」で、一切のケアなく、自分の行動に全責任を負わされていることになる。
斎藤 それは相手の尊厳を、二重のやり方で傷つけることになりますから、まさに病気の人に接する上ではいちばんいけない態度ですね。しかし治療者や家族の側がつい、無自覚にやってしまいかねないことでもありますから、たしかに反面教師になりそうな作品です。
與那覇 ええ。演じるディカプリオはいつも通りハンサムだし、本人の主観的には(不倫はしていましたが)ずっと奥さんを愛していて、「相手のためを思って」やっているつもりでいる。それが怖いわけです。心が壊れていくウィンスレットの演技も迫真で、繰り返しますが、病気の最中の人には絶対に見せないようにお願いします。
反PDCAから生まれる「人薬」
斎藤 では、私がお薦めする一本目ですが、ドキュメンタリー作家の想田和弘監督が、岡山県の「こらーる岡山」というメンタルクリニックを題材に撮った『精神』(2009年・日)です。
與那覇 たしか、斎藤さんの『「社会的うつ病」の治し方』にも登場した映画ですね。
斎藤 そうです。実はあの本で私が提案した「人薬(ひとぐすり)」という発想は、もともとこの映画に出てくる山本昌知医師が使っていた言葉を、お借りしたものなんです。
まず一番インパクトを受けたのは、この映画は精神病を扱っているのに、登場人物の顔にモザイクが入っていないことです。これは、撮る側と撮られる側との信頼関係がなければできないので、そうした実践ができただけでも価値あることですよね。
さらに、古民家のような建物で営まれているクリニックなこともあって、モザイクなしだと最初は映像を見ても、誰が医療スタッフで、誰が患者なのかがわからない。みんなが待合室代わりのお座敷でお茶を飲みながらだべっているシーンなど、完全に判別不能ですから、映画が進行するにつれて徐々に「あ、この人スタッフさんかと思ってたけど、患者さんなんだ」とわかってくる感じです。
與那覇 「治療者>患者」のような力関係が前面に出てこない、開かれた環境で対話が行われているというところは、対談本の終章で扱ったオープンダイアローグ(OD)にもちょっと似ていますね。そうした映像を見ることで自然と、映画の視聴者が「病気の人ってどうせ、こういう感じだろ?」といった先入見から自由になっていく。
斎藤 ええ。この映画がカメラに収めているのは、あくまでも通常のデイケアであってODではないのですが、同作を視聴する体験自体が「OD的なもの」だとは言えると思います。山本医師の診察の仕方も、それ自体は患者さんに対してふた言くらい、つぶやくだけで終わってしまう短いもの。しかし、いわゆる「三分間診療」みたいな冷たさはまったくなく、今週、先週、先々週……とずっと丁寧に関係を積み重ねてきたからこそ、そうした短い会話でも心が通じているんだなという、温かな連続性を感じさせます。
そういった山本医師の独特な人柄も「人薬」と言えますが、むしろ待合室=お座敷におけるn対nの相互交流も含めて、クリニックという場の全体で「人薬と呼ぶべきもの」が成立している。それを見る人にも追体験させてくれるんですね。
與那覇 ちょっと心配なのは、近年、自己啓発好きのビジネスパーソンのあいだで「コーチング」が流行っています。なので人薬と言うと「スティーブ・ジョブズを担当していたカリスマコーチのことね」のように誤解されそうな気がするのですが、斎藤さんがおっしゃるのは、これとは180度逆の発想ですよね?
斎藤 はい。コーチングというのはシステマティックなマニュアルと、「相談者を鼓舞して決断させる」といった既定の目標のもとに、役割を固定した1対1の関係で行われるものです。しかし映画『精神』が描き、私も参照している人薬とは、多様な立場の人々が上下関係ぬきで安心して語りあえる環境を用意したら、むしろあとは偶然に任せる。そこからn対n、かつ「どちらがどちらをサポートしているか」も曖昧で、しかし確実に参加者の健康を回復させる力が生まれてくる。
あらかじめ「あなたはもっとこうなるべきなんだ」といった目標を定めてしまうのではなく、この環境から何を得るかは「人それぞれ」でいいんだと割り切るところから、人薬は生まれてくる。自己啓発的な操作主義(=思いのままに心をコントロールしようとする発想)が見落としているものに、気づかせてくれるのが人薬だと考えるべきでしょうね。
與那覇 もちろん、私たちの本はビジネスパーソンの向上心自体を否定するものではありません。しかし「市場競争で生き残るには、ハイスペック人材になれ」といった操作主義的な昨今の風潮については、その問題点を検討し、異議申し立てをしています。
ネットで検索すると驚くのは、勉強中だと自認しつつ、コーチングを「してほしい」ではなく「させてほしい」という人が結構いること。つまり経済合理性に則して、人間を「コントロールしたい」という欲求が前面に出ているわけです。これは危うくないでしょうか。
斎藤 同感です。言い換えると、企業経営の現場に普及しているPDCAサイクル――定められた目標・計画に合わせてプロジェクトを動かしてゆく思考法が、ついに個人単位にまで及んできたのが、目下の自己啓発ブームとも言えます。
しかし『精神』が描く「こらーる岡山」は、山本医師にそのような作為や意図がまったくないからこそ、うまく行っているように見える。これはODもそうで、「さぁ、今日の対話では病人の状態をここまで改善させるぞ!」みたいな目標は設けないからこそ、当初の想定とは違ったきっかけで、患者の回復が起きると考えています。
與那覇 沖縄の精神科デイケアでの勤務体験を描いて、昨年話題になった東畑開人さんの『居るのはつらいよ』でも、心にまつわる施設をPDCA的に経営しようとすると、アジール(避難所)だったはずの場所がアサイラム(収容所)になってしまうと書かれていました。
斎藤 PDCAサイクルへの批判は、私たちの対談本の終章のモチーフでもありました。実は『精神』を撮った想田監督は「観察映画」という作風を掲げていて、撮影する対象に対して監督の側からはいっさい介入しないし、映像化にあたって自分の解釈も施さないんですね。だからこそ、「こらーる岡山」の人薬の効力を浮かび上がらせることができた。いわば映画自体が、「反PDCA的」に作られているとも言えます。
私は「ひきこもりシステム」と呼ぶことがありますが、たとえば治療者や家族が「何月何日までに社会復帰させる」といった目標を一方的に設定し、「定評のある治療法はぜんぶ試しただろう。なんでいまだに治らないんだ!」のように患者にあたってしまったら、まさにそうした扱い自体が原因になって、本人の心が砕け、ひきこもりが長期化してしまう。こうした悪循環から抜けるためにこそ、PDCAという発想を一度疑ってみることが大切なんです。この映画にはそうしたヒントが、どのシーンにも秘められていると思います。
(後編につづく)
斎藤環、與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』
【目次】
第1章 友達っていないといけないの? ――ヤンキー論争その後
第2章 家族ってそんなに大事なの? ――毒親ブームの副作用
第3章 お金で買えないものってあるの? ――SNSと承認ビジネス
第4章 夢をあきらめたら負け組なの? ――自己啓発本にだまされない
第5章 話でスベるのはイタいことなの? ――発達障害バブルの功罪
第6章 人間はAIに追い抜かれるの? ――ダメな未来像と教育の失敗
第7章 不快にさせたらセクハラなの? ――息苦しくない公正さを
第8章 辞めたら人生終わりなの? ――働きすぎの治し方
終章 結局、他人は他人なの? ――オープンダイアローグとコミュニズム
斎藤環「『対話』によって人間関係と自分自身を変えるための10冊」
與那覇潤「重い病気のあとで新しい人生をはじめるのに役立った10冊」
-

-
斎藤環
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
-

-
與那覇潤
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
この記事をシェアする
「斎藤環×與那覇潤『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』刊行記念特別企画」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 斎藤環
-
1961年、岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
-

- 與那覇潤
-
1979年、神奈川県生まれ。評論家(元・歴史学者)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。学者時代の専門は日本近現代史。地方公立大学准教授として教鞭をとった後、双極性障害にともなう重度のうつにより退職。2018年に自身の病気と離職の体験を綴った『知性は死なない』が話題となる。著書に『中国化する日本』、『日本人はなぜ存在するか』、『歴史なき時代に』、『平成史』ほか多数。2020年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環氏との共著)で第19回小林秀雄賞受賞。
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら