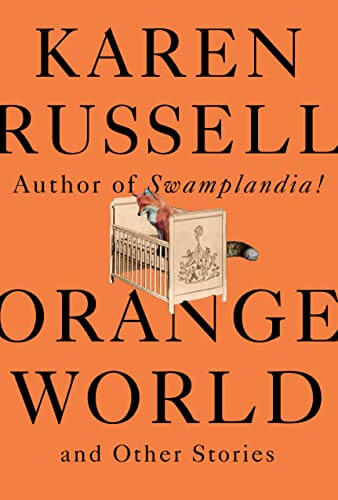(14)名文芸誌の最終号とカレン・ラッセルの新作
Tin House, Volume 20, Number 4, Summer 2019
Karen Russell, Orange World: and Other Stories (Knopf, 2019)
著者: 柴田元幸
僕がアメリカ現代文学を読みはじめた1990年ごろ、女性作家の、特に短篇小説に関してしばしば不満を感じたことを覚えている。
ひとことでいうと、誰もが「感性」で勝負しているように思えたのである。男女関係や親子関係が語られるなかで、繊細な「わたし」がどこかでかならず自己慰撫的に肯定されているような気がしたのだ。
もちろん、上等のユーモアが醸し出すトホホ感を通して自己慰撫を外からも見ているローリー・ムーアや、哲学や数学のバックグランドを活かした思索的な深さを持つレベッカ・ゴールドスタインのような例外もいることはいたが、大半の作家はうーん……と頭を抱えてしまった。もちろんこれは、いま思えば、僕の語学力・感受性(というかその欠如)の問題でもあったことは間違いない。何しろ当時は、アンとかアリスとか、Aで始まる女性作家の作品がみんな同じに思えてしまったのだから。
21世紀に入ったあたりから、そうした個人的にはあまり嬉しくない空気が大きく変わってきた。父が背負っている石のランドセルを娘が引き受ける、といった寓話的な設定が妙に切ないエイミー・ベンダー(『燃えるスカートの少女』管啓次郎訳、角川文庫)、アメリカの現実から降りて犬になった男の話や、心臓を母に提供することを強いられる男の話などから言いようのない息苦しさが伝わってくるジュディ・バドニッツ(『空中スキップ』岸本佐知子訳、マガジンハウス)、SF・ファンタジー・ホラーなどのジャンルを自在に行き来して独特の現実感をつくり出すケリー・リンク(『スペシャリストの帽子』金子ゆき子・佐田千織訳、ハヤカワ文庫FT)。それまでの感性重視のリアリズム文学とはうって変わって、みんな揃って現実と幻想とを仕切る垣根が低い人たちで、荒唐無稽な展開のなかから、いずれ――時には一行目から――切実さを生み出すところが素晴らしかった。
こうした流れのなかで、この10年くらいのあいだでもっとも印象に残る短篇を書いているアメリカの女性作家は、日本では松田青子さんが訳しているカレン・ラッセルだと思う。日本の『女工哀史』を踏まえた、女工たちが自分の体から繭を分泌するようになる「お国のための糸繰り」(『レモン畑の吸血鬼』河出書房新社 収録)などが代表作で、入念なリサーチに支えられたリアリスティックな細部から出発して、読者の信じやすさをギリギリまで試すような展開を導入し、本物の共感、恍惚、恐怖を生み出す手際は見事としか言いようがない。
さて、オレゴン州ポートランドに拠点を持つ名文芸誌Tin Houseの分厚い20周年記念号には、エイミー・ベンダー、ケリー・リンク、カレン・ラッセル3人をはじめとして9人の女性作家の短篇が掲載され、男性による短篇2本をはるかに凌ぎ、圧倒的に女性優位の一冊になっていて、むろん数だけでなく内容的にも読みごたえがある。
ケリー・リンクの“The Girl Who Did Not Know Fear”(恐れを知らなかった女の子)は、いつまで経っても飛ばない飛行機を待ってはてしなく空港にとどまる女性の話。いかにも「あるある感」に満ちた設定だが、次第に生じてくる得体の知れない薄気味悪さは、ありがちの設定だけからは出てこない。
エイミー・ベンダーの“Blame”(非難)は、子供を作ろうとしている女性を主人公に、「喋る胎児の死体」という奇想から始めて、逆に小学生のころの、紙の人形を体内に入れてみた記憶を経て、現在におけるドーナツショップの店員との会話、と逆にリアリズムの方に横滑りしていく。主人公のことを、現実から遊離した金持ちのご婦人と決めつけようとする店員との会話の落着かなさ、ぎこちなさが独特の生々しさを生んでいるのか、逆に非現実感につながっているのか、よくわからない感じが面白い。
が、ここでも一番強烈な印象を残すのは、カレン・ラッセルの“The Gondoliers”(ゴンドラ船頭たち)だろう。なかば水に埋もれた「ニュー・フロリダ」に生きる、ゴンドラ船頭四姉妹の末っ子が主人公であり、タイトルにも示唆されているとおり、あたかもフロリダが第二のヴェネチアになったかのような世界には、終末的な空気が色濃く漂っている。
Our regulars suspect there’s more to our nasally singing than we let on. For sure they know it’s not Italian. “Lady, can I please pay you to shut up?” tourists have begged me. I used to think that we were very special, the best boatwomen in the world, but Viola says no, we are only vessels ourselves: something wants to be born. Perhaps there are many others like us around the bays of New Florida and elsewhere. Women who know enough to be silent about what is developing inside their bodies.
This sensitivity grew in us softly, softly. I can only compare it to seeing in the dark. We sing, and shapes tighten out of an interior darkness. Edges and densities. Objects sing back at us: Turn hard left to avoid the fallen tree. Pole southwest to miss the gluey hill of floating garbage. Pillars thin as lampposts push fuzzily into our minds; a heartbeat later they rear out of the bay, fatally real.
Our mother could not echolocate, according to my sisters. When I was a child, I found this frightening and sad. Imagine seeing a thousand colors streaking the sky and realizing that your mother saw only one unbroken gray. But Viola says our mother could hear us crying from impressive distances, and now I wonder if she had some precursor of this ability.
常連客たちは、あたしたちの鼻声の歌に、あたしたちが装っている以上の意味があると疑っている。どう聴いたってイタリア語とは思えないのだ。「なあ、金払うから黙ってくれないかな?」と観光客たちにもよく言われる。あたしたちはすごく特別なんだ、世界最高のゴンドラ漕ぎなんだとあたしは以前思っていたけど、そんなことない、あたしたち自身もただの乗り物なんだよとヴィオラは言う。何かが生まれたがっているんだよ、と。ひょっとするとニューフロリダのあちこちの湾にも、そのほかの場所にも、あたしたちみたいな人間がいっぱいいるのかもしれない。自分たちの体のなかで起きていることについて、余計なことを言わずにいる女たち。
この感度は、あたしたちのなかでそっと、そうっと育ってきた。喩えられるものがあるとしたら、闇のなかで見る力だ。あたしたちは歌い、内なる闇のなかから形が固まってくる。縁の線や、濃密さ。物たちがあたしたちに歌を返す。ぐいっと左に曲がって倒木を避けなよ。南西に棹を操って、浮いてるゴミのべとべとの山を外しなよ。街灯柱みたいに細い柱が、頭のなかにぼんやり押し入ってきて、一拍あとに柱が湾のなかから、命取りのリアルさでぬっと姿を現わす。
あたしたちの母さんは、姉さんたちが言うには、音で物の位置を知ることができなかったらしい。子供のころあたしは、それって悲しいし怖いって思った。空に無数の色の帯が走ってるのを見ても、自分の母親にはとぎれなしの灰色しか見えてない、みたいな感じ。でもヴィオラが言うには、母さんはあたしたちの声が、ものすごく遠くから聞こえたそうだ。とすると、あたしたちの能力の、前ぶれみたいなものは持ってたのかな、といまのあたしは思う。
四姉妹の能力が、崩壊しかけた世界でどこまで役に立つのか。この能力が、いかなる黙示録的世界に彼女たちを連れていくのか……いずれ出るであろう邦訳をお楽しみに。
“The Gondoliers”がTin Houseに載ったのとほぼ同時に、この作品も含めたカレン・ラッセルの第三短篇集が刊行された。前2作の短篇集(『狼少女たちの聖ルーシー寮』『レモン畑の吸血鬼』)も素晴らしかったし、基本的に短篇で勝負している、かつ注目度大の書き手だから、新作に対するプレッシャーはものすごいと思うが、今回の一冊も見事である。特に、途方もない設定に下手に理屈をつけたりせず、私にはこの話のリアリティが信じられるんだから読者も信じてくれる!と確信しているというか読者を信頼しているというか、その度合いがすごい。たとえば“A Romance”(あるロマンス)とわざわざ副題をつけた“Bog Girl”(沼地の女の子)は、化石のように千年だか二千年だか沼地に埋もれていた女の子に恋をして、片時も彼女のそばを離れない男の子の話。発掘された死体はなぜか溶けたりもしないで美しさを保っている! そのほかにも、木の霊が若いカップルの女の子のなかに棲みつく話(“The Bad Graft”〔悪しき接ぎ木〕)、竜巻を育てて売る時代遅れの商売にしがみつく中年男の話(“The Tornado Auction”〔竜巻競売〕)、赤ん坊を護るため悪魔に乳を与えつづける若い母親をめぐる表題作(“Orange World”〔オレンジ色の世界〕)など、どの作品もそれ自体の荒唐無稽さと切実さが見事に両立している。どれも言葉の魔法に支えられた、およそ映像化不可能な作品ばかりである。
Tin Houseに話を戻すと、男女別の短篇数が何しろ2-9なのだが(詩・エッセイに関してはほぼ半々)、その「2」というのが、『すべての見えない光』(藤井光訳、新潮社)でも知られるアンソニー・ドーアと、『突然ノックの音が』(母袋夏生訳)『あの素晴らしき七年』(秋元孝文訳、いずれも新潮社)で知られるエトガル・ケレットなので、大いに期待を持たせるのだが、これがいささか当てはずれ。ドーアの短篇は、父・母・娘の家庭の危機が、アル中の母を切り捨てることで解消される、というのはさすがに安易じゃないか。ケレットは笑いと切なさが同居するのが持ち味の書き手だが、今回は笑いのみ。まあどちらの作家にも、それだけ多くを期待してしまうということなのだろうが。
リンク、ベンダー、ラッセル以外の女性作家作品もそれぞれ面白かったが、一番びっくりしたのは、今回作品が初めて活字になったというブリジェット・チャオ・クラーキンの「深海巨大症」(Bridget Chiao Clerkin, “Abyssal Gigantism”)。深海で人間が“sea monk”(科学的に言えば「モンクアザラシ」だが、文字どおり読めば「海の修道士」)によって改宗させられたらしいので科学者とバチカン教会の遣いが深海に送り出される、という何とも阿呆な設定から話は始まり、じきに出てくるこんな一節が典型的な語り口である。
Saliha was one of the three scientists on board, the other two being Maria and Natasha. Add Trevor, who had introduced himself as the team coordinator, and Ruby, and you had five, a small team considering the ambitious size of the lab: most of the solicited institutions hadn't been able to get past “sea monks.” Collectively Saliha, Maria, and Natasha held four doctorates, which meant somebody had more than one. They had never worked together or even been at the same institutions, yet seemed to know all the same people: Maria knew Natasha's advisor’s advisor, Natasha as an undergrad had lived on the same floor as Saliha’s advisor’s daughter, and Saliha was friends with the editor of a journal Maria and Natasha had each contributed to in the past. When they realized they had all signed the same open letter in the New York Times, a comradery beyond professional obligations was sealed. Natasha had just finished a postdoc and specialized in marine snow; Saliha worked for some big think tank that was often cited on NPR when statistics concerning large groups of people were called for; and Maria was at a well-known East Coast university and spent her summers in Venezuela doing something Ruby hadn’t quite caught. They had consented to swallow “sea monks” because the submarine would grant them unprecedented access to the parts of the ocean they specialized in.
サリーハは乗船した科学者三人の一人で、残り二人はマリーアとナターシャといった。これに、チームコーディネータと名のったトレヴァーと、ルビーを加えれば五人となる。実験の壮大さからすれば小さなチームだが、援助を仰いだ組織の大半が、「海の修道士」というところで引っかかってしまったのである。サリーハ、マリーア、ナターシャの三人が合わさって四つの博士号を所有していて、ということはつまり誰かが複数持っていることになる。彼女たちはこれまで一度も一緒に仕事をしたことはないし、同じ組織に所属したこともないが、みんな同じ人たちを知っているようだった。マリーアはナターシャの指導教官の指導教官を知っていて、ナターシャは学部生のころサリーハの指導教官の娘と同じ階に住んでいたし、サリーハはマリーアとナターシャがそれぞれ過去に論文を掲載した学術誌の編集長と友人だった。三人とも『ニューヨーク・タイムズ』宛の同じ公開書簡に署名したことが判明すると、職業的義務を超えた仲間意識が芽生えた。ナターシャはポスドクを終えたばかりで、海雪が専門だった。サリーハは大人数のグループに関する統計的数字が必要になるとNPR〔全米公共ラジオ〕がよく引き合いに出す巨大シンクタンクに勤めていて、マリーアは有名な東海岸の大学に所属し、夏はいつもベネズエラで、ルビーにはいまひとつ聞きとれなかった何かをやっているということだった。彼女たちは「海の修道士」については不問に付すことに決めていた。この潜水艦に乗れば、自分たちが専門にしている深海に対する前代未聞のアクセスが得られるのだから。
が、ここから切実さをめざすというよりは、いくぶん衒学的なホラ話の雰囲気を残したまますべてが進行していくところが、かえって新鮮で面白い。個人的には非常に好みの書き方で、今後が楽しみな人である。テネシー州チャタヌガ在住とのこと。
さて、この大充実のTin House2019年夏号、とても残念なことに、20周年記念号でもあると同時に終刊号なのである。McSweeney’sのように毎回判型を変えたり、Zoetropeのように毎回ゲストデザイナーを迎えたり、といった派手さはないものの、作品の充実度からすれば間違いなく全米一の文芸誌だっただけに、終刊は本当に残念。でもまあなくなったことを嘆くより、この雑誌が20年間あったことを祝福&感謝したいと思う。Thanks!
-
Tin House, Volume 20, Number 4, Summer 2019
-
Karen Russell, Orange World: and Other Stories (Knopf, 2019)
最新情報
9月14日(土)午後11時~12時、J-WaveのRadio Switchに出演(ナサニエル・ホーソーンの作品朗読)。9月21日(土)午後6時~、リーバイス®︎原宿フラッグシップストアでSwitch Vol. 37 No. 9刊行イベント(詩中心の朗読)。要予約、参加費無料(http://www.switch-pub.co.jp/switch-levis-special-event/)。「波」9月号にバリー・ユアグロー連載「オヤジギャグの華」第5回「ラヲタと先生」掲載。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら