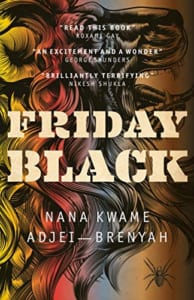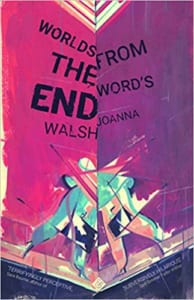(16)外の現実を増幅するか、一から現実を組み立てるか――対照的な短篇集2冊
Nana Kwame Adjei-Brenyah, Friday Black (Mariner Books, 2018)
Joanna Walsh, Worlds from the Word’s End (And Other Stories, 2017)
著者: 柴田元幸
Fela, the headless girl, walked toward Emmanuel. Her neck jagged with rich savagery. She was silent, but he could feel her waiting for him to do something, anything.
Then his phone rang, and he woke up.
He took a deep breath and set the Blackness in his voice down to a 1.5 on a 10-point scale.(Nana Kwame Adjei-Brenyah, “The Finkelstein 5”)
フェラが、首のない女の子が、エマニュエルの方に歩いてきた。首筋は華々しく凶暴にギザギザ。女の子は何も言わなかったが、彼が何かをするのを、何でもいいから何かするのを待っているのが感じられた。
と、電話が鳴って、目が覚めた。
大きく息を吸って、自分の声の黒人指数を10段階で1.5に据えた。(「ザ・フィンケルスティーン・5」)
つねに自分の「黒人指数」を意識して生きていかないといけない職探し中の若者。指数が8.0まで上がると、バスの中でも周りの乗客が離れていく。これから仕事の面接――何とか4.2まで落とさないと。
いま彼の頭にあるのは、武器を持たない5人の黒人の子供が、中年の白人男性に次々チェーンソーで首を斬られて殺された事件のこと。自分の子供2人と自分自身を守るための正当防衛だったと男は主張し、主張は認められ男は無罪となる。フィンケルスティーン図書館の外で起きたこの事件の犠牲者たちは「ザ・フィンケルスティーン・5」と呼ばれ、全米で抗議の声が上がる。「5」の中でも一番幼かった女の子(7歳)が、こうして主人公エマニュエルの夢の中にまで出てきて、何かをすることを求めている――do something, anything。
そんなある日、街でばったり会った小学校の同級生が、報復グループを組織しようとしていることをエマニュエルは知る。ザ・フィンケルスティーン・5の5人の名をくり返し唱えながら、白人を殺すのだ。こうして、すでに結果は読者も知る裁判の進行と、グループが公園で白人カップルを殺そうとするシーンとが交互に語られる。その積み重ねの迫力、展開の意外性はすさまじく、とうてい短い引用ではそのすごさは正当に伝えられない。
この短篇は明らかに、2012年2月にフロリダで起きた、丸腰の黒人の高校生を「正当防衛」で射殺した白人男性が無罪となったトレイボン・マーティン射殺事件を踏まえている。実際、当時大学生だった著者アジェイ=ブレニヤーも、裁判の判決に抗議するチラシを作ったとインタビューで述べている。とはいえこの短篇では、出来事の暴力性は二段階くらい増幅されている。友だち4人を殺されて逃げまどう7歳の女の子を追いかけてチェーンソーで首を斬った男が、いくら何でも無罪にはならないだろう……か?
リアリズムを一段階押し上げると戯画になる。だがこうやって二段階押し上げると、まるっきり絵空事からかえって独自のリアリティが生まれる。そういう魔法をこの書き手は使えるように思える。
この「ザ・フィンケルスティーン・5」が作品集の冒頭に置かれ、その後、表題作の“Friday Black”ではショッピングモールでのバーゲンに客が殺到して流血の混乱が生じるが、店の側はそれを予想して初めから死体置き場を設置している。“Zimmer Land”で、不審な侵入者を殺して家族の安全を守ったというファンタジーに男たちがひたれるテーマパークが「ジマー・ランド」と名づけられているのは、上述のトレイボン・マーティンを射殺したジョージ・ジマーマンへの言及である。あるいはまた、患者のほとんどが死にかけている病院で、やはり死にかけた父親を抱えた若者が「お前らみんな、助かったぞ! みんな家に帰れ!」と叫び、生命維持装置も外しもろもろのチューブも引きちぎった患者たちが出てくるが……という“The Hospital Where”。いずれも、現実の暴力性は最低二段階押し上げられている。それを支えるテンションの高い文章も素晴らしい。
僕はいまごろ発見して驚いているが、本が出たのは去年のことで、本国ではむろん、日本でも、藤井光氏をはじめとしていろんな人がすでに話題にしていて、知らなかったのは僕だけみたいなのだが、すごい本であることは間違いないので、「いまさら感」も顧みず紹介する次第である。
……ただ、冒頭の「ザ・フィンケルスティーン・5」が内容も文章のボルテージもあまりに衝撃的なので、その後の11作を正当に読むのが難しいのが、難といえば難。
It’s time.
I have lined them up, the two of them, holding hands. Not that they need to be lined up as they are already pressed side by side in a way I have never been able to do anything about but it seems, at this moment, as if I have arranged them in this way quite deliberately, and that they stand here, exactly as I would wish they would, through some act of volition.(Joanna Walsh, “Two”)
時間だ。
わたしはかれらを、二人を、並べて手をつながせた。実のところ並べる必要があるわけではなく、もうすでにかれらは、わたしにはできたためしのないくらいぴったり横にくっついているのだが、なぜかこの瞬間、このわたしがきわめて意図的にこういうふうにかれらを配置したかのように思えるのであり、かれらはここに、なんらかの意志的行為によって、まさにわたしが望むとおりの姿で立っているようなのだ。(「二人」)
ナナ・クワミ・アジェイ゠ブレニヤーの諸短篇の一行一行から、現実のアメリカの一面が増幅されて立ち上がってくるように思えるのに対し、イギリス人作家ジョアンナ・ウォルシュの短篇集Worlds from the Word’s End(言葉の終わりから来たさまざまな世界)では、あたかも何もない空間に書き手が人や物を一から出現させていくように思える。話題は本棚だったり、ホテルだったり、二人の秘書だったり、駅に住みつくことだったり、べつに超自然的なことは何も出てこないのだが、ごく日常的なことが語られているときでさえ、小説外の現実から現実感をいっさい借用していないかのような、独特のスカスカ感が漂う。
K ordered a new office machine. It was put beside my desk. As its wrapping was removed the smell of plastic hit the whole office. It is an old-fashioned office: the machine is the only modern thing in it. It is pearl grey: a whale of a thing. K switched it on and it started to whirr. I began to cough quite loudly like this: ‘eheugh, eheugh!’ These were real coughs but I made them even louder to show how bad the smell was. The smell the machine produced was so different to everything else in the building, which is made of paper and wood, that it made me feel sick, and so I went and stood in the hall to breathe the fresh air. K said, how long are you going to keep on doing that? And I said, Until the smell goes away. I will come back every time I have to answer the phone (this is one of my duties). K said nothing.
(“Two Secretaries”)
Kは新しいオフィス機器を注文した。機器は私の机の横に置かれた。包装が解かれると、プラスチックの臭いがオフィスじゅうに広がった。ここは古風なオフィスで、この機械はそのなかで唯一現代的な品だ。パールグレーで、とてつもなく大きい。Kがスイッチを入れると、機械はブーンとうなり出した。私はすごく大きく、こんなふうに咳をしはじめた――「エヒュー、エヒュー!」。これは本物の咳だったが、臭いがいかにひどいかを示そうとさらに大きくした。機械から出た臭いは、紙と木で出来た建物の中のほかの何とも全然違っていたので、私は気分が悪くなってきて、新鮮な空気を吸おうと廊下に出ていった。Kが、あんたいつまでそんなことしてるつもり? と言った。そして私は、臭いがなくなるまで。電話がかかってくるたびに戻るわよ(これは私の仕事なのだ)と言った。Kは何も言わなかった。
(「二人の秘書」)
ストーリー、といってもあるようなないような感じなのだが、幼い女の子が中年男を誘拐し、家に連れて帰って、男はそのまま家に何十年も居つく、という“Enzo Ponza”などは展開としても面白かった。最初の何篇かはいささか面喰らうが、読み進めていくうちに、作者がつねにゼロから言葉で世界を組み立てていくのに立ち会うのがどんどん快くなっていく。『フライデー・ブラック』と『言葉の終わりから来たさまざまな世界』、まったく対照的な2冊だが、どちらかに軍配を上げる必要はむろんまったくなく、こういうのが両方あるのはまことに悦ばしいことである。
-
Nana Kwame Adjei-Brenyah, Friday Black (Mariner Books, 2018)
-
Joanna Walsh, Worlds from the Word’s End (And Other Stories, 2017)
最新情報
11月4日(月)午後6時~7時30分、青山ブックセンター本店で『「ハックルベリー・フィンの冒けん」をめぐる冒けん』(研究社) 刊行記念トークイベント「ハック・フィンと柴田元幸の冒けんふたたび」。
11月6日(水)午後7時~9時、下北沢B&Bで浜田和範さんとフェリスベルト・エルナンデス『案内係』(水声社)刊行記念イベント「フェリスベルト・エルナンデスへの案内係」。
11月9日(土)午後6時半~、神戸市六甲の喫茶 月森で朗読会「少年少女」。
11月10日(日)午後1時~2時30分、芦屋の朝日カルチャーセンターで講演「J・D・サリンジャーの声」。
11月13日(水)午後7時~8時30分、江戸川区立葛西図書館でトーク&朗読イベント「世界文学を愉しもう Vol. 9 魔法」。
11月14日(木)午後7時半~、吉祥寺キチムでマヒトゥ・ザ・ピーポーさんと朗読・音楽イベント「革命のための黄土色の赤ん坊たち」。
11月23日(土)夕方、東急文化村B1の書店「ナディッフ モダン」で小沼純一さんと、小沼さん著『本を弾く』(東京大学出版会)刊行記念イベント(詳細未定)。
11月27日(水)午後7時~、青山ブックセンター本店で濱中利信さん、田中優子さん(河出書房新社編集部)と<エドワード・ゴーリーの優雅な秘密>展覧会閉会記念イベント(詳細未定)。
11月28日(木)午後6時15分~8時40分、国際シンポジウム「村上春樹と国際文学」第2部パネルディスカッション「村上春樹と『翻訳』」(川上未映子、マイケル・エメリック、辛島デイヴィッド)司会。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら