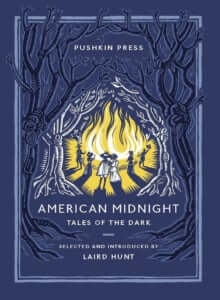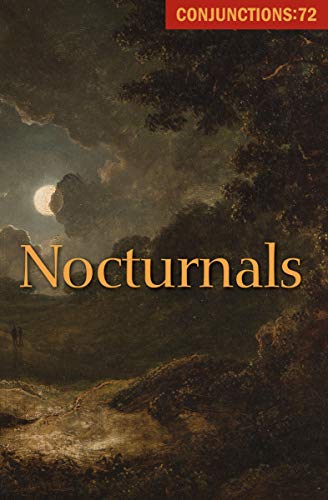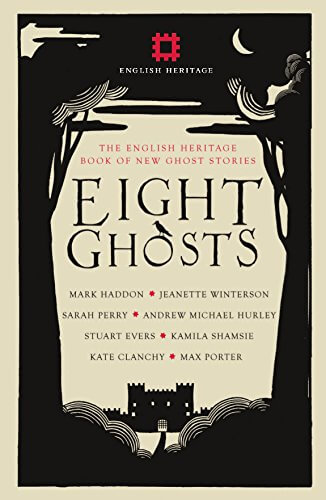(23)人格者の選んだ怪奇譚集
American Midnight: Tales of the Dark, selected and introduced by Laird Hunt (Pushkin Press, 2019)
Conjunctions, 72: Nocturnals (2019)
Rowan Routh, ed., Eight Ghosts: The English Heritage Book of New Ghost Stories (September Publishing, 2017)
著者: 柴田元幸
レアード・ハントは内容的にも文体的にもいまアメリカでもっとも興味深い作家の一人である。彼の最新作In the House in the Dark of the Woodsについてはこの連載の第5回で紹介したが、この本のイギリス版がPushkin Pressから出たと知ったときは、おお!と思ったものである。プーシキンというくらいだから、当然のごとくロシア文学のラインナップが充実している出版社なのだが、昨今は日本文学の出版にも力を入れている。古川日出男『二〇〇二年のスロウ・ボート』、柴崎友香『春の庭』、川上未映子『ミス・アイスサンドイッチ』などの英訳を出していて、しかもDavid Boyd, Polly Bartonといった最良の若手日本文学英訳者を起用している。個人的に勝手に親近感を持っている出版社なので、レアードの本を出したのを見つけて喜んだわけである。
そのプーシキン・プレスから、今度はレアード・ハントが作品を選んだアンソロジーが出た。題して『アメリカン・ミッドナイト』、サブタイトルは「闇の物語集」。これが非常に充実した怪奇小説アンソロジーである。そのラインナップは――
レアード・ハント 序文
エドガー・アラン・ポー「赤死病の仮面」(“The Masque of the Red Death”)
ナサニエル・ホーソーン「若いグッドマン・ブラウン」(“Young Goodman Brown”)
イーディス・ウォートン「目」(“The Eyes,” 別邦題「邪眼」)
ロバート・W・チェンバーズ「仮面」(“The Mask”)
シャーリイ・ジャクスン「家」(“Home”)
マーク・トウェイン「怪談」(“A Ghost Story,” 邦題「幽霊」)
ゾラ・ニール・ハーストン「スパンク」(“Spunk”)
シャーロット・パーキンズ・ギルマン「黄色い壁紙」(“The Yellow Wallpaper”)
エマ・フランシス・ドーソン “An Itinerant House”(未訳)
なかなか見事なセレクションである。まず一方で、アメリカ的な闇の物語の定番的作品がいくつか入っている。ポーによる怪奇小説といえば、「アッシャー家の崩壊」か「赤死病の仮面」のどちらかが選ばれることが多く、怖さが累積的に積み重ねられる効果を採るなら「アッシャー」、構成の緊密さを採るなら「赤死病」ということになるだろうか(僕自身、『アメリカン・マスターピース 古典篇』と題したアンソロジーを編んだときに、ポー作品を「モルグ街の殺人」にするか「赤死病の仮面」にするか最後まで迷った)。ホーソーンも、短篇全般ということでいえば、ボルヘスがカフカの先達と見た、都市に生きる人間の無名性をいち早く描いた「ウェイクフィールド」が選ばれがちだが、「怪奇」というテーマに限るなら、それがホーソーンの重要テーマであるピューリタン的罪の意識に直結した「若いグッドマン・ブラウン」が有力だろう。ギルマンの「黄色い壁紙」は、夫によって(そしてその背後に控えている男性中心の社会全体によって)自由と創造性を奪われた女性が陥る狂気を描き、1892年に刊行された当時は冷淡な反応も多かったが、フェミニズム批評が始まって以来、ほとんど聖典のような地位を獲得している。
こういう「王道」をしっかり外さないレアードの姿勢を目にして、思い出すのは自分が10年くらい前に演じた醜態である。ニューヨークへ行って、ポール・オースター夫妻、レアード・ハントとともに詩人の故ウィリアム・コーベットの自宅に招かれたときのこと。ポールとシリ・ハストヴェット、ビルとその妻ベヴァリーが大人で、僕と妻とレアードはまだほんの子供という感じの、圧倒されっぱなしの一晩が済んだあと、レアードと一緒に乗った帰りのタクシーのなかで、僕がヘミングウェイの短篇のなかでも最高の評価を得ている「心臓の二つある大きな川」について、敬意は抱くけれど万事巧みに書かれすぎていまひとつ好きにはなれない、みたいなことを言うと、レアードはけっこう驚いた顔をして、うーん僕はあの作品素晴らしいと思うけどなあ、と遠慮がちに言い、こっちはなおも酔っ払った勢いで(と、酔いのせいにしちゃいけませんが)いやいや、ああいう何もかもかっちりコントロールできている作品よりむしろ、どう続けていいかわからず未完に終わった「最後の原野」みたいな方がヘミングウェイはいいのぢゃぁ、みたいなことを断言し、翌朝思い返してみて、現代アメリカ文学屈指の作家相手にワタシはなんと偉そうな物言いをしたことか、と我ながら呆れ、少し恥じたのだった。だいたい僕は昔から、「王道」からちょっと外れたものをやたら持ち上げたがる癖がある。10代のころも、ロック聴くならビートルズやストーンズじゃなくてキンクスやバーズだぜ、みたいなことを言っていた。いまだにそういう性癖が抜けていないが、ひとごととして外から見ると、これはかなり馬鹿らしい趣味だと思う。最高のものにがっちり正面から取り組む機会をみすみす捨てるだけである。で、レアード・ハントにはそういう阿呆なところはない……ということを『アメリカン・ミッドナイト』の「王道」としっかり向きあったラインナップを見てあらためて感じたのである。幸い、人格者のレアードは僕の阿呆ぶりも許容し、その後も親しく接してくれている。
なのでこのアンソロジーについても、個人的に裏話を聞かせてもらった。それがこの紹介の第二のポイントである。王道を外さない一方で、9人中女性作家が5人(ウォートン、ジャクスン、ハーストン、ギルマン、ドーソン)というのは特筆に値する。たぶんこれまでのアメリカ怪奇小説アンソロジーだったら、女性の数は0か1だっただろう。本人もそこはすごく意識したそうで、出版社としては著作権料が発生する作家は避けたがり、ジャクスンとハーストンについては渋ったそうだが(小さな出版社が頑張ってやっているのだからそれはそれで理解できる)、無理を言ってこの2女性作家も入れてもらったとのこと。5人も入っているので、質には目をつぶって政治的正しさを重視したのだろうか、などと邪推してしまいたくなるが、読んでみるとそんなことはなく、ちゃんと質的にも粒ぞろいなのがさすがはレアード。ウォートンの「目」は目だけ出る幽霊、という奇想よりも、自分の言動が人をどう傷つけるかまったく見えていない男に対する皮肉が効いているし(まあ人のことは言えませんが)、ハーストンの「スパンク」は弱い者(だった男の幽霊)の復讐が爽快なんだか陰湿なんだかわからないのが味だし、“An Itinerant House”は怪談そっちのけで衒学に走るところがかえって不気味である。が、今回最大の収穫はジャクスンの「家」だった。しばらく前に出版された、邦訳ももう出ている作品集に入っていたのだから(『なんでもない一日――シャーリイ・ジャクスン短編集』1998、邦訳2015、市田泉訳)、いままで知らなかったのが迂闊なのだが、とにかく面白かった。雨のなかに立っている老婆と子供の幽霊、という設定で、特に凝ったことはやっていないのに、滑稽で皮肉っぽい話(田舎のことを何でもわかっているつもりの都会人をからかっている)がだんだん恐怖に転じていくところが――それをこの書き手らしくごく平易な言葉でやってのけるところが――見事。オンライン朗読会に何か新しい作品が必要だからという口実のもと、自分でもさっそく訳して作品のよさを満喫した。
怪奇小説、恐怖小説というのは累積が大事なので、一部だけ引用してもあまり意味がないことが多い。なのでここでは、累積が始まる瞬間の雰囲気を伝えるために、各作品の最初のセンテンスを紹介しておこう。
The “Red Death” had long devastated the country.
Edgar Allan Poe, “The Masque of the Red Death”
「赤死病」が、赤い死が、長いあいだ国を荒らしていた。
エドガー・アラン・ポー「赤死病の仮面」
Young Goodman Brown came forth at sunset into the street at Salem village; but put his head back, after crossing the threshold, to exchange a parting kiss with his young wife.
Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown”
若いグッドマン・ブラウンは日没どきにセーレムの村の街路に出てきたが、家と道の境をまたいだあとに、うしろに向きなおり、若い妻と別れのキスを交わした。
ナサニエル・ホーソーン「若いグッドマン・ブラウン」
We had been put in the mood for ghosts, that evening, after an excellent dinner at our old friend Culwin’s, by a tale of Fred Murchard’s—the narrative of a strange personal visitation.
Edith Wharton, “The Eyes”
その晩私たちは、昔からの友人カルウィンの家で素晴らしいディナーを共にしたのち、フレッド・マーチャードの語った、奇妙な個人的「訪れ」の話によって、幽霊の気分になっていたのだった。
イーディス・ウォートン「目」
Although I knew nothing of chemistry, I listened fascinated.
Robert W. Chambers, “The Mask”
私は化学については何も知らないが、魅了されて聴いていた。
ロバート・W・チェンバーズ「仮面」
Ethel Sloane was whistling to herself as she got out of her car and splashed across the sidewalk to the doorway of the hardware store.
Shirley Jackson, “Home”
エセル・スローンは一人口笛を吹きながら車から降り、ばしゃばしゃ水を撥ね上げ歩道を横切って、金物屋の入口まで行った。
シャーリィ・ジャクスン「家」
I took a large room, far up Broadway, in a huge old building whose upper stories had been wholly unoccupied for years until I came.
Mark Twain, “A Ghost Story”
私はブロードウェイのずっと上の方にある巨大な古い建物に大きな部屋をとった。上の方の階は、私が来るまで、何年もまったく使われていなかった。
マーク・トウェイン「怪談」
A giant of brown-skinned man sauntered up the one street of the Village and out into the palmetto thickets with a small pretty woman clinging lovingly to his arm.
Zora Neale Hurston, “Spunk”
巨体の、茶色い肌をした男が、村で一本しかない通りに悠然と出てきて、パルメットヤシの茂みの中へ、その腕に愛おしげにしがみつく小柄の綺麗な女と一緒に入っていった。
ゾラ・ニール・ハーストン「スパンク」
It is very seldom that mere ordinary people like John and myself secure ancestral halls for the summer.
Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper”
ジョンや私みたいにごく普通の人間が、先祖代々続くお屋敷を夏のあいだ確保できるなんて、すごく珍しいことなのだ。
シャーロット・パーキンズ・ギルマン「黄色い壁紙」
“His wife?” cried Felipa.
Emma Frances Dawson, “An Itinerant House”
「あの人の奥さんですって?」とフェリーパが叫んだ。
エマ・フランシス・ドーソン「彷徨う家」
部屋、屋敷から始まるのが多いのは、やはり王道的怪奇小説集だからだろうか。「『あの人の奥さんですって?』とフェリーパが叫んだ」という「彷徨う家」の書き出しは、「あの人」と「フェリーパ」はどういう関係なのかという謎がさりげなく投げ出されていて面白い。夕食後の(おそらくは暖炉を囲んでの)幽霊ばなし、という点が強調されている「目」は、1910年の作品ながら、もうかなり幽霊ばなしがメタ化している(幽霊ばなしをめぐる話になっている)ように思える。
だとすれば現代の幽霊ばなしはどうなるんだろう、と思って実験小説のメッカ的雑誌Conjunctionsが去年出した“Nocturnals”(夜景集)特集号を覗いてみると、たとえばリック・ムーディの「片目のジャック」(Rick Moody, “One-Eyed Jack”)は、家に取り憑いている幽霊の話、という設定は超正統でも、その幽霊に向かって語り手が、君はいったいこの世で何をやり残したんだい、それとも何かいまだにすごく後悔しているようなことをやってしまったのかい、同情してあげるべき人間を切り捨ててしまったのかい、自分のために他人を踏み台にしたのかい、中学校で誰か友だちの悪口を言ってでもあとで実はその子が好きだったと悟ったのかい……等々、出没する理由として考えられるシナリオを語り手がえんえん2ページ近く並べてみせる。あるいはジョイス・キャロル・オーツの「夜哀」(Joyce Carol Oates, “Nightgrief”)では、夫婦が何かひどく悲しい体験をしたらしいのだが(作者の造語であるタイトルからもそれは窺える)、それについてはいっさい語らずに、彼らがまさに闇の生活に浸っていく(昼寝て、夜起き、極力光を避ける)さまをコミカルに、あるいはそれを通り越してグロテスクに描く。ムーディ、オーツ、という二人のベテラン作家がとにかく過剰に走って達者な芸を見せつけるが、さすがと思う反面、現代作家は大変だなあ、でもまあアメリカは何と言っても「過剰」が持ち味だものなあ、などとやや「気づかい」的な感慨も勝手に感じてしまった。
そういえば同じ英語圏でも、イギリスの現代作家たちが集まって新しい幽霊ばなしを書いたEight Ghosts: The English Heritage Book of New Ghost Stories(8人の幽霊――「英国の遺産」新作怪談集)などは逆に、英国流怪談の長い伝統を屈託なく活用して、マーク・ハッドン(『夜中に犬に起こった奇妙な事件』)、ジャネット・ウィンターソン(『オレンジだけが果物じゃない』)、マックス・ポーター(邦訳はまだないが近年大きく注目されている書き手)といった人気作家たちがそれぞれちゃんと新味のある作品を書いている。もちろん面白く読めるのだが、これはこれで「そこまで余裕持つなよ」と言いたい気が、ほんの少しだけ生じたりもする。
やっぱり怪奇小説は昔の方がいいのかな、と単純化したくなるが、あらためてレアード・ハントによる『アメリカン・ミッドナイト』の序文を読んでみると、ジョーダン・ピールの意欲的な怪奇映画『ゲット・アウト』とマーク・トウェインの「怪談」のつながりが指摘されている。「そのホラーと織り合わされた何層ものユーモア」が共通しているというのだ。たしかに、ピール監督もトウェインも、本気でホラーをやろうとしているんだか、ホラーのアイテムを過剰に並べてホラーのパロディをやろうとしているんだか、よくわからないところがミソである。そういえばずっと前に、Walter Kendrick, Thrills of Fear: 250 Years of Scary Entertainment (1991) という怪談史を読んで、紹介されている作品の8割方は笑ってしまう内容だったことを思い出した。怖い話が笑ってしまう話に反転するか、しないか……そのあたりがどうやら一番面白そうだ。
-
American Midnight: Tales of the Dark, selected and introduced by Laird Hunt (Pushkin Press, 2019)
-
Conjunctions, 72: Nocturnals (2019)
-
Rowan Routh, ed., Eight Ghosts: The English Heritage Book of New Ghost Stories (September Publishing, 2017)
最新情報
〈刊行〉
5月29日、今年4月~5月にバリー・ユアグローが封鎖されたニューヨークで書いた超短篇12本を収めた小冊子『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』を急遽刊行。ignition gallery のウェブサイトと、一部書店で販売。
6月1日、ポール・オースタ―『ブルックリン・フォリーズ』新潮文庫版刊行。
『波』6月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第14回「ALWAYS二丁目の月光」掲載(10回目までは原文と一緒にウェブ上でも公開)。あわせて同号にユアグロー超短篇「ボッティチェリ」も掲載。
『新潮』7月号、ポール・オースターのエッセイ「
6月15日、柴田責任編集MONKEY21号(特集「猿もうたえば」)をスイッチ・パブリッシングより刊行。
6月30日、アレン・ギンズバーグ1956年の詩集を再現した『吠える その他の詩』をスイッチ・パブリッシングより刊行。
スティーヴン・ミルハウザー短篇集『ホーム・ラン』7月に白水社より刊行予定。
〈ラジオ、オンラインイベント〉
2月に刊行されたMONKEY20号刊行記念イベント中止記念ウェブ上イベントを公開中。
6月15日刊行のMONKEY21号刊行記念オンライントーク、6月12日に公開予定。
6月20日(土)深夜零時から(つまり21日との変わり目から)J-WAVE「RADIO SWITCH」に出演、MONKEY21号を紹介するトークと朗読。
6月28日(日)午後2時から、手紙社主催GOOD MEETING の一環として第3回ZOOM朗読会「いま、これ訳してます Part 3」。
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
アイルランドのシンガー、アンディ・アーヴァインの歌詞対訳集「NEVER TIRE OF THE ROAD/旅に倦むことなし アンディ・アーヴァインうたの世界」が岩国のカフェ「ヒマール」で販売中。
下北沢の書店B&Bで手書き翻訳原稿(エドガー・アラン・ポー、トマス・ハーディ短篇)PDF販売中。
2016年6月に平石貴樹さんと行なった、平石貴樹編訳『アメリカ短編ベスト10』刊行記念トークを松柏社のウェブマガジンで6月中に公開予定。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら