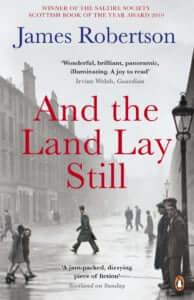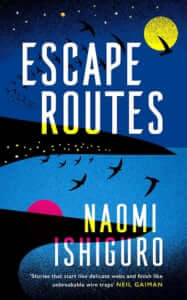(22)もっと注目されるべき作家、嫌でも注目されるだろう作家
James Robertson, And the Land Lay Still (2010; Penguin, 2011)
Naomi Ishiguro, Escape Routes (Tinder Press, 2020)
著者: 柴田元幸
自分の翻訳の話で恐縮ですが、去年12月に東京創元社から出した、カナダ人作家エリック・マコーマックの『雲』が少部数ながら増刷になった。一部にファンがいることは知っていたが、本文453ページ、3500円(+税)の本ということで増刷は始めからあきらめていたのでとても嬉しい。そしてそれ以上に、本のすぐれた読み手である人たちが読んでくれて、面白かった、よかった、とメールや手紙をくれたり書評を書いてくれたりしたのは本当に嬉しかった。何しろマコーマックが好きなので、僕はこの作家を偏愛しすぎではないか、という疚しさのようなものがずっとあったのだが、いややっぱりこの人が好きでいいのだ、という気持ちになれた。
世界的に見れば、マコーマックは日本ではまだ知られている方で(『雲』を入れて邦訳が4冊)、実のところ英語圏でもそれほど知られていないように思える。エリック・マコーマック、と英米の友人に言ってもWho?と訊き返されるのは、僕の発音の悪さだけが原因ではないと思う。やはり、作品がカナダの出版社から出ていて、最大のマーケットであるアメリカとイギリスでは流通しづらいことが最大の原因だと思う(まあカナダ人とはいってもスコットランドに生まれ育ち、スコットランド的な猟奇趣味と宿命観をいまも色濃く持っている人なので、実はカナダでもそれほど読まれていないようなのですが……)。
僕はたまたま、ずっと前に訳したカナダ発のアンソロジー(マイケル・リチャードソン編『ダブル/ダブル』、菅原克也と共訳)にこの人の短篇が入っていたので出会うことができたわけだが、きっとアメリカ・イギリス以外の国のすぐれた英語作家で、未知のすぐれた作家がほかにもたくさんいるにちがいない(もちろん、英語圏以外は言わずもがな)。昨日、ジェームズ・ロバートソンのAnd the Land Lay Stillを読み終えて強くそう思った。
これはここ数年で僕が読んだ最高の小説である。ペーパーバック版で671ページあって、訳すとたぶん400字換算で1600~1700枚くらいになると思うが、まったく長さを感じなかった。
余計なことを言う前に、まずは最初の段落(PART Iが始まる前の序文)を見ていただこうと思う。僕はもう、この一段落でやられました。皆さんも「やられる」ような訳ができるかどうかわかりませんが、とにかくやってみよう――
Sometimes it felt like walking, sometimes it felt like flying. Or it felt like floating, or drifting, or like nothing at all. No motion. Just, there you were – in, on – and there it was – below, around – a splash of land on the ocean, a splatter of stone soil grass forest road town city, and broken–off bits scattered across the great wet belly of the world. And over it splashed lochs and rivers and burns, so much cold, clear water you’d think the land would drown in it, but it didn’t, it lay there still, breathing – sodden and bogged down in some parts, rock–hard and ragged in others, but still breathing. And the sea breathing its endless breaths around it, in out in out in out, great white waves crashing on black rocks, exhausted waves flopping flatly on deserted beaches, weed washing back and forth in bays and inlets, and fish eels lobsters seals ebbing and flowing in the tidal inhalations, exhalations, and sometimes a seal watching you, ten twenty thirty minutes an hour, submerging then resurfacing, always watching you, coming closer, keeping a distance, and you watching the seal, pacing it along the shore, connected but never connected, always apart. The source of stories and legends was in those long mutual observations, those reachings for the unreachable, yearnings for the unobtainable. But that was what they were, unobtainable, and so you turned and came away from the edge, and there was the land again, the earth – rich poor red black brown – and grass flowers trees crops grew from the earth and were nourished by it. And farmers broke the earth and turned it, and that was humankind’s relationship with the land, to need it and love it and break it into giving. When you first set out there were still heavy horses pulling the ploughs but before long they were all but gone, and chugging tractors slogged their way across the patterned fields, between drystane dykes and hedgerows and fences and stands of trees, and white plumes of gulls followed the tractors by day, and black parliaments of crows convened in the trees as night fell. And in the days of early summer you might walk on through the empty hours if there was enough light and you weren’t tired. So you walked and you were alone, and later you’d lie down to rest, to sleep in the sun you’d once toiled and starved below. At other seasons, or if it was cold or wet, you found a barn or a byre or a shed or some other shelter and you bielded there and you were alone; but if the night was dry and looked like staying that way you wrapped yourself in your many layers and your big coat above them all and found a place to lie among trees, or in the lee of a wall or a hedge, you could make your bed anywhere if you were away from people, if you were in the country, and even in the wettest weather you could find shelter in caves and crannies, in empty structures made and left by men, or deep in under the thickest, lowest trees. You could lie for days if days of lying were required, measuring out what food you had, closing down your energy. Nothing was more comfortable to you than the hard roughness of the ground beneath you, nothing more comforting than darkness and utter silence or the cry of owls hunting in the moonlight and the sudden scuffling of their prey among leaves, the strange and familiar signals of night creatures going about their business. Small living things that crept near you, around you, sometimes over you. They did not frighten you, they reassured you. You could sleep like a bairn in such circumstances, hours and hours of dreamless sleep, then waking in the early light, grass heavy with dew and your breath white in the air. You’d stretch and get to your feet, stamp them, warm yourself with violent self-embraces of the arms, you’d reach into your pocket for a bit of bread or something else you had there, or if there was nothing there was nothing, you’d be off anyway, walking again. You were safe then, you were alone, you could breathe easy, and you did.
時にそれは歩いているような、時には飛んでいるような感じだった。あるいは、ふわふわ浮いているような、漂っているような、あるいはまったく何でもないような。とにかく君はそこにいて――中に、上にいて――それがそこにあって――下に、周りに大洋の上の一片の土地があって、一かけの石、土、草、森、道、町、都市があって、世界の大いなる濡れた腹に断片が散らばっていた。その上のあちこちにまた一片の湖、川、流水があり、冷たい澄んだ水がものすごくたくさんあって、こんなにあったら陸地は溺れてしまうんじゃないかと思えるけれど陸は溺れたりもせず、静かに横たわり、息をしていた、ある場所では水に浸かって沼と化し、またある場所では石のように硬くごつごつしていたが、とにかくまだ息をしていた。そして海はそれを囲んで無限の息を吸って吐いた、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて、大きな白波が黒い岩に当たって砕け、疲れはてた波が人けのない浜にべったり横たわり、湾や入江で海草が前後に揺れ、魚、鰻、海老、海豹が潮の呼気吸気に合わせて後ろに引いては前に出て、時には一頭の海豹が君を見ている、10分20分30分1時間、水にもぐってはまた出てきて、いつも君を見ている、だんだん寄ってきたり、距離を保ったり、そして君も海豹を見ている、海豹に合わせて浜を歩く、繫がっていても繫がっていない、いつも離れている。物語や伝説の源はそうした長い相互の観察のなかにあった、届かぬものに届こうとする営みのなか、手に入らぬものに焦がれる思いのなかに。けれどそれらはまさに手に入らぬものだった、だから君は回れ右して水際を離れ、するとそこにまた陸があった、土があって――豊かな地貧しい地赤い地黒い地茶色い地があって――草、花、木、作物が土から生り土に育まれた。そして農夫たちが土を耕し、鋤いた、それが人間と土地との関係だった、人間が土地を必要とし、愛し、耕して恵みを受ける。君が旅を始めたときはまだ、どっしりした馬たちが鋤を引いていたがじきにほとんどいなくなり、バタバタと音を立てるトラクターが模様のついた畑をぐいぐい進み、石塀や生垣や柵や木立のあいだを通って、昼はカモメたちの白い羽毛がトラクターについて行き、日が暮れるにつれカラスたちの黒い議会が木々のなかで開かれた。そして初夏の日々、まだ十分明るく疲れてもいなければ君は遅くなっても空っぽの時間を歩きつづけた。そうして君は歩き、君は一人だった、やがて君は横になって休み、かつては太陽の下で働き太陽の下で飢えたものだったがいまはその太陽を浴びながら眠った。ほかの季節には、あるいは夏でも寒かったり雨が降っていたりしたら、納屋か牛小屋か物置小屋か何かねぐらを見つけて、そこで身を護り、君は一人だった、けれどもし晴れた夜で、一晩ずっと晴れていそうだったら、君はいくつも重ね着した服にくるまり、その上に大きなコートをかぶって、木々のなかか壁や生垣の陰に横になれる場所を見つけた。人々から離れていたら、山の中だったら、君はどこでも寝床を作ることができた。どんなに雨が降っていてもねぐらは見つかった、洞穴や岩の裂け目、人間が作って捨てていった空っぽの住みか、あるいはびっしり繁った低木の下。必要とあらば君は何日も横になっていることができた、なけなしの食料を計算して食べ、活力を眠らせて。体の下の地面の固い荒さが君には何より快適だったし、暗闇と完全な静寂が何より心安まった、あるいは月の光を頼りに狩りをするフクロウの声と葉むらのなかでその餌食が突如ばたばた暴れる音や、夜行性の生き物たちが暮らしを営む奇妙なしかし聞き慣れた音が。君の近く、君の周り、時には君の上を這う小さな生きものたち。彼らは君を怖がらせはしなかった、彼らは君を心強くした。そういう状況で君は赤ん坊のように眠ることができた、何時間も夢なき眠りを貪れた、そうして朝早くの光で目覚め、草は朝露に重く、君の息は空気中で白かった。君は伸びをして、立ち上がり、足を踏みならし、両腕をばん、ばんと体に巻きつけて暖まり、ポケットに手を入れて、パンを、あるいは何かそこに入っているものを取り出し、何もなければ何もないまま、とにかく出かける、ふたたび歩く。そのとき君は安全で、君は一人で、気を抜いて息をしても大丈夫で、事実君はそうした。
どうでしょうか? 一人の人間がどうやら長年放浪していることはわかるものの、まだ具体的な時代も場所もわからないが(drystane=drystone; bairn=babyといったスコットランド英語が交じっているのでスコットランドの話かな、ぐらいは思うわけだが)、とにかく文章に気合いが入っていることはよくわかる。これならずっと読みたい、と思わせる。
そしてPART Iが始まり、ここからは気合いは入ったまま、内容はぐっと具体的になってぐいぐい読めるようになる。6つのパートから成る壮大な物語は、一言でいえばスコットランドの20世紀後半の歴史そのものである。自分より優れた写真家を父に持つ写真家、007のヒーローとまったく同じ名をピーター・ボンドと変えはしたがあたかも元の名が呪いのようにはたらいてスパイまがいの仕事に引きずり込まれる公務員、第一次世界大戦で心の傷を抱えて帰国したものの自分より大きな傷を負った友のことが頭から離れない労働者、自宅をサロンのように開放して多くの人物を結びつける役割を果たす女性、靴フェチの国会議員……等々に代わるがわる焦点を当てつつ、スコットランドの政治状況も盛り込みながら(この要所要所の要約が実に巧い)、あわてず急がずじっくり物語を進めていく。どのエピソードも、展開の面白さ、印象的なフレーズ、微妙なユーモアなど、つねに何か惹きつける要素を備えている。
ジェームズ・ロバートソンについては、この連載の第12回で、一年かけて書いた365本の超短篇集(365: Stories)を紹介した。短いものを書いても長いものを書いても見事な人なのである。邦訳には『ギデオン・マック牧師の数奇な生涯』(田内志文訳、東京創元社)がある。
And the Land Lay Stillは大手のペンギンブックスから出ているので、英米でもある程度注目はされているのだろうが、この見事な出来映えを思えば、もっともっと注目されるべきである。
一方こちらは、名前を見られただけで嫌でも注目されてしまうにちがいない新人作家。その名もナオミ(またはネイオミ)・イシグロ。ノーベル賞受賞者を父に持つとなれば、作家としてやっていくのは相当なプレッシャーだと思うが、デビュー短篇集を読み、インタビューを見るかぎり、(あくまで印象だが)父とは全然違うことをごく自然にやろうとしているように思える。
Escape Routes(逃走経路)と題されたこの短篇集、リアリズムとファンタジーのあいだと形容できそうな作品が多く、インタビューでも影響源・好きな作家としてアンジェラ・カーター、フィリップ・プルマン、ニール・ゲイマンといった名を挙げている。書き出しを二つ選んで訳してみると――
I was called to the palace a few days after the new king was crowned. I supposed it was a sign of the new regime, this cracking down on vermin. I just hoped it was only within the palace walls that the king was wanting to exterminate rodent-kind. He’d have had a hard job of it out in the city proper, after all, given the ferocity of the latest infestation, and then of course I’d have been out of a job if ever he succeeded.
(“The Rat Catcher I”)
新王の戴冠式の数日後、僕は宮殿に呼ばれた。新体制のしるしだな、この害獣弾圧、と僕は思った。まあとにかく、齧歯動物撲滅という王の希望は宮殿内部に限定してほしい。最近のはびこりようを思えば、都全体でやろうと思ったら話は半端じゃない。だいいちそれが成功してしまえば、僕は失業だ。
(「ネズミ捕り屋 その1」)
Once upon a time, there lived a strangely gifted eleven-year-old called Jamie. He liked trains, and planes, and spaceships, and he wanted to be an astronaut. He lived, however, in the middle of the Lake District, on a remote sheep farm. No one in his family or his small community knew the first thing about how to break into the space travel industry, or indeed even the first thing about outer space.
(“Shearing Season”)
昔むかし、ジェイミーという、奇妙な才能を持った11歳の少年がいた。彼は鉄道が好きで、飛行機が好きで、宇宙船が好きで、宇宙飛行士になりたかった。けれども彼は湖水地方の真ん中の羊牧場で暮らしていた。家族の誰も、そして近所の誰も、スペーストラベル産業にどうやったら入り込めるのか、まるっきり見当もつかなかったし、そもそも宇宙についても何ひとつ知らなかった。
(「剪毛の季節」)
どちらも男性が主人公・視点的人物であるところが目を惹くが、これは全9篇のうち8篇がそうである。重要な他者としては女性が何人も出てくるのだが、主人公が女性の作品は1篇のみ。女性作家の短篇集としてはかなり珍しいことだと思うが、ここにどこまで深い意味を読むべきかはわからない。まあ少なくとも、自分の体験にちょっと色をつけて小説にする、みたいなやり方はしない人だということはよくわかる。
上2篇のうち「ネズミ捕り屋」の方は「その1」とついているとおり、三部作になっていて、その3本が短篇集の3、6、9番目に置かれている。これは単純な仕掛けだが非常に効果的である。あいだに入っている作品(4、5/7、8番目)もこの三部作にどことなく響きあうところがあって、本全体にゆるやかで豊かなつながりが生まれている。リアリズムとファンタジーのあいだの作品が多いと書いたが、この三部作が一番おとぎ話的な要素が強く、異様に精緻なネズミ捕りを作るネズミ捕り屋、駄犬一匹だけが友だちの若き王、ネズミたちと仲よしの王の妹といったキャラクターも興味深く、これが一番面白かった。だがほかの作品も、リアリズム的に話が進むなかで最後にふっとおとぎ話的な次元に飛ぶものがいくつかあって(屋上で鳩たちと仲よくなった女性の許に、鳩よりずっと大きな鳥が現われ、彼女をどこかへ連れていく……らしいところで話が終わったり)、リアリズムとファンタジーを無理なく巧みにつなげるというよりは、あまりにも唐突にモードが変わるのでこっちは逆に武装解除されてしまい、これはこれで面白いかなと思わされる、なかなか大胆な作風である。
「逃走経路」(escape routes)という言葉は3つの作品に出てくる(このタイトルの作品はない)。だから、日常的制約に縛られた現実から逃走することが本全体のテーマである、とか言えなくもないと思うが、まあべつに言う必要もないかと思う。
いずれにせよ、この質であれば「イシグロの娘」というレッテルばかりが先行する、という事態にはならずに済みそうである。2021年には長篇も出るとのこと。楽しみである。
-
James Robertson, And the Land Lay Still (2010; Penguin, 2011)
-
Naomi Ishiguro, Escape Routes (Tinder Press, 2020)
最新情報
画家・平松麻さんの作品集ZINE『Things Once Mine かつてここにいたもの』(スイッチ・パブリッシング)に「太古につながった絵」を寄稿。
アイルランドのシンガー、アンディ・アーヴァインの歌詞対訳集「NEVER TIRE OF THE ROAD/旅に倦むことなし アンディ・アーヴァインうたの世界」が岩国のカフェ「ヒマール」から出ました。
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasが5月10日(日)から持ち帰り販売してくれます。
2月に刊行されたMONKEY20号刊行記念イベント中止記念ウェブ上イベントを公開中。
5月16日(土)深夜零時から(つまり17日との変わり目から)J-WAVE「RADIO SWITCH」に出演、一時間ほぼずっと朗読します。テーマは「ただいま読書中」。
5月23日(土)午後2時から手紙社主催GOOD MEETING の一環として第2回ZOOM朗読会。詳細は後日に。
『波』連載、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」、ウェブ上でも読めるようになりました。英語原文も併載。
下北沢の書店B&Bで手書き翻訳原稿(エドガー・アラン・ポー、トマス・ハーディ短篇)PDF販売中。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら