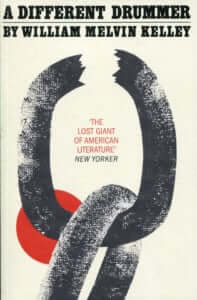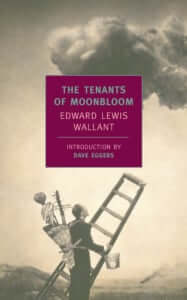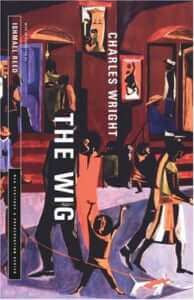(24)笑っていいとも?
William Melvin Kelley, A Different Drummer (1962; riverrun, 2018)
Edward Lewis Wallant, The Tenants of Moonbloom (1963; New York Review Books Classics, 2003)
Charles Wright, The Wig (1966; Mercury House, 2003)
著者: 柴田元幸
「カルト的人気」とか「忘れられた古典」とかいう宣伝文句を見ると、つい買ってしまう。買ってしまうのだけれども、結局ツン読で終わってしまうことも多い。これではいけないと思って、未読の本の山のなかから何冊か引っぱり出してきた。
まずはウィリアム・メルヴィン・ケリーの『違う太鼓叩き』(William Melvin Kelley, A Different Drummer)。タイトルはヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン』(1854)の一節“If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.”(もし誰かが仲間と歩調が合わないなら、それはたぶん、違う太鼓の音を聴いているからだ)から来ている。
1957年、アメリカ南部の小さな町サットン。町で唯一のよろず屋の店先で、暇な白人男たちがたむろしている。フォークナーの小説などでもおなじみの風景である。店のかたわらで、スーツケースを携え、よそ行きの服を着た黒人の男がバスを待っている。バスが来て、男は乗り込む。べつに珍しい光景ではない。だが次のバスにも、そのまた次のバスにも、黒人たちは乗り込み、去っていく。家族が荷馬車で去っていく。比較的豊かな者は、自動車で。そうやってじきに、州全体から黒人が一人もいなくなる。
……という現代の話と並行して、奴隷売買がまだ行なわれていた時代の物語が組み込まれる。アフリカから着いたばかりの奴隷船に、すさまじい巨体で怪力の男が乗っていたという話。
Nobody, not even folks what claims to-a seen it, is really certain about what happened next. It must-a been them crewmen, who was still holding all them chains, relaxed when they saw all that money, because the African spun around once and nobody was holding nothing except maybe a fist full of blood and skin where them chains had rushed through like a buzz saw. And now the African was holding all them chains, had gathered them up like a woman grabs up her skirts climbing into an auto, and right off he started for the auctioneer like he understood what that man was saying and doing, which could not-a been since he was African and likely spoke that gibberish them Africans use. But leastways, he did go after the auctioneer and some folks swears, though not all, that, using his chains, he sliced his head off—derby and all—and that the head sailed like a cannon ball through the air a quarter mile, bounced another quarter mile and still had up enough steam to cripple a horse some fellow was riding into New Marsails. Fellow came into town babbling about having to shoot his horse after its leg got splintered by a flying head wearing a green derby.
(注)claims to-a seen it: claims to have seen it
must-a been: must have been
them crewmen: those crewmen(以下、them+名詞 のthemはthose)
次に何があったのか、誰ひとり、この目で見たと言いはる連中ですら、はっきり言える奴はいない。きっと、まだ鎖を握ってた乗組員の連中が、そんな大金を見て思わず力を緩めちまったにちがいない――アフリカ人が一度くるっと回ると、もう誰も鎖なぞ握ってなくて、鎖が丸鋸みたいにするっと抜けていった握りこぶしが血だらけになって皮膚も剝げちまってた。で、アフリカ人はひとりで鎖を全部握って、女が自動車に乗り込むときにスカートの裾をつまむみたいに持ち上げて、すぐさま競売人めざして駆けだしたんだ、まるっきりそいつが何と言っていて何をやろうとしてるかわかってるみたいに。こいつはアフリカ人で、たぶんアフリカ人が喋るあの訳のわからない言葉を喋るわけだからそんなことありえないんだが、とにかく競売人めがけて走っていって、何人かが誓って言うには、いやそうじゃないって言う奴もいるんだけど、鎖で競売人の頭を、山高帽から何からひっくるめてスパッと切り落とすと、頭は大砲の弾みたいに空中を500メートル飛んでいって、あと500メートル弾んで転がって、それでもまだ勢いはたっぷり残ってて、どっかの男がニューマーセイルズに向かって走らせていた馬の脚を駄目にしちまった。男は口から泡吹いて町へ来て、緑の山高帽をかぶった頭が飛んできて馬の脚をやられちまったから撃つしかなかったって言ったんだ。
しかもこのアフリカ人、腋の下に大きな腫瘍があるのかと思ったら、なんと赤ん坊を抱えている。片手で赤ん坊を抱え、もう一方の手で鎖を貴婦人のスカートの裾みたいに持ち上げながら、易々と森へ逃げるのである。
どうやらこの神話的なアフリカ人の末裔が、現代において、畑に塩をまき家畜を殺し家に火を点けて町を去ることで、黒人大移動の流れを始動させたらしい……。
というわけで、およそ現実の歴史では持ちえなかった力を黒人に与えた一種のほら話、願望充足の寓話かと思える始まり方であり、文章も活きがいいことこの上ない。ところがこれ以降、話はだんだん暗くシリアスになっていく。章ごとに舞台もスタイルも変わるなかで(文章の見事さは一貫しているが)、大移動を始動させた黒人男、その男と一緒に(主人の息子の立場で)育った白人青年、その青年が大学で出会う大秀才の黒人等々の視点から、なぜ黒人たちは町を出ていったのかという問いの周りを物語は旋回しつづける。
なかでも一番つぶさに描かれるのは、大学で出会った黒人の友に感化されて、人種問題・階級問題の解決をめざす運動に身を投じ、不動産業を営む父の下で黒人たちから家賃を集めて回る仕事だけはやりたくないと思うに至る白人青年である。人種的偏見に染まった白人たちの暴力もむろん描かれるが、この小説ではむしろ、偏見に染まっていないつもりの白人の挫折に、いっそうはっきり焦点が当てられている。
いずれにせよ、なぜ黒人たちが町を去ったかという問いで読者を引っぱりながら、その問いにすっきりした答えを出すことを拒み、その背後にある大きな文脈を、長いタイムスパンのなかで考えるようごく自然に読み手に促す流れは素晴らしい。
『違う太鼓叩き』は長年忘れられていたが、2018年、ジャーナリストのキャスリン・シュルツが『ニューヨーカー』誌に寄稿したエッセイ「アメリカ文学の失われた巨人」(Kathryn Schulz, “The Lost Giant of American Literature” )がこの怪著/快著の復活に力あったようである。
『違う太鼓叩き』は1962年刊。そしてこの一年後の63年に刊行された、エドワード・ルイス・ウォーラントの『ムーンブルームの賃借人たち』(Edward Lewis Wallant, The Tenants of Moonbloom)は、まさに兄が所有する安アパートの住人たちから家賃を集めて回ることを仕事にしている男が主人公である。
裕福な人間などいるはずもない人々から毎週家賃を徴収するノーマン・ムーンブルームは、アパートに関するもろもろの不満を聞かされるのはもちろん、彼らの人生の悩みや苦しみも否応なく知ることになる。最初の数十ページは、家賃を集める木曜日、ノーマンが一世帯一世帯の人々と交わすやりとりがめまぐるしいテンポで描かれる。
作者のエドワード・ルイス・ウォーラントは、アメリカでは(おそらく日本でも)シドニー・ルメット監督の映画『質屋』の原作者として知られる。そしてあの映画が、強制収容所で妻子を殺された元大学教授の質屋を主人公とする重々しい映画であったことを思えば、このムーンブルームの家賃徴収話も、さぞ深刻な内容かと予想したくなるが、これがさにあらず。『ムーンブルームの賃借人たち』の語り口は終始コミカルで、『違う太鼓叩き』の前半にも通じる、絶望を通り越したかのような、ほとんどやけくその笑いに貫かれている。
“It smells good,” Norman said, sitting in the cramped kitchen. Unfortunately his chair faced the little closet where the toilet was. With its heavy, wooden water tank above it, it looked like a seat in a torture chamber. On one side of it, the wall bulged dangerously, like an enormous contusion; it looked as though a great body of water were pushing at the wall, and Norman imagined Basellecci sitting on the toilet with his pants down and the water suddenly bursting through on him and drowning him.
「いい匂いですね」と狭苦しい台所に腰かけたノーマンは言った。あいにく彼の椅子は、トイレがある小さなクローゼットと向きあっていた。頭上に重たい木の水槽があるせいで、トイレは拷問室の座席のように見えた。一方の側の壁は、巨大な打撲傷のごとく危険に膨らんでいて、大量の水が壁をぐいぐい押しているみたいに見える。バセレッチがズボンを下ろしてトイレに座っている最中、水が突如噴出してきて彼を溺死させるさまをノーマンは思い描いた。
が、『ムーンブルームの賃借人たち』も、コミカルなトーンは維持しつつ『違う太鼓叩き』同様に話はだんだんシリアスになっていく。ノーマンははじめ、住人たちの不平不満を適当に聞き流している――水漏れを直せだの、廊下の電球を取り替えろだのといった要求に応じる予算はとうていないのだ――が、だんだんその訴えが執拗なブローのように効いてきて、ついに彼は、家賃収集人としての職務を超えて、すべての作業を自分でやることを決意する。はたから見れば生活はほとんど破綻してしまうが、本人はある種の恍惚に包まれている。これを愚かな迷妄と見るか、気高い殉教と見るか、その判断を読者に委ねている点が見事だが、少なくとも殉教でないと言いきっている気配はないとは言える。
『違う太鼓叩き』『ムーンブルームの賃借人たち』2冊のうち、1冊は悲劇的に終わり、1冊は(少なくとも表面的には)楽観的に終わる。はじめ僕は、一方は「かくありますように」という祈りでありもう一方は「かくありませんように」という祈りなのだから、もしかするとこの両者は入れ替え可能ではないか(つまり、暗い終わりは明るい終わりを影として含み、明るい終わりは暗い終わりを影として含んでいるのではないか)と思ったのだが、そう言いきっていいか、自信はない。やはり、一方は人種問題という要素が深く入っていることが、安易な比較をためらわせる。
もうひとつの忘れられた傑作で、『ムーンブルームの賃借人たち』からさらに3年下った1966年に発表されたチャールズ・ライトの『ザ・ウィグ』(Charles Wright, The Wig)は、先達2作と同じように、狂気じみたユーモアとともに始まるが、こちらは途中からだんだんシリアスになることもなく、狂気じみたまま最後まで突っ走ってみせる。
「ウィグ」はもちろん普通は「かつら」の意だが、この小説には、冒頭に著者の断り書きが二つ付いている。
the word WIG as it is used in this story is negro slang for HAIR
(この物語で使われるWIGという言葉は黒人のスラングで「髪」の意味である)
and the story itself is set in an america of tomorrow
(そして物語自体は明日のアメリカが舞台である)
「明日のアメリカ」と銘打っているが、この物語のなかのアメリカでは、現実の1964年にジョンソン大統領が貧困と人種的偏見の撲滅を目指して訴えた「偉大な社会」(the Great Society)というスローガンが謳い上げられている。そして、うだつの上がらない主人公レスター・ジェファソンが世の流れに乗って偉大な社会の一員になるために頼るのは、“Silky Smooth Hair Relaxer”(「絹のように髪をまっすぐ滑らかにする薬」の意の商品名)。これを使うと髪は輝く金色になるのである……と、いかにも漫画的に安易なやり方に、この本全体を包む、すべてを茶化さずにはいられない辛辣さが表われている。たとえば、レスターの友人リトル・ウィッシュボーンをめぐる記述はこんな感じである――
Aged twenty-eight, Little Wishbone was a has-been, a former movie star. Adios to fourteen Cadillacs, to an interest in a nationwide cathouse corporation. He had been the silent “fat” owner of seven narcotic nightclubs, had dined at the White House. Honored at a Blue Room homecoming reception after successfully touring the deep South and South Africa. At the cold corn bread and molasses breakfast, Congressmen had sung “He’s a Jolly Good Nigger.” Later, they had presented him with a medal, gold-plated, the size of a silver dollar, carved with the figure of a naked black man swinging from a pecan tree.
28歳にしてリトル・ウィッシュボーンは過去の人、元映画スターだった。14台のキャデラックとももうおさらば、全国的売春組織の利権ともおさらば。かつては7つの麻薬ナイトクラブの投資者として何もせずにたっぷり利益を得て、ホワイトハウスのディナーに招かれたこともあった。ブルールーム(注1)での、深南部および南アフリカ(注2)へのツアー成功後の帰還レセプション。温めていないコーンブレッドと糖蜜(注3)の朝食の席で、下院議員たちは「こいつはいいニガー」(注4)を歌い、その後、金めっきを施した、一ドル銀貨の大きさのメダルを彼に贈った。メダルには裸の黒人の男がペカンの木(注5)から吊されている姿が彫ってあった。
(注1)ブルールーム ホワイトハウス1階の、国賓などを迎えるレセプションに使われる楕円形の部屋。
(注2)南アフリカは当時まだ人種隔離政策が採られ、南アフリカへコンサートに行ったアメリカのロックミュージシャンが非難されたりした。
(注3)温めていないコーンブレッドと糖蜜は、南部の伝統的・庶民的、ほとんどステレオタイプ的な朝食メニュー。
(注4)「こいつはいいニガー」(“He’s a Jolly Good Nigger”)は、パーティーなどで誰かを祝って歌う伝統的な歌「こいつはいい奴だもの」(“For He’s a Jolly Good Fellow”)のもじり。
(注5)ペカンの木はアメリカ南部に多く、テキサス州の州木。
白人側も黒人側も無差別に斬る、痛快な諷刺精神がこの本を貫いている(もちろんそれは、喧嘩両成敗などという話ではなく、斬らずにはいられない黒人のふるまいを生み出しているアメリカの――白人主体の――社会が糾弾されているのである)。何しろほとんどの笑いは人種ネタだから、笑ってしまってから、これって笑っていいのかと何度も自問させられる。
『ザ・ウィグ』は結末も、「かくありますように」であろうが「ありませんように」であろうが祈りには程遠い。笑いの総量は前2作より多いかもしれないが、絶望もより深いかもしれない。
-
William Melvin Kelley, A Different Drummer (1962; riverrun, 2018)
-
Edward Lewis Wallant, The Tenants of Moonbloom (1963; New York Review Books Classics, 2003)
-
Charles Wright, The Wig (1966; Mercury House, 2003)
最新情報
〈刊行〉
7月9日、スティーヴン・ミルハウザー短篇集『ホーム・ラン』白水社より刊行。
『波』7月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第15回「あんこ+『東京オリンピック』リメーク」掲載(10回目までは原文と一緒にウェブ上でも公開)。
〈ラジオ、オンラインイベント〉
7月18日(土)24時からJ-WAVE「RADIO SWITCH」で、ギンズバーグ『吠える』とその周辺をめぐるトークと朗読。
7月22日 (水) 6:30pm~、HMV&BOOKS SHIBUYAでスティーヴン・ミルハウザー『ホーム・ラン』刊行記念トーク(ライブ配信あり)。
【予定】8月8日(土)か9日(日)、手紙社主催『紙博』の一環として第4回ZOOM朗読会「いま、これ訳してます Part 4」。
2016年6月に平石貴樹さんと行なった、平石貴樹編訳『アメリカ短編ベスト10』(松柏社)刊行記念トーク、公開中。
6月15日刊行のMONKEY21号刊行記念オンライントーク、公開中。
MONKEY21号特集「猿もうたえば」にちなむ音楽のプレイリスト、公開中。
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら