私がものごころついたころの占領下の日本は、めちゃくちゃに貧しかった。焼跡をうろつく戦災孤児の群れ、ハデな安物をまとったパンパンのお姉さん、よれよれの兵隊服の男たち。食うものも乏しく、たまに配給されるアメリカ進駐軍のKレーション(缶詰の携帯食)が最高のご馳走だった。そんな時代ですね。
わかりやすく映画でいうと、戦後10年ほどのあいだに封切られた、木下恵介『大曽根家の朝』、斎藤寅次郎『東京五人男』、溝口健二『夜の女たち』、黒澤明『野良犬』などから、今井正『青い山脈』、小津安二郎『東京物語』、本多猪四郎『ゴジラ』、成瀬巳喜男『浮雲』などにいたる、モノクロ映画の最盛期――。
その記憶がつよすぎて、日本の現代史にしても、ついつい、これらの映画に映っているような戦後の光景を基点に、それ以前・それ以後というしかたで考えてしまう。いつしかそんな性癖が身についた。さしずめ野坂昭如に代表される戦後「焼跡派」の弟分といったところか。
といって、
――しょせん、きみたちにはわからんだろうけどさ。
などと、えらそうにいうつもりはない。わからんのはお互いさま。私がそうであるように、私よりずっと若い人たちの歴史感覚だって、それぞれに、じぶんが少年や少女だったころの記憶を基点に、いわば特権的にかたちづくられているにちがいないのだから。
そんなしだいで戦後日本の貧しさについてなら私は骨身に沁みて知っている。しかし、少年の私はまだ気づいていなかったが、貧しいのはじつは日本だけではなかった。アメリカ合衆国を唯一の例外として、戦後の世界は、どこをとってもとことん貧しかったのである。
では、だとすると私は、いつどのように、その現実(アメリカ以外の世界の大半が貧乏)に気づいたのだろうか。
くわしい動機はあとでのべるが、このひと月ほど、戦後のイタリア映画をDVDでまとめて見て、たぶんこれだな、これらの映画が情報源となって、少年だった私の目がアメリカだけでなく同時代の世界に向けてはじめて開かれたのだろうと、ようやく見当がついた。
具体的にいうと、いまあげた日本映画の作品群と軌を一にして、おなじ時期のイタリアでも「ネオ・レアリズモ(新現実主義)」とよばれる一連の映画がたてつづけに登場し、世界の映画界を震撼させた。そのうち、こんどあらためて見たものを製作順に列挙しておくと、
●ロベルト・ロッセリーニ『無防備都市』(1945年)『戦火のかなた』(46年)
●ヴィットリオ・デ・シーカ『自転車泥棒』(48年)『ミラノの奇蹟』(51年)
●ルキノ・ヴィスコンティ『ベリッシマ』(51年)
●フェデリコ・フェリーニ『道』(54年)
●ピエトロ・ジェルミ『鉄道員』(56年)
イタリアは第二次世界大戦でドイツ・日本と組んでファシズム枢軸国としてたたかい、ともに敗戦国になった。ただしイタリアはほかの二国とちがい、戦争末期に、国内で対ナチのパルチザン(ゲリラ)戦を敢行している。その輝かしくも悲惨な体験をもつ映画人たちが、戦後の混乱した庶民生活を題材に、なまなましい、ほとんどドキュメンタリー映画といっていいような鮮烈な作品を、たてつづけに発表した。
ここで忘れてならないのは、戦争終了時、米英軍の空爆と9か月におよぶパルチザン戦によって、チネチッタ撮影所をはじめとする映画スタジオの多くが活動不能になっていたこと。
それでも、なんとか映画をつくろうと思えば、カメラを持って街にでて撮るしかない。その現実の街や村で、群衆だけでなく、重要な役までもプロの俳優にまじって、ふつうの男女や子どもたちが演じるという、それ自体がゲリラ的な映画手法が編みだされ、さきのリストにあるようなネオ・レアリズモの名作がたてつづけに生まれることになった。
とはいうものの当時の日本人が、これらの映画を、ただちにリアルタイムで見られたわけではない。
なにしろ占領軍はアメリカ映画を最優先し、ほかの国々で製作された映画の上映には、いわず語らずの規制を課していましたからね。日本での公開はようやく占領も終わりにちかい1950年あたりから。ただし私のような子どもが封切館で見る機会はすくなく、こうした地味な作品となると、たいていは何年かのち、場末の3番館や名画座で見るのがふつうだった。これらの映画にしても、おそらくは50年代後半、高校生のころにはじめて見たのだと思う。
――あれ、ここにも焼跡や闇市があるぞ。戦災孤児やパンパンや職にあぶれた男たちもいるし、アメリカ軍が放出したKレーションもでてくる。なにもかも、しばらくまえの日本にそっくりじゃないの。
いや、なにもイタリア映画にかぎらない。イギリスの、デヴィッド・リーンの『逢びき』やキャロル・リードの『落ちた偶像』、フランスのアンドレ・カイヤット『裁きは終りぬ』、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー『情婦マノン』、ルネ・クレマン『禁じられた遊び』などの、同時代のヨーロッパ映画にはじめて接したのも、おなじ50年代の後半だった。
ドイツ映画はまだ復活していなかったけど、それでもロッセリーニの『ドイツ零年』やキャロル・リードの『第三の男』などの現地ロケによって、敗戦直後の荒廃したベルリンやウィーンの光景や人びとの暮らしぶりも、なんとか目撃できたしね。
そしてこれらの映画体験をつうじて、やがて、日本の場合は「占領」だったが、東欧やほかの少数の国(フランコ独裁下のスペインや中立国スイスなど)をのぞく西ヨーロッパ諸国は、「マーシャル・プラン」として知られる大がかりな経済復興支援計画によって、強大化したアメリカの経済圏にいやおうなしに組みこまれ、それが米ソ冷戦の時代にまっすぐつながってゆく、というようなことも次第に理解するようになるのだが……。
――うーん、でも見た当座となると、どう考えても、まだそこまで深くは認識していなかったぞ。
それよりも、世界には、それまで少年の私を魅了してきたハリウッド映画の途方もない明るさとは別種の、焼跡と貧困のどん底から、あるかなきかの、かすかな光をみつけようとする多くの映画があることを知り、いつしかその暗い魅力に共感するようになった。それにつれて、いままで暗くていやだと感じていた日本映画(娯楽映画以外の)までが魅力的に思えてきた。そういったほうが妥当な気がする。
*
で、ここから話は須賀敦子の『トリエステの坂道』に跳ぶ。じつをいうと、この本こそが、さきほど「動機はあとでのべる」と書いた、私がイタリアの戦後映画を見なおそうと思い立った、その「動機」にほかならないのです。
と書けば、須賀の熱心な読者なら「ああ、あのことか」とすぐ気づくにちがいない。そうでない方は、まずは、この本におさめられた「ガードのむこう側」という文章の、「その日、私は一九五一年にヴィットリオ・デ・シーカが監督した『ミラノの奇跡』という映画を見たころのことを、夫に話していた」とはじまる一節を読んでみてください。
それは、見わたすかぎり焼け野原という戦後の風景のなかで、地下の油送管が破れたのを、石油を掘り当てたと勘違いして大さわぎする人々をめぐるコメディーで、トトという孤児院そだちの善良な主人公が、もと貴婦人やら、大学教授、イカサマ師、夜の女などと結託して、その土地の買収をたくらむ資本家に立ち向うという、なんとも他愛たわいないストーリーだった。ネオ・レアリズモと幻想が奔放に交差する手法が、しかし、あのころの私たちにはたとえようもなく新鮮に思われ、焼け跡にはいろいろな感慨があった戦後の日本でも評判になった。
須賀のいう「夫」とは、いうまでもなく、ミラノ・コルシア書店(連載13を参照)の中心人物のひとりで、ほどなく早逝するジュゼッペ(ペッピーノ)・リッカをさす。そのペッピーノとともに、しばしば彼女は都心部のはずれにあるかれの実家――鉄道員だった父親から母がひきついだ6階建ての鉄道官舎をたずねていた。
その家で、ある日、むかし見た『ミラノの奇蹟』について、「あんまりおもしろかったから、三回も見ちゃった」と話すと、あはは、とペッピーノが笑っていった。
「あの映画のシーンはどこで撮ったか知ってるかい?」
「わからない」
「土手のむこうさ」
「むこうって?」
「三ツ橋のあっち側だよ。あそこならデ・シーカらしく、背景になにもつけくわえる必要がなかったんじゃないかな」
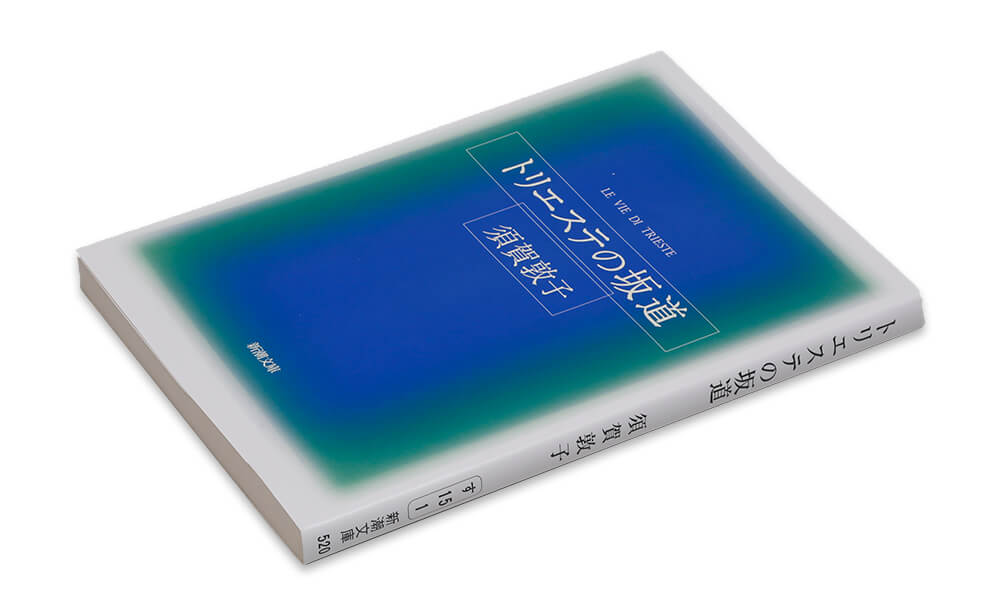
須賀もびっくりしたろうが、私もおどろいた。彼女に数年おくれて、9歳下の私もおなじ映画を、その「おもしろさ」にひかれてなんどか見ていたからです。といっても、もう半世紀以上もまえのことだから、
――空襲で家を失った人びと(なぜか奇人変人ばかり)が、広い空き地に建てた廃物利用のバラックでのんきに暮らしている。しかし、そのせっかくの集落がチャップリンの無声映画にでてくるような太った資本家とまぬけな警察隊の手によって破壊され、最後は、追いつめられた何十人ものホームレス(といっても空襲の被災者だから家族持ちも多い)の群れが、主人公のトトを先頭に、ミラノの大聖堂前広場から箒にまたがって、たれこめる雲の彼方の理想郷めざして消えてゆく――。
いまとなっては、もはやそのていどの記憶しかのこっていないのだが、それでも、あのバラック集落の光景だけは、なんとかいきいきと思い浮かべることができる。
その広大な空き地が、20年たってもまだ鉄道官舎まえの「土手のむこう」にひろがっていたというのだからね、そりゃあ、おどろきますよ。ペッピーノの話では、土手の上はミラノ・ローマ間の鉄道線路になっていて、10年ほどまえに死んだかれの父親は、すぐそこに見える線路わきの信号所につとめていたらしい。
そうと知った以上は、あのなつかしい映画をぜひもういちど見ておきたい。そこで、さっそくネットのレンタル・サイトで借りてきたら、なるほど、その草ぼうぼうの土手なるものが繰りかえし、なんどもでてきた。
たとえば、この土手を集落の住人たちや警官隊が懸命によじのぼったり転げ落ちたり――そんなドタバタ騒ぎを通りすぎる列車の窓から乗客たちが笑いながら見ていたりする。ただし土手のあちら側にあるはずの6階建ての鉄道官舎や信号所は、どこにも見あたらない。なぜだろう。撮った場所がちょっとずれていたのだろうか。
この土手は、のちに手にした大竹昭子の写真ルポ『須賀敦子のミラノ』によると、いまは「堤全体がコンクリートの壁で土どめされて」いるらしい。「土手沿いの壁にヨーロッパの各地で見られるアメリカ風のグラフィティーが描かれ、道端には自動車の部品や廃品などがころがり、『昼間でもひとりでは歩きたくない、どこかうさんくさい空気』はいまもかすかに残っている」のだとか。

――あそこならデ・シーカらしく、背景になにもつけくわえる必要がなかったんじゃないかな。
そうペッピーノがいうのは、それまでにデ・シーカが『自転車泥棒』や『靴みがき』や『ウンベルト・D』などの冷徹非情な作品で、セットにたよらず、できるかぎりロケで撮るというネオ・リアリズモ映画の原則をきびしくつらぬいていたからである。
ところが、にもかかわらずデ・シーカは、じぶんの新作に、箒にまたがったホームレスたちが歌いながら天空の奥ふかくに消えてゆく、というような「幻想」を平然と導入してしまった。
そういえば、こんど見て思いだしたが、終わりだけでなく、この映画は、無邪気なおばあさんが朝のキャベツ畑でワンワン泣きわめく裸の赤ん坊(トト)をみつけるという、よくある「おとぎ話」ふうの光景からはじまっていたのだった。その意外な、でも明確に意図された「他愛なさ」が、おそらくは須賀や、そして私のような「あのころの私たちにはたとえようもなく新鮮」なものと感じられたのだろう。
*
そして、もうひとついうと、ミラノならぬこの時期の東京にも、じつは大小とりまぜて、この種のルンペン集落があちこちに存在していたのです。
とりわけ忘れられないのが、中央線・御茶ノ水駅の外堀(神田川下流)側の急な斜面にあった、ちっぽけな集落。あれで10軒ほどもあったろうか、プラットホームに立つと、すぐそこに焼けたブリキや廃材でつくったバラック群が見えた。たいていはひっそりしていたが、ときには洗濯している女性や、ぼんやりとこちらを眺めている子どものすがたを見かけるようなこともあった。
そしてこのいつも見慣れた光景が、『ミラノの奇蹟』とおなじ1951年に刊行された獅子文六の『自由学校』という小説によって、にわかに有名になる。いや正確には、同年、松竹と大映という2つの映画会社がきそって映画化し、おなじ5月に同時封切りしたことによって、というべきか。なにしろそのことで、5月の第1週を「ゴールデンウィーク」と呼ぶ習慣が生まれたくらい大きな話題になったのだから。
この昔むかしのベストセラー小説が、思いがけず、2016年にちくま文庫から復刻された。こまかいことはそれで読んでもらうとして、この小説の勘どころは、中年サラリーマンの五百助(体重八〇キロの茫洋たる巨漢)が、会社づとめと威勢のいい妻の圧政を逃れ、放浪のはてに、お茶の水(作中ではお金の水)のバラック集落に住みつくところにあった。

孤児院を卒業したトトは大事な鞄をぬすんだコソ泥の手引きで土手のむこうの集落にたどりついた。同様に五百助も、水道橋の防空壕で出会った「拾い屋」(廃品回収業者。「バタヤ」ともいう)の老人によって、外堀にかかるお茶の水橋をわたってすぐ右側の細道を下った斜面の集落にみちびかれる。
五百助も、この谷間に人が住んでることを、中央線で通勤してる時代に、眼にとめないでもなかったが、戦後の住宅払底の現象として、驚くに値いするとも思わなかった。ただ、少し殺風景な気持はしていた。悪くいえばゴミ捨て場の中に、人間が住んでるようで、もうちっと、工夫はないかと、思っていたのである。ところが、今、爺さんの後について、深く、谷間へ降りていくと、電車の窓から見たのと、ひどく、印象がちがうのである。
ちがうのも道理、見た目とちがって、この集落は、最初に小屋を建てた「爺さん」と、あとにつづく「家を求める術のない人々」が、みずからの手でつくりあげた「生活共同体」だったのである。
警察や区役所から文句をいわれないように共同便所を設けたし、輪番制で水くみ場を清掃する決まりもある。住民のほぼ全員が拾い屋なので、ワラやムシロを灰にして農家にとどけるというようなゴミ加工もはじめた。ほかの品々もふくめて、「仲買人の搾取」を避けるべく、ここで分類したゴミをじぶんたちで問屋に持ちこむという廃品回収のしくみが生まれていたのだ。
おかげで生来、怠け者の五百助も、このごろはゴミ拾いで「百円ぐらいしか稼がない」――煙草はモク拾い、入浴も冷水浴ですむし、だから「よけい稼いでも、意味ないのである」といったバタヤ暮らしをつづけるうちに、それまでとは「比較にならない、心の自由と安定」を感じるようになった。
こんなに早く、こんなに近く、彼のエデンの園を発見しようとは、夢想もしなかった。あまり、ラクに発見したので、果して、これがホンモノであろうかと、疑心暗鬼も起こるのであるが、とにかく、彼の空想と、はなはだしい隔りはない気がするのである。この谷間では、時代と社会の支配力が、非常に弱められ、個人がラクラクと呼吸してるのは、争えない事実なのである。
ここでの集落の記述は、おそらくまったくのフィクションではなく、作者自身や、この小説を連載した朝日新聞の担当記者が実地にしらべ、それをもとに書かれたものだったのであろう。
ただし、そこを「時代と社会の支配力」のそとにある「個人がラクラクと呼吸」できるような「エデンの園」――のちに網野善彦が日本の中世に発見した「無縁」のアジール(避難所)として、さらにいうならば五百助にとっての「自由(の)学校」としてとらえたのは、いうまでもなく獅子文六のしごとだった。しごと、もしくは想像力のなせるわざ。ようは「空想」です。
ただし、これとおなじ時期、かならずしも「空想」とはいいきれない、しかものちの須賀敦子とも無縁ではないような自立した「生活共同体」に向けての試みが、まったく存在しなかったわけではない。浅草の言問橋西詰(浅草寺側。いまの隅田公園)にあった「蟻の街」とよばれるバタヤ集落がそれ――。
東京大空襲で家も生業も失った人びとが、その焦土に古い木材やトタンや紙箱やむしろのバラックを建て、廃品回収によってかろうじて日々の糧を得ていた。その人びとが1940年代末、元ヤクザともいわれる小澤求を中心に、のちに「蟻の街」と呼ばれるようになる自治組織をつくり、戦前の劇作家・松居松葉の息子で、脚本家・随筆家の松居桃楼、聖フランシスコ修道会のゼノ修道士などの、いささかならず奇人めいた支援者たちとともに、国や自治体にたよらず、じぶんたちだけの力で生きていこうという活動をはじめる。
以下、おもにウィキペディアによってしるすと、この約600坪の土地は、もともと戦災者や引揚者や戦没者遺族などの援護にあたる「同胞援護会」という社会福祉法人が管理していたもので、小澤がそれを借り受け、仕事のない人びととその家族を住まわせて、ガラスくず、鉄・銅くず、縄くず、紙くずなどを回収して再生工場へ送る自前の「仕切り場」としたのだという。報酬は出来高払いで、「仕切り場はいわば生活共同体となった」とウィキペディアはいう。松居桃楼は、その同胞援護会に近い法律事務所のアルバイト事務長でもあったらしい。
そして、この過程で、いつしか活動のシンボル(『ミラノの奇蹟』ではトトに当たる)と目されるようになったのが、北原怜子という、まだ20代の熱心なクリスチャン女性だった。
北原は1929年生まれ。東京農大教授(経済学者)の娘で、桜蔭高女(現・桜蔭中学/高校)と昭和女子薬学専門学校(現・昭和薬科大学)でまなび、1949年、メルセス会女子修道院で洗礼をうける。1953年にでた彼女の『蟻の街の子供たち』という本によると、北原はその3年まえ、たまたま出会ったゼノ修道士(黒い修道服の「白い髭のおじいさん」)によって「蟻の街」の存在を知り、最初は慰問のため、のちにはみずから街に住みこんで、子どもたちの教育環境をととのえるべく、バタヤのひとりとして働くようになった。

ところが、まもなく「蟻の街」は東京都に立ち退きをせまられ、だったら移転先をよこせとあの手この手の折衝をつづけた結果、都の斡旋によって深川8号埋立地(現在の潮見)に5000坪の土地を買い取り、そこに移転することになる。そう決まったのが1958年1月20日。そしてその3日後に北原は過労と結核のために世を去る。わずか28歳だった。(この項つづく)
須賀敦子『トリエステの坂道』みすず書房、1995→新潮文庫、1998
須賀敦子『ミラノ 霧の風景』白水社、1990→白水Uブックス、2001
大竹昭子『須賀敦子のミラノ』河出書房新社、2001→文春文庫『須賀敦子の旅路』2018*
獅子文六『自由学校』朝日新聞社、1951→ちくま文庫、2016
北原怜子『蟻の街の子供たち』三笠書房、1953→聖母の騎士社「聖母文庫」、1989
*『須賀敦子の旅路』は、ミラノ、ヴェネツィア、ローマと須賀の足跡をたどった著者のシリーズに書下ろしの東京篇を増補しまとめたもの。
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








