1953年に、北原怜子の『蟻の街の子供たち』と松居桃楼の『蟻の街の奇蹟』という2冊の本が、あいついで刊行された。
そして1958年、北原の死の直後に、あらためて松居の『蟻の街のマリア』という伝記が出版され、松竹で五所平之助監督によって映画化される。『自由学校』の映画は、たしか吉村公三郎監督の大映版を中学生のころに見たと思うが、こちらは見ていない。北原や松居の本も読んでいない。なのに「蟻の街」のことは、それなりにしっかりおぼえている。新聞や週刊誌(ただし1953年はまだ『週刊朝日』と『サンデー毎日』と『週刊サンケイ』しかなかった)が、よっぽどハデに報じていたのだろう。
――ほほう、では須賀さんは?
もちろん知ってたんじゃないの。須賀敦子は北原とおなじ1929年生まれで、松山巖の『須賀敦子の方へ』によると、聖心女子学院高等専門学校在校中の1947年(翌年、同校は聖心女子大学に切り替わる)、18歳の年にカトリックの堅信礼を受けている。北原の(堅信礼に先だつ)洗礼は49年だったから、ほぼ同時期と見ていい。そんな須賀が「蟻の街のマリア」の出現に、なにがしか関心をいだかなかったわけがないのだ。
なかんずく――。
当時の須賀については、いまもあげた松山巖の本にくわしいが、それによると、このころ聖心女子大では、全学生に「三河島セツルメントの子どもたちを〔学内に〕招き、世話をしたり、日曜学校、バザーなどへの参加」が義務づけられていたらしい。戦前の東京下町では、ボランティアの大学生や教会関係者が三河島などのスラムに住みこんで、子どもたちの教育や医療にあたるセツルメント(社会福祉)活動がおこなわれていた。そのつながりが戦後の聖心でよみがえり、若い須賀もその活動に積極的にかかわっていたみたい。
と、そのようにしるした上で、しかし、と松山は語をつぐ。
大学生の須賀は、奉仕活動を通じ、三河島のセツルメントや日曜学校で、貧しかった当時の日本でも、さらに困窮した最下層を生きる子どもたちに出逢った。多くは戦争で親を失った戦災孤児だったはずだ。子どもと仲好くなって、はじめは信仰をまさに実践していると考えたに違いない。しかし慈善活動に学校の行事として積極的に参加しながらも、いや、し続けたからこそ、(略)慈善には自己満足に陥る危険性が伴っているという思いが萌してはいなかったか。(『須賀敦子の方へ』)
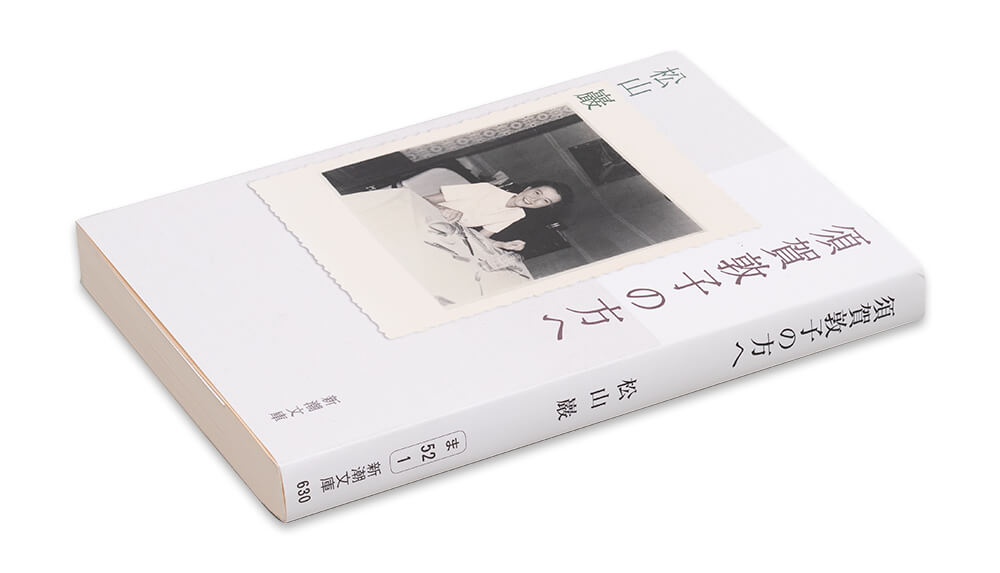
松山がそう感じたのは、ずっとのち、1977年に聖心女子大の同窓会会報によせた文章で、50歳ちかくなった須賀が、こんなふうにのべているのを読んだからであろう。
福祉という柵を設けて、ふつうの(ふつうの に傍点)人間と同じように生きられない(られない に傍点)と私達の決める人を、そこに閉じ込めてしまう。そして、自分は、福祉のお世話になんかならないで済む世界に、ぬくぬくと生きている。もし私が、そんな福祉の対象になる立場に置かれたとしたら、どんなにつらいだろうか。(「福祉という柵」)
福祉や慈善の活動にはげみ、子どもたちと仲よくなればなるほど、「ぬくぬくと生きている」じぶんのめぐまれた境遇に充足し、そのことで「あらゆるハンディキャップを負った人たち」から遠い人間になってしまう。どう考えてもこれは「自分の求める社会」とはちがう。そう須賀がしるすのを読んで、たぶん彼女は30年まえのあの奉仕体験によって、こんなふうに考えるようになったのではないか、と松山は推測した。おそらくそういうことだったのだろうと私も思う。
ではこうした福祉や慈善の「柵」をどう乗り越えればいいのか。
まず考えられるのは戦前のセツルメント活動家たちがそうしたように、じぶんがスラムに住み、そこで「最下層を生きる」人びととともに生きること。そして大学教授の娘で、姉の嫁いだ浅草の大きな履物問屋で「ぬくぬく」と暮らしていた北原怜子(つまり「いいとこのお嬢さん」)がえらんだのが、その生き方だったのです。
入信してまもなく、ゼノ修道士に頼まれてクリスマス会を手伝ったのをきっかけに、北原は頻繁に「蟻の街」に足をはこび、子どもたちの面倒を見るようになった。寄付された衣類や文房具をとどけ、読み書きや算数をおしえ、病気の子を見舞う。あるいは、じぶんの部屋でピアノを弾いて聖歌をおしえるとか、メルセス会女子修道院の復活祭の催しに子どもたちを連れてゆくとか、などなど。
ところが、北原の『蟻の街の子供たち』によると、こうした活動をつづけるうちに、若い須賀とおなじく、彼女もまた「慰問をする」じぶんと「される人びと」とのあいだに「目に見えぬ大きな溝」があると感じるようになる。そこである晩、思いきって「蟻の街」の精神的支柱ともいうべき「松居先生」のバラックをたずねると、そこで「正直の話、僕はカトリックが大嫌いだから」という先生に、こてんぱんに痛めつけられてしまった。
「いわゆる慈善事業が、何千年つづいて来ても、世の中から貧乏人がへらないのは、そこ(そこ に傍点)なんですよ。金持ちのお嬢さんが暇つぶしに、お小遣いの余りを貧乏人に恵んで歩いたって、世の中はよくなりっこないのです。(略)ありがたいというより貧乏人にとっては、ほんとうに不愉快なことなのです。心から気の毒だと思う気持ちがあるのだったら、一緒に裸になって、一緒に苦労しないではいられない筈じゃありませんか」(『蟻の街の子供たち』)
北原も真摯なカトリック信者だったから、その場ですぐに納得したわけではない。
しかし「イエズス様が、一未信者の口をかりて」私を鞭撻しているのだと考えなおし、やがて「蟻の街」の一員として暮らす決心をかためる。そこでまずやったのが、じぶんの住まいをかねた2階建ての勉強小屋を建て、空き箱で代用していた勉強机を買うために、子どもたちといっしょにリヤカーを引いてゴミ回収をすることだった。最初のうちは恥ずかしかったけれども、すぐに慣れ、しばらくすると大きな板囲いの「バタ車」を借りて、上野公園や川向こうの花街にまで遠出するようになっていたのだとか。

*
ここまで書いたところで、ちょっと気になることがでてきた。この『蟻の街の子供たち』は、じつは北原怜子がじぶんで書き下ろした本ではないのです。
じっさいには彼女の私信や子どもたちの作文をあとから編集したもので、三笠書房の編集者にすすめられ、北原が拒むので、やむなく「松居先生」こと松居桃楼が「責任を負う」かたちで刊行されたらしい。とすれば、とうぜん松居の筆もかなり加わっていたにちがいない。そのことは「この著書の内容のよさは、すべて彼女のものであり、字句の誤りその他の不備な点の責任は、すべて私にあることを言明しておく」という松居名の「あとがき」からも想像がつく。
ただし、どこまでが北原がじぶんで書いたことで、どこからが松居の考えなのかが、よくわからない。そこで同じ年に松居がだした『蟻の街の奇蹟』という本をあわせて読んでみることにした。といっても60年以上もまえにでた本だから市立図書館にはない。でも、さいわい県立図書館の検索ページで見つけることができたので、さっそく取り寄せてもらった。

そこでまず結論からいうと、さきの「僕はカトリックが大嫌いだから」にはじまる一文もふくめて、すくなくとも「先生」の発言は松居が書いた(もしくは大幅に手を入れた)ものとしか考えられない。なにしろハイテンションのお説教口調が、かれ自身の本にあまりにもよく似すぎているのだ。かといってつい気軽にそうしてしまったというのではないですよ。この本を読んで知ったのだが、これにはそれなりの理由があったのです。
松居桃楼は1910年生まれ。かつては日本統治下の台湾で演劇行政にかかわったこともある「夢見る策士」タイプの人物だったらしく、「蟻の街」(命名者は松居)の生活にかかわるうちに、ここでも新しい夢想がいつしか大きくふくらんでしまう。
――警視庁のしらべでは、いまの東京には大小合わせて188のバタヤ集落があるという。その全住民が福祉や慈善に頼らず、じぶんたちの力で暮らしていけるような「桃源郷」(大規模なゴミ回収システム)をきずけないものか。
ところが、これとおなじ時期に、じつは東京都の側でも、これらの集落を順次撤去すべく、その準備が着々とすすんでいた。こうしたお上の暴挙に対抗するにはマスコミの力を利用して広く世論にうったえるしかない。そのための切り札として「カトリックが嫌い」なはずの松居が思いついたのが、なんと「蟻の街」のまんなかにカトリックの教会を建てることだった。
――「蟻の街」だけならあっというまに焼かれてしまう。しかし教会となれば、そうそう簡単にはつぶせまい。
そこで1951年、ゼノ修道士の尽力もあって、さきの2階建てのオンボロ小屋の屋上に木の十字架を立てて「蟻の街の教会」が発足する。『蟻の街の子供たち』の出版も、北原怜子を「蟻の街のマリア」とよんでつよい光をあてたのも、すべてはこのせっぱつまったマスコミ戦略の一環だったのだ。
そしてこの作戦はめざましい成功をおさめ、深川の潮見地区に広大な代替地を手に入れることができた。ただしその後、高度経済成長がすすむにつれて住人の数が減り、60年代になるとバタヤ集落はすっかり姿を消してしまう。バタヤ桃源郷の夢の終わり。いまはあの「蟻の街の教会」の後身にあたる「カトリック潮見教会」だけが、辛うじて生きのびているのだとか。
で、以下は余談になります。この『蟻の街の奇蹟』という松居の本を読んでいたら、終わりちかくで、思いがけずこんな記述にぶつかった。
ある雨の日、「松居さん、いる?」と、「蟻の街」のかれの部屋を、国土社という小出版社の編集者がたずねてきた。今朝、ラジオのニュースを聞いていたら、「東京都がバタヤ部落をつぎつぎに焼き払う」というので、びっくりしてとんできたのだという。そこで例によって、
「蟻の会は現代のメシヤだと僕は信じているんだ。(略)蟻の会は、世界中のひとが素裸になって蟻の運動を起せば、天国は目の前に現われると教える。(略)バタヤ部落を犯罪の温床だなんていうけれど、本当の犯罪の温床は刑務所と警察と〔東京都の〕民政局なんですよ」
そういつもながらの熱弁をふるっていたら、その「バタヤの聖書」をうちで出版させてくれませんか、と編集者がいった。じつはそれがいま私の書いているこの本だというのである。
しかしホントにおどろいたのはそのあと。念のためあとがき(余白をかりて)に当たってみたら、そこにこんな1行がとびだしてきた。
「とくに二年間雨の日も風の日もバタヤ部落にかよって、私をはげましてくれた山口瞳君には感謝のことばを知らない」
――えっ、山口瞳って、あの?
しらべると、たしかに山口瞳は1946年、19歳のとき「鎌倉アカデミア」(戦後、多彩なジャンルの芸術家や知識人が創設した自由大学校)に入学し、その一方で国土社に就職して、編集者として2年間そこにつとめていたらしい。
しかも松居はおなじあとがきで、「山口君が蟻の街をおとずれるきっかけをつくってくださった吉田謙吉氏夫妻」にも、あわせて感謝の意を表している。
吉田謙吉は、築地小劇場の第一回公演『海戦』で名をあげた前衛的な舞台装置家で、関東大震災で廃墟と化した銀座を舞台に、「考現学」の同志・今和次郎とともに、「バラック装飾社」という奇抜な建築活動をくりひろげたことでも知られている。だから、いわば焼け跡のバラック天国の先駆者ですよ。したがって松居桃楼にとっては演劇とバラック運動の両面で大切な人物だったのだろうが、じゃあ山口瞳にとっては? おそらく「鎌倉アカデミア」での師弟として知り合ったのだと思うけれども、それをたしかめる元気が目下の私にはない。ざんねん。
*
思わず長々と書いてしまったが、須賀敦子にすこしおくれて青春期をすごした特権によりかかって、いまここで私がいいたいのは、ようするに、
――あのころ須賀が悩み、新しい時代のカトリック教徒としてどう生きてゆくかを真剣に考えはじめたのは、ほかでもない、まだ東京のいたるところにバラック集落があり、おおぜいの難民化した人びとが身近にいた、そんな環境においてだった。
ということなのです。
そこで、ふたたび松山巖の『須賀敦子の方へ』にもどっていうと、このころ、つまり北原が「蟻の街」の住民となった50年代初頭、須賀敦子は慶應大学大学院(社会学)に籍をおき、武者小路公秀、有吉佐和子、犬養道子といった他大学の若者たちと、カトリック学生連盟の一員としての活動をはじめていた。
須賀の大学院入学が1952年。この年の日本は「血のメーデー事件」や「破防法(破壊活動防止法)反対闘争」などで政治的にも激しく揺れていた。もちろん2年まえにはじまった朝鮮戦争もまだつづいている。
そんな時代に彼女が参加したカトリック学生連盟は、全学連のような戦闘的な学生組織でこそなかったが、ナチス占領下のフランスのレジスタンス運動から生まれた「神を信じようが信じまいがともにファシズムとたたかう」という姿勢をひきつぎ、聖と俗とをへだてる垣根を取りはらう「カトリック左派を標榜していた」らしい。そして当時のフランスでは、と『コルシア書店の仲間たち』で須賀がしるしている。
この〔カトリック左派の〕神学を一種のイデオロギーとして社会的な運動にまで進展させたのが、エマニュエル・ムニエだった。彼が戦後、抵抗運動の経験をもとに説いた革命的共同体の思想は、一九五〇年代の初頭、パリ大学を中心に活躍したカトリック学生のあいだに、熱病のようにひろまっていった。教会の内部における、古来の修道院とは一線を画したあたらしい共同体の模索が、彼らを活動に駆りたてていた。(「銀の夜」)

そしてもうひとつ、須賀たちは、ムニエのいう「あたらしい共同体」の実践例として、「エマウス」という社会運動がはじまったらしいという噂も、カトリック・ネットワークをつうじて、ぼんやりとではあるが耳にしていたと思われる。
なにしろアメリカ以外の全世界が貧乏だった時代なのだ。ミラノや東京にかぎらず、パリの街でも、戦争によって住む場を奪われた多くの人びとが生きるすべもなくさまよっていた。そんななかで1949年、アベ・ピエール神父の提唱によって、これらの人びとがゴミ回収によって自分と他人の生活をささえあう運動がそだってゆく。それがエマウス共同体運動――。
と書けば、この運動が日本の「蟻の街」によく似ていたことがわかるだろう。じっさい、エマウス運動の開始された49年に来日した神戸夙川教会のロベール・ヴァラード神父が、その二年後、蟻の街の北原怜子と出会い、それをきっかけに、神戸で「暁光会」というゴミ回収による共同生活運動をはじめているのだから。
そして、やがてその暁光会がエマウスの日本支部になる。しかも松山巖作成の年譜によると、おなじころ、夙川の実家に帰省した須賀がヴァラード神父の活動を知り、参加を申しでたが「女の子はいらない。文学をやりなさい」とことわられた、というようなこともあったらしい。
とすれば、さきに私は「須賀は北原や蟻の会になんらかの関心をもっていたはず」という意味のことを書いたけれども、あれもまんざら根のない推測ではなかったのです。
おなじ松山の年譜に、須賀が東京でデ・シーカの『ミラノの奇蹟』を見たのは1951年だったとある(ただし日本封切は52年11月だから、正確にはそれ以降だろう)。
つまりはミラノでもパリでも東京でも、世界の各地で「最底辺の人びとのユートピア的な生活共同体」というヴィジョンがバラバラに生まれ、神を信じようが信じまいが、それがなにがしか魅力的な(ときには愉快な)ものと感じられていた、そんな時代。そういえば、いま思いだしたぞ。「蟻の街」の活動をフォローしつづけた『サンデー毎日』で、加藤芳郎の貧乏マンガの傑作『オンボロ人生』の連載がはじまった。あれがやはり1954年のことだったのです。
*
かくも困難な時代にひとりのカトリック教徒として私はどう生きていけばいいのか――。
そのことをたしかめたいと、1953年に、須賀敦子は政府援助留学生として、カトリック左派運動やエマウス運動の本拠地であるパリにむかった。しかし、とうとう納得できる解答を得られないままに、1960年、いくつかの偶然の出会いもあってミラノ・コルシア書店の活動に加わり、その中心にいたペッピーノと結婚する。
この間の遍歴については『ミラノ 霧の風景』や『コルシア書店の仲間たち』などの著作にくわしいので、とくには触れない。ここでの私の関心は、神戸の、きわだって知的で裕福な家庭にそだった若い女性が、鉄道員の息子ペッピーノとの結婚によって、生まれてはじめて貧困の現実をじぶんで生きることになった。その落差によって須賀がうけた衝撃の深さにある。それを知る手がかりとして、もういちど戦後イタリアのネオ・レアリズモ映画に頼ることにしたい。
戦争が終わって10年がたち、マーシャル・プランの時代も終わって、庶民の暮らしはいくぶんか楽になっていた。そんな時期、つまりネオ・レアリズモ運動の末期につくられた映画に、ピエトロ・ジェルミ監督の『鉄道員』がある。『ミラノ 霧の風景』中の「鉄道員の家」によると、1956年製作のこの映画を、須賀はペッピーノが67年に死んで20年ほどのち、東京ではじめて見たらしい。
〔夫が死んでまもないころに〕もしこの映画を見ていたら、おそらく私は自分が溶けてしまうほどの、もういちど立ち上がれないほどの衝撃を受けただろう。ごくはじめのところで、主人公〔ジェルミ監督がみずから演じるローマ・ミラノをむすぶ急行列車の機関手〕が夜中によっぱらって家に戻ってくる場面がある。ドアに鍵をさしこんで家に入っていくと、家族はみんな出かけていて、あたりは真っ暗だ。その瞬間、あ、スイッチは左側にある、と私のなかのだれかが言って、私を完全に打ちのめした。どの鉄道官舎も間取りが似ていて、映画に出ているアパートメントは、それほど、あのミラノ・ローマ本線の線路沿いの夫の実家そっくりだったのである。

いかにも、この時期になると、庶民の暮らしはたしかにいくぶんか楽になっていた。とはいえ、それは敗戦直後の極限的な貧しさにくらべればという話で、おなじ時代の日本と同様に、とうてい豊かといえるまでにはなっていない。
そんななかで、鉄道官舎の狭い家に古い家具がぎっしり詰めこまれ、その隙間で、頑固な鉄道員の父とやさしい母、そして3人の子どもたちがひしめきあって暮らしている。それが映画『鉄道員』の世界なのだが、それからさらに10年がたち、須賀敦子が次男の「嫁」として実家をおとずれたときも、鉄道官舎では、まだおなじような暮らしぶりがつづいていたらしい。
ただし、彼女を「打ちのめした」のは、たんなる物質的な貧しさではなかった。
映画『鉄道員』では、主人公のベテラン機関手が、ある日、とびだした自殺者を轢き、そのショックで赤信号を見のがして衝突事故を起こしそうになる。それによる不本意な左遷に、娘の離婚と息子の家出がかさなり、やけになったかれはスト破りに走って仲間から孤立してしまう。
そして、『トリエステの坂道』にある「キッチンが変った日」というエッセイによると、ペッピーノの家族もまた、戦後すぐ、これによく似た、いや、それ以上に大きな不幸の連鎖を経験していた。まず兄のマリオ、ついで妹のブルーノが、どちらも「貧乏人には死に到る病として恐れられていた結核」で死ぬ。そして、こんどは信号手の父親が機関車に接触し、化膿した傷口を癒やせないまま長いあいだ苦しみ、退院後のある日、ちょっと横になるよ、といったきり死んでしまう。ようは戦後、この一家にはペニシリンなどの高値な抗生物質を買う力がなかったのです。
こうして「三人の生命が、短いあいだにむごたらしく家族からもぎとられて、ひきちぎられていったあと」と、須賀は「キッチンが変った日」にしるしている。
……〔そこにあるのは〕このうす暗い部屋と、その中で暮らしている人たちの意識にのしかかり、いつ熄むとも知れない長雨のように彼らの人格そのものにまでじわじわと浸みわたりながら、あらゆる既成の解釈をかたくなに拒んでいるような、あの「貧しさ」だった。(略)私は、彼らが抱えこんでいるその「貧しさ」が、単に金銭的な欠乏によってもたらされたものではなく、つぎつぎとこの家族を襲って、残された彼らから生への意欲まで奪ってしまった不幸に由来する、ほとんど破壊的といってよい精神状態ではないかと思うようになった。
そしてこの家族をさらなる不幸がおそう。精神的にも物質的にも、のこされた一家の大黒柱ともいうべき次男のペッピーノが死んだのだ。
以下、松山の年譜によってしるすと、1967年3月、「ペッピーノが肺の病にかかるが、一時快方にむかい、収入が少なく、入院させることをためらう」うちに、容体が急変。「無理にでも早く入院させていたらと、悔やむ」も、ほどなく6月3日、まことにあっけなく世を去っていった――。
ここでの「ためらう」や「悔やむ」の主語はもちろん須賀敦子ですね。
この一家は「貧しさ」ゆえに、父親のみならず、息子や娘までもむざむざと死なせてしまった。その4人目のペッピーノの死後、あとにのこったのは乏しい年金で暮らす老いた母親と、たよりない弟だけ。つまり、これは裕福な家庭の娘として異国にやってきて、思いもよらず、そんな境遇においつめられた女性の「ためらい」や「悔やみ」にほかならないのです。
それからまた20年がたち、須賀は東京で『鉄道員』を見て、あの当時、この映画を見たら、「自分が溶けてしまうほどの、もういちど立ち上がれないほどの衝撃を受けただろう」と感じた。そして『ミラノの奇蹟』とちがって、なぜか『鉄道員』の話をしようとしなかった生前のペッピーノのことを思いだす。
――あのころは気づかなかったけど、かれはきっと、「貧しさ」によって「生への意欲」をうばわれた一家の苦しみを、この映画であらためて確認させられるのがいやだったのだ。
しかも、その「破壊的といってよい精神状態」が、ペッピーノ自身の死によっていっそう決定的なものになる。その「破壊的」のうちには家族の一員として「私」もいた。それがおそらく須賀のいう「立ち上がれないほどの衝撃」が意味することだったのでしょう。
そして、こう考えると、はじめに引いた「福祉という柵」という文章の、「もし私が、そんな福祉の対象になる立場に置かれたとしたら、どんなにつらいだろうか」という1行が、以前とはべつなふうに読めてくる。
この文章は「福祉の対象になる」者ではなく、かれらを「ふつうの人間と同じように生きられない」と決めて、福祉の「柵」の向こうに追いやってしまいかねない者の視点から、みずからを批判するというしかたで書かれている。通常、そうとしか私たちには読めない。
しかし須賀がこの文章を書いたのは1977年――ペッピーノの死からまだ10年しかたっていない時期なのです。とすれば、ここでの「もし私が……」という一行も、ただのカタチだけの仮定ではない。そこにはわずか10年まえ、じぶんがイタリアで「福祉の対象」になりかねない貧しい家族の一員であったころの「つらい」記憶が、まだなまなましく染みついていたにちがいない。そう考えることも可能なのではないか。
1977年といえば須賀が日本にもどって6年後――その間、彼女は練馬区関町に設けた「エマウスの家」を拠点に、20人ほどのボランティアの若者たちとともに廃品回収にはげんでいた。帰国まえに神戸暁光会のヴァラード神父とイタリアで会い、そこでの話にはじまる運動だったらしい。
この「エマウスの家」の活動については、須賀もほとんど語っていないので、具体的なことはよくわからない。
でも、それがゴリゴリの使命感というよりは、「ためらい」や「ゆれ」や「うたがい」もすすんで受け入れる、ゆるいかたちの運動だったらしいというていどの推測はつく。そんななかで須賀は「家」に寝泊まりし、ときには廃品回収のためGパン姿で小型トラックを運転してまわったりもした。ただし、そこにはいつも「あれあれ、オバサンがそんなむりをして」という笑いがつきまとっていたみたい。その点で、ともすれば美談にされがちだった往年のバタ車をひく北原怜子とはちがう。
そして1975年の末に「エマウスの家」のリーダー役をしりぞき、大学教師と物書きの暮らしに移ってゆく。カトリック入信と聖心での奉仕活動にはじまる彼女の宗教的な活動家時代の終わりです。そのあと『ミラノ 霧の風景』にはじまる日本での7年間の短い文筆生活をへて、1998年に69歳で没した。もしいまの私の年齢まで生きることができたら、やがて大きく完結したかもしれない「世界文学」の構想をあとにのこして。
北原怜子『蟻の街の子供たち』三笠書房、1953年→聖母の騎士社「聖母文庫」、1989年
松居桃楼『蟻の街の奇蹟』国土社、1953年
松山巖『須賀敦子の方へ』新潮社、2014年→新潮文庫、2018年
須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』文藝春秋、1992年→文春文庫、1995年
須賀敦子『トリエステの坂道』みすず書房、1995年→新潮文庫、1998年
須賀敦子『ミラノ 霧の風景』白水社、1990年→白水Uブックス、2001 年
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








