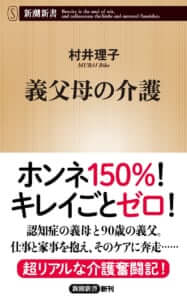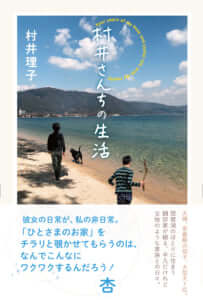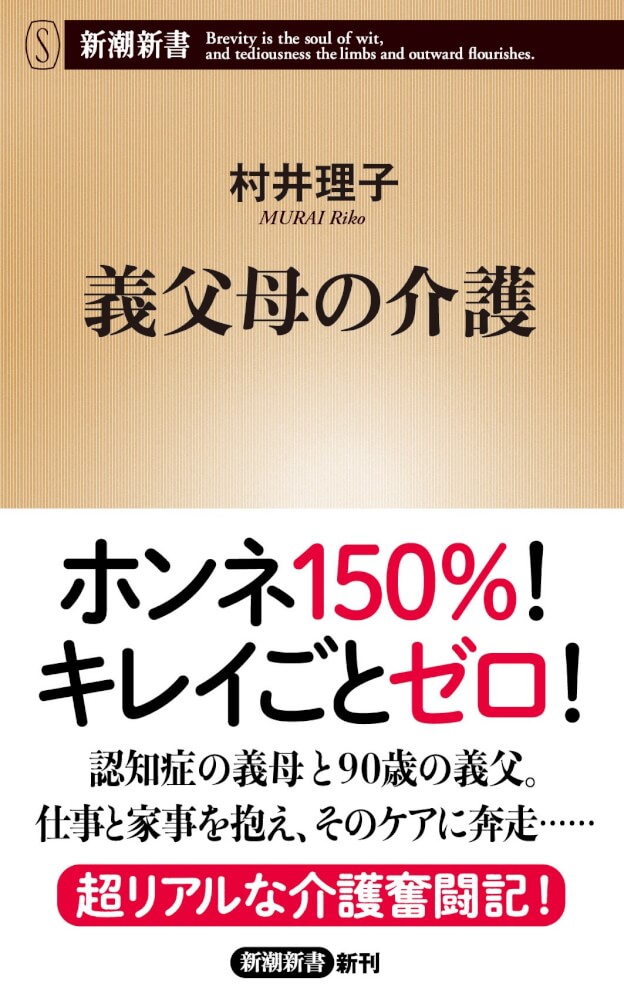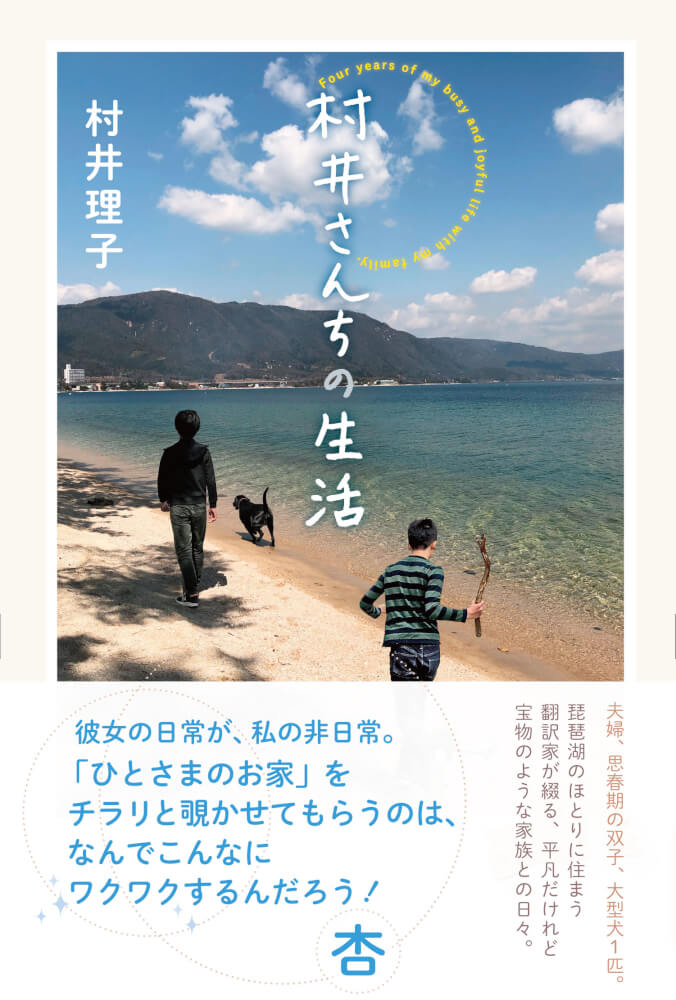村井家の後期高齢者介護は、特に大きな事件もなく、坦々と過ぎていっている(もちろん小さな事件は数え切れないほど発生しているが)。介護を経験している方々はおわかりかもしれないが、介護の現場において、何も特別なことが起きていないということは、とても良いことなのだ。介護されている側からしたら、坦々とした日常は退屈かもしれないが、介護している側からすれば、すべてがスムーズに回転している日々は貴重だ。いつ何時、何が起きるかわからないのが認知症患者や後期高齢者の日常で、電話が鳴ってビクッとなる回数が減るだけで、こちらの生命力もアップしてくるように思える。
余裕が少しできて気が楽になった途端に、目の前がぱっと明るくなり、気づいたことがたくさんある。今回は「後期高齢者介護ライフハック」を書いてみようと思う。
最近、夫が以前より介護に関わるようになったことで、私が夫の実家に登場する機会が減った。そんな状況でたまに実家に立ち寄ると、義父も義母も、やっとチャンスが来たとばかりに、私にいろいろと頼み事をするようになった。
それも、声を潜めて「〇〇(夫の名前)には言わないで欲しいんだけれども……」という言葉ではじまる頼み事だ。その内容はといえば、食材の量を減らしてほしい、お弁当の量を減らしてほしい、お菓子の量を減らしてほしい……などなど、すべて夫が持ち込む食材の量を減らしてくれというものなのだ。
実の子の介護と、義理の関係の介護の違いは、このような場面でも微妙に出る。私は主婦だということもあって、食材を使い切ることの難しさはわかっているので、持ち込む量は最低限にしている。生野菜はほぼ、持ち込まない。持ち込む前にはひと工夫している。例えばほうれん草やニンジンには、あらかじめ火を通す。きゅうりは刻み、トマトはスライスする。すべて少量にして、一日で食べきることができる量にしている。
一方夫は、子の親に対する愛情だろう、良い食材をドーンと大量に持ち込む(ステーキなど)。両親に食べさせてあげたいという気持ちは痛いほど伝わるが、調理のことは考えないようだ。片付けのことなど、無論考えない。夫が悪いのではない。ただ、そういう現実があるということだ。
時々大量に野菜などを送りつけてくる親に腹が立つという投稿をSNSで散見するが、わが家の場合は逆パターン。子が親に対して「たっぷり食べてほしい」と思う気持ちで持ち込む食材に対して、親は消費することに苦労しているというわけだ。冷蔵庫を開けて中身を確認しながら「なるほどねえ〜」と言う私に、義父母はすがるような目で私を見ながら、「頼む」と言っていた。私はこれをわがままだとは思わない。義父母もありがたいと思いつつ、食材を消費できない罪悪感を抱えているのだろう。
義理の両親の訴えがあってから、私がある程度下準備した食材が、夫によって義父母の実家に運ばれるようになった。寒いから豚汁と思うのなら、作ってから鍋ごと持っていくようにした。最近はお米を炊くことにも苦労しているようなので、わが家で炊いて、0.5合ずつラップして冷凍し、それを持ち込むようにした。食材の切り方にも工夫が必要になってきている。嚥下が難しくなってきている義父に配慮して、多くの食材を小さめに刻むようにしている。
この時参考にしているのが、保育園や小学校の給食だ。最近ではSNSで給食の調理動画が増えているために、レシピには一切困らない。本当に不思議なことに、高齢者には子どもの給食メニューが大ウケなのだ(ちなみに参考にしているのは、「あおいの給食室」)! ちなみに高校生もよく食べる。
そしてもうひとつ気づいたことがある。介護する側は、ネットバンキングやネットオーダーなど、インターネットを利用したサービスの利点を最大限に利用すべきだということ。高齢者の家には毎月、予想外の請求書類が到着する。お花代、青汁、いただいたプレゼントへのお礼代金……その多くが銀行振り込みだったりする。高齢者が支払に行くことが不可能な状況で、彼らにとって大きな負担だ。義父はいままで数千円の料金を支払うために、タクシーで銀行まで行き、待っていてもらい、家まで送ってもらっていた。支払額よりタクシー料金の方が高いという状況だった。コンビニでの支払はできない。機械が怖いし、店員さんに迷惑をかけたくないそうだ。
今は、私が実家に行く度にそのような請求書を精査して、可能な限りその場でケータイを使って振り込むことにしている(PayPayによる決済も楽でいい)。もちろん、その金額は義父が手渡してくれる。時々多めに渡してくれるので、しめしめと思いながら素直に受け取って、帰りにケーキを買ったりしている。知り合いにお菓子を贈りたいという義母からの願いも、その場でインターネットショップで解決する。高齢者にとって、些細なことが心の負担になりがちなので、とにかく、ツールを揃えておいて、様々な状況に対応してあげることがいいのではないかと思う。会話が途切れたら、iPadで古いドラマを見せている。こういう工夫もできるのだ。
そして最後は、これは工夫というか、私の個人的な、介護における最大の楽しみなのだが、義父母に頼まれるまま荷物の整理をする際に見つけた、私の趣味にバッチリ合う古いお宝を、義父母の許可を得て、譲り受けている。
先日は、義父が現役の頃に使用していたという大変古い重箱を発見した。あまりにも素晴らしい塗り物の重箱で、ひと目見て「なにこれ、じいさんの持ち物にしてはかわいいやん」と思い、「お義父さん、この重箱、いらないんですか?」と聞いてみた。すると義父は、「おお、さすがやなあ。それはすごくいい重箱で、四十年前に買った当時も結構な値段がしたものやで。あんたが使いなさい」と言ってくれた。おせち料理には忸怩たる思いがあるものの、かわいいは正義だ。あっさり頂いて、今は私の部屋にある。義母からは古い文学全集をたっぷり頂いた。義母が読書家でよかった。私のお宝は増え、義父母の家は片づく。こんなに素晴らしいことはないじゃないですか。面倒くさいことも、宝探しと考えたら、すごく楽しいことになるのだ。
今回はこんな形で、ささやかな介護のライフハックを紹介したが、もし読者のみなさんにもアイデアがあれば、教えていただきたい。
-

-
村井理子
むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 村井理子
-
むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら