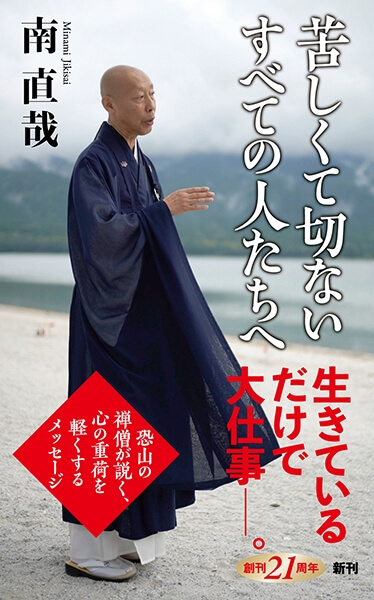九、小指の折れたダースベイダー
著者: 南直哉
なぜこの世に生まれてきたのか? 死んだらどうなるのか?――その「答え」を知っているものなどいない。だから苦しい。だから切ない。けれど、問い続けることはできる。考え続けることはできる。
出家から40年。前著『苦しくて切ないすべての人たちへ』につづいて、「恐山の禅僧」が“生老病死”に本音で寄り添う、心の重荷を軽くする後ろ向き人生訓。
肋骨を2本、折ってしまった。面目ない話である。
この原稿を書いているのは5月15日、今のところ、額を畳に着けての、正式な礼拝ができない。情けないことである。
骨折したのは4月の29日。その前1週間は、福井の本山(永平寺)にいた。年間で最も大きな法要で、連続説教をするように命ぜられ、ありがたい役目なので、気合を入れて頑張ったわけである。
その疲れもあったか、29日午後、自分の住職寺に戻って、本山から持ち帰った荷物を片付けていた時に、階段で足を滑らせたのだ。
左胸から叩きつけられるように落ち、しばし息もできない激痛。折れたとすぐにわかった。ただ、5分ばかりうずくまっていたら、息が通って、立てた。立てたら、歩けた。試しに鞄を持ったら、右手には持てる。
5月1日は恐山の開山日である。少なくとも29日中に東京まで出ていないと、この大事な日に、本尊の前に立てない。私は、馴染みのタクシー運転手による、「このまま病院に行きましょう」という、同情に満ちた再三の説得を振り切って新幹線に乗り、30日の夕方には、青森に戻った。その直後に行った救急外来で、肋骨2本の骨折が確定したのである。
67歳直前の骨折者の帰還について、周囲の評価は、「バカ」と「ムボウ」に二分された。昔の「死んでもラッパを放しませんでした」の兵隊ではないが、「折れても恐山に帰った」院代だったのである。ゴールデンウィークの法要と法話は、まさに「特攻」的蛮行だったと言えよう。
実は、この種の「蛮行」は、これが初めてではない。本山修行時代に一度やっているのである。
修行道場には、夏と冬に100日間を限りとして2回、「安居」と呼ばれる、いわば修行強化期間がある。この期間中は、原則として修行僧の外出を一切禁じ、修行に集中する。例外は疾病・負傷、師匠から要請された緊急の要件くらいである。
期間中、道場は「首座」という修行僧のリーダーを選ぶ。入門2年目くらいの者がなる。そこに「書記」と名付けられた補佐役が付く。4年目以上の古参がなる場合がほとんどだ。さらに、この二人の身辺の世話をする、「弁事」という、この年に入門した1年目の修行僧がいて、以上3名で「首座寮」と称する部署を構成する。
すると、鉄壁の年功序列組織である道場の内実を知る者は、一目了然、期間中の実権を「書記」が握っていることを理解する。「書記」が最高権力者とは、どこぞの国の独裁政党のようだ。
私は、入門4年目の夏、この「書記」になった。まだ「ダースベイダー」と呼ばれる前であったが、当時を知る者は、「あの頃がとにかく一番ヤバかった」と言う。
私は、熱意に満ちた首座から懇請されて、書記になった。彼の純情な期待に応え、近来稀なる強度の修行で、この期間を貫こうと決意したのは、当時の自分の浅はかさからして、致し方ないことであった(後輩にとっては、「致し方ない」ですむ話ではない)。
かくして私は、「安居」突入の朝、修行僧を招集して、仁王立ちで訓示した。
「いいかあ! 今回の安居は全員一丸、修行一色でぶち抜く!! 外出は一切許さん!!! 風邪なら肺炎、ケガなら骨折、外に出られるのは、その時だけだ!!!! わかったかああ!!!!!」
「はああいいっっ!!!!!!!」
これを聞いた者たちの何人かは、「この安居は大変だ、もしかすると犠牲者が出るかもしれん」と思ったそうである。
文字通りの大号令を発して、私は意気揚々と首座寮に引き上げた。その時、途中の廊下の敷居に、右の足先が引っかかって、妙な姿勢でよろけた。
「パキッ。」
澄んだ小さな音がした。途端に、右足の小指に、ハンマーで叩かれたような激痛。疑いようもなく折れたのである。右足は踵だけで歩いて首座寮に帰ると、小指はすでに紫色に腫れ上がり、親指ほどの太さになっていた。
私「まいったなあ」
首座「ヤバいですよお……」
弁事「書記おっさん(和尚さん、の意)、早く病院に行かんと」
私「行けるわけないだろ!」
弁事「だって……」
「大号令」の舌の根も乾かぬうちに、「ぶち抜く」覚悟の最高権力者が、いかに骨折といえども、おめおめ外出できるわけがない。どうする? 隠す以外にない! 3人は鳩首合議した。「文殊の知恵」を出そうと言うのだ。
まず、歩けるか。一歩ごとに涙が滲むかもしれないが、何とか歩ける。正座も、最初は痛いが、途中で麻痺する。すると、朝のお勤めは大丈夫だ。この時期、檀信徒が申し込む供養の法要が多く、その時には規則により「襪子(法要用の足袋)」を着けるので、指は見えない。
しかし、僧堂での坐禅は素足であり、そもそも包帯を巻いたような負傷者は、堂内には入れない。私は弁事に言った、
「オイ、ガムテープを持ってこい」
「えっ?」
ベージュのバンデージなどという気の利いたものは、当時の道場にはない。とにかく肌色っぽいものを巻き付けて固定すれば、僧堂内は暗いから、さほど目立たず乗り切れるだろう。なんとかなるかも、と思いかけた時、首座が言った。
「でも、振鈴はどうします?」
振鈴とは、道場での起床の合図で、柄のついた大型の鈴を持った修行僧が二人、大伽藍を上下に分かれ、鈴を振り振り、全力疾走で一周するのである。首座寮は3人が交代で、階段だらけの上回りで鈴を振ることになっていた。
「ダメだ。歩けても、走るのは無理」
首座と弁事は当然だろうという顔で言った。
「振鈴は二人でしますから、いいですよ」
「ダメだ。ケガがすぐバレる」
「でも、その足で……」
「うーん、もはや是非もない! キセルをやろう!」
「はあ?」
私は提案した。朝、修行僧が起床して、寝具を片付けたり衣を着たりで、まだ堂内にいる間に、私が最初の鈴を振り、大階段の下で待機している弁事にタッチする。弁事は、修行僧が身支度して堂から出て来るかどうか、という間合いで大階段を駆け上がり、建物に跳び込む。
建物内でも、まだ修行僧は各部署にとどまっていて、階段・廊下に人目は乏しいから、この間に弁事は建物を突っ切り、反対側の階段を駆け下りて、そこに待っている書記(つまり私)に鈴を渡す。受け取った書記は何食わぬ顔で、階段や回廊に出始めた修行僧の目の中で、鈴を振る。これが「キセル」である。
「5日以内にバレますよ」
「黙れ! これはもう、志の問題だ!」
我々は、このキセルをひと月以上実行した。だが、5日ではバレなかった。そうではなく、2日目の朝には、全部バレていたのである。骨折も、キセルも、ガムテープぐるぐる巻きの坐禅も、青ざめた顔をして耐えた正座も、全部。
安居が終わり、しばらくしてから、私は何人かから聞いた。
「あの朝、書記おっさんが骨折したという話は、たちまち山内に広まりました。だから、その日のうちに病院に行くと、みな思っていました。骨折なんだし」
「でも、行かない。翌朝、最初と最後だけ、スキップみたいな変な走り方で、振鈴をしている。坐禅に出てきたと思ったら、妙な靴下みたいなものをはいている。よく見りゃ、ガムテープだ」
「あれで、我々はみな、思いました。今度の首座寮は本気だ。書記が口に出したことを甘く考えると危険だ」
「この安居は、お互い体に気を付けよう。これじゃあ、骨折しても外に出してもらえるかどうか、わからないぞ。ともかく100日は彼らに従って無事に過ごそう、そう言い合いました」
彼らは、全て承知の上で、何も言わずに我々に従い、協力してくれたのである。
おそらくこの日から、私は「ダースベイダー」の道を歩きはじめたのだ。後に「怖がられていることは確かだが、本人が思っているほど嫌われていない」と言われた、右足の小指が曲がっている「ダースベイダー」である。
*次回は、7月7日月曜日更新の予定です。
-

-
南直哉
禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 南直哉
-
禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら