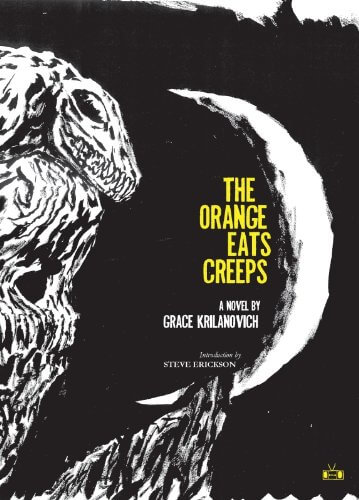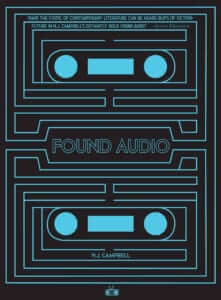(17)インディーで行こう
Grace Krilanovich, The Orange Eats Creeps (Two Dollar Radio, 2010)
N. J. Campbell, Found Audio (Two Dollar Radio, 2017)
著者: 柴田元幸
作家のケリー・リンクが夫と経営しているSmall Beer Press(small beerとはアルコール分の薄い安価なビール。「つまらないもの」の比喩として使われたりする)や、文芸誌『グランタ』の元編集者ユカ・イガラシが引き継いだSoft Skull Press(「柔らかい頭蓋骨」は特に熟語とかいうことではなく造語)など、アメリカのインディー・パブリッシャーズ、すなわち独立系出版社には気の利いた名前が多い。なかでも、個人的にいい名だと思うのは、2005年創立、オハイオ州コロンバスを拠点に、やはり夫婦で経営している小出版社Two Dollar Radioである。会社のロゴはこんな感じ。
地元の本好きが集まるカフェを経営し、超低予算映画をたまにプロデュースしたりしながら、“books too loud to ignore”(無視するには騒々しすぎる本)をモットーに年に6冊ずつ本を出している出版社である。
僕が最初に出会ったTwo Dollar Radioの本は、グレイス・クリラノヴィッチの『オレンジはヘンタイを食う』(Grace Krilanovich, The Orange Eats Creeps, 2010)である。迷わず買ったのはスティーヴ・エリクソンが序文を書いていたからである。彼が推す作家なら、少なくとも刺激に欠けるということはありえない。
We are sluts. We not only devour each other, but we bite, hard. We’re blood-hungry teenagers; our rage knows no bounds and coagulates the pulse of our victims on contact. We devour them too; the bodies of mortals become drained when they reach our fangs. Our cause is nothing, we believe in nothing. Actually, we believe in Methamphetamine. I’ve been living off crank, cough syrup, and blood for a year now. I ride the rails with a bunch of immoral shitheads, hopping freight trains, secreted away in rail cars across this country. We have no home, no parents. I can’t remember being a child, maybe I never was one. But I’m sure I’ll never die; I get older, my body stays the same. My spine breaks, and then gets back together. I have the Hepatitis, I give it to everyone, but it never will actually get me. Our kind doesn’t die from anything, all we do is die all the time.
あたしたちはあばずれ。たがいを貪り喰らうだけじゃなく、嚙みもする、力いっぱい。あたしたちは血に飢えたティーンエイジャー、あたしたちの怒りはとどまるところを知らない、あたしたちの餌食に触れただけでそいつの脈は凝固する。あたしたちは餌食も貪り喰らう、死すべき人間の体はあたしたちの牙に届いたとたん血が抜ける。あたしたちの大義は何もない、あたしたちは何も信じない。いや、メタンフェタミン〔ヒロポンと同じ〕は信じるか。あたしはこの一年、クランク〔メタンフェタミンの粉末〕と、咳止めシロップと、血で生きてきた。あたしは背徳の麻薬常用者の連中に交じって列車にタダ乗りする、貨物列車に飛び乗って、車両のなかにこっそり隠れてこの国を旅する。あたしたちに家はないし、親もいない。自分が子どもだったことをあたしは思い出せない、もしかしたら子どもだったことなんかないのかも。でも自分が絶対死なないことははっきりわかる、年をとっても体はそのままだ。背骨が折れても、また元に戻る。あたしは肝炎を持っていて、みんなにうつす、でも自分は絶対にやられない。あたしたち一族は何があっても死なない、あたしたちはいつもいつも死んでるだけ。
というわけで、吸血鬼の若者たちが、ほとんどすべてスーパーとコンビニと駐車場から出来ているように思える今日のアメリカを、なぜか1930年代の大恐慌時代っぽく貨物列車で放浪する。ストーリーはあってないに等しく、一足先に旅立った姉を探そうという語り手の女の子の想いのみを緩い指針に、出来事や記憶がほとんどランダムに羅列される。これはまあやっぱり大手出版社からは出ないだろうなと思うが、全篇を貫く駆動感は大したものである。まさに「無視するには騒々しすぎる本」。スティーヴ・エリクソンの序文は、本の凄味とエリクソンの凄味両方を伝えているので一部紹介しておきたい。
I’m probably getting too old to speak for the times, so I won’t guess as to how this novel speaks for them. I think it can be called a romantic novel, if you want to, but if so then it’s the romanticism of excess—of experiential derangement and a carnal nihilism that reveals itself as an act of liberation before it’s exposed as an act of courage. A young nomad haunted by visions of her lost sister searches for something she can’t identify, driven by a nearly feral instinct that will know what she’s found only when she's found it. The woods she infests and the beaches she crosses are filled with wild music, wilder oaths and their subsequent betrayals, the wildest silences and the whispers that finally rupture such silences. The narrator falls into and out of the company of other young subterraneans. I think there’s love in here but that may be sentimentalism on my part. What there certainly is is a pulse, an arterial signal, a viscera of the psyche, and though for some the intensity and boldness may be a shock, for the rest of us the exhilaration of such a novel is nearly beyond calculation.
私はたぶん時代を語るには年をとりすぎてきているだろうから、この小説がどのように時代を語っているかは考えない。何ならこれをロマン主義的な小説と呼んでもいいと思うが、だとすればそれは過剰さのロマン主義だ――経験に基づく錯乱と、解放の行為として自らをさらすがやがて勇気の行為であることが明らかになる肉体的ニヒリズムとのロマン主義。失われた姉の幻影に取り憑かれた若い放浪者が、自分でも何とはっきりは言えない何かを探す。彼女を駆り立てるほとんど野獣的な本能は、何かを見つけて初めて自分が何を見つけたかを知るだろう。彼女が寄生する森や横断する海辺には狂おしい音楽が満ちている。もっと狂おしい誓いと、やがて生じるその裏切りに満ち、最高に狂おしい沈黙と、いずれその沈黙を破裂させる囁きに満ちている。語り手はほかの若き地下人たちの仲間に加わり、また逸れる。ここには愛があると思うが、それは私の感傷にすぎないかもしれない。間違いなくあるのは脈動であり、動脈の信号、魂のはらわたである。一部の人々にとって、その烈しさと無謀さはショックかもしれないが、私たちのような連中にとっては、こういう小説がもたらす高揚はほとんど計算のしようもない。
こういうものを書く人が次にどういうものを書くのか、そもそも次を書く必要があるのかどうかもよくわからないが、現在までのところ、グレイス・クリラノヴィッチ第二作は発表されていない。ツイッターを見る限り、充実した子育て生活を送っているようではある(ちなみに、ヤッピーのシリアルキラーを描いたブレット・イーストン・エリスの怪作『アメリカン・サイコ』を独特の静謐感に包まれた映画に仕立てた女性監督メアリー・ハロンが、現在『オレンジはヘンタイを食う』を原作とする映画を撮っている模様。楽しみである)。
そしてつい先日出会ったTwo Dollar Radio本は、これもやはりデビュー作で、N・J・キャンベルの『ファウンド・オーディオ』(N. J. Campbell, Found Audio, 2017)。“Found audio”というのは“found object”、すなわちそこらへんに落ちていた物とかで作る芸術の呼び名(日本ではフランス語を使ってObjet trouvé〔オブジェ・トゥルーヴェ〕と呼ばれる方が多いか)のもじりだろう。読んでみるとまさに、偶然発見されたカセットテープに吹き込まれていた独白の書き取り、という設定の文章が作品の大半を占めている。「N・J・キャンベル」がこれらのテープをどのような経緯で入手したかのメモ、テープ起こしをした人物の断り書き、などいかにもそれらしい外枠的な文章が並んだあと、1998年ごろに録音されたと思しき“Tape 1”は次のように始まる。
[Male, Age: 48-52. United States American, Midwestern Accent. Designation: “American”]
[American]: In ’91 I went down to the bayou, because I had heard of a man who bounty-hunted snakes—not water moccasins or any other native snake, but pythons and anacondas and big-game species that had been imported as house pets from Southeast Asia and dumped into the bayou. They bred and became invasive species. Actually, now there’s a hunting season for invasive snake species in the South every year in the Everglades with prize money for the largest haul. The name of the man I was looking for was Otha Johnson. He was a Louisiana native that I had heard of when doing a piece for National Geographic on the shifting waterways of the Everglades. A friend, the French-Algerian journalist Julien Belmonte, had mentioned him in passing as one of the "natural wonders" in the area. He said that as this man’s full-time occupation was to hunt and kill snakes for the Department of Natural Resources, he was sure to be a good story. He said that he had actually tried to track him down a few years before, while he was working with my ex—the award-winning journalist Bianca Terrazas—on an assignment about modern-day trappers. I thought, if they couldn’t do it, I wanted to, and I immediately started doing some background research on the guy.
〔男性、48-52歳、合衆国アメリカ人、中西部訛り、以下「アメリカ人」〕
アメリカ人 91年に私は南部のバイユー〔緩やかな流れの澱んだ水域〕に行った。金目当てで蛇を狩る男の話を聞いたからだ――ヌママムシとか土着の蛇じゃなくて、ニシキヘビとかアナコンダとか、家庭用ペットとして南米から輸入されてバイユーに捨てられた大物の種とかを狩るのだ。実際、今日の南部では毎年、エヴァグレーズ〔フロリダ南部の大湿地帯〕で侵入種の蛇の狩猟期がちゃんとあって、一番大きいのをつかまえた奴に賞金が出る。私が探していた男の名前はオーサ・ジョンソンといった。ルイジアナ生まれで、私は『ナショナル・ジオグラフィック』の依頼でエヴァグレーズの水路の変化について記事を書いている最中にこいつのことを聞いた。ジャーナリスト仲間で、フランス゠アルジェリア人のジュリアン・ベルモントが、何かのついでに、あの地域の「自然の驚異」のひとつとして奴の名を挙げたんだ。天然資源省に雇われて蛇を狩って殺すのがこの男の本業なんだ、面白い記事が書けると思うぜとジュリアンは言った。実際、ジュリアンも何年か前にこいつを探し出そうとしたことがあったという。奴が私の元恋人――売れっ子ジャーナリストのビアンカ・テレザスだ――と組んで、現代の罠漁師について調査を進めていた最中のことだ。こいつらができなかったんだったら俺がやってやろうじゃないか、と私は思って、すぐにこの男の背景を調べはじめた。
ソースは文書ではなくテープであるからして、一部ノイズが入って聴きとれなかったり、背景に不思議な音が聞こえたり(頭上でヘリコプターが飛んでいる音が22秒続くとか――“The distance is difficult to gauge”〔距離は測りがたい〕とわざわざ書いてあってそりゃそうだろうと思うが、何せテープ起こしをした人間はオーディオテープの録音時期・状況特定のプロなのだ)、欠落した物語が重ね合わされたり入れ子状に組み合わさったり……と、ポストモダン小説的手法の典型的一変形という感じで、なかなか楽しそうである。が、「無視するには騒々しすぎる本」というのとはちょっと違うんじゃないか? と始めの方では思える。それに、この本にもスティーヴ・エリクソンが推薦文を書いているのだが、その“Amid the static of contemporary literature can be heard blips of fiction-future in N. J. Campbell’s defiantly bold Found Audio”(現代文学の雑音に混じって、フィクションの未来のパルスが聞こえる――N・J・キャンベルの挑戦的に大胆な『ファウンド・オーディオ』のなかに)という、例によってエリクソンらしい熱い言葉からするとこの本、いささか軽すぎないか? と思ってしまう。が、読み進めていくと、取り壊し寸前の九龍の城砦をはじめ夢とも現実ともつかぬ場から場へ主人公が転々とし、「夢の街」を探しはじめるなか、ポストモダン的な遊びがだんだん「本気」になっていくようにも思えるのである――
“The City of Dreams,” he started, “is different for everyone. And for everyone, it is also the same.”
“Does it have to do with dreams—with actual dreaming?” I asked.
“Oh, yes,” he said.
“So sleep is involved?” I asked.
“In a way,” he said.
Now, it’s not hard to understand that, at this point, I was more or less confused. Was this City of Dreams “The” City of Dreams, the fabled City of Dreams, or—as I stood and thought about it—just a way for the Triads to experiment with how much money they could make by cooperating and then splitting the profits equally?
As I was going about it in the way that I was, I had no way of knowing, but I knew exactly why I was talking to the person I was talking to.
Religion is a powerful tool. Mao knew it, and the Triads, obviously, knew it as well. It works as an opiate, yes, but it also works as an incredibly sophisticated language. The reason I wasn’t frustrated with any of this man’s answers was because I knew he was telling me—with extreme precision—everything I wanted to know. I knew that because I had seen this hundreds of times before with dozens of different religions.
「夢の街は」と男は切り出した。「すべての人にとってそれぞれ違っている。そしてすべての人にとって、同じでもある」
「それって夢とは関係あるんですか? つまり実際の、夢を見る行為と」と私は訊いた。
「ああ、もちろん」と男は言った。
「じゃあ眠りも絡んでるわけ?」
「ある意味では」
想像に難くないだろうが、この時点で私は相当混乱していた。この夢の街とやらは、唯一無二、本物の「夢の街」、名にし負う夢の街なのか、それとも――私はそこに立って考えた――単に三合会の金儲けの実験なのか、協力したのち儲けを等分することでどれだけ多くの金を儲けられるかをめぐる?
こんな感じでやっていては、わかりようもないはずだが、私にははっきりわかった、まさにいま自分がなぜ、この人物と話しているのかが。
宗教は強力な道具である。毛沢東はそれを知っていたし、三合会も明らかに知っていた。それは阿片としてはたらく、だが同時に、驚くほど洗練された言語としてもはたらくのだ。この男の答えのどれひとつにも私が苛立たなかったのは、この男が私に、この上なく精緻に、私が知りたいことをすべて語ってくれているとわかったからだ。それがわかったのは、私がもうこれまでに何百回も、何十というさまざまな宗教でこれを見てきたからだ。
――こういった「夢の意味」「人生の意味」「世界の意味」をめぐる思索(に向かう兆し)がくり返し現われるなか、これをどこまで真面目に受けとればいいのか、僕は最後までわからなかった。これ全部遊びにとっていいんだ、と思うには言葉の端々があまりに真剣に思えたし、反面、この本ははっきり何らかの「道」を説いているのだ、と確信するにはその語りはあまりに混乱していると思えた。要するに、よくわからない。たぶんそれでいいのだろう。この一節でも、男の答えは、「答え」を提示するというよりもはるかに、問いについてより深く考えることを語り手に強いている。この本が読者に強いているのも、そういうことなのだと思う……か、どうかも、実はいまひとつわからないのですが(そしてこれも、それでいいのだろうと思うが)。
ちなみに、本筋とは全然関係ない(と思う)のだが、テープの途中で突然5か国語の断片が飛び込んでくる箇所があって、そのひとつが日本語で、38~42歳の男性が「日本人訛り」で「よろしくお願いします…」と発言する。これに付された“the relatively literal translation”(ひとまずの直訳)というのがなかなか奇怪で、これもまた意図を図りかねた(日本語についての情報提供者がいい加減なことを言ったのか、提供者と作者が合意の上で奇怪な訳を作ったのか……)が、面白いことは間違いない。その「よろしくお願いします」の「ひとまずの直訳」は――
“Favorably, of course—with a hope that we can make this work to our advantage...”
(もちろん、好都合に――私たちがこれを私たちに有利なように持っていけることを期待して)
-
Grace Krilanovich, The Orange Eats Creeps (Two Dollar Radio, 2010)
-
N. J. Campbell, Found Audio (Two Dollar Radio, 2017)
最新情報
12月4日(水)午後7時~8時30分、横浜の朝日カルチャーセンターで講演「アメリカ文学 光と闇」。
12月17日(火)柴田編訳『新装版 柴田元幸ハイブ・リット』、柴田ほか訳『新装版 ポール・オースターが朗読するナショナル・ストーリー・プロジェクト』(ともにアルク)刊行。
12月19日(木)正午~午後9時、原宿のVACANTで「翻訳家・柴田元幸の朗読フェス」。共演トオイダイスケ、坂本美雨、けもの、トウヤマタケオ。
12月20日(金)エリック・マコーマック著、柴田訳『雲』(東京創元社)刊行。
12月21日(土)午後4時50分ー5時50分、東京大学本郷キャンパス法文二号館一番大教室で、日本エドワード・サピア協会研究発表会で講演「翻訳で伝わるもの、伝わらないもの」。
「波」12月号にバリー・ユアグロー連載『オヤジギャグの華』第8回「ミスター・ピーピー」掲載。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら