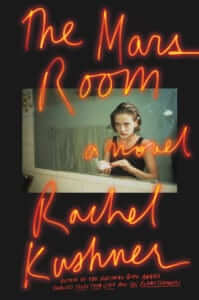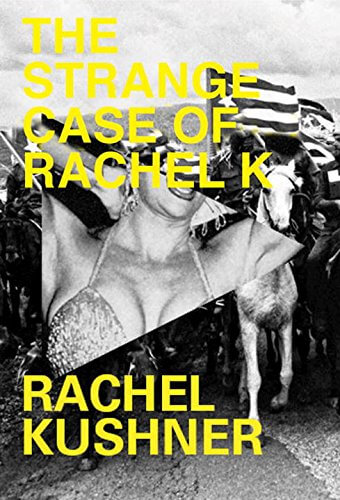(20)ブランズウィック・シチューの作り方 レイチェル・クッシュナー最新長篇がすごい
Rachel Kushner, The Mars Room (2018; Scribner paperback, 2019)
――, The Strange Case of Rachel K (2015, New Directions)
著者: 柴田元幸
レイチェル・クッシュナーのThe Mars Roomは、女性刑務所の話である。当然ながら半端でない悲惨と怒りと哀しみがあるが、と同時に何度も笑ってしまう。悲惨のあいまに笑いが救済のように交じる、なんていうのではなく、悲惨と笑いとがいつも背中合わせにくっついている。たとえば以下は、ウサギを我が子のように可愛がっている囚人がいて、そのウサギを、別の囚人が何食わぬ顔で茹でてしまうというエピソード。
Teardrop had boiled the rabbit in a pot with her stinger while the rest of us were programming. When we came back for afternoon count, the room was infused with the heavy smell of cooked meat.
“What kind of spread is that?” Conan asked.
Brunswick stew, Teardrop said.
Afterward, Conan kept saying, “Didn’t even have no seasoning, I mean nothing,” as if that was the infraction, eating Button’s pet rabbit unseasoned. “Anyway, a proper Brunswick stew is squirrel, not rabbit.”
Button crawled into her bunk with her rabbit’s little shirt that she had sewn. She stayed that way for a day.
“Are you sick?” a unit cop shouted at her.
Button, face in her pillow, did not answer.
“If you are not sick, and not going to your assigned program. I’m writing you up, Sanchez.”
The way Button clutched the little shirt reminded me of how Jackson held his stuffed ducky when he slept. He had been sleeping with the ducky since he was a baby. He would grip it tight, all night long. The last time I saw the ducky was the night I was arrested. Jackson, crying, police all around him. Holding his ducky and screeching. Mommy! Mommy!
“You can get another rabbit,” I told Button. “You’re good with them.”
Eventually she did, and trained it, put the same clothes on it, gave it the same name.
ティアドロップはあたしたちがプログラムをやってる最中、電熱器でウサギを茹でたのだった。あたしたちが午後の人数確認に戻ってくると、部屋じゅう肉を茹でた匂いが充満していた。
「これ、何のごちそう?」コナンが訊いた。
ブランズウィック・シチュー、とティアドロップは答えた。
あとになって、コナンは何度もくり返し言った。「なんの味付けもしなかったんだよ、ほんとになんにも」まるでそのことが――バトンのペットのウサギを味付けしないで食べたことが――いけないんだという感じに。「だいたいさ、ほんとのブランズウィック・シチューってリスなんだよ、ウサギじゃないんだよ」
バトンはウサギに縫ってやった小さなシャツを抱えてベッドにもぐり込んだ。そのまま一日そうしていた。
「お前、具合悪いのか?」担当の看守がどなった。
バトンは枕に顔を埋めて、答えなかった。
「具合が悪くないのに割り当てられたプログラムに行かないんだったら報告書に書くぞ、サンチェス」
バトンが小さなシャツを握りしめてるのを見て、ジャクソンが寝るときアヒルちゃんのぬいぐるみを抱いてたことをあたしは思い出した。赤んぼのころからずっと、アヒルちゃんと寝ていたのだ。一晩じゅう、ぎゅっとしがみついてる。あたしが最後にアヒルちゃんを見たのは逮捕された夜だ。そこらじゅうに警官がいて、ジャクソンは泣いていた。アヒルちゃんを抱いて、ママ! ママ! と絶叫していた。
「また別のウサギ、飼えばいいよ」あたしはバトンに言った。「あんた、育てるの上手だから」
やがてバトンはほんとに別のウサギを手に入れて、しつけて、同じ服を着せて、同じ名前をつけた。
父親だって監獄で息子や娘のことを想うだろうが、母親が息子や娘を想うことにはやはり特別の切なさがある……という命題を前提にするのではなく、語り手をはじめとする囚人たちの言動を通して、そのことを、少なくともこの刑務所では本当にそうなのだと実感させる。感傷に堕さず、読み手の感情にたしかに訴えてくる。この筆力はすごい。もう少し続きを――
Only once had Button talked to me about her own baby. She told me what happened. From prison they took her to a hospital, where they stored her in a room with an armed guard. The guy even followed her to the bathroom, where she tried, in cuffs, a waist chain, and ankle shackles, to clean herself, wash the blood and afterbirth from the insides of her legs, put on the postpartum underwear and giant maxi-pad they tossed her way.
“They had somebody on me the whole motherfucking time.”
I pictured a cop standing over the newborn, already half criminalized, the cop watching it to be sure of no sudden movements.
バトンは一度だけ、自分の赤んぼのことをあたしに打ちあけた。何があったか、聞かせてくれた。監獄から病院に連れていかれて、武装した見張りがいる部屋に入れられた。そいつはトイレにまでついてきた。トイレでバトンは、手錠、腰の鎖、足枷をはめられたまま体を綺麗にしようとした。内股から血と後産を洗い流そうとし、連中が放り投げてよこした産後用の下着と巨大なナプキンを着けようとした。
「四六時中ずうっと、見張りつけられたんだ」
あたしは看守が新生児を見下ろして立ってる姿を思い浮かべた。赤んぼはもう半分犯罪者扱いで、看守は赤んぼが突然動いたりしないか見張っている。
「あたし」ことロミー・ホールは、ストーカーの男を殺した罪で無期懲役2回分の刑を背負っている。出所の望みはゼロ。The Mars Room(火星の部屋)というタイトルは、彼女がストリッパーとして働いていたクラブの名である。刑務所での現在と、The Mars Roomでの過去とが交互に語られるなか(どっちがより悲惨だかよくわからないが、笑えるのは圧倒的に刑務所の方)、囚人に文学を教える教師の男が訪れるようになってから、話は大きく動き出す。『アラバマ物語』などはとっくに卒業していて、ジャンキーたちを描いたデニス・ジャンソンの『ジーザス・サン』に鋭く反応するロミーに教師は惹かれる。ロミーは教師を利用して、なんとか息子ジャクソンと連絡を取ろうとし……筋を明かすのは控えるが最後の数十ページは本当に引き込まれた。これだけ感情を揺さぶられた結末も久しぶりである。
レイチェル・クッシュナーは数年に一冊のペースでじっくり長篇を書いてきた作家だが、The Strange Case of Rachel K(Rachel Kの奇妙な事例)という小品集をThe Mars Roomの前に出している。いつもは大手出版社から本を出しているが、これは昨年小山田浩子の『工場』を刊行するなど良質の翻訳書をたくさん出しているニュー・ディレクションズから。表題作は、Rachel Kというから手の込んだ自己言及作品かと思いきや、ハバナに流れてきたダンサーと、フランス人ナチスをはじめとする男たちの妖しいやり取りが核にある話。
“Zazou dancer Rachel K!”
If she says she’s from Paris, she’s from Paris, is her sentiment. Being from Paris means filing her nails to a point and lacquering them in Hemorrhage Red. Drinking beer with grenadine. Carrying a parasol made of rice paper, with a Chinoiserie pattern like her stage partition—a peacock, lotus and reeds. Wearing painted-on fishnets, dressing like a zazou in short skirts and stacked wooden heels. Eating mouthfuls of cocaine. Douching with champagne. She believes that people are born every minute of their lives, and what they are in each of those minutes is what they are completely. Zazou, and from Paris, are things she does. Things she is by virtue of doing them.
「ザズー・ダンサー、ラシェル・K!」
あたしはパリの出だと言えばパリの出なのだ、そう彼女は考えている。パリの出だとは、爪にやすりをかけて尖らせ、出血の色の赤に塗ること。ビールにグレナディン・シロップを入れて飲むこと。ライスペーパーで出来た、ステージの仕切りと同じシノワズリー模様の――孔雀、蓮、葦――パラソルをさす。絵を描き込んだ網ストッキングをはいて、短いスカートのザズーみたいな服を着て、木のスタックハイヒールをはく。コカインを口一杯頬張る。シャンパンで膣洗浄する。人間は人生の一分一分生まれるのだと彼女は思っている。それぞれの一分のその人間が、まさにその人間なのだ。ザズー。パリの出、それが彼女のやること。それをやることによって、彼女はそれなのだ。〔「ザズー」は第二次大戦中フランスの、アメリカのド派手なファッションを真似たようなサブカルチャー〕
アイデンティティなんてものはその都度作るもの、という発想はアメリカ文学ではお馴染みだが、この人がこうやって書くと何ともリアルで、なまめかしかったり荒々しかったりリアルかつシュールだったりする。
レイチェル・クッシュナーは本人も師と仰ぐドン・デリーロと比較されることが多いが、少なくともThe Mars Roomは情にも強く訴えるという点で、デリーロとはまた違った持ち味がある。
-
Rachel Kushner, The Mars Room (2018, Scribner paperback, 2019)
-
――, The Strange Case of Rachel K (2015, New Directions)
最新情報
3月7日(土)午後7時から青山ブックセンターでポール・オースター『サンセット・パーク』(新潮社)刊行記念イベント。※開催中止
3月24日(火)午後7時から青山ブックセンターで日本文学翻訳者ポリー・バートンさんと対談「縦のものを横に、横のものを縦に―日英翻訳と英日翻訳」。
「波」3月号にバリー・ユアグロー連載『オヤジギャグの華』第11回「コンビニお化けスポット」掲載。
編集部注・イベントの開催については、状況によって変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら