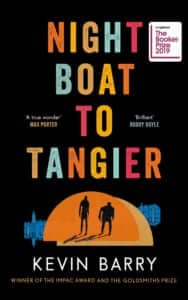2018年秋にケヴィン・バリーが日本に来てイベントを一緒にやってものすごく面白かったのだが、そのとき印象的だったのは、初対面の僕相手でも、ケヴィンがセンテンスの終わりに僕の名前をたびたび呼んだことである。うん、僕は……だよ、モト。君は……をどう思う、モト?
一般論で言うと、そうやってセンテンスの最後に相手の名前を付けるのは、日本語のセンテンスの終わりに「……だよね」「……だからさ」といった語尾を付けるのと似たような機能だと思う。だから、そこから得る印象もまちまちなのだが、ケヴィンの場合、それがとても温かく感じられて、ごく自然に相手との距離を縮めることに長けた人柄のあらわれに思えた。
なので、ケヴィン・バリーの最新長篇『タンジール行き夜行船』の書き出しを読んだときも、つい本人の声を思い出してしまった。
Would you say there’s any end in sight, Charlie?
I’d say you nearly have an answer to that question already, Maurice.
どうだい、なんか終わり見えてきてるかい、チャーリー?
うーん、その問いへの答えは君、もうほぼ持ってるんじゃないのか、モーリス。
読み進めればわかるとおり、この小説のかなり多くの部分は、中年男二人モーリスとチャーリーの会話から成り立っているので、こうやって「チャーリー」「モーリス」と呼びあうのは、誰が喋っているのかをはっきりさせるという実用的効果もあるのだが、むろんそれは副次的な話である。まずはこの呼びあいによって、二人のあいだにある親密さが伝わってくるという点が大事。試しに、原文でも和訳でもいい、“Charlie” “Maurice”を抜いて読んでみてほしい。全然違った感じがするはずだ。
それにしても、見事な会話である。発言一つひとつにしっかり声があり、個性とユーモアがあり、しかもそれをそこらへんのおっさんでも十分現実に使いうる語彙で組み立てている。ケヴィン・バリーはすでに第7回で、ジョン・レノンを主人公とする、やはり会話が見事な長篇Beatlebone (2015) を紹介したが、この『タンジール行き夜行船』ではさらに磨きがかかっている。
もう少し続きを読んでみると――
Two Irishmen sombre in the dank light of the terminal make gestures of long-sufferance and woe—they are born to such gestures, and offer them easily.
It is night in the old Spanish port of Algeciras.
Oh, and this is as awful a place as you could muster—you’d want the eyes sideways in your head.
The ferry terminal has a haunted air, a sinister feeling. It reeks of tired bodies, and dread.
There are scraps of frayed posters—the missing.
There are customs announcements—the narcotraficante.
A blind man roils in night sweat and clicks his teeth to sell lottery tickets like a fat, rattling serpent—he’s doing nothing for the place.
発着所のじめっとした光に陰気に照らされたアイルランド人二人が、忍苦と悲嘆のしぐさをしてみせる。彼らはそういうしぐさに生まれついていて、それらをさらっと当たり前に差し出す。
古いスペインの港、アルヘシラスでの夜。
で、ここは、ちょっと探した程度じゃなかなか見つからないひどい場所だ。目が頭の横に付いてたらいいのに、と思ってしまう。
フェリー発着所は何かに憑かれたような、邪悪な感じが漂っている。疲れた肉体と、恐れの臭いがする。
あちこち破れたポスターの残骸――尋ね人。
税関の告示――麻薬密輸業者。
盲人が一人、夜の汗にまみれてせわしなく動き、歯を鳴らして、太ったガラガラ蛇みたいに宝くじを売ろうとしている。こいつも全然この場の足しになっていない。
中心人物二人に加えて、語り手の声も(翻訳でどこまで伝わるか心許ないが)同じくらいイキがよく、表現がいちいち生きている。これはえらく楽しそうである。
ところが。
モーリスとチャーリーがなぜここアルヘシラスの発着所にいるかというと、これがけっこう深刻な話なのである。
モーリスには3年前から行方不明の娘がいて、その娘ディリーが、今夜この港にタンジールから着くか、この港からタンジール行きの船に乗るかもしれない、という曖昧な情報を彼らは聞きつけてここへやって来たのだ。彼らはチラシを配り、ディリーっていうんだ、ディルかもしれない、小柄な子なんだよ、可愛い子なんだよ、知らないかい、と人々に訊いてまわる。二人ともただの暇なおっさんではないことが明らかになるのである。
とはいえ、そこでもやはり、二人の言葉はどこか漫才的であり、最初に引用した冒頭のかけあいと同じく、ある種の型を演じているような印象を与える。切実さと演技性とが、この小説ではどこまでも絡みあっている。まあ読み進めるなかで、だんだん切実さが前面に出てくる、ということはある。スペインの港にうさん臭い中年男二人となって行きつくまでに、彼らがたっぷり傷つき、それ以上にたっぷり人を傷つけ、麻薬密売で大金持ちになり、その金を無駄に失い(冒頭で「尋ね人」「麻薬密輸業者」への言及があるのは、だから、この小説の主要な要素二点を予告していてなかなか芸が細かい)、自分たち二人のあいだでも大きな裏切りを犯し……と、二人が相当壮絶な人生を送ってきたことが次第に見えてくるのである。
とはいえ、演技性、漫才性の方も、完全に消えてしまうことはめったにない。たとえば、モーリスが片目を失った当時の様子は、次のように語られる。
And a tongue on her, Cynthia. When I came back without the eye on me? From Tangier? She took one look, after all I’d suffered, and she said who the fuck do you think you are, Thom Yorke?
Never heard of him. Or hang about . . . He wasn’t a lame boy from Summerhill?
He’s the lad out of Radiohead, Charlie.
Never liked them. Whining bastards. And the amount of money the cunts are making? They should have the ukuleles out.
He have the one eye guzz on him.
Making any amount of money. And he whining out of him like a stuck goat? Should have his mambas out.
Do you think it made me handsomer, Charlie? In a peculiar way? The fucked-up eye?
It gave you a bit of character, Moss.
Sayin’ I had none beforehand?
You were bland-enough looking as a younger gent, Maurice, in fairness.
で、言うこともキツくてさ、シンシア〔モーリスの死んだ妻〕は。俺が片目になって帰ってきたときなんか。タンジールから。こっちは死ぬ思いしてきたのに、一目見ただけでこう言ったんだ、いったいあんた誰のつもりよ、トム・ヨーク?
聞いたことない。いや待てよ……サマーヒルにいた、足の悪い奴じゃないよな?
レディオヘッドのメンバーだよ、チャーリー。
俺あいつら嫌いなんだ。情けない声出しやがって。なんであんなクズどもがあんなに儲けるんだよ? あいつらウクレレでも鳴らしてりゃいいんだ。
片目が利かないんだよ。
どっさり金儲けやがって。あの野郎、刺された山羊みてぇな情けない声出しやがって。あんな奴、太鼓でも鳴らしてりゃいいんだ。
で、俺さ、もっとハンサムになったかな、チャーリー? ちょっと変わったふうにさ。駄目になった目で。
まあちょっと品格みたいのはついたよ、モス。
それまではなかったってことかい?
若き日の君は、まあ当たり障りない見かけだったよ、モーリス、正直言って。
ここを読めば、内面の痛みが漫才性を要請していることはかなり明らかだろうが、かといって漫才性=偽りの表面/隠れた痛み=真実 という二分法になってもいない。表層には表層のリアリティがある。そこが面白い。
回想される過去はけっこう波乱含みだし、どんどん地獄の出張所のように思えてくるアルヘシラスの港には、モーリスの娘ディリーが本当に到着して……と、ストーリー的にも実はけっこう充実しているし、「頭でっかち」という形容からはもっとも遠い感触の小説なのだが、にもかかわらず、主役はやっぱり言葉、とこれほど味わい深く実感させてくれる作品もそうザラにない。
-
Kevin Barry, Night Boat to Tangier (Canongate, 2019)
最新情報
〈刊行〉
『波』9月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第17回「狐と探偵」掲載(第14回までは原文と一緒にウェブ上でも公開)。
〈ラジオ、オンラインイベント〉
9月19日(土)午前10時30分~11時45分、バリー・ユアグローさんと、バリー・ユアグロー『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』(ignition gallery)刊行記念Zoomイベント。
9月19日(土)午後2時から、手紙社主催GOOD MEETING の一環として第5回Zoom朗読会「いま、これ訳してます Part 5」。
9月19日(土)24時からJ-WAVE「RADIO SWITCH」でトークと朗読。
9月22日(火・祝)午後2時から青山ブックセンターで早助よう子さんと、早助よう子『恋する少年十字軍』(河出書房新社)刊行記念トークイベント「この人はなぜこういうものを書くんだろう?」。
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
朝日新聞金曜夕刊に『ガリバー旅行記』新訳連載中。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら