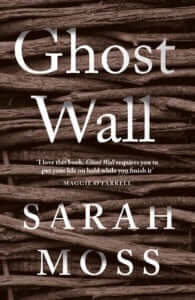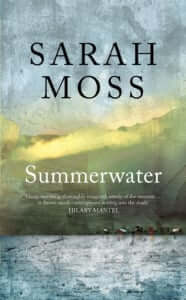(27)中篇小説の意外な爆発力
Sarah Moss, Ghost Wall (Granta Books, 2018)
-----, Summerwater (Picador, 2020)
著者: 柴田元幸
スコットランドのグラスゴーに生まれ、イングランドのマンチェスターで育ち、現在はアイルランドのダブリンに住む作家セアラ・モスの2018年刊中篇のタイトルはGhost Wall。バスの運転手で、家庭では強権的、ほとんど暴君の父親。ひたすら夫を恐れ夫に従う母親。そんな両親それぞれに複雑な思い(愛情・反抗心・それぞれ違った嫌悪……)を抱く17歳の娘。物語はこの17歳の娘シルヴィーによって語られる。
一家は毎年休暇をイングランド北部の自然の中で過ごすのだが、今年はそこに、考古学の教授一名(男)と、大学院生三名(男2、女1)が加わる。彼らの目的は太古の暮らしの実体験であり、シルヴィーの一家は、なかばそのお手本である。あたかも、シルヴィーたちが、いにしえの人々により近い存在であるかのように。
食べ物も山の中で漁り、文明の利器を極力排除して「太古に還る」試みがコミカルに描かれもするが、そのすぐ向こうで、いまにも暴力が噴き出そうとしていることがひしひしと伝わってくる。一方では、はるか昔に行なわれていた生贄の儀式を貫いていた、太古の暴力。もう一方では、妻・娘に対して父親が行なっている、いま現在の暴力。この二つがシルヴィーの、そして読者の頭の中でどんどん重なってくるところへ、教授のよりソフトで隠微な暴力性も加わってくる。父親と教授は、階級的には対立するものの、家父長的な立場としては不気味に連帯してしまうのだ。
そうやって話が進んでいくうちに、巻頭に置かれていた、謎めいた短い序章の意味がだんだん見えてくる。第一段落を引くと――
They bring her out. Not blindfolded, but eyes widened to the last sky, the last light. The last cold bites her fingers and her face, the stones - not the last stones - bruise her bare feet. She stumbles. They hold her up. No need to be rough, everyone knows what is coming. From deep inside her body, from the cord in her spine and the wide blood-ways under the ribs, from the emptiness of her womb and the rising of her chest, she shakes. A body in fear. They lead the fearful body over the turf and along the track, her bare feet numb to most of the pain of rock and sharp rushes. Chanting rises, the drums sound slow, unsyncopated with the last panic of her heart. Others follow, wrapped against the cold, dark figures processing into the dusk.
人々は彼女を連れ出す。目かくしはしておらず、目は最後の空、最後の光に向けて開かれている。最後の寒さが彼女の指と顔を嚙み、石が――最後の石ではない――裸足の足を傷つける。彼女はよろめく。人々は彼女を立たせる。荒っぽくやる必要はない。これからどうなるのか誰もが知っている。体の奥深くから、背骨の腱と肋骨の下の血の広い通り道から、空っぽの子宮と持ち上がる胸から、彼女は震える。恐れに包まれた体。人々は恐れる体を導いて芝土を横切らせ、小径に沿って歩かせる。裸足の足は麻痺していて、石ころや尖ったイグサの痛みの大半は感じない。単調な歌声が上がり、ゆっくり鳴る太鼓は彼女の心臓の最後のパニックと連動しない。ほかの者たちがついて来る。寒さを防ごうと着ぶくれした暗い姿たちが、夕暮れの中へ練り歩いていく。
要するにこの小説の流れは、冒頭で語られたこの遠い昔の、ひとごとである情景が、どんどんひとごとではなくなっていく流れにほかならない。
ちなみに‘Ghost Wall’とは、ローマ軍に侵入されたブリトン人が、先祖の首を並べて作った防御の壁(むろんそれは何の役にも立たなかった)を指す。これが言及されることで、物語の暴力性と、その目的の無意味な残酷さがいっそうはっきり浮かび上がり、そこからクライマックスに直結する。中篇ならではの、緊張感が一貫して維持された一冊。
土着的な人々とインテリとが、同じ場に居合わせて中途半端に対立するGhost Wallは、ブレグジットの寓話として読まれることも多かったようだが、この8月に刊行されたセアラ・モスの最新作Summerwaterは、早くもコロナ禍の只中にある世界の寓話と読まれることも多いようだ(書き上げられたのはコロナ以前にちがいないが)。「休暇中の人たちが異常な状況に追い込まれる、あるいは自らを追い込む中篇」というところまでは前作と同じと言っていいだろうが、そのあとはだいぶ違う。
舞台は、スコットランドのグラスゴー近辺の、「ホリデイ・パーク」と称される湖畔の別荘地。夏の休暇を過ごしに来た家族連れ、結婚前のカップル、隠居した老夫妻等々が、連日の雨続きでほとんどstay-at-home状態を強いられ、(何しろほかにすることもないので)雨の中たまさか外に出ていく隣人たちの動きをけっこうじっくり観察することになる。Ghost Wallでは境遇も信条も違う人たちが異様な隣接を余儀なくされるが、こちらではソーシャル・ディスタンスがほぼ強制的に保たれている。
それを反映するかのように、Ghost Wallが(古代を夢想した序を除き)一貫して17歳のシルヴィーの視点から語られていたのに対し、こちらは章ごとにそれぞれのキャビンの中の一人に焦点を当て、視点もめまぐるしく変わる(かつ、章と章のあいだには鳥や蟻や木の視点から語られる短い幕間も挿入される)。まず感じるのはキャビン間の隔たりであり、キャビン内での隔たりだが(どの夫婦もたがいにいちおう気を遣いあい、内心たがいのふるまいを隠微に憤っている)、読んでいくうちに強まっていくのは、降りつづける雨が象徴するように、誰もが何か同じものに縛られ、同じ場に閉じ込められている感覚である。
There’s nothing happening out front. Rain, the loch, the trees, more rain. Ostentatious rain. Pissing it down. You’d think it couldn’t keep up like this, that the water would run out. She holds her hand over the pan but it’s barely warm, those old electric rings take for ever. Voices out there, car doors; she leans over the sink to see the family from the lodge behind going out, or at least trying to; the dad’s sitting in the car watching the rain while the mum’s trying to get one of the little boys to put his coat on and the other one’s peering round the door. Justine, that’s her name. Northern accent, somewhere near Manchester, said this is the first time they’ve been here and honestly probably the last, no way it’s worth the money, and Milly didn’t say Josh’s parents were letting them stay for free.
表では何も起きていない。雨、湖、木々、もっと雨。これ見よがしの雨。ざあざあと。こんなに降るはずなんてありえなさそうなもの、水がなくなってしまいそうなものだ。彼女は鍋の上に手をかざすがほとんど暖まりはしない、こういう古い電気コンロって暖まるのにすごく時間がかかる。外で声がして、車のドアの音。流しの向こうに身を乗り出すと、うしろのロッジの一家が出かけるところ、少なくとも出かけようとしているところ。父ちゃんは車の中に座って雨を眺め、母ちゃんは小さい男の子の片方にコートを着せようとし、もう一人の子はドアの陰から外を覗いてる。たしかジャスティーンっていう名前。北部の訛り、マンチェスターあたり、ここへ来たのは初めてなの、正直言ってこれが最後だわね、全然お金に見合わないもの。こっちはジョッシュの両親にただで使わせてもらっていることをミリーは黙っていた。
文字どおりにも比喩的にも寒い事態が続くが、なかには温かいエピソードもある。もう一組四人家族がいて、夫が妻に、僕が子どもたちを湖畔で遊ばせてるから君は一時間何でも好きなことをするといいよ、と言う。残された妻はいろいろ思案した挙げ句、熱い紅茶を入れて夫と子どもたちの元に届けるのだ(これは読んでいて自分も紅茶が飲みたくなりました)。
だが、そういう温かな信頼感(と、片付けるのももしかしたら見当外れなのかもしれないが)で作品全体を包むには、作者モスはあまりにリアリストである。Ghost Wallで最後は暴力が噴出したように、こちらも最後は、ある外国人家族が開くパーティーの騒音が元で、みんなが抱えていた焦燥や苛立ちが一気にはけ口を見出す。二作とも、結末での爆発のさせ方は、それまでの筆致が抑制されているだけにいっそうすさまじい。この二冊で、中篇小説独特の可能性がよく見えた気がした。
Ghost Wall というタイトルも秀逸だったが、こちらのSummerwater、湖畔の別荘地を舞台とする物語にはぴったりという気がするが、実はこれ、登場人物の一人が子供のころからずっとつい間違えてしまう、ある詩に登場する実在の地名(の言い間違い)である。サー・ウィリアム・ワトソン(1858-1935)に「セマーウォーターのバラッド」(The Ballad of Semerwater)と題された、‘Deep asleep, deep asleep, / Deep asleep it lies, / The still lake of Semerwater / Under the still skies’(深く眠って、深く眠って/深く眠って横たわる/セマーウォーターの静かな湖/静かな空の下)で始まる詩があるのだ。この人物が、Semerwaterが正しいと知ったあともついSummerwaterと言ってしまう、という設定に、登場人物たちが周りの人々とのあいだに――そして自分自身とも――つねに持ってしまうちぐはぐさが巧みに暗示されている。
これは作者のインタビューを読んで知ったことだが、ブレグジット、それに(いわば事後的に)コロナ禍のことももちろん念頭にはあったけれど、作者にとってそれより大きな問題は気候変化だという。といって、スコットランドの異様な長雨を、そうした意識の直接の表現と取るべきなのかはよくわからない。また、Summerwaterの章のあいだにはさまれた、人間社会と対比された自然の描写も多種多様で、一律に気候変化への警鐘というわけではない。
The sound waves pulse like the rings around a thrown stone, spreading out across the rainy night.
Music crosses raindrops, the air full of noises and riddled with movement. Sound waves travel through the cabin’s open door and through the gaps in the windows, over the waterlogged earth, into all the ears in the woodland. The fox cubs feel it through the earth of their den, the bats in their rafters. In a nest of bracken up on the hillside, the doe pricks her ears towards a running beat too heavy for wolves. The anthill pulses. Damp trees absorb the higher frequencies, swallow the energy into the wetness and wood-flesh, so it is the bass that penetrates your head and drums on the drums inside.
音波は投げた石の周りに広がる輪のように脈打ち、雨の夜の中を広がっていく。
音楽が雨粒を横切り、空気は音に満ち、動きにあふれる。音波はキャビンの開いたドアを抜け、窓のすきまを通り、水浸しになった土の上を越え、森林のすべての耳の中に入っていく。狐の子らは巣の土を通してそれを感じ、蝙蝠たちは垂木の中に感じる。丘の中腹にあるシダの巣の中で、牝鹿は耳をそばだて、狼にしては重すぎる走る足音の方に向ける。蟻塚が脈打つ。湿った木々は高い方の周波数を吸収し、そのエネルギーを、湿気の中、木の肉の中に吞み込む。だから、あなたの頭に浸透し、内なる太鼓をどんどん叩くのは低音の方だ。
パーティーの騒音も、人間にとっては苛立ちの種でも、自然の生き物にとっては、ある種の祝祭性さえ帯びているような書き方である。もっともこれも、自然の力強さに対する信頼というより、一種の祈りのようなもの、願望の表現なのかもしれない。よくわからない。だがそのあたりが曖昧だからこそ、この小説が教条主義に陥ることもなく豊かな余韻が残る。人間のちっぽけさとは対照的な大らかな自然、という話にまとめもせず、人間の破壊によって危機に瀕した自然、でもなく、いわばただ普通にそこにある自然が、セアラ・モスの小説では息づいている。
-
Sarah Moss, Ghost Wall (Granta Books, 2018)
-
-----, Summerwater (Picador, 2020)
最新情報
〈刊行〉
10月2日、文芸誌MONKEY英語版第1号刊行。紀伊國屋書店と、スイッチ・パブリッシング ウェブサイトで販売。
10月15日、文芸誌MONKEY22号「悪霊の恋人」刊行(スイッチ・パブリッシング)。
『波』10月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第18回「EDOアプリ」掲載(原文とあわせてウェブ上でも公開予定)。
〈イベント〉
10月10日(土)午前10時から、早稲田大学主催MONKEY英語版第1号刊行記念オンラインイベント(英語部分の通訳なし)。きたむらさとし、柴崎友香、古川日出男、翻訳者+編集者(の一人が柴田)。
10月11日(日)午後3時から、柴崎友香さんと『百年と一日』(筑摩書房)刊行記念のB&B主催オンライントーク「短編小説の魅力と朗読の悦楽」。
10月17日(土)午後2時から、スイッチ・パブリッシング主催のMONKEY22号刊行記念オンラインイベント。
10月18日(日)午前10時から、国際文化会館での川上未映子さん×ローランド・ケルツさん対談(英語部分の通訳なし、オンライン配信あり)のイントロダクション担当。
10月31日(土)午後2時から、手紙社主催GOOD MEETING の一環として第6回Zoom朗読会「いま、これ訳してます Part 6」。
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
朝日新聞金曜夕刊にジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』新訳連載中。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら