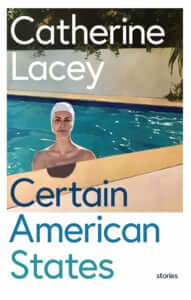(28)Don’t call me anything
Catherine Lacey, Pew (Farrar, Straus & Giroux, 2020)
――, Certain American States (2018; Picador paperback, 2019)
著者: 柴田元幸
アメリカにおいて、人を区別する上での最重要要素は性差と人種と貧富である。特に最初の二つは線も比較的引きやすいから、小説を読んでいてもこれらについては、登場人物に関しいち早く、多くの場合何らかの間接的な情報を通して知らされる。この二点がわからないと、読んでいてだんだん不安になってきて、何か読み逃していないか、はじめの方に戻っていったりする。
それと同じように、この『ピュー』と題された小説に出てくる、大変同調圧力が強い小さな町の人々も、一人の人物を前にして大きな不安を覚える。その人物は男か女かもわからないし、見ようによっては白人にも黒人にも見えるのだ。
Now, what is it that we call you, dear? he asked. I looked at the empty television screen, saw ghostly reflections in it. A name? the Reverend asked again. Really, whatever you’d like to be called, that’s all we’re asking.
I didn’t want to be called anything.
I thought of leaving the room. I thought of leaving the house and going somewhere, but I somehow couldn’t. Some kind of force or threat was in the room, all over the house. The parrot called out. Hello? I gathered my hands in a fist behind my back.
Well, the Reverend said, not much of a talker, now are we?
All talk. No game, the parrot said. All talk. No game.
Steven and the Reverend laughed and the sons did not laugh. Jack muttered something under his breath, and Steven stamped on the boy’s foot.
さて、君のことを何と呼んだらいいかな? と牧師は訊いた。何も映っていないテレビ画面を見た。人が映っている、幽霊みたいな姿がいくつか見えた。名前は? 牧師はまた訊いた。ほんとに、何て呼んでほしいか、それを訊いてるだけなんだよ。
何とも呼ばれたくなかった。
部屋を出ていこうかと思った。家を出てどこかへ行こうかと考えたけど、なぜか出られなかった。何かの力だか脅しだかが部屋の中に、家じゅうにあった。オウムがハロー?と呼びかけた。両手をこぶしに固めてうしろに回した。
うーん、あんまり喋らないみたいだね、牧師が言った。
口ばっかり。何もしない、とオウムは言った。口ばっかり。何もしない。
スティーヴンと牧師は笑って息子たちは笑わなかった。ジャックが何か小声でつぶやいて、スティーヴンがジャックの足を踏みつけた。
――というわけで、訳者は“I”を訳す義務を放棄してしまいました。大人だったら「私」でいいだろうが、この人物はどうやら10代なかば(さすがに年齢はある程度特定できる)。この年齢にふさわしい、無色透明な一人称単数の代名詞、日本語にないですよね?
さて、「何とも呼ばれたくな」いこの人物を、牧師は「ピュー」と命名する。道端の溝(gutter)で拾った猫をガターと名づけたのと同じに、教会の信徒席(pew)で眠っているところを発見されたからピューだ、というのである。
ピューをひとまず家に置くことにしたこの家族が(ピューは彼らがいつも座る信徒席で発見されたのである)、何か暴力的なものを表面下に抱えているのはこの一節からも窺えるし、この異様に同調圧力の強い共同体全体もそうであることが、随所からそれとなく伝わってくる。
だから、その暴力がピューに向けられ、彼/彼女が何者であるか、暴力的に暴かれるか決めつけられるかしてもおかしくないだろう。だがそうはならない。そういう暴力に走るには、この町の人々はあまりに慎み深いのだ。服を無理に脱がせば性別はすぐにわかるだろうが、彼らは決して無理強いしない。これを偽善と呼ぶのはたやすい。何しろ彼らは二言目には宗教的な決まり文句を口にするので、そうするのはとてもたやすいのである。
だがそうしてしまうと、この本の特異性を見逃すことになる。アメリカ版の裏表紙に刷られた推薦文で、レイチェル・クッシュナーはこう書いている。
The people of this community are stifling, and generous, cruel, earnest, needy, overconfident, fragile, and repressive, which is to say that they are brilliantly rendered by their wise maker, Catherine Lacey.
この共同体の人々は、鬱陶しく、寛容で、残酷で、ひたむきで、他人の是認を必要とし、自信過剰で、脆く、抑圧的である。言い換えれば彼らは、彼らの賢明な創造主キャサリン・レイシーによって、ものの見事に描かれているのである。
まったくそのとおり。共同体の暴力が個人をつぶす話にも収斂せず、さりとて個人の叛逆が共同体に対して見事勝利を収めるというようなすっきりした話にもならず、ピューという一個の謎を通して、共同体のなかの、たがいに矛盾し打ち消しあうような要素が一緒くたに浮かび上がる。これがこの小説の第一の強みである。
そしてもうひとつの強みは、逆説的な話なのだが、ピューとは何者なのか、いくら読んでも我々読者にもいっこうにわからないことである。作品は一貫して一人称で語られているにもかかわらず、ピューは自分の内面についてほとんど語らない。最初に引用した箇所のなかの「何とも呼ばれたくなかった」というのがこの人物にとっては最大級の心情吐露である。『白鯨』の語り手イシュメールは、「俺のことをイシュメールと呼んでくれ」(Call me Ishmael)とあの大作を語りはじめながらもほとんど誰にもそう呼んでもらえない、ある意味さみしい人間だが、ピューはそういうさみしさとは無縁である。Don’t call me anything.いや、それも違うか……ピューはそんなふうに積極的に否定的メッセージを発しはしない。ただ黙っているだけである。
過去についてもいっさい明かさないし、そもそも明かしうるのか、過去の記憶があるのかどうかもよくわからない。人々はそんなピューに接し、往々にして自分の思いや記憶をとうとうと語る。カーソン・マッカラーズの『心は孤独な狩人』で、聾啞者シンガーに町の人々が自らの思いを語るように。
今日ではこういう場合、誰もが「ピューには何かトラウマ的体験があって記憶を抑圧しているのでは」と考えるわけだが、むろんそのような都合のいい体験が見えてくるわけでもない。まぎれもなくいろんなことを見て、感じて、素朴な言葉で見事に語る人物であるにもかかわらず、彼女/彼を共同体に取り込もうとする人々に対し情報提供を拒むのと同じに、ピューは読者に対しても何ら情報を提供しない。意図的に隠しているのか、そもそもそういう情報が意識のなかにないのかもわからない。そのわからなさが逆説的に、なんとも快いのである。
それが快いのは、自意識や虚栄心といった余計な荷物をしょい込むことなく、物事をクールに観察し、時には鋭くその本質を見抜いて、切れのいい言語で表現する人間がそこにいることがわかるからだ。
The drawer was lined with old newspaper, the classified section, yellowed and falling apart in shards. One of the ads read—
SON—You are not being
hunted for anything but to
find you. Come Home.
—MOTHER—and I wondered if this SON ever allowed himself to be found, if this particular SON had seen this paper and knew that he was the SON this MOTHER was trying to find, and I wondered if the MOTHER was really only hunting her SON for no reason other than to find him, if anyone could ever seek anyone for only one reason. It seemed she must have wanted something more than to just find him, and it seemed to me that a person might have many reasons, many many reasons, to not Come Home. But it only seemed that way to me and I am only one person, ruined by what I have and have not done.
引出しには古新聞が敷いてあって、広告欄が黄ばんで、ばらばらに崩れかけていた。広告のひとつはこうなっていた――息子へ あなたを探している
のはただ あなたを見つける
ためです。帰ってきて。
――母――この息子はこのあと見つかったんだろうか、この息子はこの新聞を読んでこの母が見つけようとしている息子とはじぶんのことだとわかったんだろうか、とおもった。母はほんとうにただ見つけるためだけに息子を探してたんだろうか、人がだれかを探すときってひとつだけの理由で探すことってあるんだろうか、とおもった。きっと母はただ息子を見つける以上のことを求めていたんじゃないか。だれかが帰っていかない理由ってすごく、すごくたくさんあるんじゃないか。でもまあ、じぶんにはそうおもえるだけで、じぶんは一人の人間でしかないし、これまでやったこと、やらなかったことでダメになってしまっている。
反復がある種の叡智と淡いユーモアにつながっているところが、ピューの語り口の大きな魅力だが、加えて、この母と息子の関係に、ピューは共同体と自分の関係を微妙に重ねあわせているだろう。帰ろうとしない息子に、ピューはおそらく共感している。「この息子はこのあと見つかったんだろうか」とひとまず訳した箇所の原文は、“if this SON ever allowed himself to be found”で、厳密には「この息子はこのあとじぶんが見つかることを許したんだろうか」と訳すべきであり、いかにも「見つからない方が正しい」と言いたげである。とはいえ、この重ねあわせで話をきれいにまとめることも避けて、最後に「でもまあ、じぶんにはそうおもえるだけで……」とつけ加えて自らの正しさに水を差すあたりも、これまた非常に共感できる。
内容的には全然違っていても、作者キャサリン・レイシーが『ピュー』の前に出した短篇集Certain American States(『いくつかのアメリカの州』、あるいは『いくつかのアメリカ的状態』とも読める)でも、そうした文章の見事さは共通している。たとえばこれは、表題作「いくつかのアメリカの州」の書き出し。
I was one of those babies who look as if they won’t survive to dinnertime, but somehow do, then become toddlers with the tics and nerves of a used-up veteran. Nervous about the television, whether it was on or off; nervous about the sun rising or setting; nervous over every knock at the door and nervous in the silence too. Leonard, that man who raised me, he is the one who remembers my nervousness. He once told me that on the first day of my life, on that still-dark morning, I looked up at him and he looked down at me and he knew and I knew and we both knew that we’d always dislike each other. My mother was such a good friend, though; he felt he had no choice. He couldn’t possibly say no—not to a woman whose belly had watermeloned overnight.
Godfather? Me?
Yes, she said, who else?
私は世にときどきいる、夕食時間まで生きのびられそうにないのになぜか生きのび、やがて疲弊しきった帰還兵並のチックと神経過敏を抱えた幼児になるたぐいの赤ん坊だった。点いていようがいまいがテレビに過敏、昇る朝日沈む夕陽に過敏、ドアをノックする音一つひとつに過敏で静まりかえってもやっぱり過敏。私を育てた人物レナード、私の神経過敏を記憶しているのもこのレナードである。あるとき彼が語ったところによれば、私の人生の第一日、そのいまだ暗い朝、私は彼を見上げ彼は私を見下ろし彼は知り私は知り我々は二人とも知った、我々が今後ずっとたがいを嫌うであろうと。でも私の母はすごくいい友人だったから、選択の余地はないとレナードは感じた。ノーだなんて言えっこない、一夜にして腹部が西瓜化した女性に向かって。
名付け親? 僕が?
そうよ、と母は言った。ほかに誰がいるのよ?
『ピュー』の緊張感はないが、そのぶん、もっぱら言葉の遣い方から生じるユーモアが前面に出ている。短篇集全体が、こうしたユーモアに支えられている。
この箇所は自分の育ての親について語っているが、12本の短篇、大半は男女関係の話である。正直言って、男女関係からもう少し離れてくれると個人的にはありがたいのだが、まあそれはないものねだりというものだろう。どう生きてもいずれ白けてしまうことを認めつつ、でもそれを自分の繊細さや不器用さのせいにして遠回しの自己憐憫and/or自己祝福に浸りもせず、さりとて人間への無根拠な信頼に着地したりすることも当然なく、しなやかな言語使用から見えてくるしなやかな精神でもって、「まあとにかく何とかやっていくしかないな」と呟くような姿勢が感じられて大変好ましい。
-
Catherine Lacey, Pew (Farrar, Straus & Giroux, 2020)
-
――, Certain American States (2018; Picador paperback, 2019)
最新情報
〈刊行〉
11月6日、エドワード・ゴーリー『金箔のコウモリ』刊行(河出書房新社)。
『波』12月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第19回「ベルサイユの傘、プレーボール!」掲載。原文とあわせてウェブ上でも公開予定。
〈イベント〉
11月6日(金)午後7時半から、『オスカー・ワイルドで学ぶ英文法』刊行記念オンラインイベント「英文学と英文法を楽しもう」にゲスト出演。
11月7日(土)午後5時から、『マーティン・エデン』出町座上映記念トーク&朗読ショー(リモート出演)。
11月18日(水)午後8時から、「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」の一環としてドミニク・チェン、岸本佐知子両氏とトーク(Zoom配信)。
12月5日(土)午後3時半から、朝日カルチャーセンター横浜教室で講義「片隅の小宇宙 アメリカの『ひっそりとした声』を探して」(教室受講+オンライン)。
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
朝日新聞金曜夕刊にジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』新訳連載中。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら