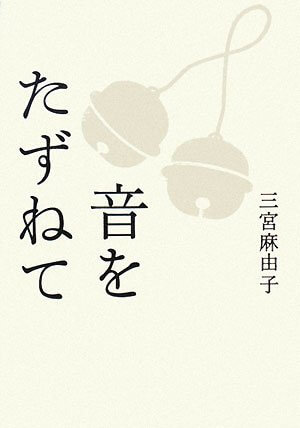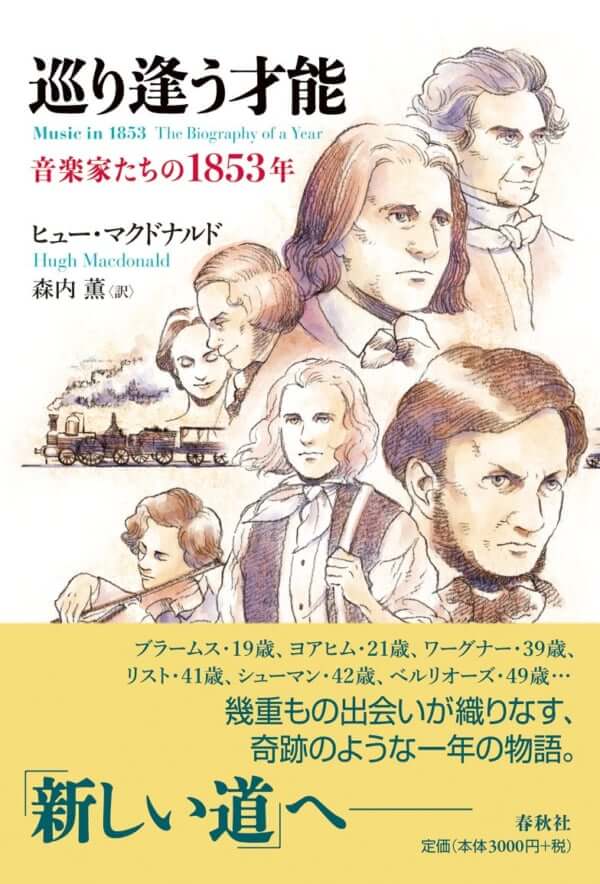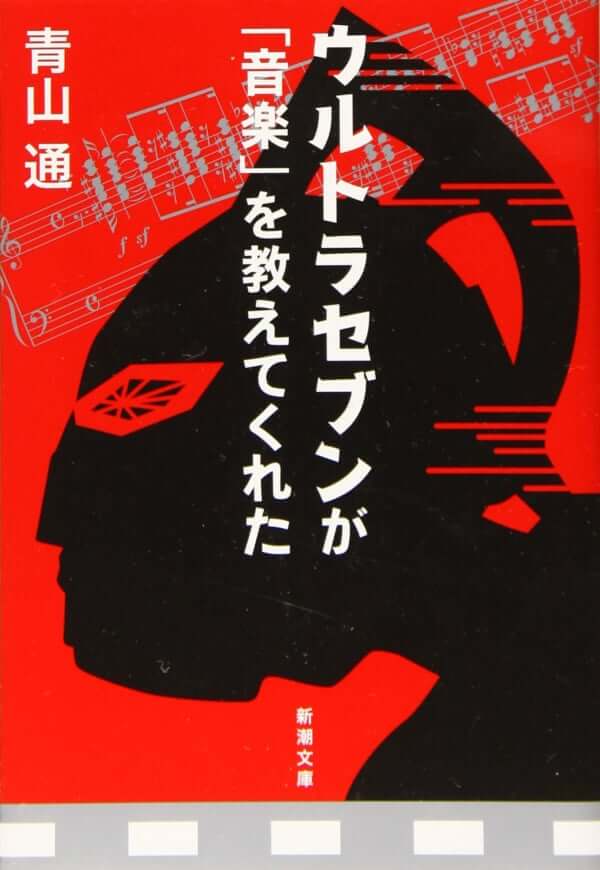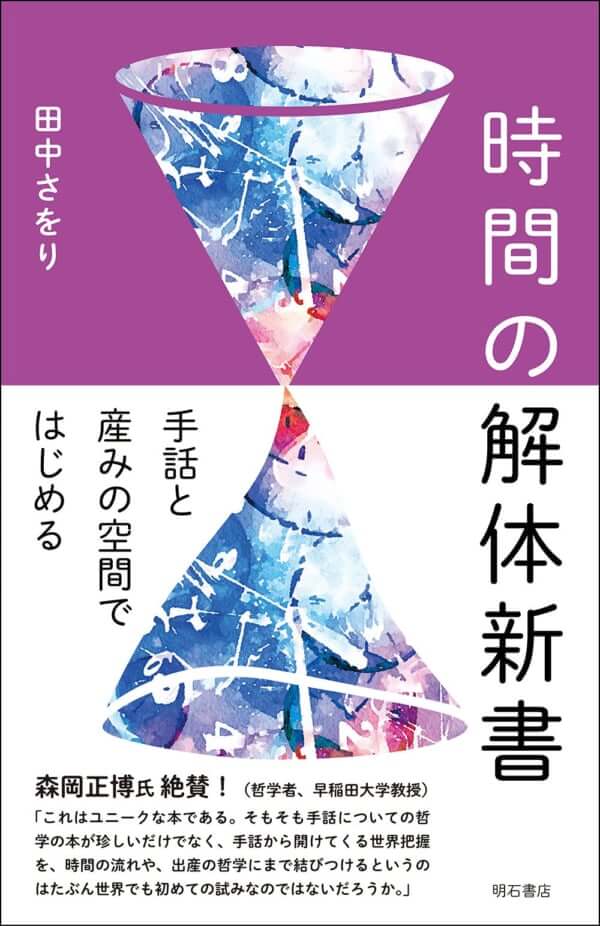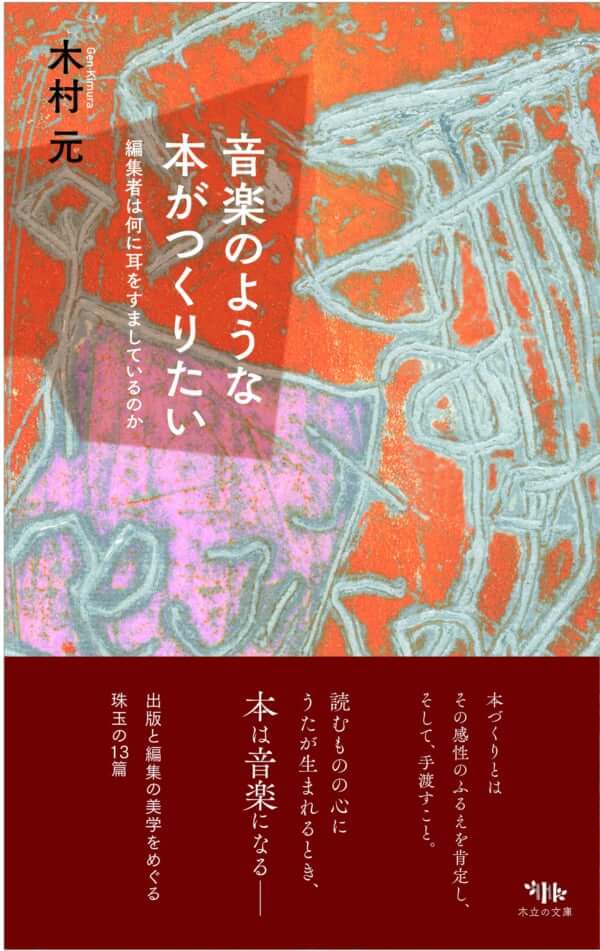(14)編集者・木村元の10冊
音楽のように心に共鳴する10冊
著者: 木村元
笠井瑠美子ほか『本を贈る』
桂川潤『本は物である』
C.S.ルイス『別世界物語』三部作
梨木香歩『f植物園の巣穴』
三宮麻由子『音をたずねて』
H.マクドナルド『巡り逢う才能――音楽家たちの1853年』
青山通『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』
宮野真生子+磯野真穂『急に具合が悪くなる』
田中さをり『時間の解体新書――手話と産みの空間ではじめる』
木村敏『あいだ』
突然だが、みなさんは「音楽書」というものを読んだことがおありだろうか。厳密には「音楽書籍」といったほうがいいのかもしれない。平たくいえば「音楽について書かれた本」である。書店に行くと、店の奥の、なんとなくそこだけ照明も暗いような気がする一角に「芸術書」と表示されたコーナーがあり、「クラシック」「ジャズ」などとジャンルごとの仕切り板があればまだいいほうで、たいていは「音楽」と一緒くたにされて、せいぜい棚2段くらいのスペースに棲まわせてもらっている本たちの総称だ。
その「音楽書」だけを手がける編集者としてのキャリアを始めて、そろそろ34年になる。ジャンルでいえば、クラシック、現代音楽、ジャズ、ロック、J-POP、ワールド・ミュージックなど、音楽と名が付けばなんでも相手にするし、本のカテゴリーでいえば、評論、エッセイ、伝記、大中小の辞典、プレイヤー向けの教則本、果てはPC用音楽ソフトの解説本まで、ひととおりこなしてきた。担当した本を数えたことはないが、おそらく400冊以上になるだろうか。
15年前には、元同僚と二人で音楽書専門の出版社を創業した。会社のホームページができたときに、なにか創業のマニフェストをと思って書いたのが「音楽のような本をつくりたい」という文章だ。これまでは「音楽についての本」をつくってきたけれど、これからは「音楽のような本」をつくってみたい――そんな抱負を記した。
「音楽についての本」には、その本を必要とする強い動機をもった読者が存在する。たとえばピアノを学ぶ子ども、音楽を勉強する学生、こんど聴きに行くオペラの作曲家について知っておきたいと思う愛好家――対象とする市場が明確であればあるほど、その本がどれだけの数売れるのか、いくらくらいの値段であれば買ってもらえるのかがはっきりする。そうした可変的なファクターを数値化し可視化して、コアターゲットを絞りこんで商品開発するのが、マーケティングの要諦であり、それを話し合う場が企画会議であろう。
しかし、じつをいうとわたしたちは会社を創業してから、いちども企画会議を開いたことがない。企画会議で数値化されて明確になっていくマーケットと、自分がつくる本を読んでほしいとイメージしている読者とのあいだに、どんな関係があるのか。自分がつくりたい本の内容を、なにゆえマーケットに合わせてアジャスト(調整)しなければならないのか――。そこにどうしても必然性がみいだせないからだ。
話は急に現在に飛ぶ。このたびの新型コロナウィルスの感染拡大にともない、「3つの密を避ける」とか「外出を8割減らす」ことが推奨され、「繁華街の外出者数」や「新規感染者数」の増減が毎日発表されるようになったが、これなどもビッグデータをもとにわれわれの日常的な行動を数値として可視化し、それにもとづいて対策を考えるというマーケティングの手法にもとづいたものといっていい。
ミュージシャンの星野源が「うちで踊ろう」という動画を投稿したのはそんな折のことだった。それぞれに異なる生を生きている個に向けて呼びかけた「うちで踊ろう」というメッセージは、無個性な数値を構成する一粒の「ドット」として自分をアイデンティファイされることにたいして、わたしたちが内心もっていた違和感と共振したのではないか。また、安易にブームに乗っかろうとして強い反撥を受けた時の首相の目には、やはり「数としての国民」の姿しか見えていなかったのではないか――。
わたしたちがつくる本も、それぞれ異なった個性をもつ読者が、「おもしろかった」「感動した」「役に立った」と言ってくれれば、それでいい。彼ら彼女たちは結果としてひとつのマーケットを構成するのかもしれないけれども、ひとりひとりはちょっとずつ「想定される典型的なターゲット」から“ずれて”いるだろう。それがおもしろい。その“ズレ”をこそ肯定したい。星野源の動画に“コラボ”した無数のパフォーマンスが、どれひとつとして同じものなどなく、その違いを楽しむうちに、ひとつの巨大な「バズり」を生んだように、1冊の本もまた多くの読者の心にひとつひとつ異なった「うた」を芽生えさせ、それが結果として豊かなアンサンブルを響かせる――。それこそが、わたしがつくりたい「音楽のような本」なのである。
前置きが長くなってしまった。ここでは、わたしが編集者として「こんな本がつくれたら!」とあこがれ、目標にしてきた本を10冊選んだ。
オマケに、1冊1冊にBGMも付けてみた。昨年上梓した拙著『音楽が本になるとき――聴くこと・読むこと・語らうこと』(木立の文庫)でも、音楽配信サービス「Spotify」で専用プレイリストをつくってQRコードを本に載せたところ、ことのほか好評だった。ここでもリンクをクリックするとSpotifyで音楽を聴くことができるようになっている。わたしの好みを反映してクラシックが多いが、楽しんでいただければさいわいだ。
笠井瑠美子ほか『本を贈る』(三輪舎)
わたしの音楽体験の根っこには中学のときに始めたバンド活動がある。ヴォーカル、ギター、ベース、キーボード、ドラムス……それぞれに役割がちがい、価値観や音楽性も異にする個人個人が、ひとつの音楽を「いかにカッコよく聴かせるか」という目的のために力を合わせるところがグッとくるのだ。同じように、書く人、編集する人、校閲する人、デザインする人、印刷する人、製本する人、売る人など、さまざまな専門家たちが寄ってたかって「本」というひとつの世界をつくりあげている――そのありさまがギュッと凝縮された1冊。
→大学生の息子に教えてもらったバンド。最近でもこんな「バンドらしい」サウンドが聴けるんだとうれしくなった。
桂川潤『本は物である』(新曜社)
本づくりは多くの場合、学校で学べるようなものではない。身銭を切ってできるだけたくさんの本を読み、こんな本をつくってみようと試行錯誤し、ときには失敗もしながら、実地に身につけるほかない。それでも、その過程で「メンター」と呼びたくなるような先人にめぐりあうこともある。昨年7月に急逝した装丁家・桂川潤さんはわたしにとってそんな存在だった。「本は物である」という桂川さんのテーゼは、音楽や本を前にしてひととき隣りあうことで成立する「コミュニケーションの三角形」というわたしの考えの基層のひとつとなっている。
→バレンボイム指揮ウェスト=イースタン・ディヴァン管弦楽団のライヴより。1台の譜面台を前にパレスティナとアラブの奏者がともに演奏する。「コミュニケーションの三角形」のイメージそのものの光景。
C.S.ルイス『マラカンドラ──沈黙の惑星を離れて〈別世界物語1〉』(ちくま文庫)
C.S.ルイス『ペレランドラ──金星への旅〈別世界物語2〉』(ちくま文庫)
C.S.ルイス『サルカンドラ──かの忌わしき砦〈別世界物語3〉』(ちくま文庫)
『ナルニア国物語』で有名なC.S.ルイスが1938~45年に発表したファンタジー3部作。「神学的SF」ともよばれ、ナチズムや行き過ぎた科学主義に対して自身のキリスト教的価値観を強く打ち出している。完結編の『サルカンドラ』には、悪の組織から逃れてきた女性を、主人公ランサムのもとに集う善意の人々が「本」でもてなすシーンがある。供されるのはシェイクスピア、オースティンなどの古典。どんな苦境にあっても受けとめてくれて、いっとき心を休らわせることのできる場を本はつくってくれる。
→C.S.ルイスと同時代の英国の作曲家ヴォーン・ウィリアムズがシェイクスピアの詩に付けた曲を、ロルフ・ジョンソン(テノール)、キーンリーサイド(バリトン)、ジョンソン(ピアノ)の演奏で。
梨木香歩『f植物園の巣穴』(朝日文庫)
「f植物園」に勤める男が古樹に穿たれた動物の巣穴(?)に落ち、さまざまな不思議な体験をする物語。「f」とは何か──この謎を読後も折にふれて考えていたのだが、最近になって、もしかしたらヴァイオリン属弦楽器の胴体にある「fホール」を巣穴に見立てたもの?と思いついた。ヴァイオリンの銘器ストラディヴァリウスの音響の秘密が科学的にはけっして解明できないことにも似て、本があたえてくれる感動がいったいどこから来るのか、ほんとうのところはわからないけれども、読んだあと何度も何度も思い返し、感動のありかを探してしまうこともまた、名著の条件なのだろう。
♪バッハ《無伴奏チェロ組曲第6番》BWV1012より第5曲〈ガヴォットI・II〉
→ヴァイオリン属のなかでも樹木を思わせるのはチェロだ。名手アンナー・ビルスマのバロック・チェロで、バッハの作品のなかでも野趣あふれるナンバーを。
三宮麻由子『音をたずねて』(文藝春秋)
全盲(本人は「シーンレス」と表現する)のエッセイスト、三宮麻由子さんはお箏やピアノをよくする音楽家でもある。この本は三宮さんが、身のまわりにあふれるさまざまな音を題材に、そこからひろがるイメージや思いを、軽妙な筆致と、ときおり差し挟まれる俳句(三宮さんは俳人でもある)とで描いた随想集。花火の音から空の広さを感じとるその感性の自由さ!
→「花火」といえばヘンデル《王宮の花火の音楽》かとも思ったが、そこは少しずらしてモンテヴェルディがバロックの夜明けに放った号砲たる音楽を、ガーディナー指揮イングリッシュ・バロック・ソロイスツの演奏で。
H.マクドナルド『巡り逢う才能――音楽家たちの1853年』(春秋社)
この本は「音楽史」に分類されるのだろうが、そこで扱われるのは「1853年」という1年だけ。この1年のあいだに、ブラームス、シューマン、リスト、ベルリオ ーズ、ワーグナーといった綺羅星のような才能が交錯し、本人たちも意図していないような歴史の流れがそこから噴出していく。「森を見て木を見ず」では、歴史の真実は見えてこないのだ。
→ブラームスというと髭もじゃのいかめしいおじさんのイメージだが、民謡調の親しみやすい歌曲も多く残している。この曲にぴったりなのはやはりヘルマン・プライの演奏。
青山通『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』(新潮文庫)
あなたのまわりにもいるかもしれない「クラヲタ」(=クラシックおたく)。おそらく50~60代の、多くは男性で、もしかしたら子どものころ、ウルトラセブンのファンだったかも!?――そんなトンデモ理論をぶち上げたくなるほど、1967年から68年にかけて放映されたウルトラセブンの音楽はクラシカルな魅力にあふれていた。とくに最終回のクライマックスで流れるピアノ協奏曲! その作曲者は誰か、演奏者は誰なのか?――本書はひとりの少年がその謎にせまるうちに、クラシックの魅力にめざめていく一種のビルドゥングスロマン。もともとはわたし自身が編集担当した1冊で、文庫版の巻末にはエッセイを書いている。
→ネタバレになってしまうが、ウルトラセブンの最終回で流れたのがこの音源。リンク先に飛べばわかるので、演奏者の名前は書かずにおきます。
宮野真生子+磯野真穂『急に具合が悪くなる』(晶文社)
人間の不運や不幸の多くは、煎じ詰めれば「なぜ自分だけが?」という疑問にいきつく。数限りない可能性があったはずなのに、なぜほかならぬこのわたしだけが――。癌を患い、「急に具合が悪くなる」不安とともに生きていた哲学者が人類学者に出会い、語りあうなかで、二人が病という偶然を冷徹に見つめ、そこから意味を紡ぎだし、最終的にそれを必然として受けとめるにいたる過程を描いた美しくも力強い往復書簡集。音楽や本との出会いもまた、偶然でありながら「出会うべくして出会った」必然を感じさせてくれる。その尊さを忘れずにいたいと思う。
♪バッハ《汝の道をゆだねよ》BWV244(《われ心よりこがれ望む》BWV727)
→2人の女性の出会いということで思い浮かんだのが、アコーディオンの御喜美江さんとヴィオラの今井信子さんのデュオ・アルバム『Antiquities』の終曲。
田中さをり『時間の解体新書――手話と産みの空間ではじめる』(明石書店)
理屈というものは、たいがい「原因-結果」の因果律にしばられているもの。それはものごとのなりゆきを時系列で説明する「語り」が人間の理性を構成すると考えられているからだ。しかし本書によれば、手話や出産というものは、過去-現在-未来をひとつの空間に置いて、自由に行き来する体験であるという。これは、過去に聴いたフレーズが現在のメロディに意味をあたえ、未来に到達する終局を予感しながら、すべてを同時的に味わう音楽の体験とも通ずるのではないか。新しい哲学の可能性を予感させてくれる書。
♪リヒター《リコンポーズド──ヴィヴァルディ「四季」》より〈春1〉
→過去-現在-未来をつなぐ音楽として、現代作曲家のなかでも「ポストクラシカル」とよばれる潮流の第一人者であるマックス・リヒターの《リコンポーズド》を。ヴィヴァルディの《四季》を「再作曲」したもの。ホープ(ヴァイオリン)、リヒター(キーボード)、デ・リッダー(指揮)、ベルリン・コンツェルトハウス室内管弦楽団の演奏で。
木村敏『あいだ』(ちくま学芸文庫)
最後に、昨年8月に世を去った父・木村敏の著書から1冊を紹介したい。父は精神科医で、書名はその思想の代名詞ともいえるキーワード。過去-現在-未来がひとつながりの時間として感じられること、昨日の自分と今日の自分、明日の自分が「ひとりの自分」であると確信できることの根拠とは何なのか、それらの「あいだ」には何があるのかというのが、父が生涯考えつづけたテーマだった。好きだった音楽を論じることについてはストイックだった父だが、本書ではめずらしく、合奏する演奏家と演奏家のあいだ、演奏家と聴衆のあいだ、音と音とのあいだなどを縦横に論じていて、ひとつの音楽論としても読める。そのためか、とくに音楽家の読者の多い本でもある。
♪ドビュッシー《ベルガマスク組曲》より第1曲〈プレリュード〉
→父がひと仕事終えたときなどによく弾いていた曲。このチッコリーニの演奏がお気に入りだった。
*
最後にちょっとだけ宣伝を。拙著2作目となる『音楽のような本がつくりたい――編集者は何に耳をすましているのか』(木立の文庫)の発売に合わせて、「本屋B&B」(東京・下北沢)でブックフェアを開催してくれることになった(2022年2月1日~、終了日未定)。本稿で紹介した本をはじめ、多数の「音楽のような本」を並べていただいている。よろしければ、ぜひお運びください。
-
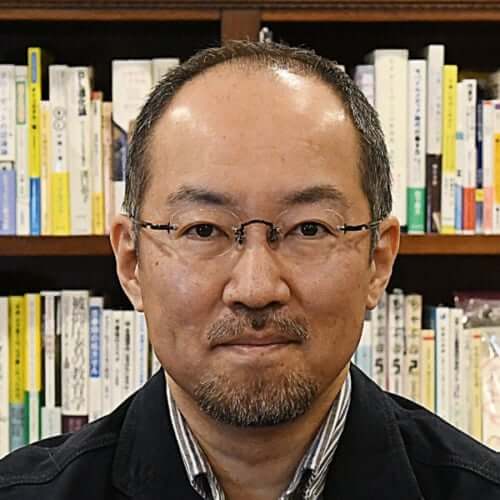
-
木村元
書籍編集者。株式会社アルテスパブリッシング代表。
1964年京都生まれ。上智大学文学部哲学科を卒業後、株式会社音楽之友社に入社。2007年独立して株式会社アルテスパブリッシングを創業。音楽書を中心に旺盛な出版活動を展開。「音楽書と人文書を融合。独自ジャンル創出」(『新文化』2017年6月15日号)と評される。
著書に『音楽が本になるとき──聴くこと・読むこと・語らうこと』(木立の文庫、2020)、『音楽のような本がつくりたい──編集者は何に耳をすましているのか』(同、2021)。
桜美林大学リベラルアーツ学群非常勤講師。国立音楽大学評議員。「ダ・ヴィンチ音楽祭in川口」および「北とぴあ国際音楽祭」アドバイザー。
Twitterアカウント @kimuragen
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-
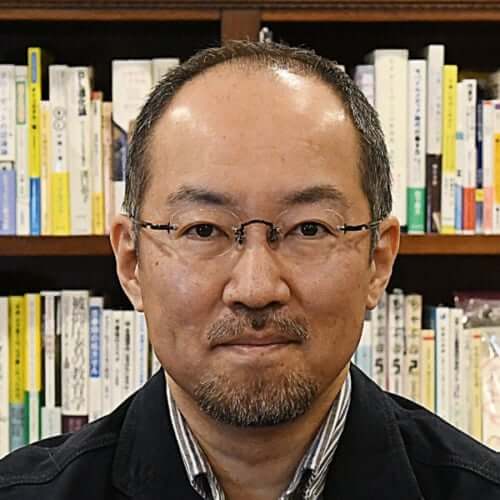
- 木村元
-
書籍編集者。株式会社アルテスパブリッシング代表。
1964年京都生まれ。上智大学文学部哲学科を卒業後、株式会社音楽之友社に入社。2007年独立して株式会社アルテスパブリッシングを創業。音楽書を中心に旺盛な出版活動を展開。「音楽書と人文書を融合。独自ジャンル創出」(『新文化』2017年6月15日号)と評される。
著書に『音楽が本になるとき──聴くこと・読むこと・語らうこと』(木立の文庫、2020)、『音楽のような本がつくりたい──編集者は何に耳をすましているのか』(同、2021)。
桜美林大学リベラルアーツ学群非常勤講師。国立音楽大学評議員。「ダ・ヴィンチ音楽祭in川口」および「北とぴあ国際音楽祭」アドバイザー。
Twitterアカウント @kimuragen

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら