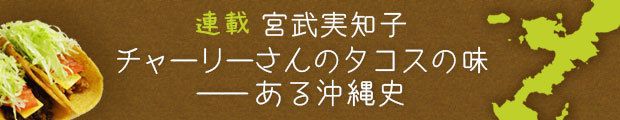(前回までのあらすじ)「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。奄美群島の喜界島の出身である。1953年に奄美が本土復帰して以降、外国人としての逆境にありながらレストランを営んできた。
「復帰っ子」という表現が沖縄にある。昭和47年に生まれた世代を指す。「本土復帰から〇年」がそのまま年齢になり、私もその一人だ。
この奇妙な言葉を初めて聞いたのは、沖縄の男性と結婚することが決まって挨拶廻りをしていた時のこと。覚えきれないほど多くの親戚や「親戚のようなもの」に次々と紹介され、「はじめまして」と頭を下げる。ぎこちなく出身を聞かれ、お世辞を言われた後、年齢ではなく「何年の生まれね?」と聞かれる。
元号を使っていた期間が短い沖縄なら西暦のほうがいいのかと気を回して「1972年です」と初めのうちは答えた。相手は怪訝な顔で「干支でいうと何?」「昭和の何年?」などと重ねて聞く。そして、急に嬉しそうな心得顔になって、「あ、あんた、復帰っ子ね?」と歓迎モードになるのだ。
「復帰っ子」は魔法の呪文だった。中高年世代に効果絶大で、あちらの心のバリアが一気に下がる。これは便利だ。聞かれる前に自分から、出身地とセットで「復帰っ子です」と名乗るようになった。私そっちのけで、「あの日、あの頃、自分は何をしていた」とそれぞれの思い出話に花が咲く。
昭和47年生まれで良かった、と初めて思えた。これまで「第二次ベビーブーマー」やら「団塊ジュニア」やら味気ない名で呼ばれ、進学や就職のたびに「かつてない倍率」だの「氷河期」だのと不安を煽られてきた。沖縄に来て初めて、生年だけで無条件の合格が出たのだ。
そういえば、沖縄にきて初めての国政選挙の時、掲示板でひときわ目立つポスターに足を止めた。「復帰っ子です!」という極太の明朝体が、ポスター画面の半分を占める。ハンサムな候補者の笑顔より大きく、投票用紙に書かせるべき氏名より大きく。沖縄政財界でたいそう有名なその苗字より大きい「復帰っ子」に感心して見入った。とはいえ、その人の誕生日は昭和48年2月。沖縄では昭和47「年度」もみな「復帰っ子」を名乗るらしい。かくも「復帰っ子」は説得力を持つ。
沖縄では「復帰っ子」以外に、特定の世代を表す言葉はない。沖縄の出生数グラフは、見慣れた日本のグラフとはまったく違う形をしており、突出した第一次ベビーブームはなく、ゆえに第二次ベビーブームもない。丙午(ひのえうま)の凹みも浅いし、沖縄戦の年に生まれた世代にも名前はついていない。「復帰っ子」だけが特別だ。
そこには「生まれながらの日本人」になった世代への期待感があるそうだ。だから厳密には沖縄生まれだけが「復帰っ子」で、私は該当しない。それでも「昭和47年生まれ」というだけで嬉しそうな顔をしてもらえる。
沖縄の一般の人たちにとって、本土復帰の年が特別に明るい記憶であることを意味するのではないだろうか。
どうでもいい個人情報を付け加えると、婚姻届けを提出した日は5月15日。夫から「結婚記念日にしたい日があるか」と聞かれて「どうでもいい」と答えたら、「では、ぜひ復帰記念日の5月15日にしたい」と強く希望された。
「当時、自分は小学2年生だったが、5月15日を指折り数えて待っていた。絶対に忘れない、めでたい日付だ。周りの大人たちがみんな嬉しそうで、自分たち子供も嬉しくてたまらなかった。日の丸の旗を振って喜んだ。ぴかぴかの青空が広がるような、喜びで光り輝いていた記憶がある」
小学2年生だから、理解も記憶もあどけない。なにしろ彼は、沖縄の島々が「ひょっこりひょうたん島」のごとく自力で動いていって、その日、物理的に本土にくっつくと思っていたらしい。
そして、実際のその日は、雨だった。

1972年5月15日午前零時をもって沖縄返還協定が発効、「沖縄県」が復活した。
その日は午前10時半から東京の日本武道館と那覇市民会館を結んで政府主催の「沖縄復帰記念式典」がおこなわれ、午後2時から同じ市民会館で「新沖縄県発足式典」が開かれた。
共産党と社会党(当時)は式典参加を拒否した。東京でも沖縄でも式典と同じ時間帯に抗議集会が開かれている。沖縄では式典会場に隣接した与儀公園で、復帰協(沖縄県祖国復帰協議会)主催の「5.15県民総決起大会」があった。
県民大会では、この沖縄返還は県民の要求を無視した「昭和の沖縄処分」だと主張され、5月15日を「屈辱の日」と呼んで那覇の街中をデモ行進した。(「屈辱の日」とはもともと、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効されて沖縄が日本と分離した日の呼び名だ。)「沖縄史」でよく目にする県民大会の画面には、灰色の雨が降っている。

当時の空気を正確に把握することは、その年に生まれた内地人の私には難しい。復帰前後の数年間を沖縄で過ごした報道関係の人からは、当時、日本政府への不信と失望がみるみる膨らむようだったという回想を聞いた。
1969年11月、佐藤ニクソン会談により72年の「核抜き本土並み」復帰が決定し、沖縄側は米軍基地の完全撤去を期待した。にもかかわらず、1972年時点で県内に87カ所もの米軍基地が残った。さらに自衛隊の沖縄駐留が決まる。「昭和19年時点の日本軍でさえ2~3000人だったのに、6000人以上もの自衛隊が来る」と不安が広がった。
当時の不安にはさまざまな背景があった。1971年の夏は大干ばつで断水が続いたが、特段の対策はされなかった。その夏ようやく実行された毒ガス撤去では、周辺住民の安全確保がされなかった。8月28日、日本政府は円の変動相場制を採用。ドルで生活する沖縄住民は、日本政府にも琉球政府にも損失を補償してもらえないのではないかと政治不信を募らせた。
復帰による諸々の変更も不満のもとだったようだ。復帰当日を「屈辱の日」と呼んだ復帰協という組織は、沖教組(沖縄県教職員組合)の割合が高かった。当時の沖教組では、復帰にともなって教育委員が任命制になることを「国家権力の介入」として大反対していた。教員の政治活動が禁じられ、勤務評定が導入されることも問題視された。「本土復帰は良いことばかりではない。基地は残り、自衛隊も来る」と教員たちは教室で啓蒙に努めるようになった。
はっきりと「即時復帰反対」を掲げる人々もいた。コザの基地労働者や業者たちである。彼らにとって、「平和憲法下の祖国復帰」は基地がなくなり、仕事がなくなることだと恐れられた。コザのAサイン・バーは、それぞれ屈強なボーイを出して戦闘訓練を受けさせ、米軍側に立って住民と対立した。
復帰に向けた「沖縄」は一枚岩ではなかった。それぞれの不安と思惑により、沖縄の内部で対立が深まることも危惧された。
沖縄の本土復帰は、勝田さんにどう映ったのだろう。
「本土復帰の日って、やっぱり感慨深いものがあるんですか?」
5月半ばに勝田家を訪ねた時、挨拶代わりに何気なく尋ねた。「いや」と勝田さんは短く答えた。「その時、308円でしたかね。ドルの交換がいくらになるのか、問題はこれだけですよ」と勝田さんは素っ気なく言った。復帰当日に始まった通貨交換では、3日前の12日夜に閣議決定された1ドル=305円が適用されたが、勝田さんの記憶では前年12月20日にスミソニアン協定で成立した1ドル=308円のレートが刻まれているようだ。
その素っ気なさは、かえって気になった。
復帰への素っ気ない態度も無理はない。本土復帰は、奄美出身の勝田さんにとって、沖縄の人とは違う意味をもつ。
1950年に沖縄に来たのは、奄美・沖縄がともに連合軍の統治下におかれたためだった。馴染みのあった大阪はもちろん、鹿児島本土へ渡ることすらできない。島を出た行き先に選択肢はなく、沖縄本島に来たのだった。
ところが、1953年12月に奄美が返還されて以降、一転して沖縄に残った奄美出身者は「外国人」となった。外国人登録証を常に携帯させられて、納税の義務はあっても市民権はない。銀行融資すら受けられず、不動産の所有はできず、職業選択は制限され、子供の進学もままならない。
1962年、コザ市議会は「奄美人の処遇に関する陳情書」を決議して、「沖縄在住の奄美人で転籍を希望する者はすみやかに転籍をさせ、同胞として同じ法のもとに生活が出来るよう」行政主席に陳情した。1965年になっても奄美出身者の処遇改善はまったく進まず、再び同じ内容の陳情がされているほどだ。
いつのことか詳しく聞かなかったが、勝田さんは子供のためを思って沖縄に籍を移した。「代書屋にずいぶんと払いましたよ」と漏らした額は、ちょっと驚くような金額だった。「こんなふうに沖縄が本土返還されるのが、いつになるか分からんかったからね」
奄美出身者にとっての本土復帰とは、ようやく日本に対しても沖縄に対しても「外国人」でなくなるということだ。悲願でもあり、「今さら」という思いもあったろう。もうパスポートなしで帰郷できる。沖縄に残るも、奄美に帰るも、さらに内地へ渡るも自由だ。
だから、ドル経済の陰りが見えてきた当時、奄美に帰った人も多かった。勝田さんも一度、鹿児島本土で大島紬の仕事でも始めようかと下見に行ったが、桜島の灰が降る気候に諦めたと聞いた。幸い移転先のタコス店も順調だ、すでに籍も移した、沖縄に残ろう、と決めたそうだ。勝田さんが沖縄に「根を張る」という最終的な覚悟を決めたのは、この本土復帰の時だったのかもしれない。
「勝田さんでも迷うんですね」と言うと、「移り変わりがあまりに激しかったんですよね、沖縄は……」と噛みしめるように呟いた。
(続く)
(※2025年2月一部改訂)
-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら