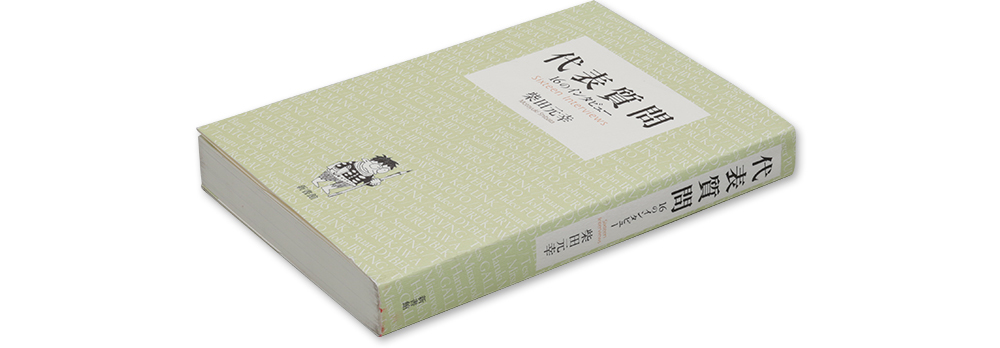敗戦後の本がない時代にそだったので、子どものころは、本は買ってもらうというよりも、どちらかといえば、友だちの家や近所のお兄さんから借りてくるものと思っていた。
その習性が70歳をすぎたころによみがえり、いまはふたたび、本は買うよりも、おもに借りて読むものになっている。なにせ退職老人だからね、懐具合に強いられて余儀なく、という面もあるにはあるが、それとおなじくらい、いや、もしかしたらそれよりも、手持ちの本をもうこれ以上増やしたくない、という気持のほうがつよいかもしれない。
――といったしだいで、以前であれば書店に向かっていたはずの足が、近年は、ともすれば図書館のほうに向いてしまう。先日も近所の図書館で何冊か借り、行きつけのコーヒー店で、そのうちの1冊、柴田元幸の『代表質問』というインタビュー集をパラパラめくっていたら、ふいに、こんなやりとりにでくわした。
『一人の男が飛行機から飛び降りる』の前衛ナンセンス作家、バリー・ユアグローへのインタビューで、おなじアメリカの、たとえばジェームズ・サーバーなんかからの影響はないですか? と柴田が問いかける。
ユアグロー もちろん大好きです。「ウォルター・ミティの秘密の生活」という、映画にもなっている、サーバーの短篇の中で一番有名なやつがありまして……。
柴田 映画の邦題は『虹を掴む男』ですね。ええと、ケイリー・グラントでしたっけ……。
ユアグロー いや、そうじゃなくて、ほら……。
客席 ダニー・ケイ。
ユアグロー そうそう、ダニー・ケイ。どうも(笑)柴田元幸『代表質問』新書館
あれあれ、おふたりとも、ダニー・ケイをよく知らないの?
ちょっとおどろき、いそいで「略歴」に当たると、柴田は1954年生まれで、ユアグローはその5つ上。したがって前者は私よりも16歳年下。後者となると、ほんの11歳しか下にすぎない。つまりは団塊世代とそのすこしあと。なのに、ほんとかよ、あのダニー・ケイの名がパッとでてこないなんて。
でもまあ、しかたないか。念のために、いちおう説明しておくと――。
ダニー・ケイは1913年生まれ。私にとっては父親の世代の天才的なボードビリアンで、34年にはマーカス・ショーというレビュー一座とともに来日し、前年に開館したばかりの日劇(いまの有楽町マリオン)の舞台に立った。停電で真っ暗になった舞台に、ライトを手にひとりで登場し、コミックソングやパントマイムでみごとに場をつないだという伝説がのこっている。
その後、ブロードウェイ・ミュージカルで売り出し、ハリウッドに招かれて、さきのふたりの会話にでてきた『虹を掴む男』(1947)の成功によって、だれもが知る映画スターになった。
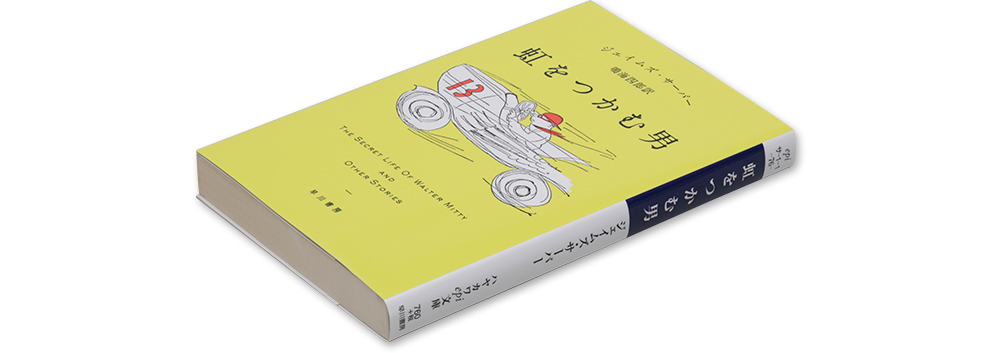
私がこの映画を見たのは50年代はじめだから、まだ中学生のころ。当時は土曜の授業が午前中だけだったので、学校が終わると、したしい友人とつれだって、よく映画を見に行った。とくに好きで通っていたのが、アメリカ製の新旧の喜劇映画をこまめに上映していた板橋弁天坐という映画館――。
学校にちかい目白駅で電車に乗り、つぎの池袋のりかえ、板橋駅で降りると、駅裏の、まだあちこちに空襲の焼け跡がのこる原っぱの向こうに、赤い柱の映画館が見える。ローレルとハーディの「凸凹コンビ」、ビング・クロスビーとボブ・ホープの「珍道中シリーズ」、ディーン・マーチンとジェリー・ルイスの「底抜けコンビ」など、どれも、このガランと大きな映画館の木の椅子にすわって見た。そのひとつが、ほかならぬ『虹を掴む男』だったのです。
主人公のミティはパルプマガジンの編集者で、やかましい母親の尻にしかれた気弱な男なのだが、車を運転していても会議の最中でも、「ポケタ、ポケタ、ポケタ」という奇妙な音をきっかけに、とつぜん夢の世界にはいってしまう。そのデイ・ドリーム(白日夢)の中でミティ君はいつも、ミシシッピーの賭博師や空の英雄や早撃ちガンマンやカリスマ外科医など、颯爽たるヒーローに変身している、のではあったが……。
この映画で、ダニー・ケイの度外れに明るく達者な芸にはじめてせっした私は、たちまち魅了され、あとにつづく『ヒット・パレード』『アンデルセン物語』『ホワイト・クリスマス』『5つの銅貨』などの作品を、ひとつのこらず追いかけて見るはめになった。
ボードビリアンとしてのダニー・ケイの特技は、機関銃なみにモーレツな早口ソングと、それに合わせて顔面筋肉をフル動員し、秒単位で、めまぐるしく表情を変えてみせる「顔芸」――よく知られた出し物として、おそらく私は『ヒット・パレード』で見たのだと思うが、チャイコフスキーの『悲愴』第3楽章にのせて、51人のロシア人作曲家の名をわずか38秒で一気にまくしたてる「チャイコフスキー」があった。
同様の芸が『虹を掴む男』でも見られたし、『5つの銅貨』でのルイ・アームストロングとの「聖者の行進」のにぎやかな掛け合いもそう。ビートのきいた語りに近い早口ソングという点では、いまのラップに似ていないでもない。いってみれば、その爆笑寄席芸版である。
しかし、それにしても、まいったな。なにせ私より10歳かそこらしか年下でない方々が、これほどの人気者の名を、もうはっきりとは思いだせずにいるというのだから。
もっとも1959年製作の『5つの銅貨』ののちは、とくにめだつ作品もなく、さしもの人気者も、いつしか、ユニセフ親善大使とかニューヨーク・フィルとの共演イベントとかの、なかば引退した大物スターの席にゆっくりと移っていった。ようは、たまたま私の少年期がかれの全盛期にかさなったというだけの話で、柴田さんやユアグローたち、すぐあとにつづく世代の人びとにとっては、早くもライブ感を失った「歴史上の人物」と化してしまっていたということなのだろう。
――おや、「歴史上の人物」ときたか。それだって、けっこう古いコトバだぜ。
うん、いわれてみれば、たしかにそう。
ダニー・ケイがスクリーンでもっとも魅力的だった時代――つまり戦後すぐのころから60年代の終わりまで、NHKラジオに「二十の扉」という人気番組があった。藤倉修一アナの司会で、宮田重雄(画家)、七尾伶子(声優)、大下宇陀児(探偵小説作家)、藤浦洸(作詞家)といった常連メンバーが、「それは動物ですか?」「人間ですか?」「男ですか?」といった問いを20回かさねて、かくされていた答えを当てる。そこに「それは歴史上の人物ですか?」という問いがよくでてきた。「歴史上の人物」というのは、ここからはやりはじめたことばだったのだ。
『虹を掴む男』に主演した当時はまだ30代なかば――少年だった私の目にはあんなにも輝かしく映っていたダニー・ケイが、わずか十数年後には、ともすれば「それは歴史上の人物ですか?」と問われかねない、うすぼんやりした存在と化している。
その酷薄な現実に私はなかなか気づかない。でも、どこかの段階で、この場合でいえば柴田元幸のインタビュー本を読むなどして、おくればせながら、その事実に直面させられる。そして同様の体験をなんどか繰りかえすうちに、ふと気がつくと、私自身や、私と同年代の連中までが「歴史上の人物」になりかけていた。すなわち、じぶんの体験が早々と歴史のうちに繰りこまれ、それにつれて「私の時代」がしだいに後ろにずれてゆく……。
*
この「私の時代が後ろにずれてゆく」感覚を、2008年に平凡社から『ジェローム・ロビンスが死んだ』という本をだしたときにも、さんざんに味わわされた。

ジェローム・ロビンスは、20世紀のアメリカを代表するバレーダンサー兼コレオグラファー(振付家)で、大衆文化の世界でも、ミュージカル『ウエスト・サイド物語』『屋根の上のバイオリン弾き』などの舞台や映画の振付家・演出家・共同監督として広く知られている。
ただし私がかれの名を最初に知ったのは、もっと古く、やはり中学生のころに繰りかえし見たジーン・ケリーやフランク・シナトラの『踊る大紐育』というミュージカル映画の――より正確にいうならば、1944年に盟友の作曲家レナード・バーンスタインとともに、そのもとになったブロードウェイ版『踊る大紐育』をつくった人物としてだった。つまり青少年期の夢見る私にとってのロビンスは、その軽快な明るさによってダニー・ケイやジーン・ケリーとならぶヒーローのひとりだったのです。
ところが、そのロビンスが1998年に79歳で死んだのち、たまたま目にしたアメリカのインターネット新聞の追悼記事で、半世紀まえ、かれが「赤狩り」の密告者だったという辛い事実を、はじめて知ることになった。
――1947年というから、ちょうど『虹を掴む男』が公開されたのとおなじ年、米ソ冷戦が激化するなかで、アメリカ下院議会の非米活動委員会がFBIと組んで、ハリウッドを舞台に、共産党員や元党員、その同調者たちを片っ端から摘発する大がかりな活動を開始し、300人をこえる映画人や演劇人がハリウッドから追放された。
そして、その追悼記事によると、この陰惨な「赤狩り」がすすむなかで、元共産党員で、ブロードウェイで大ヒット中の『王様と私』の振付家だったロビンスが公開聴聞会の場に引きだされ、かつて党員仲間だった8人の映画人の名を告げていたというのだ。
――ええっ、まさか。
かんたんには信じがたい。でも、さらにしらべてみてわかった。私が知らなかったというだけで、これはまぎれもない事実だったのである。
しかしそれにしても、かれはなぜそんな裏切り行為に走ってしまったのだろう。『ジェローム・ロビンスが死んだ』は、そのなぞを解くというミステリー仕立ての本なのだが、これを書いたとき私には大きな誤算がひとつあった。
映画『ウエスト・サイド物語』や『屋根の上のバイオリン弾き』が日本で封切られたのが1961年と71年。ほどなくそれらの舞台版(劇団四季と東宝ミュージカル)も登場し、けっこうな評判になった。であるからには、と私は思った。とうぜんジェローム・ロビンスの名も、それなりの広がりで知られているのだろうな。とすれば、すべてとはいわずとも、そのうちのかなりのかずの人が、かれが「赤狩り」の密告者だったと知ったら、私とおなじように、きっとつよいショックをうけるにちがいない――。
ところが、そうではなかったのですね。本をだしてみてわかった。ずっと若い人たちはともかく、私よりすこし若いだけの団塊世代の人びとですら、ジェローム・ロビンスときいて「あァ、あの……」とピンとくる人のかずはきわめて少なかった。
「大きな誤算」というのはそのこと。なにしろ私としては「だれもが知っている高名な20世紀人の意外な人生」式の本を書いたつもりだったのだから。しかもロビンスだけではない。前世紀なかばのハリウッドの「赤狩り」に関心をもっている人も、ほとんどいないらしい。誤算につぐ誤算。なるほどね、どうやら「私の時代」は、はるか遠い昔のことになってしまったらしいや。
そして、もうひとつ――。
これもこの本を書いていて知ったのだが、ジェローム・ロビンスとダニー・ケイは、じつは若いころ、なかなかにつよい縁でむすばれていたのである。
1930年代、ペンシルヴァニア州ポコノ山中の保養地で、毎夏、青年労働者むけのサマー・キャンプが催されていた。小さな劇場があり、まだ20歳になるやならずの貧乏ダンサーだったロビンスは、そこで何年か、教師を兼ねるダンサーとしてはたらいていた。
やがてそこにダニー・ケイという若手コメディアンが加わってくる。かれの経歴でいえば来日から数年がたったころ。ロビンスより5つ年上で、おなじニューヨーク育ちのユダヤ系移民2世。ふたりはすぐに親しくなり、この劇場で、いくつもの社会風刺的な寸劇やダンスの小品を上演した。そして1939年、思いがけないできごとが起きる。かれらの寸劇をもとにしたミュージカルが、ブロードウェイの劇場で上演されることになったのだ。
この舞台をきっかけに、ダニー・ケイは、さらに格上のミュージカル『闇の中の女』に出演し、例の早口ソング「チャイコフスキー」が大当たりして、ハリウッドへの道がいっきょに開かれる。
一方のロビンスは、このときはさしたる評価は得られなかったけれども、翌年、発足したばかりの「アメリカン・バレエ・シアター」のオーディションに合格し、『トロイのヘレン』や『ペトルーシュカ』などの舞台で、たちまちトップ・ダンサーのひとりとしてみとめられるようになった。
そして『踊る大紐育』をへて「赤狩り」へ――。
1947年10月、ナチス・ドイツからの亡命者で『三文オペラ』の劇作家ベルトルト・ブレヒトをもふくめて、19人の急進的な映画人が非米活動委員会に喚問される。
――もしあなたが売国的な共産党員でないなら、あなたの知っている党員や同調者の名をあげてください。もし拒むなら、あなたを共産主義者とみなします。
それから10年以上もつづくことになるハリウッドの「赤狩り」の開始である。
この脅迫に対して、ジョン・ヒューストン、ウィリアム・ワイラー、ジーン・ケリー、ハンフリー・ボガート、ローレン・バコール、カーク・ダグラスたち、おおくの映画人がアメリカ憲法の「修正第1条〔言論・集会の自由〕支持委員会」という抗議運動に結集し、資金カンパのための大集会をひらく。そこで司会役として開会のあいさつに立ったのが、ほかならぬ『虹を掴む男』のミティ君、いまや堂々たるスター俳優になったダニー・ケイだった。
ぼくがここにいるのは、アメリカ憲法と権利章典〔修正第1条をふくむ人権保障規定〕のためです。ぼくはこのふたつを信じているし、非米活動委員会と称する者によって、これが破壊されようとしていると信じるからです。
しかし、このスターたちの運動は、「修正第1条」をタテに非米活動委員会への協力を拒む者とは再契約しない(=解雇・追放する)というハリウッドのボス連合(映画製作者協会)の最後通告をうけて、あっけなく崩れてしまう。少数の例外をのぞいて、スターたちのほぼ全員がこの通告に屈し、重苦しい沈黙のうちに閉じこもることになったのだ。ヒューストンもボガートもダグラスも、そしてわが愛するダニー・ケイも。
この屈服をよしとしない者は通告どおり、情け容赦なくハリウッドを追われた。あやうく家族とともに国外に逃れた者もいたし、投獄や自殺に追い込まれた者もいた。
こうした混乱のなかで、委員会の喚問はいっそうはげしさを増し、『ジョルスン物語』の新進スターだったラリー・パークスや、『紳士協定』のアカデミー賞監督エリア・カザンにつづいて、ジェローム・ロビンスがせっぱつまった裏切りに走らされる。その背後には、右翼コラムニスト、エド・サリバン一派による執拗な脅迫(「おまえが非米的な同性愛者だということを暴露するぞ」など)があったといわれる。
*
それにしても、どうして私はあの時期(21世紀ゼロ年代のなかば)に、『ジェローム・ロビンスが死んだ』という本を書いたのだろうか。
いまものべたように、ロビンスの裏切りのうちにあったはずの、そうそう単純には割り切れないであろう動機のすべてを知りたい――それが直接の理由だったのはたしかだが、でもそれだけではない。知りたいと思う私のうちには、それなりに切迫した「おそれ」があったのである。
2001年9月11日の同時多発テロののち、アメリカ合衆国で、イスラム教徒へのヘイトクライムが急増し、排他的な愛国主義の空気がまたたくまにひろがってゆく。ナチズムのドイツ、ファシズムのイタリア、スターリズムのソ連、軍国主義の日本だけではない。民主主義を国是とする現在のアメリカにおいてすら、なにかあれば、国をあげての「非国民」排除の熱狂的な動きが、かんたんに起こってしまう。
アメリカがそうなら戦後の民主日本だっておなじ。もしこの国が再度そんな状態におかれたとして、はたして私に「ロビンスやカザンのようなふるまいは決してしない」と言い切ることができるかどうか。たとえいまは「できる」と思っていても、いざその場に立ったら、どうなるかわかったもんじゃない。古稀をすぎた巷の一老人までがふとそんなふうに考えてしまう。「私の時代」とは、どうやらそういう時代でもあったらしい。
そして、さらにいうと、なのに「いまの人」は、ダニー・ケイの「チャイコフスキー」はともかく、ハリウッドの「赤狩り」にも、まったくなんの関心も持っていないように見える。「それでホントに大丈夫なの?」というのもまた、この本をだしたあとで私がいだいた「おそれ」の一部分だったのです。
ところが、この本から10年がたち、あろうことか、この国でも「反日」や「非国民」といったイヤなことばが公然とよみがえってきた。
そのため、かつては「私の時代」のものだった「ことによったら裏切るかもしれない私」へのおそれを、「いまの人」までがやむなくいだきはじめたがごとき気配がある。昨2017年、たてつづけに刊行された『赤狩り』と『君たちはどう生きるか』というふたつの漫画にせっして、ようやく私はそう感じるようになった。
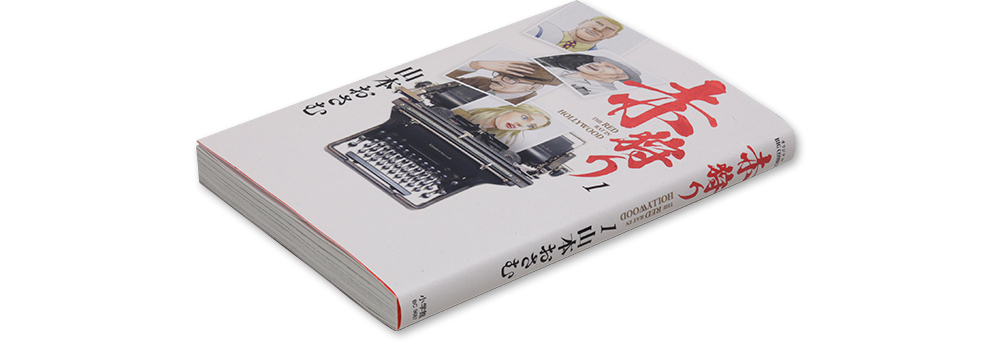
そこでまずは山本おさむの『赤狩り』について――。
この漫画は昨年5月、『ビッグコミックオリジナル』で連載がはじまり、つい最近、その4か月分が本になった。完結時には、ウィリアム・ワイラーの『ローマの休日』篇、エリア・カザンの『エデンの東』篇、そして、おそらくは『猿の惑星』 (1968)篇の三部からなる、かなりの大作になるらしい。この稿を書いているいまは、第1部『ローマの休日』篇がそろそろ終わりに近づきつつある。
ワイラーは、「赤狩り」開始の前年に『我等の生涯の最良の年』でアカデミー賞をうけた大物監督だったが、FBIの監視下におかれたハリウッドで仕事をするのをきらい、なかば集団亡命のように、おおぜいのスタッフをひきつれてヨーロッパに渡った。
そこで撮った『ローマの休日』(1953)のシナリオを匿名で書いたのが、非米活動委員会によって投獄された最初の10人のひとりだったダルトン・トランボ。このふたりを軸に、『ローマの休日』という作品の特殊な成り立ちや、かくされた主題を、さまざまな角度から照らしてゆくというつくりになっている。
つづく第2部『エデンの東』(1955)の監督エリア・カザンは、「赤狩り」に対する最強の防波堤という期待に反して、古いつきあいの友人たちの名を非米活動委員会に「売って」しまう。
権力による強制、世間の空気、あからさまな暴力などによって、それまでのじぶんの考えを捨て、親しい人びととの信頼関係を裏切るように迫られたら、はたして私たちはどうふるまえるのか。その3つの例を漫画にしかできないしかたで示してみせる。おそらくはそんな作品として完結するのであろう。それにしても、よもやこの時期になって、こんな「そのものズバリ」の漫画がでてくるなんて、想像してもいなかったな。
そして同じ年の8月、こんどは吉野源三郎の原作による羽賀翔一の『君たちはどう生きるか』という漫画が、マガジンハウス社から刊行される。

主人公は中学2年生のコペル君で、かれが体験した「あるできごと」と、かれにあててしるされた若い叔父さんの「ノート」によって構成されている。ここではくわしく紹介している余裕がないので、その「あるできごと」だけにしぼって、ざっと要約しておくと――。
登場するのはコペル君とその3人の友人、優等生の水谷君、行動派の北見君、貧しい家にそだった温和な浦川君。その浦川君を同級のいじめっ子があくどくからかい、一本気な北見君が怒ってその同級生に平手打ちをくらわせる。それをきっかけに4人が仲よくなり、なにかあったらみんなで立ち向かおうという約束をかわす。
その一方で、いじめっ子の兄の上級生グループが北見君をつけねらうようになり、ある雪の日、とうとう北見君をつかまえて殴る蹴るの制裁をくわえ、「他にも仲間がいるなら出てこい!」とどなる。浦川君と水谷君は思いきって進みでるが、コペル君はその場に立ちつくしたまま。こわくて出てゆく勇気がなかったのだ。
――ぼくは約束を守れずに、みんなを見捨てた。そして、みんなから見捨てられた。
後悔に押しつぶされたコペル君は病気になり家に閉じこもってしまう。そんな状態がしばらくつづいたのち、心配した叔父さんとの会話から、ようやくコペル君は友情回復への一歩を踏みだす……。
すぐわかるように、ここにも、権力による強制や脅迫に直面した人間がどうふるまうか、という主題が見てとれる。「赤狩り」との比較でいえば、「学校の規律を乱すな」と腕力をふるう上級生グループは非米活動委員会に、一本気な北見君はトランボに、水谷君や浦川君はワイラーに当たるといっていいだろう。ではコペル君は? さしずめ裏切りののち、じぶんはまちがいをおかしたという苦い自覚によって、ようやく『ウエスト・サイド物語』で再生の一歩を踏みだすことができたジェローム・ロビンスといったところか。
こうした漫画の売り上げが4か月で85万部をこえ、同時に刊行された原作の新装版も24万部にたっしたというのである。合計して109万部。いちどは引退宣言をして「歴史上の人物」になりかけた宮崎駿も、おなじ原作にもとづくファンタジーのアニメ化にとりかかったらしい。
原作者の吉野源三郎には、戦前、治安維持法違反で逮捕された経験がある。その後、1937年に、みずからを編集現場の長とする「日本少国民文庫」の一巻として新潮社から刊行されたのが、この『君たちはどう生きるか』だった。
私はこの漫画版のことを、筑摩書房のPR誌『ちくま』での斎藤美奈子の連載「世の中ラボ」ではじめて知った。この回のタイトルは「なぜいま『君たちはどう生きるか』なのか」――なかで斎藤が「だけど80年も前の本でっせ」と、こうしるしている。
1937年に13歳だったコペル君たちは、学徒動員の世代に当たる。彼らのような少年たちが6~8年後には戦争に動員されて命を落としたのである。にしても、なんという時代になってしまったのか。偏狭な国粋主義に抗うために、『君たちは……』が求められる時代が来るとは思ってもみなかったよ。
私のような老人だけでなく、「いまの人」までが「ことによったら裏切るかもしれない私」へのおそれをいだきはじめている。それが全面的にいいことだとは、とてもいえないのである。
―――――――――
柴田元幸『代表質問』新書館、2009。朝日文庫、2013
ジェイムズ・サーバー『虹をつかむ男』鳴海四郎訳、ハヤカワepi文庫、2014
津野海太郎『ジェローム・ロビンスが死んだ』平凡社、2008。小学館文庫、2011
山本おさむ『赤狩り』(『ビッグコミックオリジナル』連載中)第1巻、小学館、2017
羽賀翔一『君たちはどう生きるか』吉野源三郎原作、マガジンハウス、2017
斎藤美奈子「世の中ラボ」(『ちくま』2017年12月号)