私がある本をえらぶのか、それともある本が私をえらぶのか。いずれにせよ、近ごろは、じぶんとおなじ年ごろの70代から80代ぐらいの人たちが書いた本を手にとる機会が、めだって増えてきた。
いまのいま、そうである人たちの本だけでなく、そこには、かつて70代から80代だった過去の人たちの著作もふくまれる。ただし時代をさかのぼるにつれて、こうした区分けなど次第にどうでもよくなってくるのもたしか。だって、ちょっと後ろにもどれば平均年齢50歳の時代だぜ。そんな時代に生き死にした漱石や鷗外が老人であろうとなかろうと、そんなこと、もうどうでもいいじゃないの。
そして時代をさらにさかのぼると、行きつくところは古典――。
古典では、その本が歴代の読者とともに生きた時間の質量が、年齢にとってかわる。つまりは本そのものが老人なのだ。老人は老人同士、なんだか、いいつきあいができそう。そこで多くの人が、このさき年をとったら、こころやすらかに古典をひもといて暮らしたいものだ、などとねがうようになる。老人になるまえの私にもそうした傾きがなかったとはいえない。
ところが、いざじっさいに年をとってみると、なかなか思ったようにはいかんのですよ。われわれ新老人をニヤニヤと皮肉な目つきで待ちかまえている難関がいくつもある。その最大のひとつが「古典が読めない!」という難関――ざんねんながら、現今の老人には、古典をぐいぐい読みすすめる力がみごとに欠けているのである。
ここでいう「現今の老人」とは、敗戦の年に小学校に入学した私からあとの、戦後教育をうけ、そのまま年老いてしまった人びとをさす。占領下の日本でものごころついた私の場合でいえば、小学校から高校まで、習字や漢文もふくめての本気の古典教育をうけたという記憶がまったくといっていいほどない。その点にかんするかぎり、私のあとにきた人たちだって、だいたいは似たようなものなのではないかな。
その結果、いまや、ごく少数の専門家をのぞく日本人の大多数が、古典を自在に読みこなす能力を身につけそこなったままでいる。でもわれわれ以前の人たちはかならずしもそうではなかった。たとえば――このところ私は、若いころ好きだった堀田善衞が老いたのちにだした本をまとめて読んでいるのだが、なかの1冊、1989年刊の『誰も不思議に思わない』という随筆集に、こんな場面がでてくる。

臼井吉見氏と本居宣長の話をしていたとき、私はまだ『古事記伝』なるものをのぞいたこともなかった。それでこの著作について臼井氏に訊ねた。
「まだ読んでいないの。それは惜しい。あれは探偵小説のように面白いよ。是非読んでみたまえよ」
と臼井氏が言ってくれた。(略)かくて私は、その一言につられて、『古事記伝』を読んだ。それは本当に古事記という謎にみちた古典神話を、いかにして正確に(正確に、に傍点あり)読むかという(略)宣長が全智全能をかたむけた一大推理なのであった。その全智全能のかたむけ方が、読んでいると肉体的なまでに快くなるのである。
臼井氏のあの一言がなかったら、おそらくいまでも私は、『古事記伝』などは敬して遠ざかっていたことであろう。
臼井吉見は堀田より13歳上の1905年生まれ。いまは知らない人がほとんどだろうが、旧制松本高校時代からの親友だった古田晁とともに筑摩書房を創設し、戦後を代表する総合雑誌『展望』編集長として活躍した高名な編集者・評論家で、のちに谷崎潤一郎賞をうけた『安曇野』などの作家でもあった。
こう書けばおわかりでしょう。くやしいけれども、われわれとはちがう。臼井や堀田にかぎらず、かつては大学のそとの作家や評論家たちまでが、こんな会話をごく当たり前に交わしていたのです。
堀田についていうならば、『古事記伝』こそ読んでいなかったけれども、かつて、明日のいのちも知れない戦中派青年のひとりとして、『方丈記』や『応仁記』などの、戦乱や天災や飢饉があいつぐ乱世の産物ともいうべき一連の古典を、切迫した思いで読みつづけた経験があった。そうしたなかで、
戦時中の、まだ学生であった頃に、定家卿の『明月記』(明治四十四年、国書刊行会本)を入手して、ぼつぼつとあの難読そのものと言うべき、和製漢文の日記を読みはじめていたことがあって、冷泉為臣氏編になる時雨亭文庫の第一冊目も入手していたのであった。(『故園風来抄』)
ところが、その「文庫」刊行がふいに中断され、戦争が終わったのちも、いっこうに続刊の気配がない。それが為臣氏の戦死のせいだったということは、あとになって知った。「まことに冷泉家は定家卿以来、『紅旗征戎吾ガ事ニ非ズ』で、戦乱とは直接如何なるかかわりももたない、和歌の家であった」のに、と堀田はのちに「古事記から万葉集へ」という文章でしるしている。

この文章をおさめる『故園風来抄』は、朝日新聞出版刊『冷泉家時雨亭叢書』の月報連載を一冊にまとめたもので、1999年に集英社から刊行された。
『冷泉家時雨亭叢書』とは、冷泉家という名だたる「和歌の家」が800年にわたって保存してきた膨大な蔵書(自筆本・写本・古文書など)を写真版として集録したもので、全72巻(※)。そこにはとうぜん藤原定家自筆の日記『明月記』もふくまれていた。堀田の連載も、おそらくはかれの旧著『定家明月記私抄』につながる依頼だったのだろう(※『故園風来抄』刊行時。その後全100巻、別巻3が刊行された)。
この連載は、日本の古典をめぐる短めのエッセイを時代順につづるという趣向で、『懐風藻』『文華秀麗集』『万葉集』にはじまり、『土佐日記』『竹取物語』『伊勢物語』『源氏物語』『古今集』などをへて、『梁塵秘抄』『新古今集』『日本霊異記』『愚管抄』『徒然草』『応仁記』『狂雲集』と書きつがれ、1998年、連載が31回目の『一言芳談抄』になったところで、著者の死によって中断される。けっきょく、これが堀田善衞の最後の著書ということになった。
すると連載のはじまったのが1992年だから、これは80歳で没した堀田が70代後半に書いた本ということになる。
当初から、かれは、この連載であつかう原典のすべてを読むか、読みなおすかしようと決めていたらしい。もちろん、ざっと読みとばすとか、ときには必要な箇所にしぼって読んだりもしたのだろう。でも基本的には、「日本霊異記の全説話と付き合うことはなかなかのことであったが」などとグチをこぼしながらも、最後まで所期の目標をつらぬきとおすことができた。
それにしても、70代後半から80歳といえば、いまの私とまったくおなじ年ごろですよ。死を目前にしたそんなよれよれ老人が、どちらかといえば軽いエッセイ連載のために、これだけの重労働をなんとかこなしてしまう。いまとなってはもはや絶滅寸前というしかないが、しばらくまえまでは、こうした荒わざを平然とやってのける人たちが私たちのすぐそばに生きていた。そして堀田はまぎれもなくそのひとりだったのです。
*
堀田にかぎらず、かれの身近な友人たち――たとえば敗戦の2年後、『一九四六 文学的考察』(真善美社。初出は雑誌「世代」昭和21年)で華々しく登場した加藤周一、中村真一郎、福永武彦の「三秀才」(と冗談で呼ばれた)も、日本の古典に、ある点では専門の学者以上に深くつうじていた。
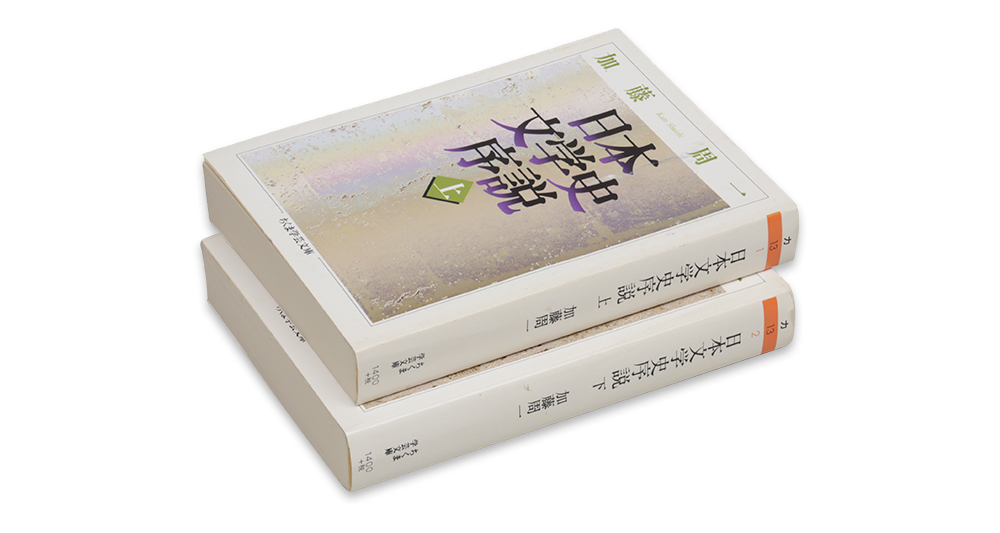
加藤周一の『日本文学史序説』(戦後はじめての本格的な日本文学通史)が『朝日ジャーナル』に毎週連載されていたのが1973年から78年にかけて。連載のさい、かれはおびただしいかずの作品を原典で読み、あまつさえ、そのころ教えていた欧米各地の大学での講義のために、重要な箇所を、そのつど英語やフランス語やドイツ語に翻訳していたのだとか。
中村真一郎も終生、平安文学や江戸期の漢詩文を読むことをやめなかった。そういえば私にも大学にはいってすぐのころ、刊行されたばかりのかれの『王朝の文学』という本を読み、『源氏物語』をプルーストにかさねて読むという離れ業にせっして、よくわからないままに、ちょっとびっくりしたおぼえがあるぞ。

ふたりの友人ほどには深入りしなかったようだが、福永武彦も、つね日ごろ、ごくふつうに日本の古典にせっしていたらしい。『南総里見八犬伝』『椿説弓張月』『東海道中膝栗毛』といった江戸末期のベストセラーをめぐる読書随筆などのほかにも、『古事記』や『日本書紀』や『今昔物語』の現代語訳がいまにのこされている。
多かれ少なかれ古典にしたしんでいたという点では、かれらよりもいくらか年長の石川淳や坂口安吾や太宰治たち、いわゆる「無頼派」の人びとや、花田清輝や大西巨人や長谷川四郎などの左派の文人たちでさえも例外ではなかった。
そののちも、いちじるしく減ったとはいえ、『日本文学史早わかり』の丸谷才一、『戯作者銘々伝』の井上ひさし、『文車日記 私の古典散歩』の田辺聖子のように、身辺に古典をおいて暮らす作家たちがまだいくらかはいたのである。しかしその井上も2010年に、2年後の12年には丸谷才一までが世を去ってしまう。かれらにすぐつづく私と同世代の作家では、そうねえ、せいぜい『仮往生伝試文』の古井由吉がいるぐらいじゃないかな。
ただしだからといって、私のように、しょぼくれて吐息をついている者だけではない。「古典が読めない」作家にも、読めないなりに、いや読めないからこそできることがあるはずだ。そんな希望的確信を大胆に現実化してみせたのが、2014年、丸谷たちのあとをつぐかのように、「池澤夏樹=個人編集」と銘打って登場した河出書房新社版『日本文学全集』だった。
父の世代の作家たちが身につけていた古典の分厚い教養が、息子の世代になると、ほとんど跡形もなく失われてしまっている。これはやっぱりまずいよ。なにはともあれ、みずからの無知無能に抗して、小説家や詩人にしかできないしかたで古典をいまに復活させてみようじゃないか。作家にしかできない古典復興。つまりは生きのいい現代語訳を――と、そう最初に呼びかけたのが福永武彦の息子の池澤夏樹だったというのも、たいへん印象的だった。
しかし、なにせ「古典が読めない」のである。そんなハンパな人間がどうやって現代語訳の作業にとりかかればいいのだろう。
そこで、そのお手本、というよりテストケース、もしくは新全集発足にあたっての派手なオープニング・ショーとして、まずは呼びかけ人の池澤夏樹が、じぶんで全集第1巻の『古事記』現代語訳を実地にやってみせることにした。

――私だって『古事記』を自力で読みこなせるわけではない。でも、いまは専門家による新しい研究や注釈がいくらも見つかるからね。それをたよりに、「書く人間」としての作家がそれぞれにきたえてきたことばの力で、古典を読みこなす。そうやってはじめれば、まあ、なんとかなりますよ。
そしてじっさい、池澤版『古事記』の冒頭におかれた「この翻訳の方針――あるいは太安万侶さんへの手紙」という文章によると、かれはこんなふうに仕事をすすめたらしい。
現代語訳の基礎として使ったのは本居宣長の『古事記伝』という礎石の上に構築された西郷信綱さんの『古事記注釈』です。読み下しについてもテクストは西郷さんのものに依りました。正直に申し上げると、学識なきぼくが作った脚注の多くは西郷さんの説を踏襲したものです。まこと先達はあらまほしきかな。先達と立てるどころか簒奪だと西郷先生に叱られるかもしれませんが。
こうやって仕上げた『古事記』を皮切りに、これまで古典とまともにつきあったことのない作家たちが、池澤とおなじようなやり方でいっせいに現代語訳にとりくみ、いまもそれが継続中――。すなわち、川上弘美訳『伊勢物語』、江國香織訳『更級日記』、中島京子訳『堤中納言物語』、角田光代訳『源氏物語』、町田康訳『宇治拾遺物語』、伊藤比呂美訳『日本霊異記』、古川日出男訳『平家物語』、いとうせいこう訳『曾根崎心中』、円城塔訳『雨月物語』などなど。
そこで引用をもうひとつ、こちらは同書巻末におかれた池澤の「解説」から。『古事記』には、それまで口頭で伝えられてきた「語り」の「寄せ集めが整理不十分なままこの本になった」印象があるとして、
〔しかし〕統一がとれていないからこそ、混乱の中に彼らの息吹が感じられる。これ以上整理してしまっては何か大事なものが失われると〔編者の〕太安万侶はわかっていた。(略)
そう考えると、本居宣長が慎重な手つきを精一杯だいじにしたことの意味もわかる。壊れ物を壊さないように次の世代に手渡す。西郷信綱も同じように『古事記』を丁寧に扱った。
その末席に自分も連なっている、とぼくが言えればよいのだが。
どちらの引用にも本居宣長の『古事記伝』がでてくる。そう、かつて堀田善衞が臼井吉見におしえられて読み、「いかにして正確に読むかという(略)宣長が全智全能をかたむけた一大推理」と感嘆したあの本です。その『古事記伝』をひきついで戦後の日本文学研究を代表する大学者、西郷信綱がまとめあげた『古事記注釈』という大著を手に、こんどは池澤夏樹が『古事記』に接近していった。
そして、その池澤の呼びかけに応じて、あやうく途切れそうになった「古典読み」の伝統を、いまの世代の作家たちが現代語訳というしかたでよみがえらせ、それを「次の世代」に手渡そうとしている。ひとつの理想を有形無形のグループの力によって社会に肉化する。という意味では古典ルネサンスをめざす文学運動の一種。それにしても、いまのような時代に、とつぜんこんな運動がはじまるとはね。まったく思ってもいなかったよ。
*
いや、すこしちがうかな。いま「とつぜん」と書いて気づいたが、池澤編『日本文学全集』の出現は、もしかしたら、かならずしも「とつぜん」といったものではなかったかもしれない。
というのも、じつはこれとおなじ時期に、古典の現代語訳という領域で、いくつかの新しい動きが生じていたから。まっさきに思い浮かぶのが伊藤比呂美訳による仏経典や中世の民衆的な「語りもの」です。つまり、2004年の『日本ノ霊異ナ話』にはじまり、『読み解き「般若心経」』、『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、『新訳 説経節』をへて、『日本文学全集』に集録された説経節「かるかや」や『日本霊異記』や『発心集』などにいたる雄渾な流れ――。

なかでも個人的には『新訳 説経節』からうけた衝撃が大きかった。
この本におさめられた「わたしの説経節」という文章によると、1600年前後、神仏のご利益や縁起伝説をタネに、「最初はお寺の門前で、それから、辻々で、あるいは門々で、(略)僧形じゃない説経節語りが大傘を広げて、その下でささらをすりすり、語っていた」土俗的な語りもの。それが説経節です。
その説経節を、30年前のある日、ふと手にとった平凡社の東洋文庫で知り、以来「説経節には惚れ抜いてまいりました」(同書「前口上」)とのべる伊藤比呂美が、そのうちの「小栗判官」「しんとく丸」「山椒太夫」の三作を現代語訳したのが『新訳 説経節』という本になった。
この3作のうちでは「小栗判官」にとりわけつよい印象をうけた。なにはともあれ、まずは以下の引用を読んでみてください。
――ゆえあって都から東国に追放された貴公子「小栗」が、郡代の娘「照手姫」と愛し合うようになる。その後、あれこれあって殺された小栗は地獄に落ちた。だが、やがて足腰の立たない餓鬼のすがたのまま蘇生し、ご利益を願う人びとが代わる代わる引く粗末な車にのせられて、はるか熊野本宮をめざす陰惨な旅をつづける。
「一引き引けば、千僧供養。二引き引けば、万僧供養」――
その長い長い道をたどる「道行き」とよばれる場面の一節です。
……どこまで行くかとたずねれば、〈九日峠〉はここですか、
坂はなくても〈酒匂〉の宿よ、
〈おいその森〉をえいさらえいと引き過ぎて、
はや〈小田原〉の町に入り、狭い小路に下馬の橋、
〈湯本〉の地蔵を伏し拝み、
〈足柄〉〈箱根〉はここですか。
〈山中三里〉、四つの辻。〈伊豆〉の〈三島〉や浦島や、
〈三枚橋〉をえいさらえいと引き渡し、
流れそうで流れぬ〈浮島が原〉……
念のために、おなじ箇所を伊藤比呂美が用いたであろう東洋文庫版から引いておくと、
……末をいづくと問いければ、九日峠は、これかとよ。坂はなけれど、〈酒匂〉の宿よ。おいその森を、えいさらえいと、引き過ぎて、はや、小田原に、入りぬれば、狭い小路に、けはの橋、湯本の地蔵と、伏し拝み、足柄、箱根は、これかとよ。山中三里、四つの辻、伊豆の三島や、浦島や、三枚橋を、えいさらえい、と引き渡し、流れもやらぬ、浮島が原……。
くらべてみればわかるように意外なまでに原典に忠実な訳文なのです。ただし大きな相違がひとつ。訳文では、この「道行き」の部分だけが散文ではなく、詩のような行分けになっていること。
そのため、原典の「これかとよ」が細かい活字組みのテキストに埋もれてしまっていたのに対して、訳文では、随所にあらわれる「ここですか」の繰りかえしが、めざましい効果を発揮する。もちろん「ここですか」という訳語もすばらしい。でもそれだけではなく、的確な行分けによって、この訳語がくっきりと目立つものになっている。
――なるほど、これは研究者にはむりだ。詩人だからこそできる芸当だろう。
と、ほとほと感心させられた。
しかも、どうやらこれは詩人の感覚だけに頼ってそうしたわけではないようなのです。さきにふれた「わたしの説経節」というエッセイによると、「惚れ抜いた」のが運のつき、池澤同様に伊藤比呂美も先人たちの手を借りて、テキストをしつこく読み込んだらしい。したがって感覚と、それに加うるに思わず知らずのめりこんでしまった猛勉強ですな。その結果、「これかとよ」にかぎらず、説経節では同一の決まり文句が繰りかえし使いまわされていることがわかった。
たとえば、語りが感情的にもりあがるときの、「あらいたはしや」「流涕焦がれ嘆きたまふ」とか、移動するさいの「犬の鈴、鷹の鈴、轡の音がざざめいて」「お急ぎあればほどもなく」とか。「これとかや」や、もちろん「えいさらえい」もその一種――。
ようするに、パクリやなぞりの行為が平然とおこなわれているのだが、「しかしまた、そこがいい」と伊藤はいう。
……同じじゃんと心でつっこみながら、くり返していくうちに、声が、ほかの声と合流して、大きな流れになって、とうとう声の文化という大海に流れ込んでいくような気がするんです。
この〔同一のフレーズや〕ブロック〔の反復〕があるからこそ、語る方もつるつると語っていける。組み合わせればいいからです。独創性など、あまり必要としません。聴く方も安心して身を任す。ブロックごとに既知の感情を思い出して、いっしょに悲しみ、いっしょに歩き、やがて、いっしょに立ち直ることができる。
これはあとでまた触れることになると思うが、じつは私にも以前、おなじ東洋文庫版『説経節』をけっこう熱心に読んでいた時期があった。
ただし、いまにして思うと、読むには読んだのだが、この延々とつづく「道行き」の箇所などは、さして気にもせず飛ばし読みしてしまったような気がする。なにしろストーリーには直接かかわらない、いってみれば、おなじようなフレーズの単調な「組み合わせ」ですからね。それを活字で組まれた散文で読んでも、私たち現代人の脳には眠たくなるほど退屈としか感じられないのだ。
しかし本来は、この退屈な「道行き」こそが「語りもの」としての説経節のいわばキモだったのではないか。と、そう伊藤は考えた。いや、そのていどの認識は私にだってあったのです。しかし頭ではわかっていても、からだがついていかない。だからこその眠たくなるほどの退屈――。
そこを伊藤比呂美は現代詩人の手のうちにある「行分け」のワザによって突破しようとこころみ、それに成功した。活字組みの原典ではあれほど退屈だった「道行き」が、ひいては説経節という中世の「語りもの」の底ふかくに埋もれていた力が、伊藤の現代語訳によって、堀田善衞のいう「読んでいると肉体的なまでに快くなる」ものとして、みごとに掘り起こされたのです。
―――――――――
堀田善衞『誰も不思議に思わない』筑摩書房、1989年
堀田善衞『故園風来抄』集英社、1999年
加藤周一『日本文学史序説』上下 筑摩書房、1975年、1980年→ちくま学芸文庫、1999年
中村真一郎『王朝の文学』新潮叢書、1957年
池澤夏樹=個人編集『日本文学全集』河出書房新社、2014年~
伊藤比呂美訳『新訳 説経節』平凡社、2015年
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








