小説であれ随筆であれ、新しい本がでたと知ると、すぐ本屋に向かう。そんな作家が私にもわずかながらいて、そのひとりが山田稔なのです。
家にもどって、ときには家に着くまえの路上で、買ったばかりの本を読みはじめる。いつものことながら、山田さんの文章を読むのはたのしい。そしてそのたのしさには、これまたいつも、かすかな「おそれ」のごときものがまじっている。そうか、もしかしたら私の場合、その一抹のおそれをもふくめてのたのしみなのかもしれないな。
というのも、山田さんはたいへんな手紙好きなので、その文章にも、かならずといいたくなるほどしばしば、古い知人や見知らぬ人との手紙のやりとりがでてくる。たとえば「久保文さんの死を知ったのは、今年(2002年・津野注)の四月二十四日付朝日新聞夕刊によってであった。享年九十」とはじまる「八十二歳のガールフレンド」という文章でいうと。
――山田稔はこの人の名を17年まえ、スウェーデンの神経科医アクセル・ムンテの手記『サン・ミケーレ物語』の翻訳者として知った。さっそく出版社あてに感想の手紙を送ると、ほどなく「なつかしい京都の下鴨からのお手紙(略)ありがたく拝見致しました」という「丁重な封書の返事」がとどいた。
なつかしいというのは、久保さんも若いころ10年ほど京都で暮らし、いつも犬をつれて下鴨神社のあたりを散歩していたから。しかも、山田稔が京大仏文科でまなんでいた当時の主任教授・伊吹武彦がまだ三高の先生だったころ、フランス語の個人教授をうけたことがあるらしい。それやこれやで、この19歳年上の女性と「面識もないままに一方的に『友達』になってしまった」のだという。
そののち2年半ほどの文通をへて上京した山田は、彼女が住む目白の酒場ではじめて久保さんと会う。「ほっそりした体つきの、鼻すじのすっと通った顔に眼鏡をかけ、ベレー帽をかぶった、いかにもモダンな感じの美しい老婦人」で、「ちょうど喜寿をむかえたばかり」とはとうてい思えない。なかんずく「飲みっぷりのみごとさ」に感嘆させられた。
ただし初対面のあとは2、3回、京都の酒場で飲んだことがあるだけ。そんな交際がゆっくりつづくなかで、彼女には、アジア・アフリカ作家会議にかかわり、「若い人たち」と日韓の戦後文学を語る会をやるというような、いまふうにいえば「リベラル左派」の活動家的な一面があることもわかってくる。
そして「たしか一九九三年のおわりごろ、出町柳の近くの小さな酒場に案内したことがある」と山田さんのいわく――九時すぎにその店をでて、並んで歩いていたら、久保さんが「ごく自然に私の腕を取り、笑いをふくんだ声で言った」
「東京の若い人たちに言ってやってるのよ。私には京都にすてきなボーイフレンドがいるって」
大通りに出て、タクシーを拾おうと立ち止まった。
「バスで帰るわ、タクシーなどめったに乗ったことがないから」
そう言うのを、寒いし、バスは何時来るかわからないからと説得した。
タクシーが来た。
「どうか気を付けてお帰り下さい」
そう気遣う私にむかって、八十二歳のガールフレンドは、
「人生はこれからよ」
そう言い残すと、車中に消えた。
それが私の見た久保さんの最後の姿だった。

この短篇「八十二歳のガールフレンド」をおさめる同題の作品集には、手紙が大きな役割をはたす文章がほかにもいくつか見つかる。なかで、久保さんとおなじ「高齢の女性」との手紙をつうじての交際という点では、「シモーヌさん」という文章がことに印象ぶかい。
フランスのセリイという町に、短篇集『小さな町で』(いまは山田稔訳がみすず書房からでている)の作者、シャルル=ルイ・フィリップの記念館がある。
1994年、かれはこの記念館で偶然、シモーヌ・レイノーという老女と出会った。町のリセ(高等学校)の元教師で、巷のフィリップ研究者でもある彼女とのあいだで、いつしか、したしい手紙のやりとりがはじまり、6年後、2000年の年賀状でそれが終わる。あいだで会ったのは99年春にセリイで開かれたシンポジウムに彼女の招きで出席したことが1回あるだけ。したがって久保さんと同様、実際に会った回数はごくわずか。あとは文通のみのつきあい。
手紙のやりとりという形での対話、それはこころが繋がっている証拠だ。こころが繋がっている以上、再会の希望は残されていると思いたかった。相手もまた、同じような思いでペンを走らせているのではなかろうか。
そう山田稔は「シモーヌさん」にしるしている。さもあらん。だからこそ私は、かれらのおだやかなつきあいのスタイルにこころひかれ、気持よくそれを読みすすめることができるのだろう。それはほかの本、『ああ、そうかね』や『リサ伯母さん』や『マビヨン通りの店』に収録された多くの文章の場合もおなじ。
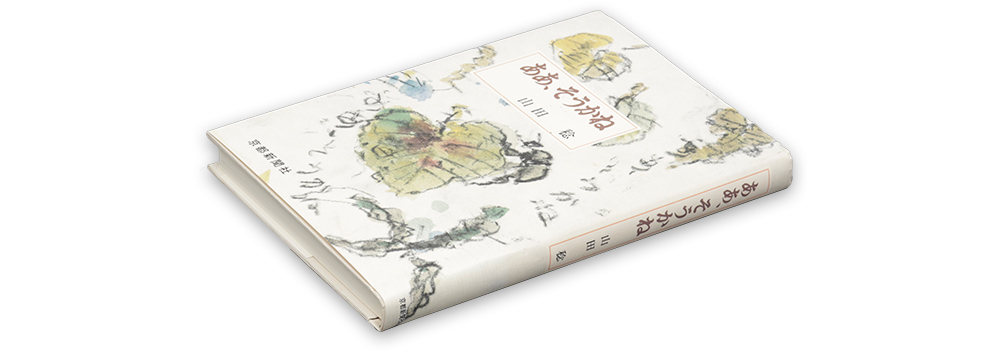
遠くはなれた土地で、それぞれにつよい自立心をもって生きる人びとが織りなす時間がしずかに流れる――。
と、そこまではいいのですよ。ところが山田さんの文章では往々にして、それらのおだやかな語りに、ふいにきびしい口調で、こんな一節がドカンと投げこまれる。
いささかユーウツなのは、最近すこしずつではあるがワープロで書いた(?)手紙(私信)がとどくようになったことである。ダイレクト・メールのたぐいにまじって、なんとも味気なく、手紙好きの私を落胆させることはなはだしい。機会あるごとに『ワープロの手紙は読まずに捨てることにしているからね』と警告を発しているが、冗談ととられるらしい。(「時代おくれ」『ああ、そうかね』)
個人的には、これがこまるのだ。なにしろ私は手紙を書くのがことのほか苦手で、ワープロや電子メールの力を借りて、辛うじてひとなみの「手紙のつきあい」をなりたたせているのだから。書くだけでなく読むのも苦手。おそらく山田さんやその手紙友だちの方々からは非人間的と思われてしまうであろう、まぎれもなく私はそちらの側に属する者なのである。
なのに、なぜこうも山田さんの手紙語りが好きなのかしらん。
たぶんそんな非人間だからこそ、じぶんにはうまくこなせない人間味ゆたかな「手紙のやりとり」に、ちょっと憧れているのだろうな。そしてだからこそ、こうしたニベもない記述に一瞬ギクリとし、あの人は頑固だから、いつどこでこうした一撃をくらうかもしれんぞと、たのしみながらも、かすかな「おそれ」をいだいて氏の文章を読みすすめることになるのだろう。
いやはや、それにしても「ワープロの手紙は読まずに捨てることにしている」とはね。これじゃあ、作者にファンレターをだすこともできないじゃないの。
*
しかも手紙だけではない。これと同様のおそれを、ときに山田稔が映画とのつきあいについて書いた文章にも抱かされてしまう。たとえば1992年にでた『シネマのある風景』という本のこんな一節――。
映画はすべて映画館でみる。家を出て、映画をみて、一杯やって帰宅するまでが私の「映画」である。ビデオは映画のうちに入れない。この態度を当分は頑迷にまもっていたい。(「破局の予感」)
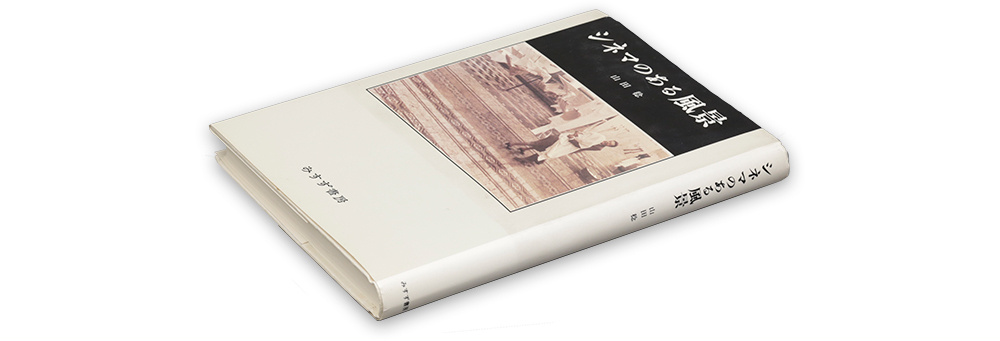
映画は映画館で見る。テレビ画面で見る映画など私は映画とみとめない。とつぜんの断定のはげしさは、手紙の場合とまったくおなじ。
ところが私の映画とのつきあいはというと、借りたり買ったりしたビデオやDVDを居間のテレビか、ここしばらくは主として書斎のパソコンで見ているのです。もう20年以上まえから、そんな見方が日常の習慣になった。
映画をもっとも集中して見たのは、高校時代から大学卒業後10年くらいまで。つまり1950年代なかばから70年代のはじめにかけて。当時は2本立てや3本立てがふつうだったから、年に150本ていどは平気で見ていたような気がする。もちろんどれも町の映画館で。そうするしかない時代だったのだから、これはとうぜん。
シネコンはもとより、いまの映画館は、そのほとんどが大きなビルの中にある。その上層階か地下。いきおい映画を見るにもエレベーターやエスカレーターを利用することになる。
でもむかしの映画館はビルの一部ではなく、たいていは、じかに地べたにせっした一戸建ての建物だった。おなじ一戸建てでも劇場や公会堂なら、入り口まで何段かの階段をもうけるのがつねだが、通常の映画館は道路から地つづき。ぶらぶら歩いて行って、そのまますっと入ることができる。私の住んでいたあたりでいえば、高田馬場の早稲田松竹、目白の白鳥座、池袋人世坐、板橋弁天坐など、みんなそう。
その地べたにたつ中小の映画館が、ある時期から、つぎつぎにすがたを消していった。
60年代から70年代にかけて映画の観客が激減し、80年代にはいるや、旧来の大手映画会社の伝統的商法(スタジオ・システム)までがあっけなく崩壊してしまう。自社のスタジオで専属監督が専属俳優をつかってつくった映画を日本各地の専属館で上映する。それがこのシステムの眼目だったから、その崩壊をきっかけに町場の専属館やその他の映画館が消えてゆくのは、いわば必然のなりゆきだったのである。
そして消えゆく映画館にかわってビデオのレンタルショップが登場する。それが80年代の終わりちかく。
そのころ住んでいた荻窪の書店にもレンタルビデオのコーナーができた。そこの棚に高校時代にいちど見たきり、とうとう再見できずにいたエットーレ・ジャンニーニ監督の特異なミュージカル大作『ナポリの饗宴』のビデオを発見し、そのよろこびをきっかけに自宅でビデオを見る習慣が身についた。
つまりは映画館からビデオ中心への転向です。でも山田稔はちがう。この種の裏切りをかれはよしとしなかった。
映画にかかわる山田さんの文章では、エットーレ・スコラ監督の『特別な一日』にまつわる何層もの記憶をつづったエッセイが好き。いまはおなじ「特別な一日」というタイトルで、やはり同題の文集におさめられている。

1938年、ファシズム政権下のローマをナチス総統アドルフ・ヒトラーがおとずれる。その歓迎式典の日、住民たちが動員されて空っぽになった巨大団地に、スピーカーからファシストの歌「ジョヴィネッツア」が大音量で鳴りひびく。そんななかで家事に疲れた主婦(ソフィア・ローレン)が、やはり居のこっていた独身の中年男(マルチェロ・マストロヤンニ)のやさしさに惹かれ「性的な関係」をもつ。男はじつはナチスの排斥する同性愛者で、その日のうちに逮捕連行されてしまう。主婦にとっても、男にとっても、そしてイタリアにとっても「特別な一日」がこうして終わった――。
1977年に公開されたこの映画を、おなじ年に山田さんは留学先のパリのクリュニー・エコールという映画館で見た。
見おわった後、カルチェ・ラタンのキャフェに腰をおろし、何時までも耳の奥に鳴りひびくナチス党歌やファシストの歌をつい口ずさみそうになりながら、一言ではいいあらわせぬ「特別な」感動をなにか辛い思いとともに反芻していたことを、いまもはっきりと憶えている。
ところがこの傑作が2年間の留学から帰国したのちも、なぜか日本ではいつまでたっても公開されないのだ。ようやく大阪のサンケイ・ホールで上映されたのが8年後の1985年3月。しかしこのときは見る機会を失し、「ふたたびみられまいと諦めていた映画」が、思いがけず同年5月に京都で上映されることになった。
私はなにか因縁のようなものを感じた。どうかもう一度みてくれ、と映画の方から誘いをうけているような不思議な気持であった。二度みたら失望するかもしれぬといったためらいなど忘れ、私は映画にはもったいないほど美しく晴れた休日の午後、四条烏丸のシルクホールへ足を運んだ。(略)
帰りのバスの中で、空にはあかあかと陽の残っているのに早や夕暮れの冷気の感じられる風を頬にうけながら、私は耳の奥でまた鳴りはじめた「ジョヴィネッツア」の旋律に聴き入っていた。いや、胸のうちで私は歌っていた。(略)
懐かしさが胸からあふれ出た。懐かしいのはこの映画なのか、初めてそれをみたパリなのか、それとも少年時代におぼえたこの曲なのか、それは自分にもよくわからなかった。私はこの映画を二度みたことを悔いるどころか、大いに満足していた。たしかにこの日は私にとっても「特別な一日」であった。
何層もの記憶のいちばん底にあるのが「ジョヴィネッツア」の旋律――と、そうきいても、8歳年下の私にはまったくなんの感慨もないのだが、山田さんはそうではない。
1937年、日独伊三国防共協定調印。そのころ7歳か8歳だった山田少年は、自宅にあった「ジョヴィネッツア」のレコードを盤がすり切れるほど聞き、リフレーンの「ジョヴィネッツア、ジョヴィネッツア」という箇所を、繰りかえし歌っていた。「ジョヴィネッツア」はイタリア語で「若さ」や「青春」を意味し、「ファシズムにまつわるいまわしい記憶の数々がなければ、躍動する若さにみちあふれ、軽快なリズム」をもつ曲だった。
そして40年後、パリの映画館でふいにこの曲にせっし、おさないころ、じぶんがおなじ歌を歌っていたことを思いだす。「ジョヴィネッツア」が大音響で鳴りひびくなか、嬉々としてヒトラー歓迎式典に向かう団地の少年たち。まちがいない、かれらは私なのだ――。
*
山田さんは、パリの映画館で見た映画を8年後に大阪で見逃し、そのあと、ようやく京都の映画館で、ほとんど奇跡的に見なおすことができた。
ことほどさように、ビデオが広く普及するまでは、いったん見逃した映画を見たり、いちど見て感動した映画を見なおしたりするのは、けっしてやさしいことではなかったのである。なにしろ東京そだちの私ですら、高校生のとき感激して見た『ナポリの饗宴』をもういちど見るには、ビデオ時代の到来を待つしかなかったのだから。
インターネットはもとより、大阪の『プレイガイドジャーナル』(創刊は71年)や東京の『ぴあ』(同72年)にはじまる地域別の情報誌もない。そんな時代だったので、場末の三番館や名画座の情報は、新聞の上映案内や大きな駅の構内に設置されていたポスター壁、あとは映画好きの友人たちの「おい、例の映画、あそこでやってるぞ」といった報告に頼るしかなかった。
そうして知った上映館にバスや電車をのりついでたどりつく。いきおい映画と町と映画館がひとかたまりになって頭に焼きつくことになる。山田さんが『特別な一日』を語る文章で、ごく当たり前のように、町と映画館の名を1つ1つ明記しているのもそのせい。
ようするに映画館時代の映画とのつきあいは「一期一会」が原則だったのである。そこには、ここで見のがしたらもうあとはない、という緊張がたえずつきまとっていた。
そして、その緊張感に後押しされて、映画的な記憶力ともいうべきものが、いやおうなしに強化される。淀川長治、植草甚一、小林信彦、和田誠といった人たちの、映画の細部についての異様なまでになまなましい記憶力――かれらにつづく蓮實重彥や川本三郎や瀬戸川猛資たちをもふくめて、あれはすべてビデオやDVDや YouTube 以前の、町の映画館で鍛えたものだったのです。
そしてもうひとつ、映画館で映画を見るという行為(上映館をさがす、バスや電車に乗る、歩く、たどりつく、見る、あとで軽く一杯)には、山田稔のいう「自由の感覚」に裏打ちされた特有の孤独感がつきまとう。そうした感覚を、どうやらかれは1970年代に留学先のフランスでしっかり身につけたらしい。すなわち、日本のような「同質社会」とはことなり、あくまでも個人を中心に成り立つ「異質社会」のフランスでは――
男も女も、子供たちですら孤独を背負い、自立をねがいつつ他者との結びつきを失うまいとして生きている。私がパリの映画館のスクリーンでくり返しみたのはそのような孤独と連帯の間にゆれる人間のドラマだった。その感動を通して自立した個人像が私の胸のうちで美化され、それへの憧れがふくらんでいく。そしてその憧れ、あるいは郷愁をいだいて今日も映画館の暗がりへもどって行く。(「パリ――シネマのように」)
1989年から92年にかけて、山田稔は朝日新聞大阪版の夕刊に、月2回の日録ふう映画エッセイを連載した。ここに引用したのは、連載終了後、それを1冊にまとめた本(前記『シネマのある風景』)におさめられた文章の1節――。
この連載を依頼され、最初のうち、山田さんは「映画については公の場では語るまいと決めていた。映画は自分だけのためのささやかな楽しみに残しておきたい」とことわりつづけたらしい。でも、たびかさなる熱心な依頼に、あとがきによると、ちょっとした「気のゆるみ」から、「身辺雑記のなかにちょっと映画がでてくる程度のもの」で、「最近、映画館でみたマイナーな映画(洋画)しか取り上げない」という条件をつけて引き受けることになったのだという。
つまるところ、映画は自分ひとりで映画館で見る――ひとりの「孤独」な人間が家をでて、映画を見たあと、近所の酒場やビヤホールで、たったいまスクリーンで出会ったばかりの、おなじように孤独な未知の人びととの「連帯」の味を反芻しながら、黙々と一杯やって帰宅する。そのプロセスのすべてが私にとっての「映画」なのだ。私はあくまでもその線でいくぞ。これはそういう宣言だったのだろう。
そしてこの宣言どおり、山田さんは、『モンテネグロ』『数に溺れて』『つながれたヒバリ』『旅する女』『父の恋人』『追憶の旅』といった「マイナーな映画(洋画)」を、京都のルネサンスホール、朝日シネマ、コマ・ゴールド、みなみ会館、大阪ではシネマ・ヴェリテ、近鉄小劇場、テアトル梅田、国名小劇、ホクテンザなどの、町中の小さな映画館(いまでいうミニシアター)で見てまわり、その体験を1篇の「身辺雑記」にまとめて新聞連載をつづけた。
この締めの一杯をもふくめて、たしかに映画館時代の「映画を見る」はそういう一連の行為をさしていたよな、と私も思う。そして、もしそれが「映画を見る」ことだとしたら、「ビデオは映画のうちに入れない」と山田さんがいうのは、しごく当然のことなのである。
ただし、そのような意味での山田さんの「映画」をささえていた映画館は、いまはほとんど消えてしまった。インターネットでしらべたら、これらのうち現存するのは国名小劇とテアトル梅田、京都みなみ会館の3館のみ(編集部注:京都みなみ会館は2018年3月末に一時閉館予定)。のこりのほとんどは前世紀中に消えていったらしい。山田さんが『シネマのある風景』の中で早くもこうしるしていたように。
京都。四条大宮のコマ・ゴールドが惜しいことに九月末で閉館になった。そのぶんだけ大阪へ出かける回数がふえるとすれば、これはしんどい。そんな目までして映画をみる必要があるのか。気ままにみて、後で軽く一杯、それがわが映画道ではなかったか。(「善悪二重唱」)
それに、山田さんの惜しむコマ・ゴールドやその他の小映画館にしても、かれがこの連載をしていた1990年前後という時期には、その多くがすでに一戸建てではなく、大小のビルの中におさまっていた。
こうした変わりゆく環境のもとで、映画館時代に身につけた、いまや古びつつあるかにみえる映画の見方を意地でも坦々とつらぬいてみせる。つよい自立心ゆえの「孤独」を背負ったまま「他者との結びつきを失うまい」と映画館にかよいつづける人間の意地。そういってもいい。
ワープロ書きの手紙や電子メールをこばみ、葉書であれ封書であれ、手紙はかならずペンを手にして紙に書く。そうでないと、遠くはなれた土地で自立心をもって孤独に生きる人たちと「こころが繋がらない」――これもおなじ意地のあらわれなのだろう。
でも私は意気地なしの裏切り者なので、もはやペンで手紙を書くようなことはしない。映画もおなじ。仕事部屋の灯りを消し、あろうことかデスク上のパソコンで見ている。
パソコンで見る映画にも電子メールにも、それでしか得られない利点がすくなからずある。
しかし、そのことで私が味わう索漠たる孤独には、ざんねんながら、山田さんの「手紙を書く」や「映画を見る」にあるような、孤独な「私」と遠方にいる「他者」とのおだやかなつながりを生む力はない。おそらくはその弱みがあるからこそ、山田稔の文章を一抹のおそれとともにたのしむことができるのだろう。そう、82歳をとうにすぎてもなお、「マイナーな映画(洋画)」を見るべく、京阪のミニシアターめざしてゆっくり歩く山田さんのすがたを想像しながらね。
―――――――――
山田稔『八十二歳のガールフレンド』(編集工房ノア、2005年)
山田稔『シネマのある風景』(みすず書房、1992年)
山田稔『ああ、そうかね』(京都新聞社、1996年)
山田稔『特別な一日』(朝日新聞社、1986年→『特別な一日――読書漫録』平凡社ライブラリー、1999年、編集工房ノア、2010年)
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








