岡山吉備高原で新しい町の建設がはじまった。そこに書斎と書庫を中心とする新居をもうけて、まず3万冊ある蔵書のうちの1万冊を移し、落ちついたら生活の拠点も、いまの横浜からまるごとそっちに移すつもりなんですよ――。
そんな話を紀田順一郎氏からきいたのが1990年代のなかばすぎだったろうか。
紀田さんは私の3歳上だから、当時はまだ60歳をすぎたばかり。質量ともに私などとはケタちがいの蔵書をかかえ、いまはいいだろうが、このさきたいへんなことになるんじゃないかな、と心配しないでもなかったので、そうきいて、なんとなくホッとしたおぼえがある。
ところが、この夏にでた『蔵書一代』という新著を読んで、がくぜんとした。あの吉備高原都市計画がバブル崩壊にはじまる不況で中断され、予定されていた交通面でのサービスもととのわないままに、移転14年後の2011年、新しい家を売り、やむなく全面撤去せざるをえなくなってしまったというのだから。

――あれあれ、そんな事態になっていたんですか。知らなかったな。
でも、ことはそれだけではすまなかったのである。
吉備高原撤退から4年のち、80歳になった紀田さんは、じぶんと妻のからだのおとろえ、自宅の老朽化、それに経済上の理由などもあって、12畳の書斎と10書庫を埋めていた3万冊の蔵書のすべてを売却し、シニア向けマンションに引っ越すという、さらにすさまじい決断をしいられる。つまりは、みずからの人生をかけた蔵書とのとわの別れ――。
ただし、蔵書を一挙にゼロにすると、精神状態に自信が持てない。いくら老い先短いとはいえ、今日明日にもお陀仏となるわけではあるまい。人生そう簡単に線引きできないところが老後の悩みで、解決策としては別れるに忍びない本を約六百冊、新居に連れていくしかなかった。たったこれだけを六〇年代に流行したスライド式書架二台に収め、新居の狭い二部屋に運びこもうという算段である。案のじょう妻からは「床が抜けたら、マンションの資産価値が下がりますよ」などと猛反対を受けたが、ここが土俵際の凌ぎどころと、もっともらしく構造式や重量計算式などを並べ、かろうじて説得に成功した。
紀田さんの著書で私が最初に読んだのは、おそらく1979年に新潮文庫からでた『日本の書物』だったと思う。もともとは『週刊新潮』のコラム連載で、完結後に単行本として刊行されたものの文庫化。『古事記』や『竹取物語』にはじまり『東海道五十三次』や『航米日録』まで、82点(連載では80点)の日本の古典が、いかにもコラムらしい達者な文章で紹介されていた。
それはそれで楽しく読んだが、なかでも最古の写本や印刷本のありかをふくめ、1点1点の書誌データが簡潔にしるされているのに感心した。『竹取物語』でいえば28.1×20.6センチと、きちんと数字でしめされていたこと。あとで知った話によると、そのつど紀田さんが所蔵元の寺社や図書館や資料館に足をはこび、じぶんで物差しを当てて計るか、その余裕がないときは手紙や電話で依頼して計ってもらうかしたらしい。
そんな面倒なことを、こともあろうに週刊誌のコラムでやってのけるとはね。おまけに80回もだぜ。私ごときズボラ人間としては、なんでそこまでやるのさと、あっけにとられるほかなかったのです。
ことほどさように、紀田さんは「しらべごとの魔」ともいうべき人なので、著作にも、書物論や出版史を軸として、大学時代にはじまる幻想怪奇文学研究から、近代日本の庶民文化史やデジタル文化論まで、おびただしい量の資料を必要とするものが多い。
資料のうちには、さまざまな辞書や事典、年鑑、地図、年表、資料集、白書、便覧、書誌など、図書館でいうところの参考図書(リファレンス・ブック)のたぐいもふくまれる。大学教師ならじぶんが属する大学の図書館にたよることもできるだろう。でも紀田さんはそうじゃなかったからね。みずからいうインディペンデントな「研究者的蔵書家」として、その種の本も、ひとりで営々と買いそろえてゆくしか手がなかった。
で、買った本のうち不要になったものを売り、その金でまた本を買う。その繰りかえしによってかたちづくられた蔵書が3万冊。そのいわば「最後の蔵書」を、こんどは一挙に6百冊まで減らさなければならないというのだから、たまったものではない。
しかも移転まで、わずか3か月。あれこれ逡巡したすえに、これは古書店行きときめた書棚に、片っ端から荷造り用テープをバッテン状に貼り、訣別のしるしとすることにした。その「×」マークがまたたくまに増えてゆく。「もはやヤケであった」と紀田さん――。
それでも幻想怪奇文学関連の1千冊ほどの洋書をどうするかの方針が立たず、ギリギリまで迷った。なにしろ「半生におよぶこだわりのテーマ」なのだ。できることなら、だれもが自由に利用できるように、なんらかの施設にまとめて保存してもらいたい。
しかし1千冊の洋書ともなると図書館も引き取ってくれない。この十数年、不況下の「聖域なき行政改革」によって予算を削られつづけてきた公立図書館には、たとえ無償で寄贈されても、それを保存するスペースがないし、整理や維持にあたるスタッフも確保できない。事情は大学図書館や各地の文学館もおなじ。ということは2006年から6年間、神奈川近代文学館の館長をつとめた紀田さんが、だれよりもよく知っていた。
――このコレクションを中心に資料館をつくりましょうよ。
そういってくれる人もいたけど、急場の役には立ちそうにない。頼みの綱の古いつきあいの大手洋古書店の社長も、連絡をとると一週間まえに亡くなっていた。かくして「ついに命運が尽きた」――紀田さんは多ジャンルにまたがる膨大な蔵書のほぼすべてを、「最寄りの大型〔古〕書店」に一括してゆだねる決心をするしかなかったのである。
そして雨もよいの師走の某日、アルバイトの運び手たちがやってきて、1日がかりで蔵書にビニール紐がかけられ、翌日、それが2台の4トントラックに積み込まれた。からっぽの書庫に立ちつくす紀田さんの頭を、「書籍なき家は主なき家のごとし」というキケロのことばがよぎる。
いまにも降りそうな空のもと、古い分譲地の一本道をトラックが遠ざかっていく。私は、傍らに立っている妻が、胸元で小さく手を振っているのに気がついた。
その瞬間、私は足下が何か柔らかな、マシュマロのような頼りないものに変貌したような錯覚を覚え、気がついた時には、アスファルトの路上に俯せに倒れ込んでいた。
「どうなさったんですか? 大丈夫ですか?」居合わせた近所の主婦が、大声で叫びながら駆け寄ってくる。
「いや、何でもありません。ただ、ちょっと転んだだけなんです」私はあわてて立ち上がろうとしたが、不様にも再び転倒してしまった。後で聞くと、グニャリと倒れたそうである。
こうして「ろくすっぽ家具もなく、五十年以上本のほか何ひとつ買い揃えることのなかった家」――紀田さんの半生をささげた私設図書館があとかたもなく消滅した。そのようすを紀田さんは、おそらくはこれまですくなからぬ犠牲をしいられたであろう夫人とともに、ただ呆然とながめるしかなかったのです。
*
こう書くと、たぶん本好きの方々には、あまりにも辛すぎる惨事としか感じられないだろう。じじつ私だってそう感じたのだから。
しかし、その一方で、
――すごいね、紀田さん。みごとにやってのけましたね。
そういって氏の壮挙を祝賀したい気もちも、いくぶんか、いや、もしかしたら、よりつよくあったような気がする。
――ははァ。でもなぜ?
――いや、じつは私にも、しばらくまえに蔵書の大幅削減をこころみて、あえなく失敗した苦い体験があったのですよ。
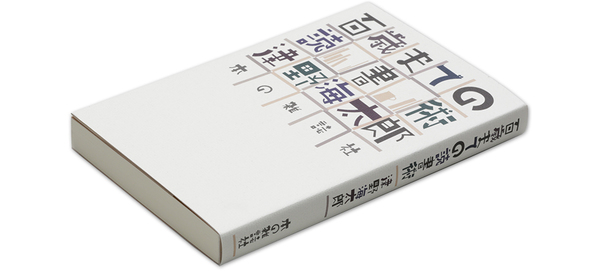
しばらくまえとは2008年。この年、満70歳になった私は、それを機に、長いあいだつづけてきた編集者と大学教師の仕事をやめた。出版であろうと大学であろうと、他人といっしょにやる仕事はもういいだろうと、心底、そう思ったので。そして、いったんそう決めると、手持ちの蔵書がやけに重苦しく感じられてきた。
蔵書といっても、私の場合、紀田さんのような堂々たるものではない。仕事柄、新刊古本をひっくるめて、本はひとなみ以上に買っていた。ただし50代の前半まではひとり暮らしで、たえず引っ越しを繰りかえしていたから、そのつど、かなりの量の本の処分を余儀なくされた。狭い部屋からまた別の狭い部屋へ。したがって蔵書の限度は3千冊から多くて4千冊ていど。それが結婚後、家を建てて収容スペースができたのをきっかけに徐々に増えはじめ、このころは文庫や新書をのぞいて、7千冊ほどになっていた。
――じぶんがおとろえ切るまでに、なんとかこれを1千冊に減らしておきたい。
そう考えるようになった理由のひとつが、このまま死んだら親しい連中にかならず厄介をかけるぞ、と思ったことだった。
これまで私は編集者や小さな大学図書館の館長として、物書きや教師やジャーナリストなどの職業インテリ諸氏の没後、のこされた蔵書をどう処分するかで家族や身ぢかな人びとが苦労するさまを、いやというほど見てきた。そのせいで、できることなら、じぶんの死後にああした状態を引き起こすのは避けたい――そんな気もちがことのほかつよくなっていたのです。
しかし、この殊勝なもくろみは、半年かけて1千5百冊ほどを減らしたあたりで、あえなく挫折した。その顛末について、2015年に本の雑誌社からだした『百歳までの読書術』という本でざっと触れ、それを紀田さんに送ったら、折り返し「身につまされました」という意味のメールがとどいた。
――なるほど、いまわかりましたよ。あれがちょうど氏が全蔵書の売却を決意した時期に当たっていたのだな。
紀田さんや私にかぎらず、昨今、おおくの職業的知識人、ないしはそれに準ずる人びとの身に、規模の大小を問わず、こうしたしんどい事態が頻繁に生じているらしい。西牟田靖の『本で床は抜けるのか』とか岡崎武志の『蔵書の苦しみ』といった、あけすけなタイトルの本も目につくしね。どうやら私たちは、おのれの限界をわすれて、あまりにも大量の本を抱えすぎているのかもしれないぞ。

私はともかく、いまの日本には、紀田さんクラスかそれ以上の蔵書家だって何十人、いや、おそらくは何百人もいるだろう。その代表が「この十年ほどの間に物故した著述家や知的活動家の蔵書数は、戦前知識人の規模をはるかに超える」と紀田さんが『蔵書一代』で列挙している高名な「物故した著述家」の方々。すなわち、井上ひさし(想定される所蔵冊数は14万冊)、谷沢永一(13万冊)、草森紳一(6万5千冊)、山口昌男(冊数不明、もはや本人もわからない)、渡部昇一(15万冊)といった人たち――。
このリストにせっして、ああ、やっぱりね、と思った。1929年生まれの谷沢から38年生まれの草森まで、その全員が、紀田さんもふくめて、おなじ1940年代に幼少年期をすごしているのだ。
明治の文明開化以降、とくに20世紀にはいって急上昇したこの国の年間出版点数が、1935年に3万点をこえる。そのいきおいが戦争の進行につれて逆流しはじめ、大日本帝国敗戦の1945年には658点にまで減ってしまった。かたい本とやわらかい本、おとなの本と子どもの本、そのすべてをひっくるめての658点ですよ。いまは年間約8万点だから、くらべればゼロにひとしい。
この出版のゼロ年に草森紳一は小学校(当時でいう国民学校)にはいった。おなじ年、紀田さんは4年、井上ひさしは5年、山口昌男は中学2年。つまり、この世代の者は、食うものだけでなく読むものもない、本への底なしの飢えとともに育つほかなかったのである。私は草森さんと同年だから、この飢えの深さを経験によって知っている。「やっぱりね」というのもだからこそ。
その後、戦後復興によって出版産業がよみがえり、公共図書館サービスが徐々に定着していっても、かれら、いや私たちの飢えの記憶が薄らぐことはなかった。
そしてその間に、参考図書や専門別の基本図書を中心として、必要と思われる本を図書館や他人の蔵書にたよらず、じぶんの所有物として手元にそろえておく――そんな習性がしっかり身についてしまった。ほしい本をがつがつ掻きあつめ、ともに暮らす家族がなにをいおうと断固としてそれを保守しつづける。紀田さんや同世代の著述家諸氏だけでなく、いっぱんの知識人、身近な人でいえば私の中学や高校の先生方も、ひとしく、そうやってじぶんの蔵書をつくっていた。そんな書斎の記憶がいくつものこっている。
じつをいうと、私はつい最近まで、こうした過度の蔵書欲は時代や環境の別なく、本好きの人びとに共通するごく当たりまえの習性なのだろうと、なんのうたがいもなく思っていたのです。
でも、かならずしもそうではなかったのですな。
鴎外や漱石や露伴はもとより、三木清や和辻哲郞や林達夫のような昭和前半期の大インテリですら、当今の基準からするとわずかな蔵書しか持っていなかった。それは紀田さんが、いまの知識人の蔵書数は「戦前知識人の規模をはるかに超える」というとおり。
戦中戦後の本への飢えが欲望のバネとなり、そこに洋書輸入の自由化、全集ブーム、さらには高度経済成長下で激化した本の大量生産・大量消費の風潮がかさなって、通常の「規模をはるかに超える」個人蔵書の巨大化がすすんだ。私は勘ちがいしていたが、実際には、どうやらそういうことであったらしい。
そして前世紀が終わりに近づくにつれて、この種の飢えの記憶や、本へのやみくもな欲求が薄れ、日常の読書する習慣までがしだいにおとろえはじめた。資産家のコレクターや情報マニアをのぞくと、紀田さんのあげる「物故した著述家」たちのような伝説的蔵書家が、今後もつぎつぎに現れるとはとうてい思えない。そう考えると、紀田さんの私的図書館の崩壊のうしろに、こうした戦後日本型「本とのつきあい方」の終わりの光景がまざまざと見えてくるのです。
*
紀田さんの『蔵書一代』を読んで「あれ?」と思ったことがもうひとつ。紀田さんなら当然あるはずの本や出版の電子化への言及が、なぜかまったく見あたらないのだ。
いまとなっては想像もつかないだろうが、1980年代が終わるころまで、職業的な文系知識人のほとんどはコンピュータを頭から拒否していた。作家や詩人や学者はもちろん、編集者も図書館人もみんなそう。おおげさにいうと、「あんな化け物に手を触れると紙の本そだちの私の繊細な魂がけがれる」と、けっこう本気で考えていたのです。
そんななかで、紀田さんは例外的に70年代末から、ハードディスクも日本語ソフトもない原始状態のパソコンと本気でつきあうようになっていた。まだ英語しかつかえないハンパな道具で、まずこころみたのが手持ちの大量の本と、8ミリと16ミリの映画フィルムの管理だったのだそうな。
そして80年代にはいると、アップルの革新的パソコン「マッキントッシュ」が登場し、それをつかって、マルチメディア、ゲーム、教育、コンピュータ通信、さらには電子本と、さまざまな領域でコンピュータにとりくむ文系人のかずが、すこしずつ増えてくる。
のちにその人びとを6人まねいて、室謙二(そのころは日米間を頻繁に往復するデジタル文化ジャーナリストでした)と私をホストに、雑誌『思想の科学』で「コンピューター文化の使い方」という連載鼎談をやった。
そのひとりとして紀田さんにきてもらったのが1993年。おなじ年に私は『本とコンピューター』という本をだし、その2年後にようやくインターネットの一般利用がはじまる。そんな時期にはじめて私は紀田さんと出会ったのです。
その席で、紀田さんは本と出版の電子化について、こんなふうに語った。
……それと流通の問題ね。重い本をえっちらおっちら運ぶというかたちでの流通システムの不備が、戦後五〇年たってもまだ解決されていない。これを根本的に解決するには、読者からこの本がほしいという注文がきたら、出版社がそれを直接、読者のプリンターに送り込むというシステムをつくりあげるしかないんじゃないかな。本をとりまく環境は大きく変わっていかざるを得ないと思いますね。それが作品の内容的な革新にもつながっていく。
この時期になると日本でも、NECの「デジタルブック」や、ボイジャー・ジャパンの「エキスパンドブック」など、電子化した本をコンピュータ画面で読むこころみが、そろそろ現実化しはじめていた。
紀田さん自身も、ワープロソフト「一太郎」や、かな漢字変換ソフト「ATOK」のジャストシステムと組んで、『日本語大博物館・悪魔の文字と闘った人々』にはじまる一連の大著の刊行や、ワープロ辞書の精緻化を現場で主導するといった活動に積極的にかかわっていた。要するに当時の紀田順一郎は、研究と実践の両面で、「紙の本」と「電子の本」という二つの世界をつなぐキーパーソンの重要なひとりだったのです。
なのにその紀田さんが、80歳をすぎてだした大切な本で、電子本の現在について、ひとことも触れていない。私ならずとも、かなりのかずの人がふしぎに思ったにちがいない。
理由はいくつかあるにせよ、ひとつにはやはり、この間に紀田さんが直面した蔵書解体の危機にさいして、かつて期待したような本の電子化はまったくなんの力も発揮できなかった。そのことがいちばん大きかったのではなかろうか。
――あのとき私が呆然と立ちつくしたからっぽの書庫を、ただちに電子の本が埋める。そんなことがありえないことはわかっている。ただ、私がなじんできた旧来の「本とのつきあい方」にとって代わるはずの、新しい時代の「本とのつきあい方」のぼんやりした輪郭すら見えてこない。そんな状態で、いまの私に本の電子化について得々と語ることなどできるわけがないよ。
きっと紀田さんはそんなふうに思っていたのだろう。そう私が想像するのは、いくぶんかなりとも同じような思いが私にもあるからです。
紙の本にせよ、電子の本にせよ、このさき私たちの読書環境や習慣がどうなってゆくかを見とおすことは、だれにもできない。でも、できればこうなってほしい、と考えることはだれにでもできる。
ただし頭のなかで考えるのと、それをおおやけの場で書いたり語ったりするのとは、また別のことですからね。
紀田さんも私も、あるいは23年まえにでた『コンピューター文化の使い方』という鼎談集のほかの参加者たち――室謙二、佐伯胖(教育学)、萩野正昭(電子出版)、松岡裕典(コンピュータ通信)、浜野保樹(マルチメディア)、平野甲賀(グラフィックデザイン)、黒崎政男(哲学)も、どうなるか予想もつかない未来に向けて、それぞれの領域で「こうなってほしい」と元気に語っていた。
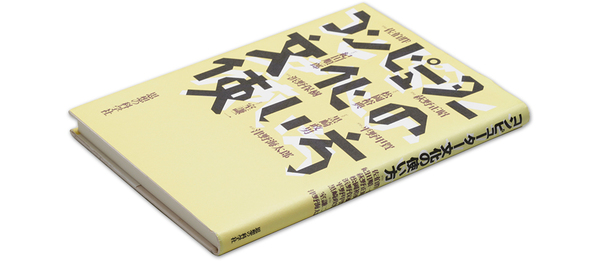
でも、いまになってわかる。私たちがあんなに元気よくしゃべることができたのは、そこに、いま私はこんなことをやっている、この先はこうやっていくつもりだ、という実践の裏付けがあったからなのだろう。
その裏付けなしに、つまり老いるにつれて実践の場から遠ざかった人間にとって、「こうなってほしい」と考えることはできても、それをおおやけの場で語るのはきわめてむずかしい。とりわけ読書というようなとことん個人的ないとなみの未来となると、そのつもりはなくとも、いつしかそこに自分勝手なグチやお説教がまじってしまう。いやだよ、そんなの。他人がどう思うかよりも、まずはそうなってしまうじぶんがいやだ。と、おそらくそんなふうに紀田さんは思っていたのではないかな。
といっても老人に実践の場がまったくないわけではないのです。その一例がほかならぬ蔵書の処分。ギリギリに追い込まれた場で、紀田さんは3万冊の蔵書をなんとかみごとに処分してのけた。80歳でも、やろうと思えばやれる。そのことを身をもって証明したといってもいい。その意味で、紀田さん、あなたは大量の蔵書に悩む人びとやその家族にとっての老英雄なのですよ。
そこで紀田さん(成功)や私(失敗)の体験にもとづく、あとからくる人たちへの教訓――。
第1に、蔵書の大幅削減はできるだけ早くはじめること。できれば体力・気力のある60代なかばまでに。
第2に、いったん決心したら、思いきって一気にやってしまうこと。そうすれば、蔵書ロスの悲哀からたちなおる余裕も生まれるだろう。
この2つのことだけは骨身にしみてわかった。では、ほどなく80歳になる私自身はどうする?
紀田さんの本にショックをうけ、そのぶんつよくなったらしい私は、このさき、もうこれ以上の大幅削減はしないと、はっきり腹をくくったのです。
失敗のあと、それでも1千5百冊ほどの蔵書をだらだらと処分したので、あと4千冊。したがって紀田さんの8分の1ていど。それくらいなら、まえもって知り合いの古本屋さんに頼んでおけばなんとかなりそう。おそらく半分ちかくは商品にならないだろうからゴミ処分。その手数料を引いて、のこった金で家族や親しい人たちが一夜、うまいものでも食ってくれたら、もういうことないよ。
―――――――――
紀田順一郎『蔵書一代』(松籟社、2017年)
紀田順一郎『日本の書物』(新潮社、1976年。新潮文庫、1979年)
津野海太郎『百歳までの読書術』(本の雑誌社、2015年)
室謙二・津野海太郎編『コンピューター文化の使い方』(思想の科学社、1994年)
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








