前号で、いまの私はまごうかたなき「落ち目の読書人」だとのべた。ひとつには「目のよわり」のせいだが、かならずしもそれだけではない、ほかにもさまざまな原因がある、うんぬん。今回はそのつづきです。
ほかにもある原因のうちで、おそらくもっとも大きいのが記憶力のおとろえでしょうな。読んだことを忘れる速度が、おそろしいテンポですすんでいること。私とかぎらず、おおくの老読書人がおなじように感じている。たとえば、この夏でたばかりの古井由吉の『楽天の日々』というエッセイ集のこんな一節――。

読んだ事をよく覚え、これを記憶の内に整え、機に臨んで適確に取り出す。これが読書家の資格であるとすれば、私は読書家の列に入らない。読んだところから、じつによく、忘れるのだ。本を閉じたとたんに、ということもある。後日になり、ふっと思い出しかけて、確めようとして本を開けば、たいていその箇所にかぎって見あたらない。
読んだ事に感嘆させられるほどに、後で綺麗に忘れる、という気味すらある。三読四読して長大息までしていたのに、机の前から立って十歩と行かぬうちに、はて、何のことだったか、と首をひねっている。(「招魂としての読書」)
古井さんは私のひとつ年上で、このエッセイを書いたのが2009年だから、この年72歳。しかし、それ以前に大きな病気をなんどか経験しているので、老いや死をつよく意識するようになったのは私よりもいくらか早かったようだ。
私とのちがいがさらにもうひとつ。
もともと古井さんは、学者となるべくじぶんを鍛えてきた折り目ただしい「読書家」なので、どんなに年をとっても私のようなしまりのない暮らしにはならない。おなじ文章によると、1日の時間をきちんと区切って、毎日、その枠のなかで内外の古典を読みつづけているのだとか。すなわち、午前中に1時間ほど散歩。昼食後、日が暮れるまで「書き仕事」にはげみ、ふたたび散歩。帰宅後、夕食と晩酌。そして「一時間ばかり眠って起き出してから、夜半を回るまでが、本を読む時間になる」――。
するとそんな夜の時間に、古井さんは、いったいどんな本を読んでいるのだろうか。
いまもいったとおり中心には内外の古典があるようです。同書所収の「病みあがりのおさらい」という文章によると、2012年に病いを得て入院。帰宅後に読んだのが島崎藤村の『夜明け前』だったとのこと。ついで室町期の連歌集。病後一年たって、ようやく「横文字」の読書を再開する。このとき読んだのがホーフマンスタールの「ルツィドール」という短篇小説で、ちなみに別の文章には、中世連歌、とくに心敬の句集読解は「年に一度はこれをやる」とあった。
この別の文章「夜の楽しみ」によると、かつて古井さんは、30歳前後のドイツ語教師の仲間たちとラテン語の勉強をしていたことがあるらしい。それから半世紀がたち、ある日、当時つかった初等文法書が書棚の片隅に押しこまれているのを見つけて、「これも気まぐれか、あるいは八十のほうに近い年齢を考えれば、向こう見ずと言うべきか」――むかしは半分ほどで挫折した「お稽古」を、こんどはひとりでやりなおすことにした。
よしなさい、およしなさい、いまさらそんな御苦労なことをしてもあの世まで持って行けるわけでなし、と内で制する声がしきりにしたが、翌日の晩には第一章から始めた。(略)昼には小説、夜には「死語」の文法と、頭の切り換えにはよいのではないかと思われた。
牛歩である。それはもとより承知の上のことなので、先を急がずにいた。いずれ道草のようなものだ。いつでも放り出せる。(略)還暦を過ぎてからギリシャ語のおさらいを、これは根を詰めてやった。あの時と較べて、やはり違うな、とうなずいては悦に入る。まるっきりの初心でもなく、やはり年の功はあるもので、呑みこみは早い。ところが、それがいけない。分かりが早いその分だけ、覚えが悪い。習ったことを、何章か先へ行くと、もう忘れている。これでは笊で水を掬うようなものだ。
ことわるまでもなく私は古典語の学習やそれに類することはしていない。難解な中世連歌をコツコツ読みとくといった綿密な読書からも、とうに見放されてしまった。したがって一老人としての私の読書が古井さんのそれにかさなる面は、ほとんどないにひとしい。
にもかかわらず私はこの一節を大いに共感して読んだ。
――身についた読書スタイルこそちがうが、長い時間をへて、古井さんも私も、どうやらおなじ岸辺にたどりついたみたい。
そう感じて愉快になったのです。
ざっといって、おなじ点はふたつ。読んだことをすぐ忘れてしまう。あっけにとられるほど苛酷な記憶力のおとろえ。まずそれがおなじ。そしてもうひとつが、「先もないのに、そんなに本ばかり読んでどうするの」という内心の声を、しばしば感度よく聴きつけてしまうこと。
小説なら硬軟を問わず、つまらないと思ったらその場で読むのをやめるし、おもしろければ最後まで読み、たのしませてもらったことに感謝する。したがって、この種の内心の声――「いまさらそんな御苦労なことをしてもあの世まで持って行けるわけでなし」と古井さんのいう「内で制する声」をきくのは、おもに新しい知識を得たり、じぶんの考えをいくらかなりとも深めるための、どちらかといえば、ちょっと硬めの読書の最中ということになる。
年をとるにつれて小説(フィクション)を楽しむ力が失われ、それにつれて、いつしか歴史や伝記や回想録や日記などを好んで読むようになった。
ラテン語文法とまではいわずとも、私の分類でいえば、どれも「ちょっと硬めの読書」に属する広い意味での勉強の本である。そして勉強であるからには、よかれあしかれ、「来たるべき未来のために」というかすかな方向性をはらんでしまう。そのぶん「なにをいまさら」という内心の声をきく機会も増えてこざるをえないのですよ。
念のために付け加えると、「ちょっと硬め」はOKなのだが、「うんと硬め」の、ゴリゴリの理論書などはまえもって敬遠させてもらう。ついこの間までは、やっかいな哲学や宗教の本でもがんばって読んでいたのに、いつのまにかそうなった。なぜかな。いまや「落ち目の読書人」と化したじぶんに落胆し、哲学も宗教も、くやしまぎれにフィクション(つくり話)の方に追いやってしまったのかしらん。
*
記憶力のおとろえに泡を食った老人が、反射的にそれを、よわった脳のせいにしてしまう。しかし最先端の脳科学者諸氏が説くところによると、加齢につれて脳の力がよわるというのは、かならずしも正確な認識ではないらしい。
ときくと、
――へえ、そうなの。
いちおうはそう思う。でも完全には説得されない。
もちろん脳と記憶力のかかわりについて、脳を専門領域とする研究者の方々が、そんなふうに考えるのはかまわないのですよ。でも老人はちがうからね。老人にとっては、脳よりも、じぶんの記憶力のおとろえのほうが、はるかに大きな問題なのです。
一日になんども記憶力のおとろえに愕然とし、そのたびに、じぶんの干からびた脳のイメージを思い浮かべる。その干からび具合を嘆きながらも、「とうとうあんたもここまできたか」と、そうなったじぶんを慶賀して笑う。そうやって嘆きをなんとか娯楽に変える。それが老人――というだけの話で、もとより脳に責任を負わせるつもりなど、あろうわけがない。
しかし、それはそれとして、もし脳のせいでないとしたら、私たちの記憶力のかくもはげしいおとろえは、いったい、なんのせいなのだろう。
もちろん老人の脳に明滅する「干からびた脳」のイメージだけでこの問いに答えるのはむり。そこで本棚から『記憶力を強くする』という古い講談社ブルーバックスをみつけてきた。この本を私は2001年に刊行されてしばらくのち、60歳代のはじめごろに読み、たのしみながら脳科学の新しい知見をおしえてもらえる「いい本」だと思った。その記憶があったので、もういちど読んでみようかと思い立ったのです。

著者は池谷裕二――脳のうちでも「海馬」を専門領域とする脳科学者で、いまは東大大学院の薬学部教授だが、当時はまだ若い助手だった。海馬というのは、大脳の側頭葉と呼ばれる場所のすぐ裏側、左右ふたつの耳の奥に位置しているごく小さな器官で、池谷さんが「記憶の司令塔」とよぶごとく、私たちの記憶のしくみにとってのカナメの役割をはたしている。そういうことも、この本ではじめて知ったような気がします。
いや、それだけではないか。さきにふれた「加齢につれて脳の力がよわるというのは、かならずしも正確な認識ではない」という見解も、もしかしたら、この本を読んではじめて知ったのかもしれんぞ。そう思って読みすすむと、案の定、こんな記述にぶつかった。
歳をとると、しばしばものごとに対する情熱が薄れてきます。ひとつのことに熱中できなくなります。感動もうすくなってきます。すると、記憶力はてきめんに低下します。じつは、歳をとって記憶力が落ちたように錯覚してしまう最大の原因はここにあるのです。感動できない大人になっているのです。生きることに慣れてしまっているのです。それではいけません。常に環境の刺激に対して敏感になり、海馬にθリズムを作るだけの緊張感を保ち続けなければ記憶力は増強しません。
よく知られているα波やβ波のほかに、なにか興味をもって見たり聞いたりしたときに海馬が発するθ(シータ)波という脳波があり、1秒間に5回ほどの周波数(5ヘルツ)でリズムを打つ。そのリズムを「θリズム」と呼ぶのだそうな。
私たちが見たり、聞いたり、触ったり、嗅いだりして得た情報は、まず側頭葉に、ついで隣接する海馬に送られる。そして海馬は、それらの情報を切ったり捨てたり「適切な形」にととのえた上で、1ヶ月ほどのちに側頭葉に送りもどし、そこに長期記憶として保存される。つまり海馬とは私たちの「記憶の司令塔」なのだと池谷はいう。
大づかみにいってしまえば、この記憶のしくみが起動するには、私たちがなにかにつよい興味をいだき、熱中したり感動したりする必要があるらしい。その刺激で海馬にθ波が発生し、それが私たちの記憶システムを動かすエンジンになる。それゆえに、そうした興味や熱中や感動の度合いが薄れた老人の記憶力は、しだいに低下してゆくほかない。
――と、ここまでは私もそれなりに理解できるのですよ。
ただ、ちょっと気になったのが、そのさきで池谷さんが、こうした記憶力の低下をふせぐには、まずは無感動状態に慣らされた老人が、その慣れから抜けだして、海馬にθ波を発生させるだけの「緊張感」をおびた環境をよみがえらせるべく「努力」しなければならない、それをしないのはあなた方の「生きることへの慣れ」のせいなのだと、つよい調子でいいきってしまうところ。
おなじようなつよい口調が、べつの章での「人は『歳のせいで覚えが悪い』と嘆きます。この嘆きはたいへんな間違いで、私から見れば、そういう人は単なる努力不足であるように思います」という記述でも繰りかえされる。
ただし、ここまで私は「老人」と書いてきたが、正確にいうと池谷さんは「老人」ではなく、たいていは「大人」と書いている。この本を書いたとき、かれは31歳。その青年の視座から見た「歳のせいで覚えが悪い」となげく「感動できない大人」とは、老人というよりも、おそらくは最後にやってくる老人をもふくめての広い意味での大人を漠然とさしていたのだろう。
ところが、あいにく私は老人なので、ついそれをじぶんの側に引きよせて読んでしまう。そして、その老人の視座から見ると、ここでの、記憶力のおとろえに「努力」や「努力不足」といったコトバで対そうとする姿勢そのものが、どこか奇妙なものに見えてしまう。脳科学的には正しいのかもしれない。でも老人にせよ大人にせよ、その正しさを現実に生きる人間に適用するしかたが、すこしストレートすぎるんじゃないかな。
若者や壮年とちがって、老人の日常には「努力」の引き金となるような野心や欲望、「ねばならない」の責任感や「よし、やったぞ」という達成感によってきざまれる、つよいリズムは存在しない。むしろ心身ともにそのリズムで生きることがむずかしくなって、はじめて人は老人になるといったほうがいいくらい。
ありていにいってしまえば、老人が生きているのは「三読四読して長大息までしていたのに、机の前から立って十歩と行かぬうちに、はて、何のことだったか、と首をひねっている」と古井由吉がいうような、思わず笑っちゃうしかない滑稽な環境においてなのですよ。
いくら「努力せよ」といわれても、「では」といきおいこんでラッパに吹き込んだ息が、そのまま音もなく尻から抜けでてしまう。
その種のむなしさは、私も、壮年と老年とのあいだでふらふら揺れる60代をへて、ようやく本格的な老人になった70代前半の、いさんで老化と折り合いをつけようとする「努力」をつうじて、いやというほど味わった。その結果わかったのは、どうやら老人には「努力」という処方は通用しないらしいということ。くわしくは本の雑誌社からだした『百歳までの読書術』という本に書いたので、よければそちらをお読みください。
*
ここ半月ほど、のろのろ読んでいるメイ・サートンの『82歳の日記』という本の冒頭ちかくに、こんな一節があった。ほかの老人たちと同様に、この老文人も、じぶんの記憶力のおとろえにさんざん悩まされていたらしい。「わたしは、新たな詩の創作にくよくよして、眠れない。ばかなわたし」などとあって――。
わたしはいまほんとうの老齢期に踏み込みつつあって、その移りゆく困難なときに、この日記を書きはじめている。七五歳のころはもっといろんなことができたと思う。ところが、ものの置き場所を忘れ、友人たちの名前、花の名前すら(先日は金盞花が思い出せなかった)忘れ、真夜中にここに書こうと思いついたことを忘れ――たくさんのことを忘れて、ときに混乱におちいり、私は衰えていく。シャツのボタンをかけるという小さなことから、どのようにしてあと数篇の詩を書くかという大きなことまで、きりのない煩わしさをどうこなしていくか。それがいまのわたしの問題。
1990年代の前半に、みすず書房から『独り居の日記』と『今かくあれども』という2冊の翻訳書が刊行され、それを読んで私は、20世紀のアメリカにメイ・サートンというすぐれた詩人・小説家がいたことを、はじめて知った。とくに後者――『今かくあれども』という日記形式の小説に、ただならぬ印象をうけた。そんな記憶がいまにのこっています。
かつて高校で数学をおしえていた76歳の女性カーロが、兄夫婦によって、むりやり私設の老人ホームに送り込まれる。その年老いた中流インテリ女性を、ホームの女性管理者が執拗に痛めつける。孤独な老女の最後の誇り(「この地獄で、私はまっとうな人間として生きる」)を的確に剥ぎとってゆく心理的ないじめのいちいちが、じつにおそろしかった。
――まいったね、こっちだって遠からずよぼよぼのインテリ老人になるんだぜ。と、そのころ50代だった私は、息をつめ、はんぶんふるえながら、この小説を読んだ。
しかもおそろしいことに、そとからのいじめや暴力にとどまらない。そんな地上の地獄のまっただなかで、カーロは「まっとうな人間」であるはずのじぶんのうちに、あろうことか、もうひとつの地獄を発見してしまう。
かつて兄夫婦と暮らしていたころ、彼女は教養にとぼしい義姉をのけものにして、兄と二人だけの知的な会話をたのしんだ。それも傷ついた義姉の憎しみの視線を十分に意識しながら。ことほどさように私はいやな女だったのよ。よじれた自尊心と偏見。それが私のもうひとつの地獄。だから「いま私が罰を受けているとしたら、当然の報い」――。
思うに、この小説がアメリカで出版された1973年、まだ61歳だったサートンは、カーロに未来のありうる「私」をかさねて、きっとこんなふうに考えたのでしょう。
――私の老年にこんな地獄を招来したくなければ、いやな私の変革をもふくめて、できるかぎり早く、そのための準備をはじめたほうがいい。
そしてその結果、彼女は、いなかの一軒家での長いひとり暮らしをはじめることになった。その最初の一年間の記録を、『今かくあれども』とおなじ1973年に『独り居の日記』として刊行。それからの40年をこえる歳月のあいだに、続篇として、みすず書房版だけでも5点(もとのアメリカ版はもっとあるらしい)の日記が刊行された。その最後の1冊が、いま私が読んでいる『82歳の日記』なのです。
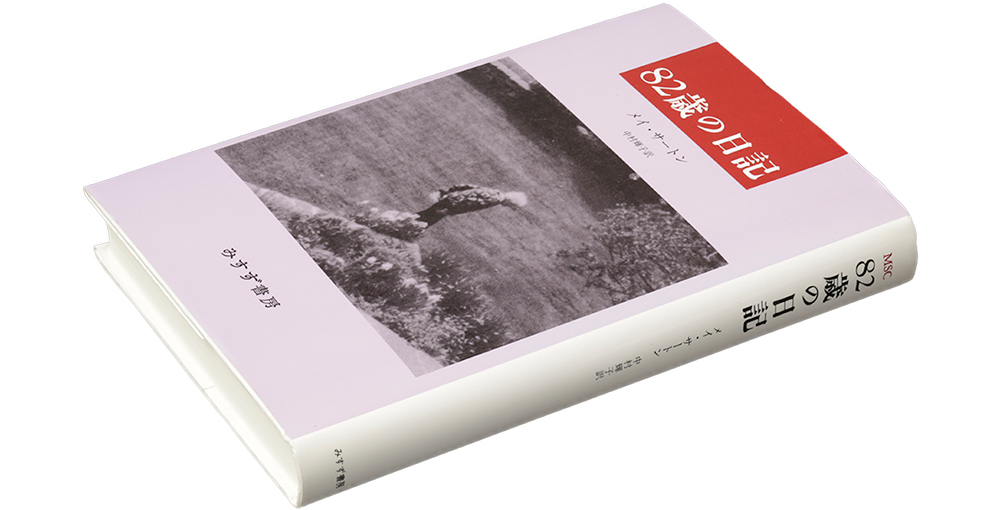
では、それからの「独り居」の日常で、はたして彼女は、じぶんの悪夢をぶじに消し去ることができたのだろうか。
ニューハンプシャー州ネルソンの牧草地にたつ住み心地のいい家、就寝まえの30分の読書、音楽、小旅行、庭いじり、愛猫とのつきあい、そして、老いてますますさかんな「書くこと」への情熱――一見したかぎりでは、あの地獄が彼女の暮らしにはいりこむ機会は、ほとんどなかったように思える。
しかし実際には、老人の日常を重苦しい影がチラッとよぎるようなことも、けっこうよくあったようなのだ。いいことやたのしいことだけでなく、それらのマイナスの体験をも、サートンはかくすことなく日記に書きとめています。
たとえば――。
彼女はじぶんを、まず第1に詩人と考えていたらしい。第2に小説家。そして第3に日記作家。ところが日記作家としての人気にくらべて、かんじんの詩の評判がパッとしない。この春も、せっかく苦心して「全詩集」をだしたのに、いくら待っても書評がでない。私は正当に評価されていない、そういえばむかしからそうだった、という怒りと焦りがつのる――。
とはいうものの、「落ち込む」とか「暗鬱な気分」とか、しょっちゅう口にするわりには、そう語る口調はさして暗くない。むしろ明るい。それは彼女の率直さがうみだした明るさで、おそらくはそれが、彼女を、忠誠度の高い、かずおおくの愛読者をもつ日記作家にしたのだろうな。
おなじ率直な明るさが読者だけでなく、老若の女性の友人たちをも引きつけ、たえず手紙を交換し、なにかあれば、そのうちのだれかが手助けにきてくれる、というような暮らしのしくみが、長い時間のなかで、いつともなくできあがっていたらしい。
ある秋の日、彼女より1歳下の、もう2度と会うことはないだろうと思っていた友人の作家が、夫とともに、まるで「奇跡」のように彼女の家を訪ねてくれた。どんな内輪の冗談でも、すぐあいてと共有できる。なんの気づかいもいらない。そんな親密な会話のよろこびをしるした1節――。
しかしわたしたちは、いつものように自分たちの記憶が欠落していくおそろしさを笑っている。ふたりに会う前に、贈呈本にサインしようとして、瞬間、記憶が真っ白になってしまった。なんという名前だっけ? 会えばこんなことも笑えるけれど。彼らももの忘れの話を披露する。(略)いま〔かれらには〕かわいくてたまらない子猫が一匹いる。だからふたりはランチのあと、もう一日はとても留守にできないと言って帰った。もちろん、猫の名前は忘れたけれど甘やかされているのはたしかだ。
しばしばとはいわずとも、老人の暮らしにも、ときにこうした至福の時間がおとずれる。会話のなかみが、ともすれば、じぶんたちの「もの忘れの話」のほうへ流れてゆく。そうなること自体がたのしい。笑える。――つまりはそういうこと。さきほど私は「記憶力のおとろえへの嘆きを娯楽に変える」と書いた。あのとき思い浮かべていたのが、ほかならぬこの光景だったのです。
訳者(中村輝子)のあとがきによれば、この会話があったころ(1993年10月)には、もう彼女はじぶんの手で日記を書くことをやめていたらしい。筋肉と骨の痛みで、タイプを打ったり、ペンを持ったりする力がおとろえ、詩も日記も、じぶんで録音したテープを助手役の女性に手わたし、そこから原稿に起こすという手のかかるやり方で「書く」しかなくなっていたのです。
若いころに彼女は乳癌を病んだ。そのため、この筋肉や骨の痛みも癌のせいなのではないかと何か月も悩み、ようやく医師がその恐れはないといってくれた。なんというよろこび。それが1994年8月1日。この日記を印刷にまわす期限がせまっている。「この仕事が終わるころには、私の容態も快方に向かう見通しがつく」だろう――そうしるしたところで、この日記は終わっています。
そして日記刊行の1年後、日記の書き手もその長い一生を終える。やはり死因は癌の転移でした。
―――――――――
古井由吉『楽天の日々』キノブックス、2017
池谷裕二『記憶力を強くする 最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方』講談社ブルーバックス、2001
メイ・サートン『82歳の日記』中村輝子訳、みすず書房、2004
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








