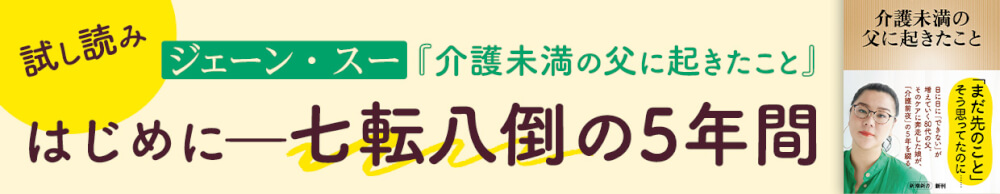2025年8月8日
はじめに――七転八倒の5年間
著者: ジェーン・スー
ジェーン・スーさんの連載「マイ・フェア・ダディ 介護未満の父に娘ができること」が、『介護未満の父に起きたこと』として、8月20日に新潮新書より発売されます!
5年前、突然ひとりで暮らしを整えなければならなくなった82歳の父。幸いまだ健康だが、家事がほとんどできないため、その生活に黄信号が灯る――。唯一の家族である娘のジェーン・スーさんが、毎食の手配から大掃除までサポートに奔走。その詳細な記録をまとめたのが、本書『介護未満の父に起きたこと』(新潮新書)です。
「ペットボトルが開けられない」「明日の予定がわからない」など、日に日に「できないこと」が増えていく父の生活を、献身的に、ときにウンザリしながら支えていきます。父の「介護前夜」に奔走した娘が綴る、七転八倒の5年間の記録です。
2025年8月現在、87歳。年老いた父を、私は大切に思っている。長生きしてほしい。愛情もある。しかし、これらの気持ちに常に行動が伴っているかと言えば、そんなわけはない。愛情の量と同じくらい腹が立つし、傷つくし、気が滅入る。嫌なことがあれば、しばらくは手を抜く。当然だ。私だって人間だもの。
室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」は、遠方から故郷に思いを馳せている詩ではないそうだ。東京で苦しい生活を強いられ、故郷に戻っても十分には受け入れてもらえないことを嘆いているのだという。つまり、故郷がファンタジーである限り、それは自分に都合よく寄り添ってくれるが、ひとたびリアリティを持つと綺麗事ではすまされない。
親もそうだろう。遠方に住む親に対し、なかなか会えないけれど元気かな、と少し後ろめたさを感じながら懐かしむ程度がちょうど良い。いい大人になった者同士が、距離を縮めて良いことなど起こるはずがない。
本書は、わが父の82歳から87歳までの生活記録である。要介護認定されるほどではないが、足腰と記憶力が弱り、自分ひとりでは生活が回せなくなった父親の生活を、如何にして滞りなく進めるかを試行錯誤した記録だ。しかも、同居はせずに。
59歳という若さで伴侶を喪い、以降、娘である私以外の手を借りながら、父はなんとか暮らしてきた。お互い都内在住ではあるが、月に一度の墓参りで顔を合わせ、互いの近況報告をする程度で済んでいた。私は父に資金援助をするだけのお気楽なご身分でいられたのだ。
そうも言っていられなくなったのが、父が82歳になってから。瞬間湯沸かし器と呼ばれた若い頃に比べれば幾分マイルドにはなったものの、まだまだ気難しく厄介な性格の父親と密に連絡を取り合い、生活をサポートしなければならなくなった。これが予想通り、否、想像以上に大変だった。
老人と言えば介護。日本には十分な介護保険制度があるから、安心。そう思っていたが、甘かった。人はいきなり寝たきりになるわけではない。そういう人もいるかもしれないが、たいていは誰もがイメージする「ザ・介護」の前段階がある。騙し騙しやっていたいままでの生活が、さまざまな理由でひとりでは回せなくなる日がやってくるのだ。
自分で入浴はできるが食事は作れない。洗濯はできるが掃除はできない。パートナーが家事全般を担当していた場合、その人の不在が生活に大きな穴をあけることになる。いなくなるまで、なにをやってもらっていたかなど、当人は意識したことがないことばかり。だからこそ、なにから手を付けていいのか、自分ではまるでわからないのだ。
まだ元気だが、どうしても自分だけでは生活が回らない。そういう事態に我が家も陥った。そして、私が介入することになった。
案の定、父との接点が増えれば、それだけ険悪なムードになることも増えた。気持ちがぶつかり合わないように、できるだけシステム化して、ビジネスライクに。そう決めて取り掛かったのが5年前のこと。ひとまず、この5年を本書にまとめ、成果報告とさせていただく。父と私の七転八倒が、誰かの役に立つことを願ってやまない。
(続きは本書でお楽しみください)
【目次より】
はじめに
第一章 老人以上、介護未満の父――2020年(父82歳)
1.突然のSOS
それは突然やってきた/生活力ゼロの父/老人以上、介護未満
2.誰がための安心か
ビジネス書に学べ!/あるべきゴールと三つの基本方針/「まるで刑務所みたい」
3.父の「できること/できないこと」
痩せるばかりの父/父の状況をノートに整理/まずはとにかく食事から/はじめての遠隔Uber Eats
4.それはまるで終わらないフジロック
「前科二犯」/お椀が持てない/家族といえどもビジネスライクに/トライアル&エラーの連続
第二章 世紀の大掃除!――2021年前半(父82~83歳)
1.さあ、次は家事代行サービスだ
父の愛した文鳥/家事代行サービスを試す/十人十色のサービス
2.大掃除を成功させるための心得
人生二度目の「世紀の大掃除」/「2回で8万円」の見積もり/大掃除を成功させるポイント/「父と娘のフジロック」がスタート
3.2日間のクリーニング公演
4時間×2日の大掃除/父の生活動線を再設計/ようやくスッキリ!/それも捨てたいけれど……
4.あきらめるところ、あきらめないところ
ドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』/「私は女・山本五十六」/しぶとい娘、父を諭す
5.三つの課題と目下の不安
メカニックとテストドライバー/主な三つのサポート/必須の父娘LINE/運動不足をどう解消させるか
6.生きるとか死ぬとかワクチンとか
「ワクチン接種」というハードル/「かわいそうな象」/やればできる……のか!?/第二幕スタート!
第三章 押し寄せる課題と尽きない不安――2021年後半(父83歳)
1.心と体重をすり減らし
減り続ける体重/「私、もう疲れちゃった」/痛恨のミス
2.我慢と焦燥の夏
遠隔での生存確認/カロリーアップ作戦/「三本柱」をバランスよく
3.結果オーライ!
久々の訪問/やればできる!/失敗もあったけど……
4.墓参りは顔見せイベント
墓地で健康診断/予想外の訃報/いいぞ、その調子
5.「良かれと思って」が仇となり
「病院好き」の父/すれ違う思惑
第四章 ついに介護サービスを検討――2022年(父83~84歳)
1.「いざ」という時に必要なこと
認知症か、性格か/「介護サービス」を相談/介護者と被介護者の“運命”を分けるもの
2.フレイルとサルコペニア
健康と要介護の“中間”/受験勉強のような老人ケア/認知症は? うつは?/思わずガッツポーズ
3.ひとまずここまで
父は元気です……/父、84歳に/「要支援」未満の父
第五章 人生は簡単には終わらない――2023~2025年(父85~87歳)
1.父の「大丈夫」を引き伸ばす
さらに細くなった父/父の生活は続く/文鳥をめぐる「大事件」/火の玉老人/「騙し騙し」を続けるだけ
2.衰えゆく父と娘のジレンマ
脱水症状、骨折、コロナ……/必要なのは、介護手前の生活援助/家事代行からホームヘルパーヘ/水頭症の手術
3.「スマート介護」で解決だ!
介護者の心を楽にするIT/タクシーアプリで移動も安心
4.コロナ、転倒骨折、癌
怒涛の一年/あんなに気を付けていたのに……/なぜこのタイミングで?/87歳、とにもかくにも現状維持
おわりに
-

-
ジェーン・スー
1973年、東京生まれの日本人。作詞家、コラムニスト、ラジオパーソナリティ。TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」のMCを務める。『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』(幻冬舎文庫)で第31回講談社エッセイ賞を受賞。著書に『私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな』(ポプラ文庫)、『生きるとか死ぬとか父親とか』(新潮文庫)、『おつかれ、今日の私。』(マガジンハウス)、『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』(文藝春秋)など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら