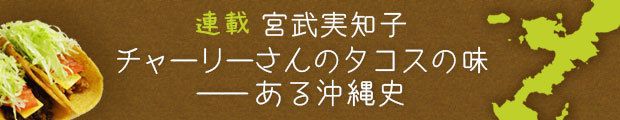(前回までのあらすじ)「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。沖縄戦の生き残りでもある。喜界島に帰った後、1950年に再び沖縄にわたり、「基地の街」コザでレストランを営んできた。
「先の大戦」とは京都では応仁の乱のことだ、と言われる(もっとも、35歳まで京都盆地に住んだが、本気で言う人には会ったことがない)。基本的にそれは日本では太平洋戦争の全体を意味し、沖縄では沖縄戦に限定される。
だが、コザをはじめとする基地の街では、もしかするとベトナム戦争なのではないか。そんな気がするくらいに、今も多くの人がベトナム戦争を語る。
沖縄にとってのベトナム戦争は、空前絶後のバブル景気だった。

ベトナム戦争の頃ね、なぜあんなに景気が出たかというと、まず米軍の新兵が沖縄に来て、2,3ヶ月おってからベトナムに何ヶ月か行きますよね。その間の給料はぜんぜん渡してないわけです、貯めてある。で、帰休兵が沖縄に来る時に給料がもらえて、また明日ベトナムへ行く日に有り金を使っていく。そういうのがマリーン(海兵隊)あたりに多かったですね。そういうわけで、ベトナム戦争の頃は景気が良かった。儲かった。
勝田さんに初めてベトナム戦争時期のことを解説された時、実をいうと、かなり驚いた。活字で知っていた「沖縄のベトナム戦争」とは、例えば以下のような「沖縄が出撃基地にされた不安」だったからだ。
1965年7月29日に、サイゴンにおける米軍スポークスマンは、沖縄から発進した米軍B52爆撃機約30機が、サイゴン東南方56キロに在るベトコン地区に爆撃を加えたことを発表した。戦争を恐れている沖縄住民は、沖縄の米軍基地がベトナムへの出撃基地となり、沖縄が直接戦争に巻き込まれていることを感知して不安と恐怖におののいた。(『コザ市史』1974年発行)
グアムの台風を避けて前日に嘉手納基地に入ったB52爆撃機が、そのままベトナム空爆に出撃したのである。それまで「補給基地」と言われていた沖縄は、以降、実質的な「出撃基地」となった。1967年5月には、現在も使われている4000m級の滑走路2本が完成し、嘉手納基地は極東最大の空軍基地となる。
沖縄側のたびたびの抗議にもかかわらず、米軍は1968年2月にB52を嘉手納基地に移駐し、連日の作戦行動の拠点とした。翌1969年3月には、米国と韓国を結ぶ大空輸作戦の演習拠点が置かれた。嘉手納基地は米軍の前進基地となった。ベトナムの人は沖縄を「悪魔の島」と呼んだという。
ベトナムに送られる新兵はまず沖縄に上陸し、金武や北部の特殊訓練施設で対ゲリラ戦訓練をおこなう。沖縄からベトナムへ向かった米軍兵士の4人に1人が死んだと言われる。
航空機や兵士だけではない。1969年には美里村(現沖縄市)の知花弾薬庫にマスタードガスやVXガスを含む毒ガスが1万3千トンも貯蔵されていることが判明。2012年になって県内新聞が報じたところによると、ベトナムで使用された枯葉剤も5000キロリットル以上が沖縄に貯蔵されていた。
当時の沖縄にとって、ベトナム戦争は身近な戦争だった。

とはいえ、沖縄は戦争の直接被害に遭わなかった。それで今や一般には「不安と恐怖」のほうではなく、バブル景気と武勇伝が語り伝えられるのか。さすがに活字で書かれたものは少ないが、沖縄に住んでいると実によく耳にする。「あの頃はすごかったよ」と、羨望や懐かしさを込めて。
BC通りで店を営む二代目の人からは、「親の代はすごかったって皆さん言いますね。羽振りの良さの桁が違う。今の人には想像できないんじゃないですか」と言われた。BC通りのBCは「ビジネスセンター」の略だが、「ブリング・キャッシュ」の略だ、という冗談もあったほどだ。
当時の儲かりようは「ドルの雨が降った」と表現される。「一晩だけでちょっとした家が1軒建つほどの収益があった。それが毎日だった」らしい。「閉店後に床に落ちたドル札を塵取りで掻き集めてドラム缶や大型ビニール袋に詰め込んだ。入りきらなくて足で踏んだ」という伝説も聞く。
米兵は財布を使う習慣がなく、ポケットに直接ドル札を詰め込む。ソファにどかっと座ると尻ポケットから札が落ち、掴み出した札をテーブルに勢いよく載せて、また札が落ちる。店は忙しすぎてレジに現金が入りきらず、足元にどんどん落としていく。それで床にドル札が積もったそうだ。
にわかには信じがたいが、「そういう店もあったでしょうね。うちはそこまでじゃないけど」と当時を知る人たちは言う。
『ロックとコザ(沖縄市史資料集)』(沖縄市企画部平和文化振興課、1998年)は、ベトナム戦争期のコザで人気があったロック・ミュージシャンたちへの聞き書きだ。さすがロックンローラー、あけすけで面白い。ステージ側から見た当時のクラブやバーの店内が生々しく伝わる。
外人さんは目の前にお金を1000ドル、2000ドル置いてそれで飲むのです。(中略)側のホステスさんがブチューとキスをしたら、もう1人の側に座っているホステスさんがそのお金を取ってパンツやブラジャーの中など、いろんなところに入れるわけです。そしたらその側のもう1人の人が「今度は私の番よ」とブチューとやっていたら、あとの1人がまたパンツなどに全部入れていくわけです。(中略)私たちは「あ、またやっている、この野郎」と見ながら演奏しているわけです。
ボーイは腕やトレイの底を水で濡らし、給仕のたびにテーブルのドル札をくっつけて失敬していく。演奏が下手だと、ベトナム帰りの米兵は灰皿や瓶などを容赦なく投げつけた。対抗したミュージシャンのなかには、生きた鶏やヘビの頭をステージ上で噛み切って血しぶきを撒くなど、過激なパフォーマンスで知られるグループも現れた。
なお、当時の1ドルは日本円で360円。貨幣価値を喩えて「コザから那覇までバスで行って、映画を見て、そばを食べて、またバスで帰ってこられる額」とよく表現される。今で言えば、4000円くらいか。むろん、ここでの「そば」とは沖縄そばである。

コザだけではない。当時は、金武(きん)のキャンプ・ハンセンもベトナムへの中継地であり演習場だった。やはり猛烈なドルの雨が降ったという。
基地内の食堂でウェイトレスをしていた女性は、食事を終えた米兵に呼び止められ、「自分は明日、ベトナムへ行く。君は親切だったから、これを全部あげる」とポケットの有り金すべてをチップにもらった。それは夫の月収をはるかに超える額で、彼女はほどなく大きな家を新築した。というような話が、いくらでもあったという。
その話を聞かせてくれたのは、「元祖タコライスの店」キングタコスの島袋小百合社長。「うちは遅れて金武に来たから、そんなに儲かっていない」と謙遜なさるが、そこは創業社長の旧居で、迷宮のような豪邸だ。家のそこここに虎や猛禽類の剥製が置かれ、巨大な水晶がごろごろ並ぶ。創業社長が集めた盆栽の置き場には、ほぼ同じ形の松の鉢が見渡す限りに並んでいた。

南部にも経済効果は及んだらしい。
那覇で産業廃棄物処理の会社を経営する裕福な知人も、やはりベトナム戦争が転機だったそうだ。当時、米軍が金属スクラップをただ同然で放出していた。それを引き取り、使える部品と使えない部品を仕分けする。ベトナムから戻ってきた大量の軍車両は弾痕も生々しく、ドアを開けると車内はべっとり血だまりが干からびていた。
「染みついて洗っても取れないのは捨てて、使える部品を中古車の業者に売るんだ。いやぁ、あの頃はよく儲かったよ!」と豪快に笑って言った。
沖縄は征く島であると同時に、還る島でもあった。
ベトナム戦争映画には名画が多い。ラストシーンが印象的な『プラトーン』のヘリコプターや、軽傷の負傷兵を振りきって出港する輸送船。行き先を考えたことはなかったが、実は沖縄だったのかもしれない。
1969年7月10日、ベトナム撤兵の第1陣120人が嘉手納基地に到着。翌週、第2陣を乗せた輸送船が軍港ホワイトビーチに着いた。以後、1、2週おきに1000人、2000人の規模で続々と山帰り(ベトナム帰りの兵士)が沖縄に上陸。「右手に銃、左手にギター」、「ヒゲ面に安堵の色」といった様子が新聞に報じられた。
撤退が始まったばかりの頃、米軍は沖縄にいるメディア関係者やカメラマンを呼んで到着風景を撮影させた。「何のための、誰に向けた公開だったのかしらね」。当時、軍港での撮影に参加した写真家の松村さんは今も不思議がる。

基地周辺がかくも賑やかだった時期、勝田さんはまだ八重島にいた。「最後まで八重島にいたレストラン」と言われたそうだ。1970年にやっと、一番街のはずれに小さな店を借り、タコス専門店にした。商売が軌道に乗り、翌年、家族でセンター地区に越した。どちらも嘉手納基地の第2ゲートに近い繁華街だ。
やはりドルの雨が降ったのだろうか。それとなく尋ねてみると、「いや、飲食店ですから、バーのようなことはありません。酒や女性にはいくらでもお金の使いようがあるでしょうが、一日に食べるご飯の量はたいして変わりませんからね」と勝田さんがちょっと面白いことを言った。

当時まだ小学生だった人が、店の様子を回想してくれた。「ベトナム戦争の頃でまず思い出すのは、お客さんの外人さんはほとんど全員が怪我をしていたことですねぇ」。包帯を巻いた人、松葉杖をついた人。店にタコスを食べにくる米兵は、怪我人ばかりだった。「八重島では、ほとんど外人さんを見なくなっていたから。たぶん子供ながらに驚いたんでしょうね。印象的でした」。
荒れる米兵のエピソードは、出撃前の酒と女性の店での話が多いのだろうか。昼のレストランで見る米兵たちは、静かに食事を楽しんでいたそうだ。
その人はさらに「基地の街の子供」ならではの思い出を話してくれた。
よく夕方になるとラッパの音が基地から聞こえました。4時頃でしょうか。物悲しいメロディーのラッパでね。聞こえると、「ああ、今日も誰か死んだんだなぁ」と思っていました。ほら、星条旗を半旗にして式典か何かをするんでしょう? ……そういえば、なんで知っていたんでしょうね。友達が教えてくれたのかな。見たことはないですよ、もちろん。でも、そう思っていました。また誰か死んだんだなぁって。
(続く)
(※2025年2月一部改訂)
-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら