――アルベール・カミュの『ペスト』がベストセラーになっている。
4月15日、郵便受けからとってきた朝日新聞の夕刊で「感染症扱う小説や歴史書に注目」という見出しの記事を読み、はじめてそのことを知った。それによると新潮文庫版の『ペスト』が、この2月以降、15万4000部を増刷しているらしい(現在までに36万4000部増刷)。いうまでもなく新型コロナウイルスのせい。したがって日本だけでなく、感染が拡がるにつれて、フランスやイタリア、英国でもさかんに売れているのだとか。
そうと知って、ちょっとおどろいた。「ちょっと」というのは、私たちの社会が大きな災厄にみまわれると、なかば忘れられていた昔の本が不意によみがえる。それはかならずしもめずらしい現象ではないからです。
たとえば2008年の小林多喜二の『蟹工船』ブーム――「就職氷河期」とか「非正規雇用」とか、日本の社会に冷酷な「ワーキングプア」状態が定着しはじめた時期に、昭和初頭のプロレタリア小説がとつぜん売れはじめた。こうした事態を災厄と感じた(一般には「本を読まない」とされる)若い人たちが、まっさきに読んでいるらしい。
じつはあのときも、「長生きをすると、こういう意外なできごとに出会うのか」と、ちょっとおどろいたのです。ただし今回、私が感じたのは「おどろき」というより「とまどい」に近かったかもしれない。というのも、こんど『ペスト』をはじめて手にした読者は、カミュが描出するペスト禍に目下の新型コロナウイルス感染を直にかさねて読んでいるらしい。ところが私には、かれの『ペスト』をストレートな感染病小説として読んだおぼえが、まったくといっていいほどないのです。
――すると私はあれをどんな小説として読んだのかね。
おそらくは、その2年後にでたジョージ・オーウェルの『一九八四年』に類するSF的な政治的寓話として読んだのでしょうな。そんな記憶がかすかにあります。「SF的」というのは、この作品が書かれた1940年代には、ペストはとうの昔に絶滅したと考えられていたから。その存在しないはずの感染病が、とつぜんフランス領アルジェリアの現実の港湾都市オランをおそう。そんな設定なので、リアルというよりも、いまでいう「SF的」と考えるほうが自然だったのです。
ただし、たしかに西欧諸国では1720年のマルセイユあたりを最後にペストはすがたを消したが、アジアやアフリカや中南米では流行がさらにつづいた。いまも完全には消えていない。なのに20世紀に入って国内での感染が消えた日本に生まれそだった私は、ほかの日本人とともに、なんの疑いもなく、ペストを絶滅した感染病と考えるようになっていた。その私がこの小説を読んだのが1960年代のはじめ。つまり大学生のころ。フランスでの『ペスト』刊行が1947年だから、その15年ほどのちということになります。
いまの日本には海外情報があふれるほどある。しかし当時はまだ、戦争から米軍占領へとつづく鎖国状態から十分に脱していなかったので、米国はともかく、最新のヨーロッパ情報となると、泣きたくなるほどわずかな量しかなかった。その断片的な情報をひろいあつめて、かの地の文化状況を懸命に想像する。そんななかで1950年――サンフランシスコ平和条約によって日本が主権を回復する前年に、サルトルの『嘔吐』に先だって翻訳されたのが、ほかならぬカミュの『ペスト』だったのです。そして、その10年後に若い私がそれを読んだ。時期はややおくれましたがね、でもまだピカピカの現代小説という感じでしたよ。
若き日の須賀敦子が、クロード・モルガンの『人間のしるし』やヴェルコールの『海の沈黙』などの、ナチス・ドイツ占領下のフランスで非合法に出版されたレジスタンス小説を翻訳で読んだ(連載13回を参照)のも、やはりこの時期のこと。
いまにして思うと、日本には戦時下の組織的な抵抗運動といったものがなかっただけに、須賀をはじめとする当時の若者たちの目には、フランスのレジスタンス運動が、あこがれの対象というか、それこそ遠い夜空に輝く星のように映っていたのだろう――などと、ひとごとのようにいっているけれども、まぎれもなく私もそんな若者のひとりだったのです。
それだけに、カミュがナチス占領下で地下出版された雑誌『コンバ(闘争)』の編集長だったらしいと、どこかで読むか聞くかして、「ああ、やっぱり」と思った。そのことも、私が『ペスト』を政治的寓話として読むことになった理由のひとつだったにちがいない。そして、こうした読み方を裏づけるかのように、『ペスト』の巻頭には、ダニエル・デフォーの『疫病流行記』(末尾の「追記」参照)のこんな一文がおかれていた。
ある種の監禁状態を他のある種のそれによって表現することは、何であれ実際に存在するあるものを、存在しないあるものによって表現することと同じくらいに、理にかなったことである。
ようするに当時の私は、ここでいう「ある種の監禁状態」をナチス・ドイツ占領下のフランスをさすものと推測し、そして「他のある種のそれによって」の「それ」を、幻の、つまり現実には「存在しない」ペストと理解したのです。そして対ナチのレジスタンス運動を、ペストに支配された仏領アルジェリアの要港での医師ベルナール・リウーたちの活動(ボランティアの「防疫隊」)によって暗喩的に「表現」したのだとも。
こうした読み方がまちがっていたとは思いません。カミュにしても、新しい作品の冒頭にデフォーの一文をおこうときめたときは、おなじように考えていたはずなのだから。しかし、たとえまちがいではなかったとしても、この寓話がもつ意味は、無知な若造だった私が考えていたほど単純なものではなかった。
いや、すこしは気づいていたのかもしれないな。でもその先にまで踏み込む力がなく、そのまま放置してしまった。そして、そうした中途半端な状態が延々とつづいたのち、おなじ人間が、このたびのブームに感じた「とまどい」をきっかけに、とりあえず時間もあることだし、もういちど『ペスト』を読んでみようと思い立った。
ただし思い立ったはいいが肝心の本が手もとにない。こんなとき、すぐに向かう近所の図書館は「閉鎖要請」で休館したままだし、行きつけの書店も3つあるうちの2つが休業中。辛うじて営業をつづけている残りの1店でさがしてみたけど、なんだい、ここにもないじゃないの。聞くと、在庫はとうに売りつくし、いつ入荷するかもわからないらしい。しかたなくネット通販で注文し、到着予定日に5日おくれて、ようやく新潮文庫版の『ペスト』を手にすることができた。一瞬、火事場泥棒というコトバが頭に浮かびましたね。
――おいおい、結局はアマゾンのひとり勝ちかよ。
*
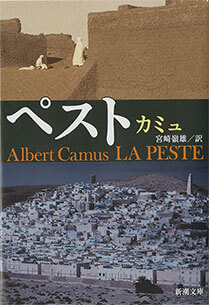
自宅蟄居に慣れた退職老人のひとり。それが私である。しかし「外出自粛」を息苦しく感じる点では非老人の方々となんの変わりもない。ときに家族にたしなめられながらも、3日にいちどは外にでて散歩と最小限の買い物をし、人気のない公園で本を読んでいる。その短い時間がことのほか楽しい。
――といった状態で、アマゾンで買った『ペスト』もその小公園で読みはじめ、あれ、小説の印象がいぜん読んだときとまったくちがうぞ、と感じた。むろん青年と老年という年齢のちがいもある。でも今回はそれよりも、「いつどんな環境でそれを読むか」というちがいのほうが、はるかにつよく感じられた。
つまりこういうことです。
かつての私が、この小説を「ペストは絶滅した」という当時の常識を前提として読んだのに対して、いまの私は、おなじ小説を「いまここにある新型コロナ」という現実の大災厄のただなかで読んでいる。その結果、以前は、
「ある種の監禁状態を他のある種のそれによって表現する」
というさいの「他のある種のそれ」にすぎなかった幻のペストが、与えられた役割を無視して、現にここに存在する「監禁状態」そのものとして浮上してきた。しかも、その「監禁状態」たるや、占領下のフランスどころではなく、新型コロナウイルスという「新ペスト」感染下の全世界にまで拡がっているのです。
そのため、この小説にしるされた一連のできごと――またたくまに増える感染者や死者の数とか、都市や国境のみならず、個人店舗から美術館や図書館にいたる諸空間の閉鎖とか、人影が消えた街路とか、病床や薬品の絶望的な不足とか、極端なまでの清潔の要請とか、唯一の輸送手段となった電車に「できうるかぎりの範囲で背を向け合って、互いに伝染を避けようとしている」乗客たちとか、そして、つねに遅れをとる頼りない行政組織とか――私をふくむ読者はそのことごとくを、SF的な寓話、つまりは空想上のできごととしてではなく、それこそリアルに、いまじぶんが体験しつつある災厄にかさねて読まざるをえなくなった。
で、私の場合でいうと、とりわけなまなましく感じられたのが、この本にでてくる「埋葬」についてのこんな記述だった。すなわち感染下での埋葬の特徴は「迅速さ」であったとして、
……すべての形式は簡略化され、そして一般的なかたちでは葬儀の礼式というものは廃止されていた。病人は家族から遠く離れて死に、通夜は禁止されていたので、結局、宵のうちに死んだ者はそのまま死体だけでその夜を過し、昼の間に死んだ者は時を移さず埋葬された。もちろん、家族には知らされたが、しかしたいていの場合は、その家族も、もし病人のそばで暮していた者なら予防隔離に服しているので、そこから動くことができなかった。家族が故人と一緒に住んでいなかった場合には、その家族は指定された時刻に出向くのであったが、その時刻というのは、遺体が清められ、棺に納められて墓地へ出発する時刻だったのである。
すぐわかるように、このオランのペスト(とその土台となったペスト流行の古記録)では、身近な人が死んでゆく場から家族や友人が強制的に引きはなされ、遺骸が骨になって自宅に戻されたところで、やっと対面を許されるという段どりになっている。
しかるにかつての私はといえば、この異様な記述をただの補助的な挿話とみなし、あっさり読みとばしてしまった。その証拠に私には、こんな記述があったという記憶のかけらもないのです。なのにその私が、こんどの再読では、読みとばすどころか、おなじ記述を「とりわけなまなましく」感じている。いうまでもない。このおそるべき「死の礼法」が、いまや世界のいたるところで現実のものになっているのだから。
――とすると私は、いつからそう感じるようになったのだろう。
象徴的にいえば、3月20日に高熱と呼吸困難で入院した志村けんが、わずか9日後に亡くなり、そのまま二重の袋に密封されて荼毘に付された。あのできごとのあまりに「迅速」すぎる進行ぶりに、ほかの多くの人たちと同様、私も並々ならぬ衝撃をうけた。やはりそのせいが大きかったのではないだろうか。
志村氏の73歳になるお兄さんが「そばに行って手を握ることもできなかった。火葬場に行くときすら会えない。残念です」とテレビで語っていた。そのやるせない口調をいまも忘れずにいます。そしてその2か月後、半世紀ぶりにカミュの『ペスト』を手にした私は、この小説を「ストレートな感染病小説」として読むのは当然と考えるようになっていた。
老人にはじぶんが育った時代を、ほかとはちがう特別な時代と考えたがる傾向がある。私でいえば「戦後」――1940年代後半から70年代の終わりにかけての時期が、その「私の時代」にあたる。年齢でいえば小学校入学から30歳代の終わりごろまで。この時期の経験を基準に、思わず知らず、あらゆることがらを「私の時代」に引きよせて判断してしまう。
――いや、ちょっとちがうか。
そんな傾向があるのは事実なのですよ。でもその一方で、老人も「私の時代」だけでなく、そのあとにくる時代――つまり「私」よりも若い「かれら」にとっての「私の時代(複数)」とも、それなりに浅からぬしかたでつきあっている。それもまた、もうひとつの疑いようのない事実なのですから。こんど『ペスト』を再読して、そのことがよくわかった。いかに私が昔の読み方に頑固にこだわろうとも、それが唯一の正しい読み方ではない。別のとき、別の環境で読めば、おなじ私が、いやもおうもなく以前とは別の読み方をしてしまう。たとえ80歳をこえようと、生ものとしてこの世に存在する以上、そうならざるをえんのですよ。
ただし、もしそうだったとしても、そのことで、むかし同じ小説を「SF的な政治的寓話」として読んだ私が消えてしまうわけではない。
いってみれば、たまたま私は、長い人生で「いまはもうない幻の感染病」としてのペストと、「いまここにある現実の感染病」としての新型コロナウイルス(いわば新ペスト)の双方を一身で体験することになった。その体験を仲立ちに、気がつくとカミュの『ペスト』自体が、寓話性と記録性というふたつの性格をあわせもつ多層的な作品に育っていた。おかげで、いまは私も『ペスト』をそのような作品として読むことができる。それはそれで、なかなかにうれしいことなのです。老人読書にわずかに残された特権のひとつといっていいほどにね。
*
カミュの『ペスト』には「SF的な政治的寓話」という一面がある。ただし、その「寓話」が意味するものは、むかし「無知な若造だった私が考えていたほど単純なものではなかった」と、さきほどのべた。
若い私が無知だったのは当然として、では、どのていどに無知だったのだろう。その無知さ加減を計るためにも、なぜカミュがこの小説を書こうと思い立ったのかを、きちんと把握しておきたい。さいわい昔とちがって、いまは日本語で読める伝記や新しい研究がいくらもある。ただし、いかにヒマな退職老人とはいえ、それらをいちいちチェックしている余裕はない。そこで、まずは『カミュの手帖』として知られる仕事ノートに当たってみることにした。
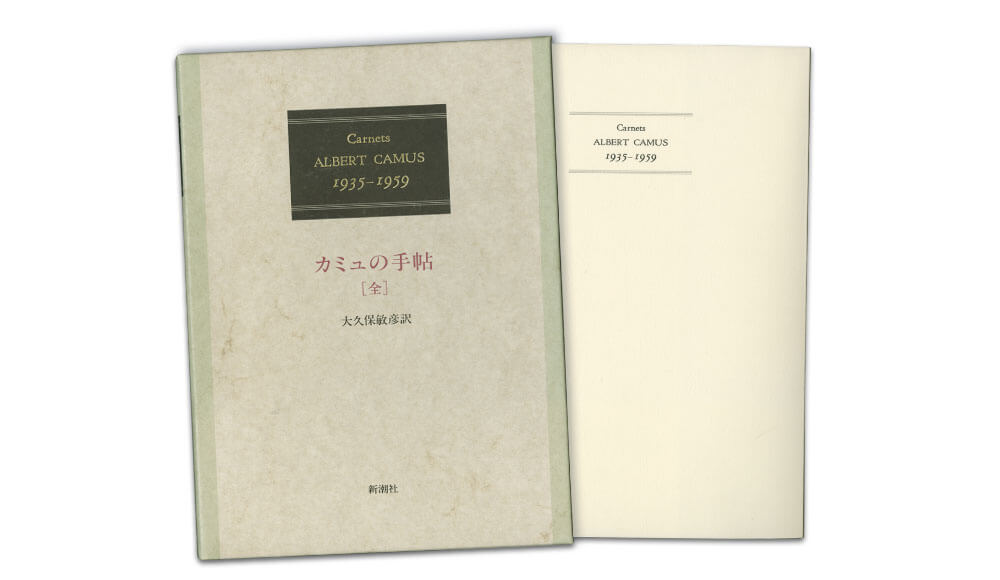
――『カミュの手帖 1935―1959(全)』大久保敏彦訳、新潮社、1992年。
ところが、これがA5 判でなんと680頁もある大冊なのです。したがって、できれば近所の市立中央図書館の書斎席(4人用の小部屋が6つ並んでいる)でメモをとりながら読みたいのだが、ざんねんながら休館中。古本で買えば1万円近くするようだし、かといって新潮社編集部は在宅勤務らしいので余計な迷惑をかけたくない。そんなこんなで、だらだらと先延ばしにしていたら、ようやく6月2日に図書館が再開された。もちろんすぐに駆けつけました。慣れ親しんだ図書館がこの時期にどう変貌しているか、それも見ておきたかったしね。
で、まず気がついたのが、児童席や社会人席の椅子がすべて撤去されていたこと。もちろん書斎席も利用不能。おまけに入館時間も30分にかぎられている。つまり当分のあいだ館内読書は禁止、読みたい本は借りて自宅で読んでください、ということなのだろう。
それともうひとつ、書棚のあいだに小さな机がいくつも置かれ、いちど手にとった本は元にもどさず、そこに積んでおくという仕組みができていた。新旧の本の森をぶらぶら散歩しながら、目についた本を手にとり、ちょっとのぞいてはまた棚にもどす。そうした図書館の楽しみ方も、しばらくは、あきらめるしかないらしい。利用者にかぎらず、これは図書館にとっても、かなりつらい決断だったのではないかしら。
ともあれそんな状態なので、『カミュの手帖』も館内で読むわけにはいかない。老人には重すぎる本だけど、肩にかけたズダ袋につっこんで、息もたえだえに持ち帰りましたよ。
この本は1935年から59年までの24年間の手控え帖(9冊)を一巻にまとめたもので、『ペスト』関連の記述は、そのうちの1939年から48年までの3冊のノートにみつかる。なかの「一九四一年四月」の項に、「幸せな町。人びとは、それぞれの生き方に従って、暮らしている。そこにペストが発生する。するとどんな生き方も意味がなくなってしまう」とはじまる作品の構想が、早くも「ペストあるいは冒険(小説)」という仮タイトルつきで、かなり具体的にしるされていた。
この年、カミュは結婚したばかりの妻の故郷オランに居を移し、哲学的なエッセイ『シーシュポスの神話』を書き上げた。そして前年に完成していた『異邦人』とあわせて、パリのガリマール書店からの刊行がきまる。そのためもあってフランスに滞在中の翌42年11月、ドイツ軍が占領地域をフランス全土に拡張し、カミュは妻の住むオランに戻れなくなってしまう。そうしたなかで、同年10月23日、『ペスト』の執筆を開始。前記の構想からかぞえて1年半がたっていた。そして翌43年、かれのノートにこんなメモがしるされる。
ぼくはペストという手段を用いて、ぼくらみんなが苦しんでいるこの窒息状態と、これまで体験してきた脅迫と追放との雰囲気を表現してみたい。同時にこの解釈を存在一般の概念にまで広げたい。ペストはこの戦争でともに反省と沈黙を味わった人たちの姿を伝えるだろう――また道徳的苦しみのイマージュをも。
この年の春から、カミュは先述の地下出版誌『コンバ』に執筆者兼編集者として積極的にかかわるようになっていた。
ただし母体となるレジスタンス運動は、かつて私が乏しい情報にすがって想像していたように単純なものではなかった。「夜空に輝く星」という面もたしかにあった。でもそれだけではない。対ナチ抵抗運動の勝利という目標を共有しながらも、共産党や社会党などの左派、旧来の右派や保守派、ドゴール派、カトリック派などの大小のグループが、複雑に入り組んだ争いをつづけていた。それもまたカミュの参加した時期のレジスタンス運動の内実だったのです。
そして戦争末期、ドイツ敗退が近づくにつれて、戦後政治の主導権をめぐる党派間の対立がはげしさを増してゆく。
しかしカミュはその種の対立にかかわることを陰に陽に拒みつづけた。諸党派がそれぞれに掲げる「正義」には距離をおき、貧困や孤立や恐怖や裏切りや無力感といった苦しみを抱えた人びとが、ヒロイックにではなく、その息苦しさのままに現実と立ちむかい、一見したところ弱々しい「連帯」の力によって、「正しいこと」と「自由であること」という目標を、ふたつながらに実現してゆく。それがかれの考えるレジスタンス運動の究極的にめざすところだったのです。
したがって、カミュがさきの引用でいう「窒息状態」とは、なによりもまず、その苦しみや息苦しさ――「戦争でともに反省と沈黙を味わった人たち」の内なる「道徳的」(というよりも倫理的)な葛藤を意味していた。
ただし、ここでいう「戦争」は対ナチ抵抗運動だけでなく、それをもふくむ第二次世界大戦の全体を同時に意味していたらしい。さらにいえば戦争とファシズムと革命ですね。ふたつの世界大戦(総力戦)やナチズムやスターリニズムなど、多様な全体主義がかたちづくる20世紀にあっては、ペストは外から強いられた「監禁状態」としてあるだけではない。ペストの世界に生きる者もまた「ある種」のペストであらざるをえないのだ。カミュのいう「窒息状態」とは、そのような内も外もひっくるめた災厄としてのペストを意味していたようなのです。
*
しかし、さしものペストもやがて退潮期にはいり、ある晴れた朝、ついに封鎖都市オランの門が開かれる。教会の鐘がひっきりなしに鳴りひびき、広場という広場で家から飛びだした人びとが踊り、「苦悩の時期は終りを告げ、しかも忘却の時期はまだ始まらぬ、この息づまる瞬間」を祝っていた。そして、その群衆のなかを歩きながら、語り手の医師リウーが考える以下の一節によって小説がしめくくられる。
市中から立ち上る喜悦の叫びに耳を傾けながら、リウーはこの喜悦が常に〔=かつての流行終結時と同様に〕脅やかされていることを思い出していた。(略)ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反古のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを。
そして、この第2次世界大戦下で書きはじめられた小説が、1944年のパリ解放(ドイツ敗北)をまたいで1947年に刊行され、たちまち戦後世界でのベストセラーになった。
ただし最初に読んだフランスの読者たちは、この「苦悩の時期」と「忘却の時期」にはさまれた祝祭的瞬間の記述を、すくなからず複雑な気分で読んだにちがいない。なぜか。対ドイツ戦争に辛うじて勝利したよろこびの一方で、かれらは、ナチス占領下での「対敵協力」の苦い記憶をなまなましく抱えていたからです。
いまにして思うと、そのことを私に最初におしえてくれたのは映画だったな。
アンリ=ジョルジュ・クルーゾーの『情婦マノン』(1949年)や、アラン・レネの『二十四時間の情事』(1959年)などの戦後フランス映画に、しばしば、ナチスの将校や兵士と関係をもった女性たちが、頭を丸刈りにされて街を引き回される陰惨なリンチの場面がでてきた。
――うーん。でもさ、「非国民」とわめきながら、ゲラゲラ笑って女たちを引き回す民衆の「正義」だって、実際にはどうだったのか、わかったもんじゃないぞ。
映画を見ながら、そんな印象をつよくうけ、ようやく私も、フランスにおける対敵協力者問題の厄介さに気づいたのです。
それにフランスの「対敵協力」だけでなく、日本でも、戦前・戦中の知識人や民衆の「転向」(強権に押し負けてじぶんの思想を捨てる)をめぐって、吉本隆明や鶴見俊輔といった「戦中派」の人たちが「息苦しい」議論をかさねていた時期でしたからね。もしまたそんな時代がやってきたら私はどう動けるか。もしくは動けないか。それが「戦後派」の私たちにとっても、けっこう大きな問題になっていたのです。
そして「厄介さ」という点ではカミュ自身も例外ではなかった。戦後すぐのころ、対敵協力者として活動していたある作家を死刑に処すという動きに同調して、寛容派のキリスト教作家フランソワ・モーリヤックと論争になり、さんざん悩んだすえに自説を撤回するというようなこともあったのだとか。かれのいう「窒息状態」――「戦争でともに反省と沈黙を味わった人たち」の内なる倫理的な葛藤とは、どうやらそうしたことをも意味していたらしい。
――と、ここまで書いて、唐突なようだが、この4月10日、安倍晋三首相が官邸をたずねた田原総一朗に語ったという、こんなコトバを思いだしました。
……実は私自身、第三次世界大戦は、おそらく核戦争になるであろうと考えていた。だが、このコロナウイルス拡大こそ、第三次世界大戦であると認識している。
このコトバに接して、すぐに私は、その1か月まえのトランプ大統領の発言(「私は、ある意味、自分のことを戦時下の大統領だとみなしている」)を連想した。「戦時下の大統領」とは、いうまでもなく、第2次世界大戦のルーズベルトや、イラク戦争のジョージ・ブッシュのような、「大きな危機に対処すべく全権を握った政治的指導者」をさす。
そこまでのことを安倍首相が考えていたとは思いたくない。しかし、2013年9月、東京オリンピック開催が決まったIOC総会での、「フクシマについて、お案じの向きには、私から保証をいたします。状況は、統御されています」という演説や、この3月、東京オリンピック開催の1年延長を決めたさいの、「人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証として、完全な形で東京五輪・パラリンピックを開催する」といった発言を併せ考えると、トランプにならって、もしかしたらこの国の首相も、と考えざるをえなくなるのです。
――コロナウイルスの世界規模での感染を「第3次世界大戦」とみなし、敵の力を「統御」し、それに「打ち勝つ」。フクシマがそうだったように、わが日本国にはそれができたし、これからもできるだろう。
しかし、口先だけ大政治家ぶってみせたところで、実際には、そんなことはできっこないと実証してしまったのが20世紀なのだからなァ。
たとえばフランス北部の農地には、第1次世界大戦でドイツ軍と仏英軍のばらまいた毒ガス弾1300万発の何分の1かが、いまも不発のまま埋まっている。21世紀中に処理を終えることができるかどうかさえわからないのだとか。もちろん福島原発の膨大な汚染水や放射能ゴミをどう処理するかも、依然として不明なまま。それなのに、なにが「状況は統御されている」、なにが「人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ」なのさ。
むしろ逆でしょう。人類には、そうそうハッピーには「制御」も「打ち勝ち」もできないものがあり、その領域がますます拡がりつつある。そして20世紀半ばに、早くもそう感じていた少数の人間のひとりがカミュだった。こんど『ペスト』を読みなおして、ようやく私もそのことに気づいたのです。
――ペスト菌は死なない。この災厄を人びとが忘れたころを見計らって、「人間に不幸と教訓をもたらす」べく、あらためて「どこかの幸福な都市」をおそうだろう。
このリウー医師の禍々しい予言のとおり、このたびの新型コロナウイルスも、やがておとずれるであろう終結の時を境に、しだいに忘れさられてゆくにちがいない。現に私が、いや私たちが、あれほど悲惨だったアジア太平洋戦争や原爆や東日本大震災の記憶を、あやうく忘れかけているようにね。
そんな絶望的に弱々しい存在が私たちなのだ。では、そんな情けない私たちに、いったいなにができるのか。
明確な答えを呈示するかわりに、カミュは、ペストに感染された都市で、さまざまな苦しみを抱えながら孤立して生きる人びとが、ひとり、またひとりと集まって、いつしか「防疫隊」という組織ができあがるプロセスを、ていねいに描いてみせた。自殺する者もペストに感染して死ぬ者も、神父も泥棒も、恋人と再会できた者も妻を失った者もいる。鉄のように強靱な組織ではなく、矛盾だらけの、そんなぼんやりした集合体――そう、つまりは先にいった「一見したところ弱々しい連帯」ですよ。
こうした小さな「連帯」が生じては泡のように消える。その繰りかえし。そこからはじめるしかない。それが未来に向けたカミュの呼びかけだったのだろう。この呼びかけに応じる条件は、私がはじめて『ペスト』を読んだころより、いまのほうが熟しているように思える。それゆえの、とつぜんのベストセラーだったのではないか。
*
(追記)
この原稿を送ったら、校閲の方が、カミュの『ペスト』巻頭におかれた引用は『疫病流行記』からのものではないようです、と指摘してくださった。指示にしたがって、インターネットの「現代ビジネス」というサイトをのぞくと(2020.5.1)、そこに「コロナウイルス時代にデフォー『ペストの記憶』が教えてくれること」という記事がみつかった。
筆者は、『疫病流行記』の最新訳『ペストの記憶』」 (「英国十八世紀文学叢書」第3巻、研究社、2017年) の翻訳者・武田将明氏で、それによると、この一文は、じつはその前年、『ロビンソン・クルーソー』の好評にのって刊行された『ロビンソン・クルーソーの敬虔な内省』(1720年)の序文から取られたものらしい。
それによると、デフォーはそこで、かれ自身が「孤独な人生で経験したできごと」〔つまり「ある種の監禁状態〕ですな)を、ロビンソン・クルーソーの無人島における冒険譚〔おなじく「他のある種のそれ」〕に置きかえてみせたのだとか。へえ、とするとカミュも――と考えはじめるときりがないので、いまはご紹介するにとどめます。
アルベール・カミュ『ペスト』宮崎嶺雄訳、創元社、1950年→新潮文庫、1969年
アルベール・カミュ『カミュの手帖 1935―1959(全)』大久保敏彦訳、新潮社、1992年
ダニエル・デフォー『疫病流行記』泉谷治訳、現代思潮社、1967年
田原総一朗「緊急事態宣言発令後に、安倍首相に会って僕が確かめたこと」田原総一郎公式サイト、2020年4月14日
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








