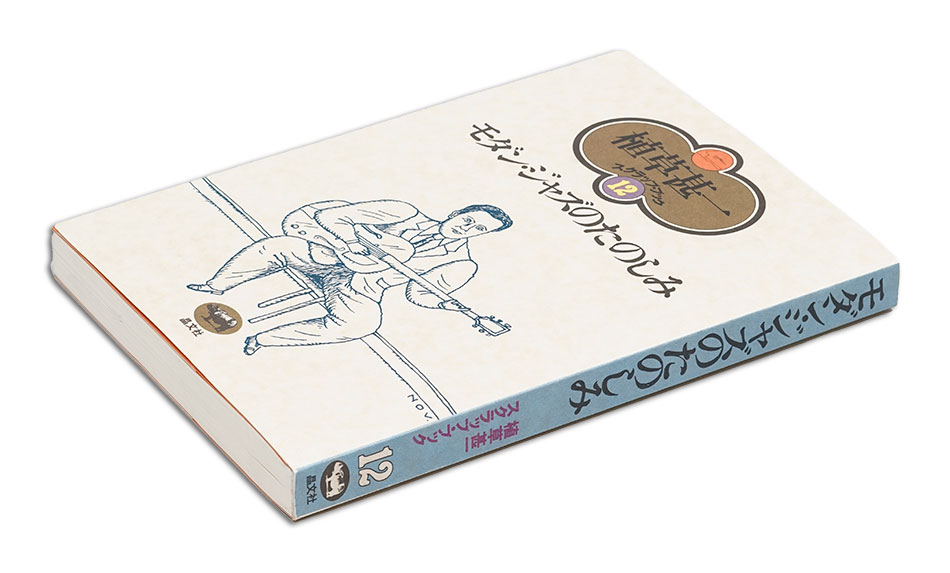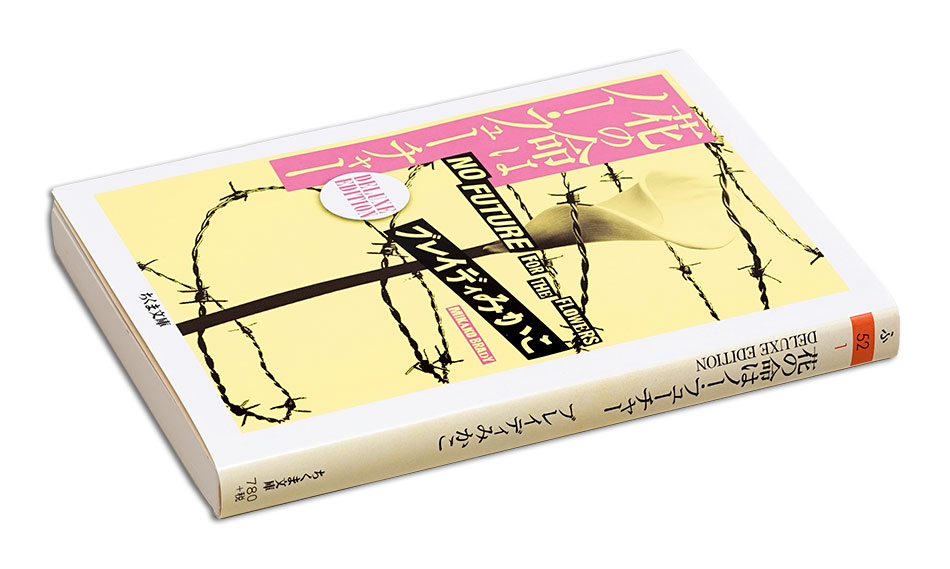絵本やマンガにはじまる「面白い本」ばかり読んでいた子どもが、成長するにつれて、しだいに「かたい本」や「まじめな本」を読むようになる。いや、なって当然、そうでないとまともな大人とはいえないぜ(あれ、高校生のくせにまだマンガを読んでるの?)といった空気が、けっこう濃厚に社会にただよっていた。それが私のそだった時代ですね。
つまり本には低級と高級の区分があって、そこをローからハイへと一段ずつ上っていくという「読書の階段」の秩序が、日本とかぎらず、おおくの国や地域でまだ生きていた時代――。
ただし私についていうと、大学を卒業した1960年代なかば(前回の東京オリンピックのころ)には、この大正教養主義に端を発するじぶんみがき、すなわち「人格形成」の階段をはなれ、もっとあけすけにいってしまうなら、「高級な本」を読みこなすのに必要な外国語や数学、こみいった概念語などを身につける根気も集中力もなく、もろくもそこから落っこちて、べつの道を歩くようになっていた。でもね、高校から大学にかけて、しばらくこの階段とつきあったおかげで、そんな人間なりに「なじみのない本の領域にも気軽に踏み込んでいくていどの度胸はついたし、じぶんが面白いと感じる本の領域を大きく拡げることもできた」のですよと、この連載の前々回でそう書いた。
では、そんな「読書の階段」という旧式エンジンに大きなヒビが入ったのち、つまり現在、いったい私たちはなにに背中を押してもらって、「面白いと感じる本の領域を大きく拡げる」ことができるのだろう。
いいかえれば、私たちの読書を「なじみのない本の領域」にむけてかきたてる新しいエンジンはどこにあるのか。もしそれが見つからなければ、本がもつ力も私たちの読書習慣も、しだいに弱々しいものになっていくしかないのではないか。――といったことを、じつはその先で考えてみたいと思っていたのです。ところが予期せぬ白内障手術でそれがむずかしくなった。で、今回はそのつづき。
――といってはみたものの、いまものべたとおり、私には、こうした大問題を精緻に考えつめ、目のさめるような結論にたどりつくというような芸はない。あるのは乱読をふくめての多様な体験の残りかすと、それにもとづく直感くらい。そこで思いだしたのが、むかし植草甚一氏がよく口にしていた「勉強」という語です。たとえば、
こんどは丸善へ行って小型だが上等なクロース・カバー製ノート・ブックを買ってきた。買ったレコードの演奏メンバーや曲名を書きこみながら勉強するのが、とても面白くなったからである。
(「レコードを買いだしたころの話をもう一度」『モダン・ジャズのたのしみ』)
植草甚一『モダン・ジャズのたのしみ』晶文社
植草甚一といえば、希代の「散歩と雑学」の人で、「勉強」といった堅苦しいコトバとは、あまり縁がないように思える。
ところが植草さんの書いたものを読んでいると、あちこちでこの二文字にぶつかるのですよ。そのズレ具合が読んでいて楽しい。思わず笑ってしまう。そこで、むかし植草さんのミステリー・エッセイを集成して本をつくったさい、『雨の日はミステリーの勉強』という書名を提案したら、その場で『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』と訂正されてしまった。
――おお、モロ植草調じゃん。
ちょっと感動しました。ことほどさように、植草流ブラブラ散歩文体には、意外にも「勉強」の語がよく似合うのです。では、この植草さんの「勉強」への偏執はいったいどこから生じたのだろう。以前、『したくないことはしない――植草甚一の青春』という本を書いていて、その原点といえそうな体験が見えてきた。
中学にはいった年の夏、甚一少年は、神田の書店で姉さんにウェブスターの『あしながおじさん』の原書を買ってもらった。それをきっかけに英語が好きになり、ひいてはどんな科目であれ、勉強すること自体に異様なまでにのめりこんでしまったらしい。だから、いってみれば勉強中毒。もしくは鶴見俊輔いうところの「1番病」です。
学校から帰るなり二階の部屋で机にしがみつきどおしだったなあ。(略)英語から始めて、その日に教わったことを全部暗記しないと気がすまないのであって、ただそれだけだった。そうして夜になって寝るときには、(略)『カミサマ』と形式上つぶやいてから『一番にしてください』と忘れないでたのんだ。
(『植草甚一自伝』)
植草甚一『植草甚一自伝』晶文社
ところが、こうして中学の5年間を「1番」でとおしたガリ勉少年が、あえなく一高入試に失敗してしまう。その挫折感もあって学校秀才の道をはずれ、以後は、映画とかミステリーとかジャズとか買い物とかファッションとか、学校から遠くはなれたところで「勉強」の語をさかんにつかうようになった。ようするに、そとから強要されるのではなく、いわば街の一散歩人として、じぶんが関心をもった世界(都市型の大衆文化)にそのつど自発的に突っ込んでいく。そうした行為を勝手に「勉強」と呼ぶようになったようなのです。
私たちは「勉強」ときくと、かつて甚一少年がそうだったように、学内テストや入試にむけての暗記中心の学校教育をまっさきに思い浮かべてしまう。
でも、かならずしもそうではないのですね。
この語はもともと「がんばってつとめる」というほどの意味で、そこから「学問や技術をまなぶこと」や「商品を精いっぱい値引きして売ること」を意味するようになった。したがって原義からすれば、大人になった植草さんがジャズや映画にのめりこみ、「雨降りだからミステリーでも勉強しよう」などと、場ちがいなところで「勉強」の語をつかうようになったのも、かならずしもズレたふるまいではなかったことになる。そう考えて私は前記の『したくないことはしない』という本にこうしるした。
〔一高に落第して〕学校の成績とは無縁の暮らしになったのちも、植草さんは勉強をやめようとしなかった。「道楽」というかわりに「勉強」という。勉強というしかたで惑溺する。そんなタイプの勉強好き。植草甚一という人物を考える上で、これは重要な一点だと思う。
いや、なにも植草さんにかぎらないか。教養主義的読書の常識が崩れたのちの「読書へのいざない」として、もしかしたら、こうした植草流の「勉強」の語のつかい方が「重要な一点」になるかもしれないぞ。
――「教養」読書から「勉強」読書へ。
うん、あんがい、いい線なんじゃないかしら。

*
若者の「本ばなれ」や「活字ばなれ」という流行語が生まれたのが1980年代はじめだから、もう長い時間がたつ。
その間に若者だけでなく、大学教師をふくむ大人たちまでが、それ以前の世代にくらべて本を読まなくなり、気がつくと、「だれにとっても本を読むのはいいことなのだ」という前世紀の常識が、ほとんど通用しなくなっていた。
私も20世紀そだちの人間なので、そのことをさびしく感じないわけではない。
でもだからといって、よくいる同世代の老人諸氏のように、「だめじゃないか。このさき日本がどうなるか心配だ」などと叱り口調で憂慮してみせる気分にもなれない。本が諸メディアの中心にどっしり腰を据えていた時代は終わった。それはもはや否定しようのない現実だと思うけれども、その一方で、われわれの時代の読書とはちがう本とのつきあい方が、さまざまな場所で実際にそだちはじめているようなのだから。
そこでまっさきに頭に浮かんだのがブレイディみかこさんの本とのつきあい方です。
すでにこの連載でも書いたように、いま、みかこ氏はダンプ運転手の夫と中学生の息子とともに、イギリス南東部の港湾都市ブライトンの公営住宅地(労働者階級の人びとの町)で暮らしている。
ところが、この地で彼女が親しくしている隣人たち――かつては労働党の支持者だった「おっさん」連中のほぼ全員が、じぶんの配偶者もふくめて、2016年の国民投票でEUから離脱する側(ブレグジット)に票を投じたのです。
そうと知って、「えらいこっちゃ、と思った」とみかこ氏はいう。
そとにいる人たちなら「排外に走った愚かな人々」と遠くから罵倒しておけばすむだろう。だがみかこ氏の場合、そうは簡単にいかない。なんといっても彼女は、そとから来て、20年まえにこの地に住みついた者(移民)として、「これまでも、これからも、彼らと一緒に生きて」いくしかないのだから。
でも、日ごろつきあっているとわかるのだが、配偶者も友だちの「おっさん」連中も、トランプ支持のアメリカ人とはどこか気風がちがう。なのにメディアなどでは「ポピュリズム」の一語でひとつにくくられてしまう。ちょっとちがうんじゃないの。そんな気がしてならない。だとしたら、どこがちがうのか。ちがうはずの英国の労働者の多くが、なぜEU離脱をえらぶことになったのだろうか。
そんなわけで、よく理解できない事柄に出会ったときに人類がせねばならないことを、いまこそわたしもしなければならない、と思った。勉強である。(『労働者階級の反乱』まえがき)
そう、ここでも「勉強」なのです。
したしい隣人たちの気風、暮らしのスタイル、その思想はいつどこで、どのようにかたちづくられたのか。それを知るために、まずはイギリスの労働者や労働運動の歴史をしらべてみよう。そこで、植草さんの「道楽」とは性質がちがうけど、みかこ氏もまた、いやおうなしに抱えてしまった疑問に「勉強」というしかたでまっしぐらに突っ込んでいった。
その成果は、2018年刊行の『ブレグジット狂騒曲』(弦書房)を皮切りに、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)や、それと対をなす「ワイルドサイドをほっつき歩け――ハマータウンのおっさんたち」(筑摩書房のPR誌『ちくま』連載中)などの報告エッセイにも、しっかり取りこまれている。
しかもそれだけではない。それらの本のうちに、ほかのものとは毛色のちがう小さな本が一冊まじっていた。さきに「まえがき」の一部を紹介した『労働者階級の反乱――地べたから見た英国 EU 離脱』という光文社新書がそれです。しつこいようだが、おなじまえがきからもう一か所、べつの一節を引いておくと、
……このように、本書は、英国在住のライターが、EU離脱投票で起きたことを契機として、配偶者を含めた自分を取り巻く労働者階級の人々のことを理解するために、まじめに勉強したことの覚え書きといえる。
まったく個人的な学習記録ではあるが、ロイヤルファミリーやアフタヌーン・ティーの階級についてはよく知られていても、日本にはほとんど伝えられていない階級の人々の現状や、主流派とは違うもう一つの英国の歴史について、祖国のみなさんに少しでも関心を持っていただけるきっかけになればと願っている。ブレイディみかこ『労働者階級の反乱――地べたから見た英国 EU 離脱』光文社新書
ここからもわかるように、この本は著者の「まったく個人的な学習記録」――著者が勉強のために読んで知りえたことや考えたことを、発見のたのしみとともに要約してしるした読書ノートを、そのまま本にまとめたようなものなのです。
ただし本を読むだけでなく、あわせて、これまでのエッセイでおなじみの隣人たち(中年の男女8人)に、「なぜあなたは離脱に賛成したの?」、もしくは「反対したの?」という短いインタビューをこころみている。
印象的なのは、程度の差はあれ、かれらの多くがじぶんを「労働者階級」の一員と考え、その力や誇りを不当に奪われてしまったと感じていること。移民問題にしても、「俺はあんたみたいな移民には何の文句もないんだよ」と、配達業の運転手をしている隣人はいう。
ちゃんとここに住んで、家庭を作って生活しているんだから、もう俺らの一部だ。……問題は、金だけ稼ぎに来て荒稼ぎして帰る奴らなんだ。(略)配達業のドライバーなんて、〔EU移民の〕ポーランド人ばっかりだよ。(略)で、英国人はちょっとでも雇用主に文句を言うと解雇される。黙って働く人材はいくらでもいるんだから、反抗的なドライバーはいらないってね。
――じゃあ、当然あなたはハード・ブレグジット〔離脱強行派〕支持だね。
当たり前だろ。そういうつもりで離脱に〔票を〕入れたんじゃなかったとか今さら言っている奴らが信じられない。
そうキッパリいってのけたのに、なぜかこの離脱強行派(右派と目される)支持者は、「親代々の労働党員」であることをやめようとしない。若者たちがどう冷笑しようと、「昔の労働者階級は、地元のフットボール・クラブと労働党への忠誠心が変わらない」「俺たちワーキングクラスには、保守派の奴らにカウンターを張っていくという任務がある」と頑固につぶやきつづけている。
こうした対話をつうじて、それにしても、この「英国労働者階級の人々」の「反逆的で、反権威的で、やけに誇り高い」心性は、いったいどこからきているのだろう、そこが理解できなければ、いまのかれらの屈折した選択のなぞをとくことなどできようわけがないと、みかこ氏は考えはじめたわけですね。そこでたどりついたのが「歴史」の勉強だった。
英国労働者階級は一朝一夕にしてできたものではない。彼らの考え方やアイデンティティ、社会全体が彼らを見る目は、長い歴史の中で生成され、築き上げられてきたものだ。別の言い方をすれば、現在の労働者階級の人々は、長い歴史の結果としてそこにいる。もしもブレグジットが本当に「英国労働者階級の反乱」だったとすれば、それもまた彼らをめぐる長い歴史の果てに起きたことなのだ。
そしてみかこ氏は、ジャスティン・ジェストの『ザ・ニュー・マイノリティ』をはじめとする新しい研究に接近し、その過程でみつけたオックスフォード大学の歴史学者、セリーナ・トッドの『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』という大著を中心に「勉強」を深めてゆく(本や文献はとうぜん英文のもの。でも、さいわいこの本はみすず書房から邦訳がでている。まだ読みはじめたばかりだが、いい本だと思います。――と書いたところで、つい最近、『ザ・ニュー・マイノリティ』の邦訳が弘文堂からでたことを知った。ジャスティン・ゲスト『新たなマイノリティの誕生――声を奪われた白人労働者たち』。こちらもぜひ読みたいけど、うーん、いまの私にそこまでの馬力がのこっているかどうか)。

*
以上、みかこ氏の「学習記録」の詳細は彼女の本で読んでもらうとして、ここでは、なかでもっとも重要と思われる箇所だけを手みじかに紹介しておくと――まず、ここでいう「労働者階級」がイギリスに最初に出現したのは第一次世界大戦を目前にした1910年だったらしい。
この年、イギリス各地で炭鉱に端を発する労働者たちのストライキが続発し、ロンドンでは、サフラジェットと呼ばれる女性参政権運動の武闘派が警察と衝突して血みどろの暴動になった。あわてた自由党政権が翌年、国民保険法(病気と失業)を施行し、その対象に中流・上流階級の家の召使い(当時は労働者のうちで最大の割合をしめていた)がふくまれていたため、かれらのうちに「われわれも労働者なのだ」という自覚がはじめて生じた。「雇用主にとって、召使いはもはや所有物ではなく、彼らの台所や居間にも、労働争議を起こしかねない労働者がいたのである」
このあたりで「人間〔=イギリス人〕の性質が変わった」とヴァージニア・ウルフがいうように、イギリス社会の「主人と召使い、夫と妻、親と子」関係に大きな揺れが生じ、この揺れのなかで1918年に成年男性と30歳以上の一部の女性に選挙権があたえられて、同年の総選挙では労働党が自由党を圧して第二党となり、1920年代半ばに、保守党との二大政党時代が開始される。
しかし、その後も繰りかえし不況や失業の波がおそい、「困窮する北部と裕福な南部」、資産家たちの居住区と「不潔で荒廃したスラム」といった「分断」が、いっそうすすんでゆく。そのイギリス社会をふたたび劇的に変えたのが、第2次世界大戦から戦後の「福祉国家」発足にいたる5年間の体験だったのです。
1940年、ナチス・ドイツの猛攻によって孤立したイギリスが窮地に追いこまれる。その逆境をどたん場で支えたのが労働者階級だった。18歳から41歳までの男性労働者が最前線の戦場でたたかい、のこった者は工場で軍需品・戦車・武器などを黙々とつくりつづけた。女性たちの多くも工場や病院や役所に動員され、政府とメディアは「労働者」を「ザ・ピープル」と呼びかえてハッパをかけつづけた。
でも事実上、と『ザ・ピープル』の著者セリーナ・トッドはいいます。この「ピープル」はたんなる「人々」や「民衆」ではなく「労働者階級」を意味していた。国民の大半を占めているのに、それまでは「二級市民」でしかなかった労働者階級を、はじめて「社会の主役」に押しあげた。それがこの戦争だったというのですね。
そして戦争が終わり、おなじ1945年の総選挙で、イギリスを勝利にみちびいた英雄ウィンストン・チャーチルの保守党が大敗し、クレメント・アトリーを首相とする労働党政権が誕生する。この思いがけない「ちゃぶ台返し」には、戦争期をつうじて実感したじぶんたちの力と誇りを、ふたたび「保守党の奴ら」にうばわれまいとする人びとの、「こんな国だったらいいのにな」という「ささやかな願い」があった。そして「すごい」のは、この「〔人々の〕願いが乗り移ったかのような政治家たち」が登場し、それを「次々と形にしていったことである」とみかこ氏はいう。
アトリーを先頭に、これらの知力と実行力をあわせもつ政治家たちは、戦時中、必要にせまられて生まれた完全雇用や配給制をさらに維持し、そこに強化された社会保障政策(医療、教育、住居、国民保険など)を加えて、「ゆりかごから墓場まで」という福祉国家のビジョンをかかげ、それを着々と実現していった。
こうした政治家のひとりに保険と住宅問題を大臣として担当したアナイリン・ベヴァンがいる。かれは「それまではトイレも浴室もない薄暗いスラムの部屋で暮らしていた人々」に、「通気性がよく、明るく、バスルームがあって、断熱が施された、でき得る限りの最良の住宅」を与えようと粘りに粘った。
また、一軒ずつの住宅だけではなく、図書館、博物館、体育館や学校など、総合的な街のデザインを視野に入れた文化的なニュータウン・プロジェクトが、英国のあちこちで進められた。ベヴァンがウィリアム・モリスの言葉を何度も復唱して吃音症を克服したのは有名な話だが、プロレタリアートを解放し、生活と芸術の一致を果たさねばならないと言ったモリスをベヴァンは敬愛していた。ベヴァンは労働者たちに住む場所を与えるだけでなく、健康で文化的なライフスタイルを提供したかったのだ。
なるほど、それでわかったぞ。この「ちゃぶ台返し」をもたらした力――私が好きな『麦の穂をゆらす風』や『わたしは、ダニエル・ブレイク』の映画監督ケン・ローチがいうところの「一九四五年のスピリット」の背景には、私が気づかなかったというだけの話で、ウィリアム・モリスをもまきこんで延々とつづけられてきた歴史の蓄積があったのですね。
そして、このモリスの夢を敬愛する福祉国家の実現(人びとの「ささやかな願い」を政府や地方自治体や労働組合がささえる)をあきらめない運動が、いまも辛うじてつづいている。みかこ氏がいう「英国労働者階級の人々」の「反逆的で、反権威的で、やけに誇り高い」心性(アメリカやロシアや中国、もちろん私が体験してきた戦後の日本ともちがう)も、どうやらそのなかでかたちづくられてきたものらしい。なにしろ、ブレイディ一家が暮らすブライトンの公営住宅地だけでなく、みかこ氏が保育士として働いていた託児所も、いま息子が通っている公立中学も、もとはといえば、べヴァンたちが構想した「ニュータウン・プロジェクト」の産物だったのですから。
ところが、1951年に政権をとりもどした保守党のもとで、日本でいえば高度経済成長期にあたる「消費と分割払い」の時代にはいると、夢のなかみも変質し、「労働者階級の結束」も「戦後の数年間のような強固さ」を徐々に失ってしまう。そして70年代には、またしても悪化する経済不況のなかで、労働党政権下での福祉国家政策こそがその元凶なのだという空気が生じ、やがてそれが1979年から90年にかけてのマーガレット・サッチャーの長期政権につながっていく。パンクロックに入れあげたみかこ氏が高校をでてロンドンに渡ったのが1983年、結婚してブライトンに移ったのが96年ですから、その前半がこのサッチャー時代だったことになります。
*
――これからは「社会や国に依存せず、個人が自分の努力と能力で成功を勝ち取る時代」だ。もはや「地方自治体と労働組合は(略)庶民の自由を脅かしている諸悪の根源」にすぎない。
サッチャーはそういいはなって、「小さな政府」による緊縮財政(支出を削りに削って国家財政を再建する)に走った。つまり「一九四五年のスピリット」とは真逆のちゃぶ台返し。でも「国民みんな平等に貧しくなりましょう」という彼女の呼びかけに反して、実際に「貧しくなっていったのは労働者階級だけだった」
しかも賃金が大幅に減り、失業者が増えただけでなく、戦後、かれらの暮らしを支えてきた福祉社会のしくみも、それこそ「諸悪の根源」として、あからさまなしかたで解体されてゆく。そして、このグローバル化された自由主義経済とむすびついた緊縮財政がサッチャー以後もつづき、そのため個人の暮らしだけでなく、人びとが生活する地域(コミュニティ)のありようまでが崩れはじめ、EU移民の急増、さらにはイギリス連合王国を形成するスコットランド、ウェールズ、北アイルランドとの関係悪化までがかさなって、イギリスの「ブロークン・ブリテン(ぶっ壊れた英国)」化がすすむ。この過程を、みかこ氏はたまたま身をもって体験してしまったわけですね。
ただし、みかこ氏の体験はほかの日本人観察者とはちがう、いくつもの複合する視点をもっていた。パンクロック、託児所、地方都市の労働者コミュニティの3つの体験がそれ。さらに日本人移民の女とアイルランド移民2世の男とその息子との家庭がそこにかさなる。
夜中に酒を飲みながらやかましい音楽を聴いていると、隣の部屋で寝ている息子が起き上がってきて生徒会長風に説教を垂れやがるので(「眠れないので時間をわきまえてほしい」とか「酒量を減らして良識ある大人になってくれ」とか)(中略)でもティーンになったら必ずどこかで道を踏み外すなと思って、そのときが訪れるのをわたしはワクワクしながら待っている。
(『花の命はノー・フューチャー』)
ブレイディみかこ『花の命はノーフューチャー』ちくま文庫
そんなアナーキー「かあちゃん」がとつぜん歴史の勉強をはじめ、かつて彼女がのめりこんだセックス・ピストルズたちのパンクロックが、はるか昔、1950年代後半から60年代にかけて、ジョン・オズボーンの戯曲『怒りを込めて振り返れ』の衝撃にはじまり、演劇、小説、映画、音楽など、あらゆる領域にひろがった「労働者階級のニュージェネレーション」によるイギリス文化の「一大革命」につらなるものであったことに、ハッと気づく。ほんとに「とつぜん」とか「ハッと」だったのかはわかりませんよ。でも、みかこ氏の「勉強」にはそんな生気がいつもたちこめているのです。
パンクはもとより、かつての演劇や小説や映画でも、その中心には下層階級の「怒れる」不良少年や少女や青年たちがいた。であるからには、いまも身近でみかける「どうしようもない若者たち」にイライラさせられながらも、かれらを冷たく突きはなすことはできないし、したくない。この立ち位置もまた彼女が「勉強」によってみつけた「一九四五年のスピリット」の一面だったのでしょうな。
みかこ氏が保育士としてかかわってきた託児所も、サッチャー以来の緊縮経済によって崩壊寸前にまで追いつめられてしまった。その過程は、私たちも『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)などの彼女の著作によって、なまなましく知ることができる。だがそんな辛い環境におかれても、保育士たちは保育水準の低下をふせごうと懸命に工夫をかさねている。それはいま彼女が母親としてかかわっている公立中学の教師たちもおなじ。なかば絶望しながらも、けっしてあきらめない。しぶとい。つまりは根っこのところで明るい。と、これまでイギリスのような福祉国家で暮らした経験を持たない陰鬱な日本人読者の目には映るのです。
そしてコミュニティ――。
これについてはすでになんどか書いたので、ここでは、さきに紹介した「配達業のドライバー」氏の発言にかぎってもういちど触れておくと、かれはおなじインタビューでこんなふうに語っていた。
俺は英国人とか移民とかいうより、闘わない労働者が嫌いだ。黒人やバングラ系の移民とか、ひと昔前の移民は……この国に骨を埋めるつもりで来たから、組合に入って英国人の労働者と一緒に闘った。でも、EUからの移民は、出稼ぎで来てるだけだから、組合に入らない。
「ひと昔前の移民は……」というかれの昔話にはそれなりの根拠がある。みかこ氏の勉強によると、じじつ、1950年代の労働者階級はまさしく「英国でもっとも早く移民を受け入れた層だった」からです。かれらが住む「貧しい地区」は同時に移民労働者の居住地域でもあり、また「同じ職場で働いていることが多かった」ので、「よそ者たち」ともいつしか「友人としてつきあう」ようになっていた。おなじ組合に属して、いっしょに闘うというようなこともままあったのだとか。
でも、この隣人のことばからもわかるように、往年の労働者たちにあった「寛容性や適応力」は、いまはもうない。しかし環境さえ変われば、それが徐々によみがえる可能性だってないわけではない。おそらくみかこ氏はそうねがっているのだと思う。どれほど絶望的にこんぐらかっていようと、事態は「かならずよくなる」と断定するのではなく、たとえチラッとでも「よくなりうる」と考えるのがオプティミストであるなら、かならずや彼女もそちらの側に属しているのだろう。
*
植草さんやみかこ氏のほかにも、勉強読書の魅力を感じさせてくれる本はいろいろあります。しかし、いまは触れている余裕がないので、それはまたあらためて。
この齢になると、読書によって知識をふやすとか、じぶんの人間性を高めるとかは、どうでもよくなる。教養主義的読書はあくまでも静的だが、勉強読書は動的。そのつど思い立ってあるテーマに熱中し、それが終わるころには、またつぎの勉強がはじまっている。それが正しい読書法だとはいいませんよ。思い返せば、私の読書は以前からそっちのリズムでやってきたし、いまもそう。だから教養というよりは、そのつどの勉強のためにがむしゃらに本を読んでいる人を見るほうが好き。もちろんそれが映画や音楽であってもかまわない。まあ、それだけの話なのかもしれませんがね。
植草甚一『モダン・ジャズのたのしみ』晶文社、1976年
植草甚一『植草甚一自伝』晶文社、1979年
津野海太郎『したくないことはしない 植草甚一の青春』新潮社、2009年
ブレイディみかこ『労働者階級の反乱――地べたから見た英国 EU 離脱』光文社新書、2017年
セリーナ・トッド『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』近藤康裕訳、みすず書房、2016年
ジャスティン・ゲスト『新たなマイノリティの誕生――声を奪われた白人労働者たち』吉田徹・西山隆行・石神圭子・河村真実訳、弘文堂、2019年
ブレイディみかこ『花の命はノーフューチャー』碧天舎、2005年→ちくま文庫、2017年
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら