白内障手術の結果、裸眼で、つまり眼鏡なしでも新聞が読めるようになった。老眼鏡をかけはじめたのが40歳代の前半だから、ほぼ40年ぶりの快挙ということになる。すでに歯の3分の1はインプラント(人工歯根)になっているので、ハメマラのうちの「ハ」と「メ」はひとまず人工化できたわけだが、でも「マラ」となるとねえ。いまとなっては、そんなもの、もうどうでもいいや。そう思いはするものの、排尿面での悩みもあるからさ、できれば人工化してみたいところだけど、まあ、むりでしょう。しかたない。そこだけは生のまま消えていきますよ。
1月6日(月)
私よりも2歳下だし、かれなら私が死ぬまで元気に書きつづけてくれるにちがいない。そう思って安心していた人が、昨年の夏、ふいにすがたを消した。それを新聞で知った朝のおどろきを思いだし、2020年の最初に読む一冊を、まだ読んでいないかれの本のうちからえらぶことにした。すなわち、
――池内紀著『ヒトラーの時代』中公新書、2019年刊。
1年に7点とか8点とか、「××さん文庫」などと陰口を叩かれるくらい、本をたくさんだす人がいる。私なんか10年に3、4点だすのが精一杯なのに、よくも、あなた、こんなに書けますな。そう思って、たいていは読むのを敬遠させてもらうのだが……。
ただし例外もあって、私の場合、その代表のような人物が池内さんだったのです。1973年刊行の詩集『傀儡師の歌』にはじまり、いまあげた『ヒトラーの時代』まで、かず多い翻訳や絵本や著作集をのぞいても、46年間で128点もの自著をだしている(ウィキペディア調べ)。あらためてそう知って、あきれました。流行作家でもないのに、なぜこれほど。そして、それ以上におどろいたのが、あきれたはずの私がその半数以上をまめに読みつづけていたこと。しかも、どれも渋みのきいた軽快なユーモアを楽しみながら。
なかでも、1985年刊の『闇にひとつ炬火あり』というカール・クラウス伝にはじまり、間をおいてポツポツと書きつがれた一連の評伝ふうエッセイが好きだったな。『モーツアルトとは何か』『ちいさなカフカ』『ゲーテさんこんばんは』『カフカの生涯』『カント先生の散歩』『闘う文豪とナチス・ドイツ』など。『闘う文豪……』ではトーマス・マンの亡命の日々を追い、それがまっすぐ『ヒトラーの時代』につながっていった。
したがって、これまで大いに楽しませてもらった池内さんの語り口をもういちど楽しみたい。いうまでもなく、それがこんど年始めの読書に『ヒトラーの時代』をえらんだ第一の理由だったのですが、それだけではない。そこには同時に、イスラーム研究者の池内恵に「書き手としての父・池内紀の死」(『中央公論』2019年11月号)という一文のあることを知って、近所の図書館でさがして読み、氏の父上と同年輩の「書き手」のひとりとして切ない衝撃をうけたという、もうひとつの理由があった。いや、あんがい、そっちの理由のほうが大きかったのかもしれないぞ。
では、なぜ私は恵氏の文章にそれほどの衝撃をうけたのだろう。つまるところ息子の目に映った老父の日常が、おなじ年ごろの私が思い浮かべる池内さんの老いっぷりと、あまりにもかけはなれていたのです。
ここ数年、肉体の衰えと、それに伴う知力の低下を強く感じるようになった父は、自信に満ち溢れていた頃を知る者にとって信じがたいような弱音を吐くようになった。(略)自らの衰弱の実感と死の予感に、父は心底恐れ慄いていた。老いと死への準備を軽妙に語ってみせ、それなりの読者の反応を得てもなお、自らの恐怖を払拭するに十分ではなかっただろう。
恵氏のいう「老いと死への準備を軽妙に語ってみせ……」とは、おそらく、2017年に毎日新聞出版からでた『すごいトシヨリBOOK』をさすものと思われる。私も以前、この本に登場する「赤い明るい」衣類を L.L.Bean で買いもとめる紀氏のすがたに触れ、「老人のありようが、前世紀の70年代あたりから徐々に変化しはじめ、ついに現在にいたった。その新老人のはしりが私たち」なのだろう、と書いたおぼえがある(連載13回を参照)。
ところが実際には、老いによる衰弱の進行を容赦なく裏づけるように、『ヒトラーの時代』の記述に少なからぬ事実のまちがいがあることを、インターネットで複数の研究者に指摘されてしまう。それにしても最後の著書がなぜ「これまでになく瑕疵の多いもの」になったのか。「死が迫り来るのを感じた時に、書き手としての人生の意味や結論を、性急に求めようとしたのだろうか」と恵氏はのべている。
〔これらの〕指摘を、父は深刻に受け止めていたことが、残されたやりとりから明瞭である。自らの衰えの惨憺たる結果に狼狽し、愕然とし、失望に沈んだ時期が、七月末から八月の前半にかけてあったようである。すでに一日の多くの時間、生命を維持し、肉体の苦痛に耐えることが主要な営みになっていたはずだが、可能な限りの訂正をまとめ、ついぞ理解しようとしなかったインターネットというものへの掲載に託した。
いそいでしらべると、発行元の中央公論新社のウェブサイトに、67項目からなる詳細な訂正表の掲載されているのが見つかった。これがきっと恵氏いうところの「可能な限りの訂正」なのでしょうな。
そこに「2019/08/23」という日付が付されている。池内さんがなくなったのが8月30日だから、その1週間まえ。したがって、さらにそのまえ、「七月末から八月の前半にかけて」と恵氏が書いている時期に、池内さんは「狼狽し、愕然とし、失望に沈」む一方で、最期の力をふりしぼって、編集者とともに、この訂正表づくりにつとめていたことになる。
いまそう書いて、もしもこれが私だったらと考えた。
もし仮にいまの私が池内さんとおなじ境遇におかれたとして、はたして私に、これほど息苦しい作業をここまでやりぬく気力があるかしらん。たぶんない。そこに行くまえに、あっさりあきらめてしまいそうな気がする。でも池内さんは「やる」と決め、みずからの生涯のギリギリのどたん場で、この困難な仕事をなしとげることができた。土俵ぎわでの粘りに自信のない私としては、お見事、と嘆息せざるをえない。さすがですな、池内さん。
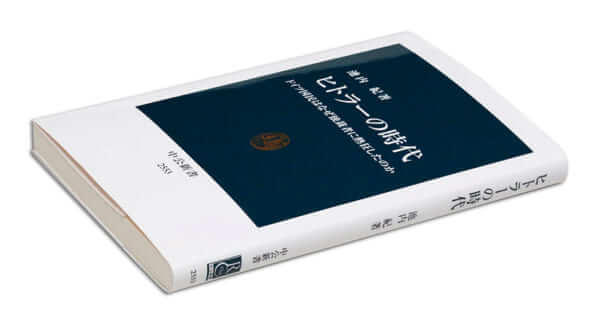
1月10日(金)
あれから4日たつのに、まだ池内さんのことを考えている。さきの一文で恵氏が以下のようにしるしていた。そのことが気になっていたのです。
〔『ヒトラーの時代』では〕制度や事実に関する平板な記述や因果関係の論述が続き、それらが精彩を欠き、不正確なところが多い。生硬な論理で単調に善悪や原因結果を論じるのは、元気な頃の池内紀が、小憎らしいほど軽やかに避けてみせるものだった。
あるいはまた――。
ヒトラーになぜドイツ人が熱狂したかを解明することが、あたかも自らのライフワークであったかのように本人は記しているが、私は信じていない。そのような問題意識も論理も、父が若く元気だった頃には聞いたことがない。
まず前者についてだが、ざんねんながら、この点では私も恵氏に同意するしかない。
私の好きな小伝シリーズでいうと、2017年の初秋、つまり先の『すごいトシヨリBOOK』とおなじ年に、発売されたばかりの『闘う文豪とナチス・ドイツ』を読み、いつもの「軽快なユーモア」がうすれ、池内さんらしからぬ「制度や事実に関する平板な記述」にとってかわられているのにとまどって、「おや、もしかしたら」とはじめて感じた。
でも、いま思うと、あのときはまだ、さほど深刻には考えていなかったな。しかし、こんど『ヒトラーの時代』の、とくにその後半で、まったく同一の記述が繰りかえしでてくるのに接し、「80歳を目前に、私同様、池内さんの頭脳もいつしかここまで老いていたのか」と認めるほかなくなった。「私同様」というのは、このところ出版社の校閲の方々に、じぶんでも信じられないような原稿のまちがいを指摘されることが、とみに増えていたからです。
ことわるまでもなく、いま書いているこの原稿も例外ではない。
毎月、書き終えた原稿データをメールに添付して編集部に送ると、10日ほどのちに、あきらかなまちがいはもとより、もしかしたらまちがいかもしれない箇所までふくめて、ことこまかく別色で指摘したデータ(むかしでいう組版ゲラ)が送りもどされてくる。誤字脱字にはじまり、人名や地名や年代などのファクトチェックまで、ハンパな量ではない。近年の私の場合でいえば、岩波書店も本の雑誌社も、もちろん新潮社も、その校閲のきびしさたるや、「まいったな。もう勘弁しておくれよ」と泣きを入れたくなるほどなのだ。
しかし、このきびしさに耐えなければ、生来のせっかち癖のまま年老いた私のような人間に、まともな本をだすことなどできようわけがない。ていどの差はあれ、それは池内さんも同様だったにちがいない。なのにかれは『ヒトラーの時代』の草稿を、調査がすすむにつれて思いついた断片を、そのつど「下書き」として知人のブログに掲載し、それを大いそぎで編集するというしかたで完成させようとした。そうあとがきでしるしている。
そこだけ読むと、池内さんが日ごろ、インターネットをごく普通に活用していたように思えるのだけど、とんでもない。恵氏によると、もともとかれの父はテレビや携帯電話とさえ無縁に暮らしていたらしいのだ。であるからには、おそらく、
……ブログという媒体が、これまで父が寄稿してきた雑誌とは異なり、(略)事実関係や表記の細部の正確さを期す作業の全てが書き手に課されていることも、父は理解していなかったか、あえて理解しなかったのだろう。その判断もまた、老いのなせる業である。
テキストを紙にしっかり印刷(=定着)する雑誌とちがって、印刷を前提としないブログには、通常、そばにいて書き手を支えてくれる専門の編集者や校閲者は存在しない。いきおい、どんなに滑稽な勘ちがいをしても、すべては書き手ひとりの責任ということになってしまう。
そうしたルールに慣れないまま、書きとばしのブログ草稿(池内さんのいう下書き)から本をつくる作業にとりかかって、池内さんは(たぶん新書編集者も)そのあまりのやっかいさに押し負けてしまったのだろう。そして、そこにはさらに、重い病ゆえの、「自分の能力の有効期間が尽きかけている。もう猶予はできない」(あとがき)という切迫した事情がかさなっていた。
となると、
――つらいね。でも人ごとではないぞ。
元編集者で、池内さん同様に年老いた書き手でもある私は、観察するのではなくされる側に身をおいて、どうしてもそう感じてしまうのです。
そしてもうひとつ、「父」はこの本を「ライフワーク」と考えていたというが、「私は信じていない」という恵氏の言明について――。
恵氏が「ライフワーク」というのは、おそらく池内さんが、この本のあとがきをこんなふうにはじめていたからだろう。
ヒトラーをめぐって、ささやかな本にした。政治家デビューから独裁者として人気絶頂にあった頃を扱っている。一九二五年から三九年にかけての一五年たらずにあたる。その年月にかぎったのは、まさに書きたかった時代であるからだ。(略)
とりかかったのは三年ほど前だが、とりかかるまでに長い「前史」というものがあった。「ドイツ文学者」として身すぎ世すぎをしているあいだ、たえず気にかかっていた。
じじつ、おなじあとがきにあるように、池内さんは、カール・クラウスにはじまり、ナチス時代を生きたヨーゼフ・ロートやジャン・アメリーやフランツ・カフカにいたるユダヤ人作家たちに並々ならぬ関心をいだき、かれらの作品を翻訳しつづけた。
――あの奇っ怪な「ヒトラーの時代」とは、いったいなんであったのだろうか。
その問いにじぶんなりの答えをだす。それはこの時代にじぶんが「選んだ〔ドイツ文学者という〕生き方の必然のなりゆき」なのだ。そう考えて私は生きてきた。――それが「長い『前史』」と池内氏が書いていることの中身だったのだと思う。
そして、その「前史」には、さらにその前史があった。
ここで池内さんは「ドイツ文学者」という語に、しばしばカギ括弧をつけている。おそらく池内さんとかぎらず、戦後になってドイツ文学を専門としてえらんだ若者たちには、じぶんが「ドイツ文学者」を名乗ることに意識過剰にならざるをえない事情があったのだろう。あけすけにいってしまえば、かれらの教師や先輩にあたる人びとの多くが、戦前戦中に、とつぜん「ナチス文学」の熱烈な賛美者に変貌してしまったこと。この「ドイツ文学者」という語には、そうした過去の重苦しい記憶がいやもおうもなく染みついていたのです。
これはたんなる推測ではない。
――1933年、ゲッベルスを長とする情報宣伝省の若手職員が書いた『鉤十字の下の小さな鼓手』という少年向け物語が刊行され、それを手はじめに、『ヒトラーの旗』『血と名誉』『鉤十字の行進』といったナチス賛美の安っぽい読物が市場にあふれた。それが「ナチス文学」である。
と、そのように説明した上で、「ついでながらつけ加えておくと、これらのキワ物のかなりが日本にお目見えした」と、池内さんは『ヒトラーの時代』で書いている。「戦後は民主的文化人として知られたドイツ文学者たちが、戦中はナチス・ドイツに入れあげて、せっせと訳していたからである」
――ああ、そういえば。
あらためて思いだしました。小学生のころ、私は『エーミールと探偵たち』『ふたりのロッテ』『点子ちゃんとアントン』などの本を読んで、はじめてエーリヒ・ケストナーという作家を知り、そのファンになった。これらの本の表紙には、のちに読んだ『飛ぶ教室』や『わたしが子どもだったころ』もふくめて、高橋健二という翻訳者の名が刷られていた。そして、それからかなりの時間がたち、もう大学はでていたかな、なにかの機会に、その人物が戦時下の日本で「ナチス文学」の公的な賛美者として活動していたことを知った。
おどろきましたよ。
だって、そうでしょうが。ケストナーはユダヤ人だったけれども、あまりにも人気があったため追放をのがれ、ナチス独裁下のドイツで苦しい生活をしいられた。そのケストナーの作品を、あろうことか、かつて「ナチス文学」の賛美者だった(そして大政翼賛会の文化厚生部長でもあった)高名なドイツ文学者が、そんな過去などまったくなかったかのように平然と訳していたというのだから。
そうと知って、なんだか裏切られたような気がした。そう、問題の高橋健二訳があまりにもすばらしかっただけにね。おかげで大好きなケストナーの作品がすなおに楽しめなくなってしまった。
しかし21世紀にはいるや、新世代のドイツ文学者たちの手で新しい翻訳がつぎつぎに刊行され、ようやく私も『飛ぶ教室』や『エーミールと探偵たち』を、池内紀や丘沢静也や池田香代子訳で気軽に読めるようになった。ほっとしましたよ。あとは私が元気でいるあいだに、いちばん好きだった『わたしが子どもだったころ』の新訳がでてくれれば、いうことないのですがね……。
こうした経験があったので、私にも、かねてからヒトラーが「独裁者として人気絶頂にあった頃」のことを書きたいと思っていた、という池内さんの気持ちがわかるような気がするのです。
そして現在、世界の多くの国に大小の独裁者が出現し、ヒトラーはラジオだったが、こんどはインターネットで、人びとの偏狭な愛国心をあおり、よそ者や異なった考えの人たちへの憎悪をかきたてる、むきだしのプロパガンダを展開している。独裁者に熱狂する「人びと」はなにも大衆だけではない。そこにはかつての「ドイツ文学者」のようなエリート知識人もふくまれる。おそらくはその「おそれ」が病床にあるかれをつきうごかしたのでしょうな。
ただし、もし21世紀の世界がこれほど急激に悪化しなければ、池内さんも、「あの時代、なぜドイツ人はあんなにもヒトラーに熱狂したのか」――そのなぞを解明するというしかたで、かれの最後の本を書くことはなかったかもしれない。私にしても、こんな先行き不明な世界のただなかでじぶんが消えていくことになるとは予想もしていなかったのだから。その意味では、こんな「ライフワーク」など本当は書きたくなかったのだよ、というのが池内さんの本音だったのかもしれないのです。
1月18日(土)
目が見えない人たちは日ごろ、どんなふうに暮らしているのだろうか。若いころ、そのことに関心をもって全盲の詩人エロシェンコの本を読んだりしたことは、すでに書いた。
でも十分腑に落ちる答えにはめぐり会えないまま長い時間がたち、一昨年、美学者・伊藤亜紗の『目の見えない人は世界をどう見ているのか』という本と出会い、「ははァ、そういうことなのか」と、うなずきながら読みおえた。その伊藤さんが昨年九月、『記憶する体』という新著をだしていたと知り、すぐに町の書店で買って、これまた大いに感心させられた。思わず「この1年に読んだ本でいちばん」といってしまいたくなるくらい。
――ほほう、どこに感心したの?
――どこといわれてもね、説明はなかなかむずかしいから、じぶんで読んでみてよ。
とりあえず頭のなかでそう答えてはみたが、じつは、こうした場面で逃げることなく「むずかしさ」と正面から向き合い、やがてその壁をじわじわと崩していくプロセスこそが、この本の読みどころなのです。

この本で語られる「むずかしさ」とは、「視覚障害」だけでなく「四肢切断、麻痺、吃音、難病、二分脊椎症などと呼ばれる、さまざまな障害を持っている」12人の人たちが、日々、どのように社会とかかわって生きているのか、その方法や技術をひとつひとつ、だれにでも通じる平明なコトバで具体的に説明してゆく――その作業が、どれほどの観察力や知力や想像力を、そしてなによりも、向かい合った「障害を持つ人」と互いに親和する力を必要とするかを指している。
たとえば――。
この本の冒頭に登場する西島玲那さんは19歳で完全に失明した。街の喫茶店でインタビューのために彼女と会い、いろいろ話をしながら、どの点で「さらに突っ込んで聞こうか」と考えていた伊藤さんは、でもじつは「まったく別のところに気を取られていた」というのですね。
〔それは〕なめらかに動くその手でした。(略)彼女は話しながら、ずっと手元の紙にメモをとっていたのです。(略)
書いているあいだ、玲那さんが指で筆跡を確認することはありませんでした。傍目には、目の見える人がメモを取っているのと何ひとつ変わらない手の動き。(略)
使われているのは、A5サイズに折られた広告の裏紙と、先の少し丸くなった鉛筆。席に通されるなり、(略)かばんからチラシの裏紙の束と鉛筆を取り出したので、ハテナと思っていたのですが、あまりに自然にメモを取り始めたので、思わず質問するタイミングを失っていたのです。
それにしても目の見えない人が、どうすればA5サイズという小さなスペースに「的確に字を置いて」いけるのだろう。もしかしたら動く手の移動距離で位置を確認しているのかも。そう訊いてみたら、「な~んも考えていない」という笑い声が返ってきた。
おまけに書くだけでなく、さっき書いたところにもどって文字や数字を丸で囲ったり、アンダーラインを引いたりしている。どうやら玲那さん(本文での呼ばれかたにしたがって、ここからは「西島」でなく「玲那」としるします)は、じぶんが紙に書いたものを映像としてイメージしているらしい。となると、彼女の「書く」も、「見えていた一〇年前までの習慣」の惰性的な反復ではなく、いまここで「現在形として機能している『書く』」だということになるじゃないの。
私がまず驚いたのはそこでした。全盲であるという生理的な体の条件とパラレルに、記憶として持っている目の見える体が働いている。まさにダブルイメージのように二つの全く異なる身体がそこに重なって見えました。(略)それはまるで一〇年という長さをショートカットして、ふたつの時間が重なったかのような、不思議な感覚でした。
「生理的な体」はさておき、もうひとつの「記憶として持っている目」というのが、ちょっとわかりにくい。というようなとき、伊藤さんが繰りだす説明のための比喩がじつに巧妙なのです。この場合でいえば、「……たとえば口内炎ができたとき」と、すかさず彼女はつけくわえる。
――私たちは、できるだけ痛くないように反対側で食べてみるとか、あまり噛まずに飲み込むとか、いろいろ意識してためしてみる。そして、しだいにそのコツをつかみ、そのうちに意識しないでも「痛まない食べ方」ができるようになる。場合によっては治ったあと、それがその人の食べ癖になることもある。その癖、つまり無意識化された習慣を、私は、その人が経験によって得た「体のローカリティ=固有性」と呼んでいます……。
したがって、ここでの玲那さんに即していうと、「ふたつの全く異なる体」のうち、全盲という「生理的な体」が彼女の第一の体で、じぶんだけの、すでに意識もしなくなった「体のルール〔法則〕」にしたがって「な~んも考え」ずにメモをとるのが第二の体――伊藤さんがいうところの「記憶する体」にあたる。その二つの体が一つになって目のまえに存在している「不思議な感覚」に、彼女はいつも「圧倒」されていたというのですね。
「いつも」というのは、玲那さんにかぎらず、伊藤さんが出会った「四肢切断、麻痺、吃音、難病、二分脊椎症など」のさまざまな障害をもつ人たちの全員が、若年アルツハイマーの人も、モーレツな幻肢痛に悩む人も、それぞれに独特の「体のルール」をもっていたから。そして、その事実に「圧倒」された伊藤さんが、なかから11のエピソードをえらび、ていねいな対話を重ねてできたのが、この『記憶する体』という本なのです。
障害をもつ人たちが社会や世界とかかわるしかたは一様ではない。めいめいの過去の体験をつうじて、個々の体が(意識する脳と別のところで)獲得してきた生き方のルールによって、異なるしかたで世界や社会と繊細な関係をとりむすんでいる……。
――とうぜんでしょう。そうに決まってるじゃない。
――うん、私だって、できればそういってみたいのだけどね。
でも、なかなかそうはいかんのよ。というのも、これまで私が、目の見えない人はだれもおなじようなしかたで「見ている」のだろうと、ばくぜんと感じていたから。
以前、この連載でふれた「舞台を見るエロシェンコ」にせよ、「テレビを見るシンガーソングライター長谷川きよし」にせよ、かれらの体がもつ、その人にしかない「固有性」には一向に気づかないまま、「目が見えない」という「一般性」だけで理解したつもりになっていた。でも、ちがうんですね。障害があろうとなかろうと、この世界にはおなじ人などひとりもいない。生理的な体と記憶する体とのそれぞれに独特な二重性。なあんだ、その点では、われわれ老人の体だっておなじよ。といったことをもふくめ、伊藤さんの本を読むことで、ようやく私もその当たり前の事実に気づいたのです。
それにしても、私が若かったころ『記憶する体』のような本が身近にあれば、きっとこうはならなかったろうな。
しかし、いまはその気になれば、こんなにいい本がすぐに見つかる。あまりにイヤなことが重なるので、ついカッとなって「時代はどんどん悪くなる」と嘆きたくなるけど、頭を冷やして考えれば、むかしより確実によくなった面だっていくらもある。おかげで私が、というよりも私の生きた時代がもつ鈍感さが大幅に修正される。すこしくやしいけどね、でもうれしい。「長生きしてよかった」とつくづく思うのです。
1月21日(火)
ここまで書いて、ひとまず『記憶する体』の読書メモを脇におき、つぎの本に移ろうと思っていたら、けさ読んだ朝日新聞の一面コラム「折々のことば」で、鷲田清一がヴァージニア・ウルフのこんな「ことば」を引いていた。
限りなく目につきにくいこういう生涯のすべてが、まだ記録されていないのよ
そして鷲田さんはこうつづける。
文学は長らく、女性を「男性との関係」という「勝手に色づけされた光」の下でしか描かなかったと、20 世紀前半の英国の作家は言う。いま必要なのは、そうした光の外で、街を行き交う女性たちの無言の経験の集積を、さらには「女性として書きながら、女性であることを忘れた女性」としての自身の知覚を描くことだと。物語体の評論『自分ひとりの部屋』(片山亜紀訳)から。
ここを読んで、私の頭がまた伊藤さんの本に戻ってしまった。で、きょうもそのつづきです。
このコラムでの「女性」を「障害を持つ人たち」に、さらに「文学」を「学問」に置き換えると、『記憶する体』の著者が、これとよく似たしかたで考えているらしいことがわかる。そうか、伊藤さんは「街を行き交う障害を持った人たちの無言の経験の集積」を、障害を持たない「自身の知覚」を「記録」することで、まるごと読者に伝えようとしているのだな。そして、そのためにはこれまでの「学問」という「光の外」に、一歩でも二歩でも、じぶんから思い切って踏みだす度胸がいるのだろう、ともね。
興味深いのは、伊藤さんが「光の外」に踏みだすにあたって、「文学」を、より限定していえば「小説」というジャンプ台を必要としていたということ。それは彼女がこの本で以下のことをやろうと決めていたからです。
1.玲那さんたち障害をもった「この体やあの体の〔無言の〕ローカル・ルール」を、だれにも理解可能な(伊藤さんの側からいえば説明可能な)コトバにしていくこと。
2.と同時に、それぞれの体の「他には代えがたいローカリティ=固有性」が、長い時間をかけて、どのようにかたちづくられてきたかを解明すること。
でも、はたしてこの作業が従来どおりの研究者の論文作法でやりおおせるだろうか。むずかしいと伊藤さんは考え、そこで思いついたのが「小説」のもつ力だった。そうした次第で、この本のプロローグに、さっそく、さきの玲那さんとの初対面の場面がハツラツと出現することになる。すなわち、待ち合わせ場所に現れた彼女は「信じられないくらい大量の荷物を抱えてい」たというのだ。
まず背中にはアウトドアブランドのごついリュックを背負っていました。さらに肩からパンパンに膨らんだショルダーバッグを斜めに掛け、脇にはなぜか大きなクマのぬいぐるみを抱えていました。加えて彼女は全盲なので、大きな盲導犬を連れています。今思えば、インタビューに答えるために、いろいろなものを用意してきてくれていたのです。
しかも彼女は、そんな大荷物とは不釣り合いなガーリーなファッションに身を包んでいました。水色のふんわりしたブラウスにギンガムチェックのスカート、髪は背中の真ん中まであるロングヘアです。第一印象は、「不思議の国のアリスが家出してきたところ」でした。
従来の論文作法にしたがえば、こうした具体的な描写(小説的記述)は、ノイズとして自動的に省かれてしまう。でも玲那さんの体の「固有性」と、その来歴をあきらかにしたいと思えば、この種の記述がどうしても必要になる。なんといっても、「生の体が持つ情報量」には「ものすごいもの」があるのだから。
たとえば、白杖や盲導犬にたよる全盲の人には「たくさんの物を持って移動することを嫌う」傾向がある。なのに玲那さんは、そうした「見えない人の常識」をまったく気にかけようとしない。ふしぎだ。「この人の中にあるいったいどんな論理が、この『家出アリス』状態をOKと認めているのか?」――いったん、そのふしぎさへの抑えがたい「興味」に背を押されてしまったからには、こうした小説的記述をはなれて探求をすすめることなどできるわけがない。
――と思いはするのだけど、ほんとにそれでいいのかしらん。
〔たしかに〕小説ならば、こうした固有性についてダイレクトに語ることができるでしょう。
ですが、学問となるとそうはいきません。哲学にせよ認知科学にせよ生理学にせよ、科学であるかぎり、普遍性のある合理的な記述を目指します。「目の見えない人の研究」や「吃音のある人の研究」はできても、具体的な「○○さんの研究」は、よっぽど特権的な例でないかぎり学問にならないのです。(略)
けれども、身体の研究として、それだけでは何だか半分な気がする。小説になるギリギリ手前で踏ん張りながら、その体をその体たらしめているパターンのようなものについて、あの「固有性の圧倒」について、科学として扱うことができないものか……。そんなもやもやをずっと感じていました。
本書は、この「もやもや」に対して、私なりに答えをだそうとした本です。
伊藤亜紗は東大大学院の博士課程(美学専攻)をへて、いまは東工大科学技術創成研究院の准教授。したがって「普遍性のある合理的な記述」という学問(科学)のルールになじんでいるし、その重要性も十分にこころえている。
ただし「普遍性」を高めるには、個々の、具体的な「固有性」をまとめて抽象化するレベルを、たえず上げていかねばならない。そして、抽象度がすすむにつれて見えにくくなる「固有性」――つまり「街を行き交う人たちの無言の経験」につよい光をあてる。それが小説の技法なわけですね。かくして伊藤さんは、「障害を持つ人たち」とのつきあいを重ねるうちに、かれらの「圧倒」的な存在感を理解するには抽象化だけでは足りない、ならば思い切って小説の力を借りてみたらどうか、と考えるようになった。
もちろん研究者であることをやめ、小説家やノンフィクション作家になるわけではない。障害のある人たちとの出会いのなかで、研究者であるじぶんが何度となく体験した「固有性の圧倒」から出発し、その体験をノイズとして切り捨てずにすむ方向での抽象化をめざす。そういう道もあるのではないか。ないと困る。でも、もしかしたらないかもしれない――といった「もやもや」した手さぐりから生まれたのが、この「記憶する体」という仮説だった。おそらくそういうことだったのではないかと思います。
しかも、この「もやもや」をなんとか突破しなければという意欲は、かならずしも伊藤亜紗だけのものではない。これまでの大学制度が行きづまるなか、学問の諸領域で、このままでは未来がないと思いさだめた若い研究者たちが、大学の内と外とを大胆に往来し、生の「固有性」を切り捨てない学問の可能性をさぐる動きがめだつようになった。
若いというのは私から見てという意味ですよ。だいたいは30代から40代の、私から見れば孫の世代にあたる人たち。かれらに共通するのは、私の世代はもとより、それにつづく世代の知識人にも付きまとっていたエリート秀才臭がうすく、そのかわりに「街を行き交う人たち」と対話する柔軟な力をごく自然に身につけていること。そのため、この人たちの仕事ぶり(本を読んで考えるだけでなく、じつによく動く)が、ことのほか新鮮に感じられる。あえて大げさにいってしまえば、
――ここにいたって、この国の知識人の気風がやっと変わりはじめたみたい。
そう私には感じられるのだが、どう思いますかと、若い方々はともあれ、まずは長い戦後をともに生きてきた同輩のご老人諸氏にそうたずねてみたい。そんな気がしているのです。
*
せっかく「かれが最後に書いた本」というタイトルを思いついたのに、書くにつれて一日分の記述が長くなり、予定していたもう一冊の最後の本、加藤典洋の『大きな字で書くこと』にふれる余裕がなくなった。気をぬくと、思わず知らず文章が「評論」ふうになってしまう。どうやらこれが私の「体のローカリティ=固有性」であるらしいや。
おかげで肩から力をぬいた文章がさらっと書けない。だから「随筆」が苦手。そう思いこんでいた私が、ほかならぬ『最後の読書』で、読売文学賞「随筆・紀行」部門の賞をいただくことになった。もちろんうれしいのですよ。でもその一方で、「ええっ、ほんとに私でいいの」ととまどってもいる。そういえば、おなじような揺れが加藤さんの最後の本にも感じられるようだ、とひとこと。あとはまたあらためて。
池内紀『闘う文豪とナチス・ドイツ トーマス・マンの亡命日記』中公新書 2017
池内恵「書き手としての父・池内紀の死」『中央公論』2019年11月号
伊藤亜紗『記憶する体』春秋社、2019年
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








