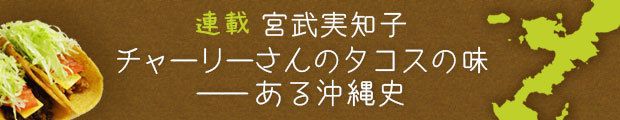(前回までのあらすじ)
「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。沖縄戦の生き残りでもある。「幸運」にも生き残れた理由は、砲兵ではなく通信兵に配属されたこと、そして早期に負傷したことだった。
4月1日の沖縄本島上陸から10日頃までの死傷者は、実は日本軍より米軍のほうが多い。日本軍の陣地網は巧妙で、ほどなく戦線は膠着。米軍は部隊の再編成をおこない、最初の総攻撃を準備した。米軍の攻撃準備を確認していた日本軍も、防備の強化と再配置をおこなった。
そして、4月19日午前6時、米軍は前進準備の砲撃を開始。火砲324門が同時に火を噴き、40分間で約1万9千発の砲弾を撃ち込んだ。戦艦・巡洋艦・駆逐艦18隻が艦砲射撃で加わり、650機の航空機がナパーム弾やロケット弾を投下して機銃掃射を行なった、と米陸軍の公式戦史は伝える。
まさにその砲撃開始の午前6時、勝田さんは負傷したのである。
先輩のサガワさんと2人、保線作業を終えて中間所へ帰る途中だった。突然、凄まじい轟音とともに土煙をかぶり、前を歩いていたサガワさんがばたりと地に伏した。「迫撃砲だ、サガワさんがやられた!」と思った次の瞬間、右肩に激痛が走り、撃たれたのは自分だと気づいた。血がダラダラと流れた。
近くにあった石部隊(第62師団)の医務室で応急処置を受けた。麻酔なしで傷口から破片を探られるのは、言葉にならない激痛だそうだ。結局、破片の一部が取れずに残り、今もレントゲンには親指ほどの金属片が写る。右腕は1年近くまったく動かせず、10年以上も右を下にして寝ることができなかった。
応急処置の後、南風原の黄金山(くがにやま)にある野戦病院に送られた。最も規模の大きい陸軍病院である。
「病院」なんて名ばかりですよ。我々が宜野座から切った木で枠だけ作って岩盤が落ちないようにして。そこでどんなベッドだか分からんで。1週間は寝たつもりだけど、あまり覚えていないです。何もない。トイレも外で。ご飯も1日に玄米おにぎり2個くらいかな。治療も2日に1回ほどしか受けられない。
総攻撃開始の瞬間に負傷するとは運が悪い。だが結果的には、負傷したことで命を拾ったのである。
*
勝田さんが戦線を離れた後が、本格的な戦闘だった。
4月19日に始まった戦闘は、東の和宇慶(わうけ)から西の城間(ぐすくま)まで約10キロの全戦線で展開。特に嘉数(かかず)の日本軍は奮戦し、米軍戦車24両を1日で撃滅したこともある。ここの戦闘を支援したのも勝田さんのいた野戦重砲兵第23連隊だ。
やがて、第一線が各地でほころび、防御線の後退が決定された。22日の深夜から翌朝にかけ、最前線は前田・仲間高地に後退、南部に温存されていた部隊も北上して、新しい防御線が固められた。勝田さんの部隊も、観測所を前田から首里の石嶺へ後退させ、最前線となった前田高地の防衛を担った。
前田高地は標高148メートルの丘で、3キロ南の首里を護る壁だ。その戦略的な価値から、米軍は「東京へのスタートライン」と呼んだ。5月10日頃まで続いた攻防戦は、日本軍にとって沖縄戦の関ケ原とも天王山ともいわれる。沖縄学研究の外間守善(ほかま・しゅぜん)はこの時、一兵卒として前田高地で戦ったが、所属大隊800人のうち生き残ったのはわずか29人だったという。
ちなみに、沖縄戦の住民被害を形容して使われることの多い「あらゆる地獄をひとつにまとめたような地獄」というフレーズは、もともとは米軍の兵士が前田高地の頂上をめぐる攻防戦を表現した言葉である。

日本軍が5月4日に決行した総攻撃は失敗し、精鋭部隊の多くと砲弾のほとんどを失った。それでも5月中旬、日本軍の残存兵力を結集させた安里地区(現在のモノレールおもろまち駅周辺)の戦闘は、米軍にとって甚大な被害をもたらした。第6海兵師団は10日間で沖縄戦最多の2662人の死傷者と1289人の「戦闘疲労」(=PTSD)罹患者を出したと記録され、多くの体験記がその凄惨さを綴る。

沖縄戦の戦闘部分は沖縄でもあまり知られていない。米軍上陸と南部撤退後ばかりが有名だが、その間こそが沖縄「戦」だ。日本軍の守りは強固だった。今なら車で15分ほどの距離を2ヶ月近くも防衛したのだから。
米軍が4月19日の攻略目標だった地点まで進出してきたのは、ようやく6月初めになってからだった。
勝田さんが陸軍病院にいた間、次々と前線から重傷患者が運び込まれた。勝田さんのように腕だけ負傷した患者は軽傷の部類に入る。軍医から「足の丈夫な者は原隊へ帰れ」と指示されて、負傷兵はひとり夜中に帰って行った。
1週間、その南風原の陸軍病院におって、それで原隊に帰ったんですが。弾も降る、雨も降る、その中を兵隊も沖縄の方もみんな右往左往で道から溢れているんですよね。そこで、首里の原隊にどうやら着いて、首里のトラズ山(虎瀬山:現在の首里儀保町)の中隊で報告して……。
原隊に復帰しても、戦線に復帰はできない。中隊の医務室で治療を受けて過ごした。やがて、前田が落ち、戦線はまた後退し、中隊の司令部も後退した。「その間、私は医務室におって治療するくらいで、あとは何もできなかったんです。早く傷ついたから助かったんじゃないかな、と今は思っておるんです」。
ある時、ふと気づいた。「私は運が良かった」「生きるも死ぬも運命だ」としきりに強調するのは、後ろめたさなのかもしれない。
勝田さんは自他ともに認める働き者だ。5年前に骨折するまで、80代後半になっても毎日2キロの距離を歩いて通勤し、店に立った。「食事以外で椅子に座ったり、ごろりと寝そべったりしたところを見たことがない」と家族も話す。じっとしているのが嫌いで、子供の頃から働いて体が丈夫なのがご自慢だ。「早く治して働きたい」と車椅子生活になっても嬉しそうに張り切っている。
そんな働き者が、主力兵器を扱う司令部直轄部隊に所属しながら、戦闘の激しいさなか、医務室にいるしかないのは歯痒いことだったろう。
「人の運命は分からない」と勝田さんはよく言う。目の前で多くの人が亡くなるのを見てきた。水汲みから帰った人が陽気な掛け声でバケツを下ろした途端、砲弾で吹っ飛んだ。壕から出た人が「今日は良い天気だ、飛行機もない」と空を見上げた瞬間、額に機銃の直撃を受けた。「もう、その場の死にざまというのはね、……なんとも言えんものです」と、ぽつりと漏らしたことがある。
一昨年、靖国神社の遊就館が勝田さんの体験談を収録しに来たのに立ち会った。最後、インタビュアーは唐突に「みんなに会えたら何と言いたいですか?」と尋ねた。生還者には必ず聞くことにしている質問だという。
勝田さんは、呆気にとられた表情をした。そして長いこと黙りこんだ。ようやく絞り出した声は、途中で涙に詰まった。
「すまない……。すまなかった……と言います」
勝田邸を辞した後、インタビュアーが「みんな、そう言うんです」と言った。
-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら