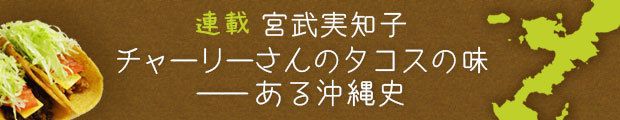(前回までのあらすじ)「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。沖縄戦の生き残りでもある。開戦直後に右腕を負傷して前線を離れ、6月半ばの斬り込み突撃を免除された。
斬り込みに出た人たちと八重瀬で別れ、さらに南へ。摩文仁の断崖に着くと、洞窟や岩陰には多くの住民や兵隊が追い詰められていた。「5000から6000人くらいおったんじゃないかな」と勝田さんは回想する。しばらく海岸沿いに滞在したのは、いかだを作って海路を北上しようと考えたからだそうだ。
今の感覚からするとずいぶん無茶な話に聞こえるが、沖縄戦中、離島奪還や総攻撃の際、くり舟やいかだで敵の占領地域に逆上陸する作戦が成功したこともある。5月30日に糸満を出た航空参謀・神(じん)直道少佐や、6月18日になって摩文仁の海岸を出発した森脇弘二大尉も、地元漁師の協力を得てくり舟で島伝いに奄美へ渡り、東京へ帰還している。

隠れる人々に向け、米軍の掃海艇は拡声器で投降を呼びかける。「みんなで手を挙げて出てきなさい」。勝田さんたちは出なかった。
「やっぱり投降してはいけないという思いがあったんですか?」
「うん、捕まるまでは投降するとかいう考えはなかったですね」
「殺されると思ったからですか?」
「いやいや。結局、なんとか生きられるだろうと思ったんでしょうね」
笑いながら話す勝田さんの当時の楽観は、私には不思議に聞こえる。
やがて一帯への火炎放射が始まった。2日ほどやり過ごしたが、その場に留まってはいずれ焼かれる。観念して、おそらく6月23日の夜、勝田さんは仲間とともに崖を上がった。摩文仁周辺の崖は険しい。飛び降りた人も、誤って落ちた人も多い。そこを200mか300m、よじ登って敵の占領地域に潜り込んだ。
「何をしようとしたのですか?」と問うと、今度は陸路で北へ向かおうとしたらしい。6月19日に下達された最後の軍命令にも、「各部隊は各局地における生存者中の上級者之を指揮し最後迄敢闘」するよう記されている。南部の組織戦が終われば北部の国頭(くにがみ)支隊に合流すべきことは了解していた。
とにかく生きて国頭へ突破しよう。島尻(本島南部)はもう終わりだ。そう勝田さんも考えた。だが、米軍による敗残兵の掃討戦は苛烈なものだった。ようやく「沖縄戦終了宣言」が出たのは7月2日のこと。6月23日の時点では「沖縄戦」はまだ何も終わっていない。
摩文仁の崖を登った勝田さん一行は、もう1人の同年兵と古年兵3人の5名。一晩一晩、八重瀬のあたりを転々とし、穴や物陰のあるところ、食べ物のありそうなところを探し歩いた。
7月の初め頃、5名ほど入れそうな穴に米が残されているのを見つけた。先客が置いて逃げたのか。水たまりの水を汲み、深夜、粥を炊いた。それから1ヶ月ほどそこで暮らし、1日1杯ずつの粥で命を繋いだ。よほど嬉しかったらしく、この話は会うたび毎回のように聞かされる。
食糧が尽きて、また移動。8月、具志頭(ぐしかみ)のあたり、今はサザンリンクスというゴルフ場になった高台から海の近くまで降りると、アダンの木の茂みの奥に隠れられる場所を見つけた。近隣は同じような日本兵が集まる場所で、10数名の別のグループと合流した。
8月末、隣の穴に民間人の姉弟がいることに気づいた。同年兵のマスヤマさんと勝田さんに、内地出身の兵士が「お前たちが一緒に暮らしたらどうか」と提案した。2人は日本兵グループを抜け、その民間人姉弟と4人で暮らし始めた。姉弟はニシヒラと名乗った。姉はひめゆり部隊で有名な女子師範学校の生徒で20歳くらい、弟は2歳下だった。
マスヤマさんは勝田さんと同じ部隊で同じ通信兵の同期、同じ奄美の出身だが京都の学校に在学していたため兵役が免除されており2歳上だった。私は京都と聞いて懐かしくなり「どこの学校ですか?」と勢い込んで尋ねたが、勝田さんは「わからない」と言う。ニシヒラ姉弟についても、なぜ姉弟だけで南部の海沿いにいたのか。やはり勝田さんは「知らない」と言った。
小さな穴で4人、身を寄せ合って潜む。年は近いが境遇の違う者同士、どんなふうに一緒にいるのだろう。互いの身の上や故郷のことを話さないのだろうか。尋ねてみると勝田さんは長いこと考え込み、ぽつぽつと話した。
「話したかもしれんけど、もう覚えてない。生活にゆとりがあると、いろいろ話すかもしれんが。どうして生きるか、もうそれだけでしょう? 食べ物をどうしよう、どうにかして国頭に行こう。それがほとんどですからね」
それでもニシヒラ姉弟には特別な親しみがあるらしい。勝田さんは終戦の5年後、再び沖縄に来た時、真っ先に彼らを探して会いに行った。師範学校を出た姉は教師になり、姉弟2人とも首里で暮らしていた。それから亡くなる少し前まで50年以上、ときどき電話したり会ったりする友人付き合いを続けたそうだ。
結局、勝田さんは3ヶ月以上にわたって南部をさまよったが、壕らしい壕に入ったことは一度もなかった。木の陰や岩穴にばかり潜んでいたという。
日本兵が民間人を壕から追い出した話はよく見聞きする。確かにそんな例もあっただろう。生きるか死ぬかの瀬戸際だ。「自分は彼らより重要な任務を帯びている」と信じる時、人はより残酷になれる。軍人の身分を振りかざして民間人を追い出した者がいたとしても、なんら不思議はない。
長らくそう思っていたのだが、どうも違うらしい。「頼んでも入れてもらえませんよ。こちらもぼろぼろですし」と勝田さんは断言した。誰もが必死だ。「ここはいっぱいだ。よそへ行ってくれ」と民間人でも平気で言う。言われたら日本兵も住民もないそうだ。
司令部の玉砕も知らないまま、まだ多くの兵士が周辺に潜伏していた。
米軍側の戦況報告集には連日の攻防が記される。例えば、6月28日には前夜に殺害した日本兵の数に添えて「斬り込み兵の多くが、武器を持たず」と追記される。米軍の記録に見られる日本兵は、「昼間はキビ畑や草の陰に隠れ、手榴弾以外は何も持たずに北部へ向かうもよう」で、「多くの日本兵が、キビ畑や藪に隠れている」。組織を離れた兵士は無力だった。
余談だが、沖縄戦遺族の援護業務に長く携わった人がこっそり聞かせてくれた話をここでこっそり書いておきたい。なぜ沖縄戦で日本兵へ壕を提供した民間人がこんなに多いのか。「もう時効だろうから」とその人は前置きをした。
沖縄戦では「軍属」となった成人男性だけでなく、老幼婦女子も軍に協力した。避難しきれず戦闘地域で命を落とした人々も多い。そうして大黒柱や将来の希望となる家族を亡くした人たちに、戦後せめて少しでも安楽な暮らしをさせたい。戦場となった沖縄では軍人も民間人もなかったのだ……。1952年、日本の主権回復とほぼ同時にいわゆる援護法(戦傷病者戦没者遺族等援護法)が制定された時、沖縄の政治家や役人たちは考えた。
アメリカ占領下の沖縄から東京へ陳情に通った人々の武勇伝は割愛するが、甲斐あって沖縄にも日本の援護法が適用された。「軍の要請に基づく戦闘参加者」と申請できれば、民間人でも「準軍属」と認定されて遺族は年金を受けられる。厚生省(当時)の役人に沖縄滞在してもらい作業を効率化させつつ、夜な夜な酒宴に連れ出しては無人になった事務所に忍び込んで承認済み書類を研究したと聞く。
そうして得たノウハウで、沖縄中の遺族たちを回って書類の書き方を指導したり代筆したりした。結果、似たような申請書類が量産された。戦闘地域で亡くなっただけでは準軍属にはならない。認定される書類とは「軍からの要請」が明らかで、内容に矛盾のないものだ。「強制・命令による壕の提供」は20項目あった中でも証拠や状況説明が少なくてすむ便利なレトリックだった。
「まぁ、今で言えば公文書偽造なんだがね。一人でも多くの人を救いたい一心で、良かれと思ってのことだった。靖国問題やらなんやらで今こんなに問題になるなんて、あの頃は思いもしなかった」とその人は力なく笑った。
本当に軍人から壕を追い出された民間人もいただろう。ただ、公式記録に残った「軍に壕を追い出されて死亡した人」は実態よりもはるかに多い。
この8月、勝田さんが潜んでいた辺りの山を歩いてみた。

山というより、岩が堆積した地質なのか。あちこちに巨岩が合わさった隙間があり、奥の空間は意外と広い。木の根や灌木で覆われた岩には、数人が座れそうな穴があちこちに開いている。地形が入り組み、ひっそり薄暗い。

潮の匂いがするほど海が近い。木々を透かして見える海には、71年前、水平線が見えないほどアメリカの艦船が停泊し、浜には夥しい死体が打ち上げられていた。夜中に波打ち際を歩く時、波に揺られた死体が足に当たるのを掻き分けるようにして歩いた、と生還者の女性からも聞いたことがある。
沖縄戦末期、陸から海から激しい砲撃を受けた山は今、鬱蒼と草木が生い茂る。花もないのに、たくさんの蝶がふわふわと舞っていた。

-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら