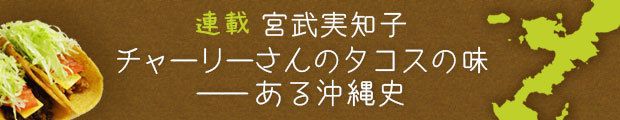(前回までのあらすじ)「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。沖縄戦の生き残りでもある。奄美群島の喜界島に復員できたが、1950年、再び沖縄へ渡ってコザのレストランで働き始めた。
勝田さんがまだM氏の店で修業していた頃、奄美出身者にとって重大な転機が訪れた。奄美群島が軍政下を脱し、沖縄から切り離されて本土復帰を果たしたのである。1953(昭和28)年のことだ。
奄美の復帰運動はすさまじいものだったようだ。
地理的には奄美群島は鹿児島と沖縄本島のちょうど中間に位置するが、歴史的には薩摩との結びつきが深い。島民の帰属意識も日本にある。沖縄本島は、むしろ侵略者であり征服者だった。
にもかかわらず、奄美は「北部琉球」としてアメリカの軍政下に入った。鹿児島との往来や交易が制限され、生活にも経済活動にも支障をきたした。さらに、戦場となった沖縄本島だけに資金が集中され、奄美の復興はないがしろにされているように見えた。本土復帰運動の兆しは、早くも1947年8月からあったようだ。
3年後の1950(昭和25)年11月24日、連合国側の対日講和条約の草案が公開された。「北緯29度以南の琉球列島や小笠原諸島はアメリカ合衆国の信託統治下に置かれる」。奄美の人々は強い危機感に駆られ、復帰運動が急速に広がった。ちょうど勝田さんが喜界島を出た直後のことだ。
翌1951年2月14日、名瀬の市役所で「奄美大島日本復帰協議会」が誕生。奄美群島の各市町村で次々と支部が誕生した。呼応して日本各地でも奄美出身者による「奄美大島日本復帰促進協議会」が結成される。東京では加計呂麻(かけろま)島出身のロシア文学者・昇曙夢(のぼり・しょむ)を委員長とする総本部が発足。以来、内外の奄美人が連携して、実に巧みな運動が展開された。
署名運動がすごい。復帰協議会が結成されて間もなく、奄美群島内の全市町村で実施された署名運動では、4月末までで満14歳以上の住民の99.8%という驚異的な数の署名が集まった。署名簿を積み重ねると3メートル近かったという。本土のNHKラジオニュースにも取り上げられた。
5月、署名簿は東京に届けられた。鹿児島県選出の代議士全員と復帰運動関係者が10日かけて陳情に歩き、6月2日、開会中の衆議院本会議で「切り離されることの危惧される諸島に関する決議案」が可決された。その国会の様子と署名簿の映像を中心に『いつの日ぞ祖国に還る』という映画が作られて全国で上映。驚いたことに、再編集されてアメリカでも上映されたという。
パフォーマンスも過激だった。8月1日午前1時、復帰協議会議長の泉芳朗(ほうろう)が名瀬市内の高千穂神社で120時間の「断食祈願」に入った。昼過ぎから奄美大島の全村、全群島の人々が呼応して次々と断食を開始。大人に混じって小中学生まで進んで参加した。
5日後、水盃を交わした密航復帰陳情団11人が3組に分かれて東京へ向かった。途中で逮捕される者、逮捕されても脱走する者、いろいろありながら8人が東京に到着し、政府や議会関係者、総司令部などを訪問して陳情した。
アメリカ国務省は、署名や断食祈願に奄美の住民感情の爆発をみて衝撃を受けたと言われる。国務省とアメリカ軍部の間での奄美をめぐる激しいせめぎあいは、元・在沖縄米軍海兵隊外交政策部次長ロバート・D・エルドリッヂ氏の『奄美返還と日米関係』に詳しい。
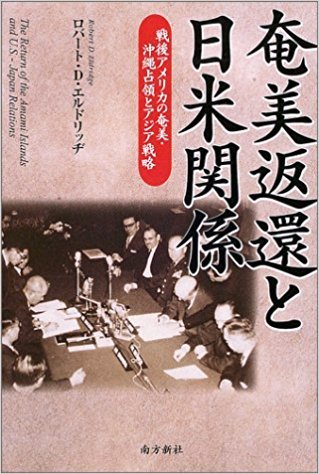
対日講和会議(1951年9月5日開幕)を経て、奄美の復帰運動はさらに過熱。対日講和条約発効の4月28日を復帰協議会では「民族屈辱の日」とすることを決め、第二次の署名運動を展開した。こちらの署名率は99.9%にも達したという。
日本政府も動く。1952年12月25日、第15回国会衆議院本会議は「奄美大島日本復帰に関する決議案」を満場一致で可決した。そのちょうど1年後、正式に奄美群島が返還されたのである。
翌1953年8月8日、韓国の帰りに日本へ立ち寄ったダレス国務長官が記者団に、「アメリカ政府は奄美大島群島を日本に返還する用意がある」と発表(ダレス声明)。報道を聞いた奄美の人々は万歳を連呼し、手を取り合って嬉し涙にくれたという。正式な奄美返還の日は12月25日。アメリカ側は「日本へのクリスマス・プレゼント」と称したそうだ。
その歓喜と興奮は、多くの記録に証言が残る。「奄美の奇跡」と呼ばれ、社会運動史に燦然と輝く「無血革命」の成功だった。領土をめぐる日米外交史のドラマでもある。

だが奄美の本土復帰は、沖縄在住の奄美出身者を窮地に立たせた。
沖縄県の『行政記録』は、急転直下の12月末を淡々とつづる。
24日:布告第27号琉球列島の境界について交付、
12月25日を期して奄美大島を日本に返還決定。
奄美地方庁廃庁式。
25日:奄美大島日本復帰す。大島船舶は外国船扱いとし、
出入手続に関して民政府から指示あり。
26日:泉副主席、池端流銀総裁退任。
30日:在沖奄美大島人の臨時措置指令第15号公布。
(1月中に臨時外人登録のこと)
沖縄で暮らす奄美出身者は、外国人扱いになった。後に沖縄が本土復帰するまでの20年近くにわたり、さまざまな制約や差別を受けたのである。
就労は困難になり、公職についていた人々は追放された。琉球政府の行政副主席や琉球銀行総裁、電電公社総裁といった政界・産業界で上り詰めた人々すら突然の退任に追い込まれた。
『琉球銀行三十五年史』(1985年)は、池畑嶺里の解任をこう記録する。
当時、ちょうど池畑は奄美大島へ出張中だったため、米軍政府は復帰の前日(1953 年12月24日)係官を派遣して、出張先で総裁解任を通告したといわれる。この総裁解任の通告は、当行の理事会に連絡することなく、任命権をもつ米軍政府が独自にとった措置であった。
琉球銀行の経営陣はダレス声明以来、奄美群島の支店や奄美出身者の処遇について検討を重ねていた。だが、米軍は1948年の琉球銀行設立時から株式の51パーセントを保持しており、経営陣の頭越しに一方的に総裁を解任したという。
池畑は銀行設立からの功労者として初代総裁に就任。6年にわたりアメリカ軍政府の政策に協力してインフレを収束させ、通貨や金融機関への住民の信頼を回復し、経済発展に貢献してきた。非凡な能力の人だったといわれる。それが出張先から沖縄本島に戻ることすら許されないまま解任された。
それだけではない。奄美出身者は参政権や土地所有権も奪われた。外国人扱いの一方で、同じ「外国人」だった他の日本国民には認められていた政府税の優遇制度は適用されなかった。つまり、権利はないままに納税の義務だけが課されたのである。
財産保有は禁じられ、銀行融資は停止された。船に乗るのすら納税証明書を持たないと切符が買えない。無職者は強制送還。在留許可証を常に携行せねばならず、持っていなければ警察に捕まり、悪くすれば強制送還である。2年ごとに外人登録を更新せねばならない。公立の琉球大学にも行けなかった。
当時の沖縄では一般に、奄美出身者が沖縄人の雇用機会を奪っているという偏見があった。犯罪者が多いという通説もあったが、この琉銀総裁のように、並外れた優秀さで政府や大企業の上層部にいる人の割合も高かった。とかく沖縄社会で目立つ存在だったようだ。
沖縄の奄美出身者は選択を迫られた。「外国」の沖縄に残るのか、「日本」となった奄美へ帰るのか。
勝田さんを沖縄へ連れてきたM氏は数年たった後、喜界島に帰ると決めた。「一緒に帰ろう」と誘われた勝田さんは「もう少しここで頑張ってみたい」と応えた。
奄美の復帰当時、沖縄本島にいた奄美出身者は5万人とも7万5000人とも言われ、その半数以上が奄美へ帰ったとされる。が、1965年にコザ市議会が行政主席と立法院議長あてに出した「在沖縄奄美人の公民権獲得についての陳情」を見ると、「沖縄に在住する奄美大島人は、永住、半永住許可者で現在約8000人」とあるので、残った人はもっと少なかったのかもしれない。
奄美へ帰った人の多くはその後、鹿児島本土や内地の都会へと流れた。沖縄残留と内地の都市、どちらがより良い生活だったのかは分からない。ともあれ、勝田さんは沖縄に残って「正解」だったと思っているようだ。
本土に行った人と沖縄に来た人はどれだけ差があるかな、と思うのだけど。 まぁ、沖縄に来た私たちはそのほうが良いんじゃないかな。例えば、沖縄に来た人は自分の家を持ったりできたけど、本土に行った人で自分の家を持つ人はあまりいないと思います。アパート暮らしとか、そういうのが多いと思う。本土もその当時は一所懸命に敗戦から立ち上がるところだったから、金の価値が……。本土に行く人はいっぱいいっぱいで、沖縄の人はある程度ゆとりのできる生活とかね、そういう開きがあったと思います。
奄美の本土復帰もまた、勝田さんにとって分岐点だったのだろう。
「こうやって沖縄で根を張って、自分の場所を作り、食文化をひとつ作ってこられたのは本当にすごいことだと思います」と素朴な感想を述べたら、勝田さんは、戦争を語る時の口癖「人それぞれの運」を口にした。
だから、その人その人に運がある、と私は思っているわけよね。もし復帰の時に奄美大島に帰っておったら、こういうこともできなかった。あの時に「よし、もうひと頑張りしよう」と決めて、ずっとここにおったから、根も広げられたと思うんですよね。友達が「一緒に帰ろう」と言ったんだけど、「いや、私はもう少し頑張る」と残ったから今があって。
この会話をした当時、私は沖縄に来て4年目だった。10年目の今でこそ薄れたけれど、ふとした拍子にあれこれ思い出して無性に帰りたくなった。大らかと言われる沖縄だろうが、異民族として永住する覚悟は重い。「もう二度と故郷の街に住むことはない」と思うと寂しかった。
それで、聞いてみた。「その時、帰ろうとは思わなかったんですか? 帰りたいって思いませんでしたか?」 勝田さんは、私の感傷を知ってか知らずか、きっぱり断言した。
いや。ここでまだチャンスがあると考えておったから。……たとえばね、どこ行っても1年生になるよりは、ここで頑張ったものにプラスして何年生かになるならば、その方がいいわけですよね。奄美が復帰した頃、奄美から本土に行く人が多かったんだけど、また向こうへ行って1年生になるよりは、ここに残った方がまだいいんじゃないか、と。いわゆる「継続は力なり」でね、続けるのが何よりもいいことです。途中で止めたらダメですね。
(※2025年2月一部改訂)
-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら