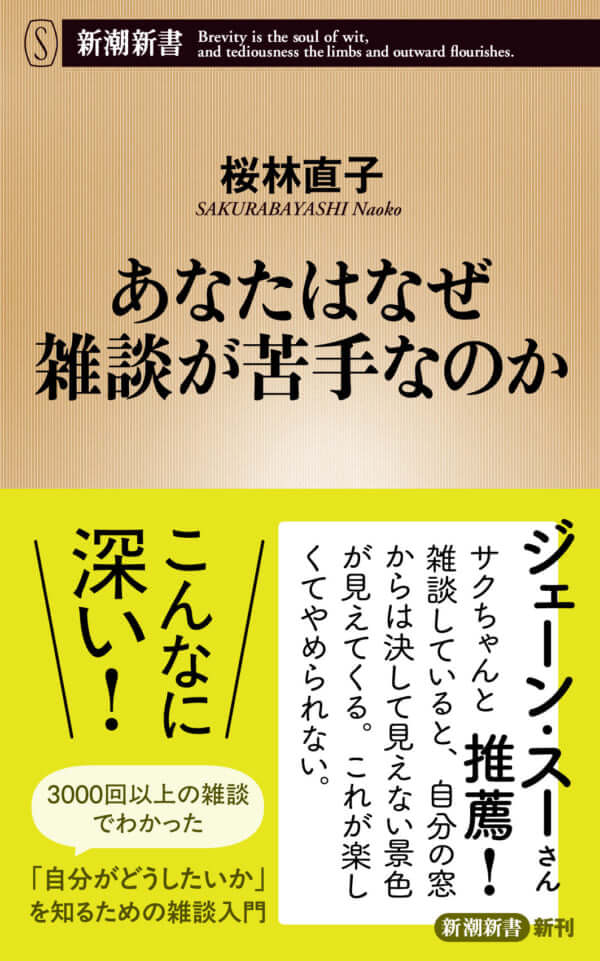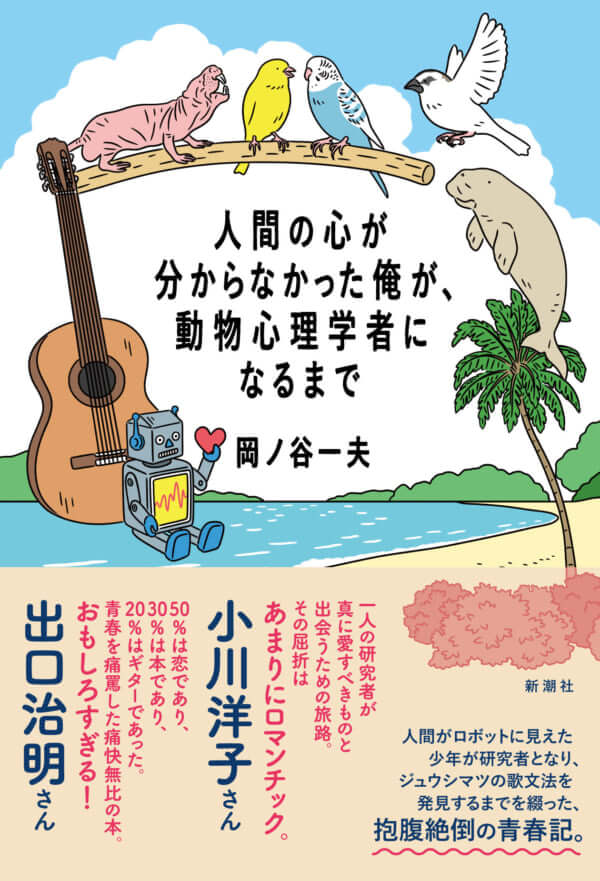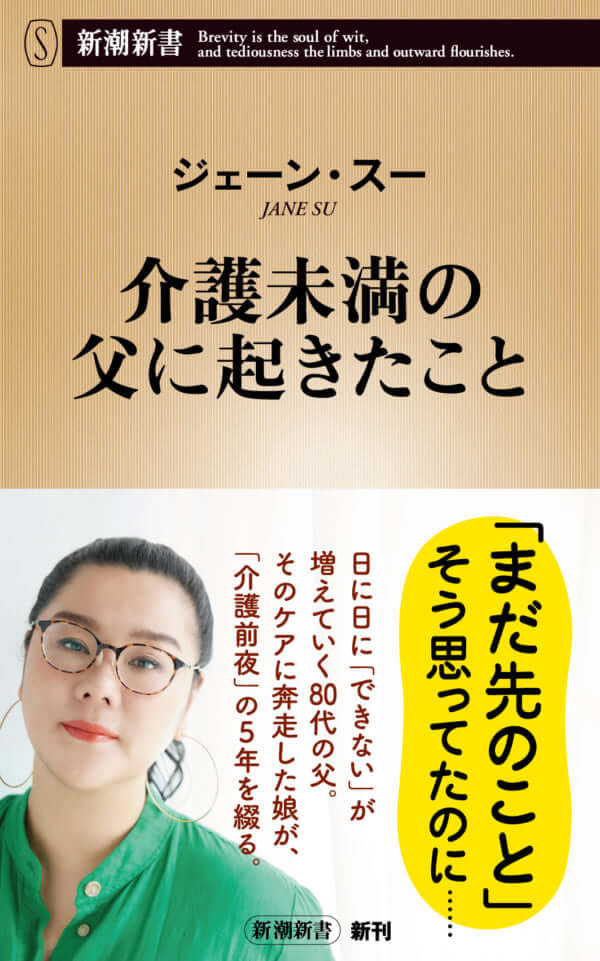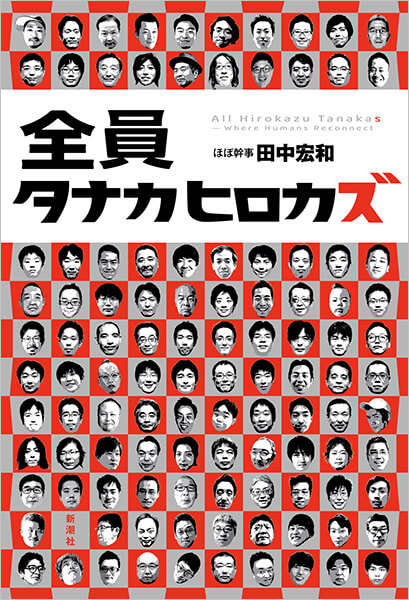「評論」一覧
-

-
- 世の中のうごき
- まなぶ
- 評論
5.「箇条書き」に抗う
最初のプロンプト 7月に入り、いよいよ、開発したソフトウェアを自分たちで日常的に試す「ドッグフーディング」の段階に入った。当初は、Picklesからのメールは週に一度……
-

-
- 世の中のうごき
- まなぶ
- 評論
4.Picklesを使いはじめるまで
単純な作動原理 日誌の執筆を支援するサービス、Picklesのアイデアの原理は、とても単純なものだ。前提として、書き手が日誌を書き溜めていく。そして週に一度、Pickles……
-

-
- 世の中のうごき
- まなぶ
- 評論
3.思考の発酵を促すAI
別様のSNSのかたちは? 主要SNSのアカウント削除後、新聞の取材を受けた。そこで前回に書いた理由を話した後に、どのような別のSNSのかたちが考えられるかと問……
-

-
- 世の中のうごき
- まなぶ
- 評論
2.「つくりながら書く」
SNSに抱いたジレンマ わたしはテクノロジーを研究する者だが、それと同時に多くのテクノロジーサービスの利用者でもある。学生時代から長年、各種SNSを使ってきた……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第20回 鉄道史上の靴と床
ミッション・スクールと鹿鳴館 杉本鉞子(えつこ)という女性を、ごぞんじだろうか。1928年に日本へかえるまで、三十年ほどアメリカぐらしをつづけてきた。生まれたのは187……
-

-
- 世の中のうごき
- まなぶ
- 評論
1.テクノロジーとの距離をはかる
人間と技術(テクノロジー)の発酵に向けて 蔵の奥に佇む木桶の中で数百年ものあいだ、眼には見えない無数の微生物たちの絶え間ない働きが、ぷちぷちと幽(かす)かな音を立……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第19回 公共の場でも抵抗は
三越百貨店の場合は 百貨店の歴史をふりかえる。今の若い人は、おどろくかもしれない。かつての百貨店は、土足厳禁の姿勢をとっていた。下駄や草履、そして靴などをはい……
-
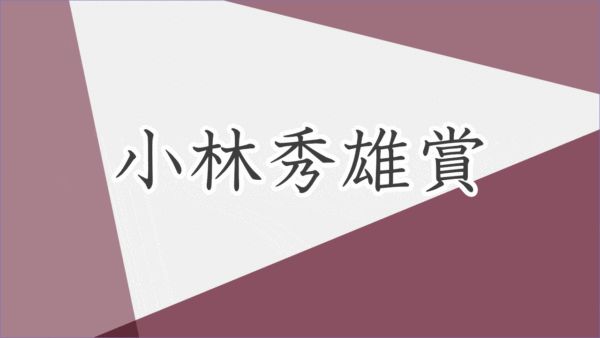
-
- こころ
- ことば
- 評論
第24回(2025年度)小林秀雄賞 受賞……
2025年8月28日午後、一般財団法人 新潮文芸振興会と新潮社の主催による「小林秀雄賞」「新潮ドキュメント賞」選考会がオークラ東京にて行なわれ、受賞作品が決定しました……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第18回 世界は靴を脱ぎだした
マテーラの日本人 『溺れる女』と邦題がそえられた映画を見た。2017年に公開された作品である。イタリアとスペインの合作ということになっている。 ヒロインのマルタは飛……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第17回 戦後のアメリカで
日本びいきの喜劇王 チャーリー・チャップリンは20世紀を代表する喜劇王である。出演した映画は数多く、いくつかの作品は、今なおくりかえし鑑賞されている。もとはイギ……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第16回 占領期の床と靴
接収した住宅で 日本は第2次世界大戦で敗戦国となった。1945年からは、占領軍の管理下におかれている。そして、この状態は1952年までつづいた。 占領政策にたずさわっ……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第14回 家のなか、店のなか
西洋人を家でむかえる時 エミール・ギメはフランスの実業家である。家業でもあった化学工業で、財をなした。その後は、世界漫遊の旅にでかけている。各地の宗教事情を、……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第13回 旅館のなかへはいる時
畳と靴 ジョルジュ・ビゴーは、19世紀後半の日本に、ながらく滞在した。そのころの日本をえがいたスケッチや漫画が、たくさんのこっている。明治中期の風俗をふりかえる……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第12回 万延元年、未知との遭遇
ここを靴で歩けるのか 咸臨丸という船については、歴史の好きな人なら、たいてい承知していよう。19世紀のなかばすぎ、つまり江戸末期に太平洋を横断した。日本史上最初……
-
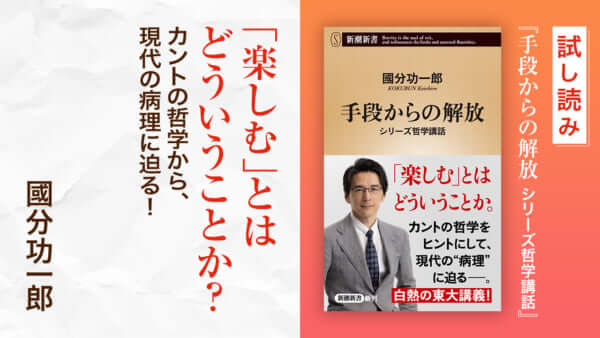
-
- ことば
- 世の中のうごき
- 評論
「楽しむ」とはどういうことか?
はじめに――楽しむことについての哲学的探究 楽しむとはどういうことなのだろう。 楽しいって何なのだろう。 私が何かを楽しんでいると言えるのはどういう状態なのだ……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第11回 ロシアから英米へ
ペリーの場合 いわゆるペリー艦隊は、1853年の7月8日に浦賀へやってきた。14日には、久里浜で浦賀奉行へ、アメリカ大統領の親書をわたしている。アメリカとも外交関係を……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第10回 ブーツ、そして靴袋
ショート・シューズではどうか 日本に拉致された船長のゴロウニンらを、とりもどす。ディアナ号にのこされた部下のリコルドは、そのため日本側との交渉へのりだした。松……
-
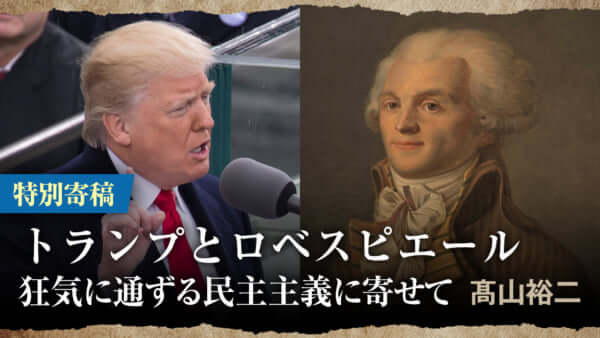
-
- まなぶ
- 世の中のうごき
- 評論
トランプとロベスピエール――狂気に通ずる……
髙山裕二『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』刊行記念エッセイ
現代世界の「専制化」の傾向 2022年5月、本サイトの連載「ロスベピエール 民主主義の殉教者」、第1回「真の民主主義を求めて」の冒頭で、わたしは次のように書いている……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第8回 オランダか中国か
蘭学者たちの新年会 オランダ正月という言葉がある。 長崎出島のオランダ商館では、しばしば正月に祝宴をもよおした。その日程は日本の元旦とくいちがう。江戸時代の日……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第7回 スリッパをはいて庭へでる
オランダのスリッパは 日本のホテルは、たいてい客室にスリッパをそなえている。宿泊者は部屋へはいると靴をぬぎ、すぐスリッパにはきかえることができる。その提供は、……
-
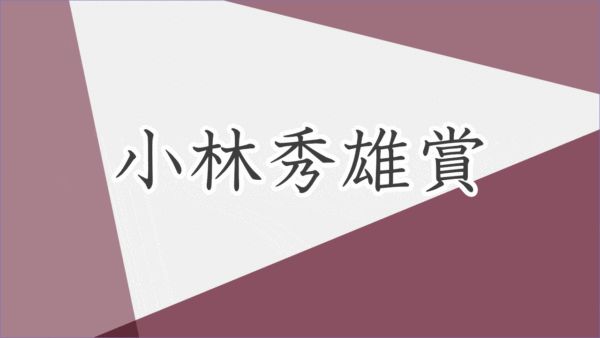
-
- こころ
- ことば
- 評論
第23回(2024年度)小林秀雄賞 受賞……
2024年8月29日午後、一般財団法人 新潮文芸振興会と新潮社の主催による「小林秀雄賞」「新潮ドキュメント賞」選考会がオークラ東京にて行なわれ、受賞作品が決定しました……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第6回 スリッパの使い道
靴とスリッパ 南蛮時代の日本へやってきた西洋の宣教師たちは、畳の部屋でミサをとりおこなった。靴は、まずはいていない。日本の生活に、その点ではあわせながら、聖祭……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第5回 日本の風俗とむきあって
陋屋で下駄をはく いわゆる南蛮時代に来日した宣教師は、日本家屋でくらしていた。教会や修道院、そして神学校などをたてるさいにも、日本建築をもうけている。本格的な……
-

-
- まなぶ
- くらし
- 評論
第4回 南蛮時代のミサ聖祭
畳とカトリック 天橋立は、京都府の宮津市にひろがる名勝である。そして、同市には、ヨハネの天主堂がある。こちらはカトリックの教会である。建物は1896(明治29)年に……
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング
「考える人」から生まれた本





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら